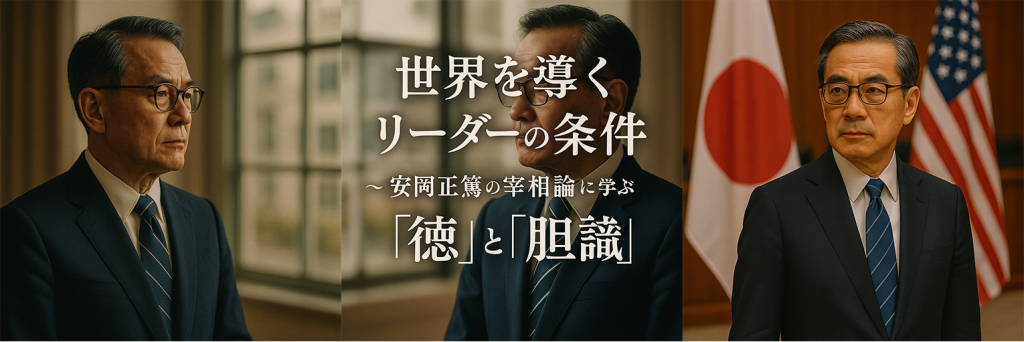
世界を導くリーダーの条件 〜安岡正篤の宰相論に学ぶ「徳」と「胆識」〜
はじめに:安岡正篤とその思想基盤
まず初めに、安岡正篤とは誰か、彼の思想基盤は何か、を明確にし、それらを足掛かりとした「宰相論」「リーダー論」の議論枠を定める。
安岡正篤略伝と思想背景
安岡正篤(やすおか まさひろ、1898年-1983年)は、日本の易学者、思想家、哲学者であり、戦前から戦後に至るまで、政界・財界・教育界など広い領域に影響を与えた人物である。
大阪市内に生まれ、幼少期より漢籍・儒学・易学の学びを重ね、後年には東洋思想・国学・仏教・老荘思想なども含む幅広い学問的教養を身につけた。
彼は「金鶏学院」などの私塾を通じて後進を育て、思想を実践路線に転じ、政財界のリーダーたちの精神的師匠とも仰がれた。
思想的には、伝統的東洋思想(儒教・国学など)を基盤としつつ、それを近代的現実に対して生きたかたちに適用しようとする姿勢が特徴である。安岡は、単なる古典回帰者ではなく、「人間学」と称すべき、人格と精神から始まる指導者教育の構想を打ち出した点で独自性を持つ。
安岡の著作としては、『東洋宰相学』『政治家と実践哲学』『活眼活学』『人物を修める』などが知られている。
戦後、公職追放や政治的制約もあったが、彼の影響力はむしろ拡がり、昭和の歴代首相(吉田茂、佐藤栄作、中曽根康弘など)に精神的な指導・助言を与えた「影の教育者」と称される。
これらを踏まえ、本稿では、安岡正篤の思想の中核たる「宰相論・リーダー論」の本質を探り、それを現代の国家リーダーに適用・比較して論じていく。
主要概念と枠組み:宰相とは何か、リーダーとは何か
議論を明晰に進めるため、まず「宰相」「リーダー」「国を司るリーダー」という言葉の定義を明らかにしておきたい。
- 宰相(さいしょう):もともと君主体制下で、君の下において国務を統轄・調整する最高実務者を指す語である。英国でいう首相(Prime Minister)、他の立憲君主国・共和制国家でいう首相・大統領・首席閣僚などがこれに相当しうる。ただし、安岡が論じる「東洋宰相論」においては、必ずしも形式上の地位ではなく、「国を導く大志・徳を以て国政を統括し、後世に太平を残す」ことのできる人物を意味する含意を帯びる。
- リーダー:広義には、ある集団・組織・国家を導く人物を指す。リーダーは統率(policy, strategy, 統制・調整)や精神的・道義的導き(vision, 高邁な志、人格的示唆)を担う。ただし、実際にはその役割や機能は多岐にわたる。
- 国を司るリーダー:国家元首、首相、あるいはそれに準ずる実質的権力を持つ人物であり、外交・安全保障・経済政策・国家理念の提示など、広範な責任を果たす立場を指す。
したがって、本稿において「安岡正篤の宰相論・リーダー論」というとき、それは形式的地位に限らず、国家を導く者に求められる本質的資質・行動規範を探ることを意味する。
以降、本稿は三部構成とし、順に以下を扱う:
- 安岡正篤の宰相論・リーダー論の核心命題
- 日本における事例と分析
- 世界的視点:欧米・アジア各国の事例と当該理論の示唆
最後に総括と今後への展望を示す。
第1部 安岡正篤の宰相論・リーダー論の核心
この部では、安岡正篤が言説の中で繰り返し主張・強調した主要命題を整理し、それらを体系的に論じる。主たる論点として以下を挙げる:
- 「三識(知識・見識・胆識)」の重視
- 「出処進退」の哲理
- 「時勢を知る」「不易流行」「大義と私利の調和」
- 「人物完成」と「徳主導の統治」
- 「忠恕・仁義・和」の精神原理
これらを順に論じ、それらが宰相・国家リーダーにとってどのような意味を持つかを示す。
三識:知識・見識・胆識
安岡正篤が繰り返し強調した基本構図が「三識」である。「知識」「見識」「胆識」の三要素からなる。
- 知識:書物・経験・教えにより得られる情報・理論・技術・史実などである。リーダーはまず、国家運営・外交・経済・社会構造などの知識を有していなければならない。しかし安岡は、知識だけにとどまることを戒め、「知識を見識に高めるべきだ」と説く。
- 見識:知識に基づく洞察力・判断力・価値観を意味する。単なる情報をそのまま用いるのではなく、何が本質かを見極め、時勢を読んで適切な判断を下す力である。安岡は、日本人・東洋思想の文脈における見識を重視し、中国思想や儒教的価値、歴史的経験を見識の根拠に据えた。
- 胆識:判断を行った上で実際に行動する勇気・胆力を指す。見識があっても、決断と実行に移す胆力がなければリーダーたりえない。安岡は、リーダーが時に「踏み込む」か「退くか」を決断する胆力を重視した。
この三識は、単なる教養概念ではなく、リーダー資質を段階的に鍛えるプロセスと捉えられる。知識 → 見識 → 胆識、という昇華の道筋を通じて、人間(リーダー)としての成熟がなされるという構想である。
この枠組みを国家リーダーに当てはめると、単に政策知見・外交戦術を知っているだけでは足らない。歴史的潮流・民意・国際情勢を洞察し、自国の文化・国家的文脈に照らして判断できる見識が不可欠である。そして、見識の判断を実際に具現する胆識、すなわちリスクを背負って実行する勇気と覚悟が最終的に問われる。
現代の国家リーダー論においても、知識過多・情報洪水の時代だからこそ、見識と胆識の差がリーダーを分けるという示唆は極めて有効である。
出処進退:出る時・退く時の判断
安岡正篤のリーダー論において、特に象徴的な概念が「出処進退」である。「出処進退」とは「いつ出てゆくべきか(進む/責務を引き受ける)」「いつ退くべきか(退く/辞する)」を意味する言葉である。
安岡は、リーダーが最も問われるのは、責務を引き受ける勇気だけではなく、退くべき時に潔く退く覚悟であると説いた。いわば、去り際にこそ人物の真価が現れる、という考えである。
この「退く」ことには二重の意味がある。一つは役割・地位から身を引くこと、もう一つは任務終結後に新しい世代へ道を譲るという意味を含む。リーダーは、永遠にその場に居続けるわけにはいない。自らの時間的限界や時代の変化を見極め、適切なタイミングで退くことができるかどうかが、リーダーの品格を問う。
この考え方は、現代政治でよく批判される「居座り」「権力の固定化」に対する一方の解として響く。リーダーが権勢を固辞して退くことをためらうと、組織・国家は硬直化し、後継者育成や制度刷新が滞る。逆に、去るべき時を誤らずに身を引くならば、信頼と尊敬を残す。
この考えは国家リーダーにとっても重い示唆を持つ。選挙制・任期制を持つ民主国家でも、リーダーの去り際の選択は制度だけでは制御できない。リーダー自身の品格・判断に依拠せざるを得ない場面が多い。
時勢を知る、不易と流行、大義と私利
もう一つ、安岡の理念の中心には、「時勢を知る」ことと、「不易流行」の思想との両立がある。
- 時勢を知る:リーダーは、国際情勢・経済構造の変化・民意の動向を敏感に読み取ることが不可欠である。これを誤れば、政策は時代遅れになり、国家は遅延を負う。
- 不易流行:古典的思想から、恒常的に変わらぬ本質(不易)と、時代に応じて変わるべきもの(流行)を調和させる思想である。儒教思想・東洋的哲理にはこの観点が古くからある。不易を貫く徳・志を持ちつつ、流行すなわち世の変化・技術革新・国際構造変動を受け入れて適用できる柔軟性が肝要である。
- 大義と私利の調和:リーダーは公共の大義を以て行動するが、それは必ずしも自己犠牲だけを意味せず、私利を完全に否定するのでもない。むしろ、私利を正しく制御し、大義と私利を整合させる能力も問われる。安岡は、リーダーがあまりにも大義一辺倒に傾いて自己犠牲・孤立化しては組織との乖離を招くとも見ていた。
このような構図を持つリーダー論では、時勢を無視した過激改革、あるいは守旧保守主義の堅持という両極端を避け、変化と伝統を統合して国を導く構えが求められる。
人物完成と徳主導の統治
安岡がしばしば強調する“リーダーの根本”は、外的能力や政策能力よりも、人物(人格)完成である。すなわち、リーダーはまず「人として正しくあること」を究めた上で、国家を導く役割を果たすべきだという主張である。
この視座は、東洋的伝統の徳治思想と相通じる。リーダーは徳を持ち、人民を説得し、徳をもって統治しなければならない。強制や力技に頼る統治は、長期的には必ず歪みと反発を招く。
徳主導の統治とは、権威・権力を背景としながらも、それを人格的・道義的正当性で補強する統治スタイルである。リーダーが率先垂範し、倫理観・公共精神を体現できる者ならば、国民や官僚・部下はそれを模倣し、より持続的な統治秩序が成立しやすいという信念がそこにある。
忠恕・仁義・和の精神原理
東洋思想的要素として、安岡は「忠恕」「仁義」「和」の精神をリーダー論における基盤原理として重んじた。
- 忠恕(ちゅうじょ):誠実・忠誠と、他者への寛恕・思いやりを兼ねる徳性。リーダーは、国や人民へ忠を尽くすこと、また民や部下への恕(ゆるし・思いやり)を持つことが重要である。
- 仁義:儒教における基本徳であり、他者を思いやる「仁」と、公正・正義の「義」を意味する。リーダーは仁義を以て行動すべきであり、衆民との調和・正道の判断を怠ってはならない。
- 和(わ):調和・協調・統合の精神。多様性や利害の対立を前提とした社会を統合し、和を以て万機を調整する力が必要となる。
これらは、リーダーが単に強い意志や支配能力だけでなく、人間性・道義性をも備えるべきという安岡の思想をよく示す。
第2部 日本の事例と分析――安岡流枠組みで見る歴代リーダー
この部では、日本における過去の首相・政治リーダーを、安岡正篤の枠組みで検討し、現代における教訓を抽出する。
対象とするリーダー例として、吉田茂、佐藤栄作、中曽根康弘、さらには戦前のリーダーを取り上げ、それぞれの強み・弱みを安岡の尺度で評価する。
吉田茂:去り際の見事さと宰相たる姿
吉田茂(1878-1967)は、戦後日本の復興と独立回復において中心的な役割を果たし、戦後日本政治の基軸を築いた首相である。吉田は占領期をくぐり抜けつつ、講和条約の締結、日米安保体制の成立などに関与した。
安岡正篤との関係も深く、吉田政治の精神的支えとも目されてきた。
吉田を安岡流枠組みで見ると、以下のような評価ができる。
- 三識
知識・政策構想においては卓越していた。占領下および復興期という激変の時代において、国際情勢・国内課題を理解し、適切な政策を打ち出した。見識という点では、アメリカとの交渉、講和自主路線、主権回復などの選択において洞察力を発揮した。胆識という点でも、講和交渉を強行して成し遂げ、圧力の強い米国との折衝に臨む勇気を持った。 - 出処進退
吉田茂の去り際は典型的な模範とされる。1960年の安保改定を巡って世論の反発が強まる中、首相は辞任を決断し、政治的混乱を抑えた。彼はその後も政治的影響力を保ったが、首相としての地位を守り続けることにはこだわらなかった。こうした潔い退き方は、安岡が理想とした出処進退の姿にかなり近い。 - 時勢・不易流行・大義と私利
吉田は近代日本の伝統と戦後秩序を調和させようと努めた。不易、すなわち日本的価値・国体維持を重んじつつ、流行、すなわち戦後の国際秩序・自由主義ルールを受け入れた。大義(国の独立・復興・国際信義)と私利(党派的利益・支持基盤調整)は慎重に調和させようと試みた。 - 人物完成・徳主導
吉田は威厳・風格を兼ね備え、政治的・外交的指導者としての徳性を備えていたと評価される。その人格的信頼性が、内閣・政党・官界の協調を助けた側面もある。
総じて、吉田茂は安岡流枠組みにおいて理想タイプに近く、その去り際の判断も含めて「宰相」のモデル例といえよう。ただし完璧な存在ではなかった。権力運営における派閥調整、閣内折衝、地元支持基盤との兼ね合いなど、現実の制約には苦労を重ねた。
佐藤栄作:長期政権と安岡的支え
佐藤栄作(1901-1975)は、吉田路線を継承しつつ日韓条約締結、沖縄返還、安保改定などを推進した長期政権の首相である。彼もまた安岡正篤と関係が深く、安岡派から精神的影響を受けたとされる。
佐藤を安岡流で検討するなら次のようになる。
- 三識
知識・政策構想は一定水準にあり、外交・安全保障・経済政策に関する知見を備えていた。見識として、時代の国際関係・アジア情勢・冷戦構造を読む力を持っていた。胆識という面では、沖縄返還や安保改定推進にあたり、リスクを承知で決断する姿勢を示した。 - 出処進退
佐藤は政界引退をきちんと行った例であり、長期政権後に潔く政権を手放した実績がある。ただし、完全に権力を手放したわけではなく、影響力を維持する構えも残した。とはいえ、首相職をいつまでも固執しなかった点は評価できる。 - 時勢・不易流行・大義と私利
佐藤は、戦後日本の国際自主路線・アジア外交重視を掲げつつ、米国との同盟関係を維持する現実主義をとった。変化を読む柔軟性を持ちつつ、保守的価値・国体意識も尊重した。大義(国益・地域安定)と私利(党勢維持・中選挙区調整)との調整には苦心したが、一定のバランスを保った。 - 人物完成・徳主導
佐藤は温厚・穏健な人柄を持ち、政治的な配慮・調整能力にも長けていた。だが、吉田と比べると政治的・外交的主導性・権威感にはやや弱さを指摘されることもある。
佐藤栄作は、安岡流リーダー観においては、長期実務政治において妥協と選択を積み重ねながら、比較的バランス感覚を保ったリーダーと評価できる。ただし、時代変化の極端性が増す中では、見識・胆識のギャップが問われやすい。
中曽根康弘:変革志向とリスクをとる宰相
中曽根康弘(1918-2019)は、1982年から1987年まで首相を務め、日本の構造転換・国際関係の再構築を目指した「行革」路線を打ち出したリーダーである。安岡との関係も語られることが多い。
中曽根を安岡流枠組みで検討すると、以下のような評価が可能である。
- 三識
知識・政策構想には積極性があり、特に行政改革・公共部門改革・外政再構築を目指した政策を掲げた。見識として、冷戦終焉期・米ソ関係・日米関係の変動を読みつつ行動した。胆識という点では、改革断行・国鉄民営化・金権政治追及など、権力抗争を伴う改革に果敢に挑戦した点は評価できる。 - 出処進退
中曽根は在任中に自らの退き時を見極め、5年内で首相職を退いた。構造改革や外交路線を一つの区切りで区切りつつ、自らの退場設計を描いた面がある。これも、安岡的な退く覚悟を示したケースと評価できる。 - 時勢・不易流行・大義と私利
中曽根は変革志向を前面に打ち出し、時代変化を先取りしようとした。既有制度・保守的価値への挑戦を見せながらも、国内保守支持層との折衝も行った。大義(国家再構築・国際競争力強化)と私利(派閥制御・政権維持)との折り合いは緊張関係を伴った。 - 人物完成・徳主導
中曽根は強いカリスマ性・リーダー性を示し、閣僚・官僚・財界を牽引した。しかし、その強引性・独断性を批判する声もあった。徳の面から見ると、リーダーの強い手腕・信念を忌避する風潮もあり、安岡流の「徳主導論」とはやや齟齬を生じる部分もある。
中曽根は、安岡の枠組みにおいて、比較的強い胆識を以て変革を断行しようとしたリーダーと見なせる。ただし、変革の速度・手法をめぐる葛藤が、見識と胆識のギャップを露わにした。
戦前・戦中のリーダー例:近衛文麿・東条英機
戦前・戦中期にも、宰相たるリーダーが多数存在する。ここでは近衛文麿、東条英機といった例を、安岡的視点から検討してみる。
- 近衛文麿
近衛は複数期にわたり首相を務め、1930年代から戦争前段階の内政・外交に深く関与した。彼の政策には内政の統制強化、国防・対支那戦略などがあった。しかし、近衛は時勢を読み違え、軍部の暴走を制御できなかった面が強く批判される。
安岡流観点で見ると、近衛には知識や政策構想はあったが、見識・胆識において決定的に乏しかった。時代変化を制御・誘導する力量を欠き、出処進退の判断も曖昧であった。彼の指導には、徳性や調和力の不足も指摘されうる。
- 東条英機
東条は軍部出身で理論家とは一線を画するが、戦争遂行において強権を振るった宰相である。彼のリーダーシップは、権力集中・軍事主義的傾向を伴った。ただし、国家の破滅的選択を導いた責任も大きい。
安岡流枠組みで見ると、東条の知識・政策能力は戦時体制下で一定の戦略性を示した面はある。しかし、見識・胆識という観点では、冷静な判断と退く覚悟を欠いた点、徳性・人間性における限界が致命的である。出処進退の観点から言えば、戦敗色が明らかになった後も退くことを怯み、国をさらなる混乱に導いた点が最も重く評価される。
これらの事例を通じて、安岡的基準は、リーダーの真価を見極める尺度として有効であることが確認できる。特に、現代においては、三識・出処進退・時勢対応などの観点が、ますます重要になってきている。
第3部 世界的視点:欧米諸国、アジアの国の事例と比較
この部では、欧米諸国およびアジア諸国における国家リーダーを対象に、安岡正篤の視点からリーダー論を比較・考察する。どのようなリーダーが安岡的枠組みに照らすと優れているか、またその限界や課題もあわせて探る。
対象として、以下のようなリーダーを取り上げる(ただし網羅的ではない):
- 英国:ウィンストン・チャーチル、マーガレット・サッチャー
- 米国:フランクリン・ルーズベルト、ジョン・F・ケネディ、ロナルド・レーガン
- フランス:シャルル・ド・ゴール
- ドイツ:ヴィリー・ブラント、ヘルムート・コール
- 韓国:李承晩、朴正煕、金大中
- 台湾:蒋介石(台湾期)、李登輝、馬英九
これらを、三識・出処進退・不易流行・人物完成等の観点から検討する。
英国:チャーチルとサッチャー
チャーチル(Winston Churchill, 1874-1965)
チャーチルは第二次世界大戦期に英国を率いた指導者として、極めて象徴的な存在である。
- 知識・見識・胆識
チャーチルは歴史・軍事・英国政治の深い知識を有し、国際情勢に対する洞察も卓越していた。さらに、重大な決断(ドイツとの戦争継続、アメリカとの同盟関係強化)を行う胆識を持っていた。彼の「血と汗と涙」の演説や、臨戦態勢の構築は、まさに胆識の発露である。 - 出処進退
チャーチルは戦後1955年に首相を退いたが、その後も保守党政治家として影響力を維持した。しかし、首相としての役割を明確に区切る判断をした点は、いわば去り際の智慧を示したと見ることができる。ただし、晩年の政界復帰や保守党内部での影響力を保ち続けた姿勢については、退くべき時・留まるべき時の葛藤を含んでいたと言える。 - 不易流行・大義と私利
チャーチルは英国の伝統・価値観を重視しながらも、時代の変動(帝国解体後の英連邦構造、戦後復興、冷戦体制)を読み取り、新しい国際秩序の中で英国の立ち位置を探った。彼はいくつもの政策決断で時代変化に応じた対応をしたが、そのなかで伝統的価値や英国の核心利益を堅持する不易性を捨てなかった。 - 人物完成・德主導
チャーチルはその豪放かつ孤高の人格で知られ、国家危機に際して国民の信頼を得るカリスマ性を持っていた。ただし、その激しい個性・強弁性・時に強行的な政治手法には批判もあり、それをどう徳性と整合させるかは複雑な問題である。
チャーチルは、安岡流リーダー論の多くのポイントにかなり近い資質を持っていたリーダーといえる。ただし、英国党派政治や議会制民主主義の限界、権力点検機構との関係をどう制御するかという点は、安岡の枠組みだけでは十分にはカバーできない。
サッチャー(Margaret Thatcher, 1925-2013)
サッチャーは1979年から1990年まで英国の初の女性首相として、強烈な変革と保守路線を推し進めた政治家である。
- 知識・見識・胆識
サッチャーは経済政策・国営企業改革・公共部門縮小などについて明確な知見をもち、それを基に保守改革を進めた。見識として、英国の国家財政・国際競争力・労働組合問題・ヨーロッパ連合関係などに対する判断力を発揮した。胆識という点では、彼女は強権的手法をとる勇気を持っており、労働組合や鉄鋼・炭鉱産業再編などに大きなリスクをもって挑んだ。 - 出処進退
サッチャーは在任11年目に党内離反と支持低下によって首相を辞任した。その去り際は必ずしも自らの意志のみで選択したものではなく、政権崩壊の中での辞任であった。しかし、政権維持を試みつつも、一定限界を見て退いた点は、出処進退の観点から評価できる。 - 不易流行・大義と私利
サッチャーは保守主義・自由主義といった不易的価値を堅持しつつ、グローバル化・市場経済重視といった流行を積極的に受け入れた。彼女はその両者の調和を図ろうと努力した。大義(国家再生・個人主義・自由主義強化)と私利(支持基盤拡大・党内制御)との折り合いをつけながら、断固改革を続けた。 - 人物完成・徳主導
サッチャーのリーダーシップは強烈な自己主張・意志力に拠るところが大きく、彼女自身の信念・価値観を前面に出した政治を行った。その点は安岡的リーダー論と整合する側面がある。ただし、調和性・包摂性という観点からは批判もあり、徳主導の統治という観点からはやや硬直性・排他性の問題がある。
サッチャーは、変革リーダーとして強い胆識を示した例であり、安岡流枠組みの多くの側面に通じるところがある。しかし、権力集中や排他的政策、退場設計の困難さなどは、リーダーシップのリスクを明示的に示す事例とも言えよう。
米国:ルーズベルト,ケネディ,レーガン
フランクリン・D・ルーズベルト(Franklin D. Roosevelt, 1882-1945)
ルーズベルトは、世界大恐慌、第二次世界大戦という未曾有の危機の中で米国を率いた大統領である。
- 知識・見識・胆識
彼は経済・外交・軍事政策に関する広範な知識を有し、見識においても国際体制・民主主義・国際連合構想などを先見的に描いた。胆識という点では、ニューディール政策、孤立主義から参戦への転換、戦時体制構築など、強力な政策決断を行った。 - 出処進退
ルーズベルトは4期目を目指したが、1945年に在任中に死去したため、自ら退く意思を明確に示したわけではない。ただし、政策決断・政権運営において退くという判断を選ぶ場面は少なかった。 - 不易流行・大義と私利
ルーズベルトは、アメリカ民主主義・自由主義という不易的価値を基軸に据えながら、時代の社会問題(失業・貧困・世界大戦)に対する対応を流行政策・制度改革を通じて行った。大義(国家再建・民主主義拡充・世界平和)を掲げつつ、党派政治・支持調整を巧みに操作した。 - 人物完成・德主導
彼は政治的カリスマ性と戦略性を備えたリーダーであったが、個人性・政権中心性ゆえに権力肥大・行政拡張を伴ったという批判もある。徳性・節制、退く覚悟という観点からは、限界もあった。
ルーズベルトは、安岡流枠組みにおいて、重大な危機において胆識を発揮したリーダー像と見ることができる。ただし、去り際を自身でデザインできなかった点、権力集中を招いた点は批判点となる。
ジョン・F・ケネディ(John F. Kennedy, 1917-1963)
ケネディは、若年リーダーとして米国の冷戦期を導いた大統領である。
- 知識・見識・胆識
ケネディは外交・安全保障政策に関して一定の知識を持ち、キューバ危機・冷戦バランス維持といった時代の岐路で見識を発揮した。胆識という点では、キューバ危機における核対峙回避、宇宙開発を通じた国家意志の提示などで大胆な政策を取った。 - 出処進退
ケネディは暗殺により任期を全うできなかった。自ら退く判断を問われる機会はなかったため、出処進退という点での評価は難しい。 - 不易流行・大義と私利
ケネディは民主的価値・市民自由という不易性を尊重しつつ、冷戦下の競争・国際性を前提とする流行志向(宇宙開発・科学技術競争・国際同盟)を積極的に取り入れた。大義(自由世界の指導・核抑止・国際協調)と私利(支持基盤拡大・若年層支持維持)を調整しながら政治を進めた。 - 人物完成・德主導
ケネディは魅力・ビジョン・リーダー性を備え、民衆の支持を集めた。しかし、内政的には政策実現力や成熟度にはやや不足を指摘されることがある。徳性・退く覚悟という観点からは、評価が難しい。
ケネディは、安岡流枠組みにおいて、若い世代の象徴的リーダーとして、胆識・ビジョンを示した例といえるが、退く覚悟というテーマには触れる機会を持たなかった。
ロナルド・レーガン(Ronald Reagan, 1911-2004)
レーガンは1981年から1989年まで米国大統領を務め、保守回帰と冷戦終結期を導いた指導者である。
- 知識・見識・胆識
レーガンは経済政策(サプライサイド経済学・減税政策)や冷戦政策(スター・ウォーズ構想など)に関して、一部批判を受けつつも一定の知識と見識を持っていた。胆識という点では、強い発言・外交政策転換・軍拡路線などを断行した。 - 出処進退
レーガンは任期2期後に退いたという形で、自ら退く選択をした。去り際をきちんと設計した例と捉えられる。 - 不易流行・大義と私利
レーガンは米国的価値(自由主義・小さな政府・個人主義)を不易軸としつつ、時代の流れ(冷戦構造変動・グローバリズム台頭)を取り入れた。大義(米国の国際的リーダーシップ・保守価値復権)と私利(共和党支持固め・内部政策実現)との調整を図った。 - 人物完成・德主導
レーガンは親しみやすい人格とカリスマ性を備え、国民とのコミュニケーション能力を重視した。リーダーシップとしての徳性と政治手腕を両立させた例と見ることができる。
レーガンは、安岡理論から見ると、比較的理想に近いリーダー像であり、退く設計も含めて一つの成功モデルといえる。
フランス:ド・ゴール(Charles de Gaulle, 1890-1970)
ド・ゴールは、第二次世界大戦中の亡命政府を率い、戦後フランス共和国を再建した象徴的リーダーである。
- 知識・見識・胆識
ド・ゴールはフランス・ヨーロッパ・国際秩序に関する見識を備え、独立外交・核戦略・ヨーロッパ統合の先駆的構想を打ち出した。胆識という点では、政変を強行し第五共和制を樹立したり、アルジェリア戦争処理、米国との距離を置く外交路線などで大胆な行動をとった。 - 出処進退
ド・ゴールは1969年の国民信任投票で否決された後、辞任を決め、自ら政界を退いた。これを潔い去り際の典型と見ることができる。また、彼は第五共和制という制度的枠組みを確立したうえで政治を去ったため、後任へ制度的責任を残した。 - 不易流行・大義と私利
ド・ゴールはフランス的価値(国家主権・文化的独自性)を不易としつつ、ヨーロッパ統合・国際システム変化という流行を読み取り、折り合いをつけようとした。大義(フランス独立・国家プレステージ)と私利(党派的根拠・権力基盤)とのバランスにおいては強い主張を保持した。 - 人物完成・德主導
ド・ゴールは国家の象徴的リーダーとしての威厳・人格性を備え、国民的カリスマを持った。政策過程の排除性・体制中心性といった批判もあるが、德性と統治理念を重視したリーダー像と見ることができる。
ド・ゴールの去り際は、まさに安岡が理想とした「進退判断力」を示す例であり、宰相論的評価においても強いモデルになる。
ドイツ:ヴィリー・ブラント、ヘルムート・コール
ヴィリー・ブラント(Willy Brandt, 1913-1992)
ブラントは西ドイツの首相として、東西ドイツ関係改善・東方政策(Ostpolitik)を進めた。
- 知識・見識・胆識
彼は冷戦構造と東欧情勢を読む見識を持ち、東方政策を通じた関与を推進した。胆識という点でも、強い外交判断と対話政策への転換を断行した。 - 出処進退
ブラントは1974年、スパイ事件の責任を取り首相を辞任した。潔い退却判断として評価される。彼は責任主義の倫理を示し、リーダーの潔さを体現した。 - 不易流行・大義と私利
ブラントはドイツ民主主義的価値を不易として、冷戦構造の変化を流行として捉え、東方関係改善・ヨーロッパ統合促進を推進した。大義(ドイツ再統一・ヨーロッパ統合)と私利(支持基盤・党内調整)との折り合いを意識しながら行動した。 - 人物完成・德主導
ブラントは謙虚で理性的な人格を備え、「ひざまずく首相」として象徴的に国民に謝罪・和解を示し、道義的リーダーシップを発揮した。徳性を前面に出した統治スタイルは、安岡流理論と親和性が高い。
ブラントは、安岡流枠組みにおける理想的リーダー例の一つと考えられる。
ヘルムート・コール(Helmut Kohl, 1930-2017)
コールはドイツ再統一を主導した首相であり、長期政権の維持者である。
- 知識・見識・胆識
コールは欧州統合・統一ドイツ・経済統合政策に関する知識と戦略を持ち、見識としてヨーロッパの歴史と未来を読む構想を有していた。胆識という点では、ベルリンの壁崩壊・統一政策を果敢に推進した。 - 出処進退
コールは1998年に首相として退いたが、その後も党内影響力を残した。退くという点での潔さは評価できるが、後継者育成・権力浸透の配慮には批判もある。 - 不易流行・大義と私利
コールはドイツ統一と欧州統合を大義とし、伝統的価値と近代的統合政策の折衷を試みた。支持基盤との調整も巧みに行った。だが、党財政スキャンダルや支援基盤疲弊など、私利制御の困難が露呈した時期もあった。 - 人物完成・德主導
コールは一定の威厳と統治力を持ったが、指導性・カリスマ性という点ではやや淡さを指摘されることがある。だが、彼の政策構想と統一プロセスの牽引力は、リーダー論的観点からも高く評価できる。
コールは、統一と再編のフェーズでリスクを取った胆識型リーダーと見なせるが、退く設計・後継者構想という点で多少の不備があったと評価できる。
アジア:韓国・台湾のリーダー
韓国:李承晩(Syngman Rhee, 1875-1965)、朴正煕(Park Chung-hee, 1917-1979)、金大中(Kim Dae-jung, 1925-2009)
李承晩
韓国初代大統領となった李承晩は、分断国家としての韓国建設期を主導したリーダーである。
- 知識・見識・胆識
李承晩は国家建設・外交政策構想を持ったが、国内統治においては強権的手法が目立った。判断力・洞察力という観点では限界も指摘される。 - 出処進退
李承晩は1960年に四月革命を受けて退陣した。政権を手放すという意味では去り際を迎えたが、自発的・潔い退去であったかは議論が分かれる。 - 不易流行・大義と私利
李承晩は国家主義・反共主義を掲げつつ、韓国体制固有の国内統治手法を用いた。大義と私利の調整という点では、強権統治と汚職問題が批判材料となる。 - 人物完成・德主導
李承晩の強い政治的意志と国家建設への情熱には敬意を払うべき点もあるが、徳性・公正性・退く覚悟という面では限界が大きい。
李承晩は、変革・国家建設のフェーズにおいて一定の役割を果たしたリーダーであるが、安岡流枠組みで理想的リーダーとは距離がある存在である。
朴正煕
朴正煕は、朴政権として韓国の経済成長・産業化を推進し、韓国近代化の原動力となった。しかしその政権には専制性や人権抑圧も伴った。
- 知識・見識・胆識
朴は国家開発・経済政策に関する戦略を有し、産業化・輸出主導政策の道筋を描いた。見識という観点では、冷戦構造の下で国際支援を取り付け、韓国を東アジア成長エンジンへと導いた。胆識という点では、権威主義統治・強権的施策を厭わず、政治的リスクを伴う判断を積極的に行った。 - 出処進退
朴正煕は1979年に暗殺され、政権を自ら退く機会を選ぶことはなかった。従って、去り際の選択を評価することは難しい。 - 不易流行・大義と私利
朴は国家主義・国家開発主義を不易的価値と見なす一方、時代の経済開発モデル・国際貿易関係という流行を取り入れた。大義(国家近代化・国家主体性)と私利(支配体制維持・軍産複合体との関係)との折り合いは常に緊張を伴った。 - 人物完成・徳主導
朴の統治には強い意志・実行力という徳の質が感じられるが、民主主義・人権原則との整合性や包摂性という点では批判も大きい。徳主導という観点からは、統治者主義性が強く、必ずしも理想型とは言い難い。
朴正煕は、国家主導開発のリーダーとして成功と批判を併せ持つ人物であり、安岡理論から見ると、胆識と実行力は高評価だが、去り際・徳性・包摂性という点で課題を残す。
金大中
金大中は、民主主義回復・人権・南北和解構想を掲げ、1998年から2003年に韓国大統領を務めた。ノーベル平和賞受賞者でもある。
- 知識・見識・胆識
金は民主主義・人権・南北関係に関する知見を持ち、見識として南北関係改善・和解政策を志向した。胆識という点では、強権統治型ではなく、対話と和解を基調とする選択には一定のリスクもあったが、韓国政界の強硬勢力と対峙する覚悟を示した。 - 出処進退
金は任期を全うし、後継政権に平和的に政権を移譲した。彼の退場の仕方は、一定の理想型に近いと評価できる。 - 不易流行・大義と私利
金は民主主義・人権という不易軸を掲げつつ、南北関係改善・東アジア構造変化という流行対応を模索した。大義(韓民族統一・平和構築)と私利(支持基盤維持・政党運営)とのバランスを取りながら政策を展開した。 - 人物完成・德主導
金は公正性・品性・リスクをとる志向性を備え、民主主義的リーダーとして尊敬を集めた。徳性・品格重視という点から見れば、比較的安岡流理論に適合する人物像といえる。
金大中は、変化期における徳性リーダーとして、安岡理論に近いモデルの一つである。
台湾:蒋介石(台湾期)、李登輝、馬英九
蒋介石(Chiang Kai-shek, 1887-1975)
蒋介石は中華民国の指導者として、中国本土から台湾への政権移転後、台湾の統治を主導した。日台関係にも深い関連を持つ。安岡は蒋介石と個人的交流もあったとの記録がある。
- 知識・見識・胆識
蒋介石は国家統一・対共産主義戦略・共和体制維持などに関する政治ビジョンを持っていた。見識として、中国・台湾・冷戦構造を読む立場を取った。胆識として、内戦・外交関係・戒厳体制運営などの強権的判断を行った。 - 出処進退
蒋は台湾期において引退という選択を明確に行ったわけではない。彼の死去後に後継体制が継がれたため、去り際判断という観点からは評価が難しい。 - 不易流行・大義と私利
蒋は「中国正統性」「反共主義」「国家統一」という理念を不易軸としつつ、冷戦構造・台湾の実情・国際体制変化という要請を流行として対応した。大義(国共内戦回復・中華主義)と私利(権威維持・治安統制)との折り合いには緊張が伴った。 - 人物完成・德主導
蒋の指導性・権威主義性・自己意志の強さは、徳主導という点では強さと同時に硬直性も孕んでいた。統治スタイルは人民の自由・包摂性を犠牲にしてきた側面が強く、安岡理論から見るとその限界は明らかである。
蒋介石は、強固な国家的使命感を持ったリーダーであったが、徳性・退く覚悟・包摂性という面で欠点も際立つ人物である。
李登輝(Lee Teng-hui, 1923-2020)
李登輝は台湾初の本土生まれ総統であり、民主化・台湾主体性強化を進めた指導者である。
- 知識・見識・胆識
李登輝は、台湾・中華圏・国際政治に関する知見を持ち、見識として、台湾アイデンティティ・国際関係・民主化の選択を判断し、台湾を国際社会のプレーヤーに押し上げた。胆識という点では、国連脱退後の国際孤立化リスク、対中国関係重視・米国との関係維持などで大胆に決断した。 - 出処進退
李登輝は、任期を全うし、政権交代を平和的に果たした。彼の去り際は比較的潔く、後進へ道を譲った政治家と評価できる。 - 不易流行・大義と私利
李登輝は台湾民主主義・台湾主体性という不易軸を掲げつつ、アジア・国際情勢変動・中国との力学変化を見据えて行動した。大義(台湾の国際地位・民主主義)と私利(政党運営・支持維持)との調整は困難を伴ったが、比較的バランスをとろうとした。 - 人物完成・德主導
李登輝は、知性と品格を備え、政治家・学者としての両面性を持った人物であり、徳主導型のリーダー像として評価され得る。ただし、与党内対立や政策過程における強行性など、完全に理想的というわけではない。
李登輝は、台湾民主化・政治転換期において、安岡理論的観点からも成功モデルになりうるリーダーである。
馬英九(Ma Ying-jeou, b. 1950)
馬英九は台湾出身の総統で、2008–2016年に2期を務め、台湾の国際関係政策を進めた。
- 知識・見識・胆識
馬英九は法学・国際関係の知見を持ち、見識として、台湾海峡関係・大陸政策・国際法的立場を重視した。胆識という点では、和平経済協力・大陸との交流拡大などを政策化したが、強制性よりも対話性を重視した。 - 出処進退
馬英九は2期目終了後、政権を平和的に退いた。退くこと自体は問題なくこなしたと言える。 - 不易流行・大義と私利
馬英九は、台湾の法治・民主主義を不易軸としつつ、経済・交流重視という流行対応を取った。大義(台湾安全・発展・国際認知)と私利(支持維持・中国との距離調整)との調整が常に緊張関係をもっていた。 - 人物完成・德主導
馬英九は冷静・理性的な性格を持ち、外交政策・対中政策において能動的に動いた。ただし、政治的支持基盤との衝突や内政調整の弱さも指摘され、徳主導統治という観点からは補強すべき課題がある。
馬英九は、安岡理論から見ると、比較的堅実なリーダーではあるが、決断的な胆識や統治変革力という点ではやや弱さを持つ。
総括と考察:安岡理論の現代意義と課題
ここまで、安岡正篤の宰相論・リーダー論を整理し、日本・欧米・アジア各国のリーダー事例を通じてその適用可能性を検討してきた。以下、本稿の結論として、安岡理論の現代国家リーダーに対する適用可能性、強み・限界、そして未来的視座を示す。
安岡理論の現代国家リーダーに対する意義
- 三識の枠組みの普遍性
情報量が膨大な現代において、知識は誰でも比較的獲得しやすくなった。だが見識・胆識において差が出るという安岡の構図は、リーダーを見極める上で非常に有効である。リーダーは知識を単に暗記するだけではなく、それを文脈的・価値的に咀嚼し、判断し、実行できなければならない。 - 出処進退の智慧
現代においても、リーダーがいつ退くかは制度面だけでは解決できない。安岡の「去り際の判断力」は、民主国家にも権威主義体制にも通じる普遍的な指針でありうる。特に、任期制であっても、政治的支持失墜、時代変化への対応力低下、後継者育成不在などの局面では、リーダー自身の判断が問われる。 - 不易流行の統合思考
国際秩序変動、技術革新、社会構造変化という流行を無視しては国は停滞する。一方で、伝統・価値観・国家理念という不易を捨てればアイデンティティや国民統合が崩れる。安岡の枠組みは、この二者を調和させるリーダーシップ思考を提供する。 - 徳主導統治と人格主義の回復
高度技術時代・制度重視時代において、リーダーの人格的信頼性や道義性が軽視される傾向がある。だが、権力を越えた信頼形成や長期的統治の安定性には、リーダーの徳性・人格性が不可欠であるという安岡の主張は、現代的視点からも重要な指針を提供する。 - リスク判断と胆識の重視
政策決断・外交判断・危機対応など「リスクをとる勇気」がリーダーには不可欠である。安岡の胆識観は、政策実行力と国際競争力を兼ね備えたリーダー像を描き出す格好の枠組みである。
安岡理論の限界と克服すべき課題
安岡理論は魅力的な理論枠組みを提供するが、それ自体が万能ではない。以下はいくつかの限界と、それを克服・補完すべき視点である。
- 制度・制度設計力の軽視
安岡の理論は、主にリーダー個人の資質・判断に焦点を当てるものであり、制度設計・制度的制約との相互関係を十分には論じない。現代国家では、権力分立・ガバナンス・チェック・権限分配などの制度枠組みが重要であり、リーダーだけに全責任を負わせるのは現実的でない。 - 多元性・民主主義との整合性
徳治的・人格的リーダー論は、しばしば「上意下達」的・権威主義的傾向を孕む危険性を含む。現代民主制の下で、リーダーの徳性・見識・胆識を尊重する一方、権力チェック・制度制約・多元的対話をどう維持するかという問題を併せて扱う必要がある。 - グローバル化・力の非対称性への対応
国家間の力の非対称性、国際制度・多国間協調・規範競争といった問題は、リーダー個人の資質だけではどうにもならない側面を持つ。安岡理論を現代国際政治に応用するには、国際構造との対話・制約を視野に入れた拡張が必要である。 - リーダー育成・継承問題
安岡理論は優れたリーダー像を描くが、どのようにその資質を育て、連続的なリーダー継承を実現するか、という制度・教育的課題を直接には扱っていない。組織・国家としてのリーダー育成メカニズムを補完的に設計する必要がある。 - 過度の理想主義リスク
人格・徳性を重視しすぎると、リーダーに過剰な道徳的ハードルを課し、実務性・柔軟性を欠くという批判がある。リーダーは現実的制約・妥協・妥当性判断を行う実務的能力も求められるため、理想と現実のバランスを取る視点が不可欠である。
今後への展望と応用可能性
安岡正篤の宰相論・リーダー論は、古典と近代・東洋と西洋を架橋する思考財産であり、現代においてもいくつかの応用可能性を持つ。以下に、施策・制度・実践面での応用視座をいくつか提案する。
- 次世代リーダー育成プログラムへの導入
企業・行政・政治・教育機関において、三識・出処進退・徳性重視のカリキュラムを導入し、リーダー育成カリキュラムを設計する。特に、判断力・リスク感覚・去るべき時を見極める力を養う教育は重要である。 - リーダー選抜・評価制度への徳性指標導入
政治リーダー・官僚・企業経営者を選抜・評価する際、単なる実績・スキルだけでなく、人格・志、退く姿勢といった徳性指標を加味した選抜基準・評価制度を構築する。 - 制度と併存するリーダー倫理設計
制度設計とリーダー倫理は並行すべきものである。任期制・チェック・透明性制度を設計する一方、リーダーの人格倫理・退場設計力を制度的にも支える枠組み(例:任期延長の制限、前任者顧問ポジションの制限、リーダー退職後のガイドライン等)を導入する。 - グローバル・国際リーダーに対する訓練への適用
国際協調・対外交渉能力を要するリーダー(大統領・首相・外相・国連高官など)に対して、三識・胆識を鍛えるトレーニングやシミュレーションを取り入れ、リスク判断力・変化対応力を向上させる。 - リーダー交代設計の文化醸成
社会・国民文化として、リーダーが潔く去ることを尊ぶ価値観を育むことが重要である。去り際に敬意を払う文化があれば、リーダーは退くことを恐れず、制度的交代が円滑化する。これは、既存の権威文化との共存・刷新を要する課題である。 - リスク時代対応リーダーシップ理論との統合
AI革命・地政学リスク・気候変動・パンデミック等、21世紀特有のリスク時代に対応するリーダーシップ理論との統合が望ましい。安岡理論を現代リスクリーダーシップ理論(レジリエンス論、アンチ・フラジャイル論など)と結びつける研究・実践が今後有効であろう。
結びに代えて:「世界を司るリーダー」に向けて
本稿は、安岡正篤の宰相論・リーダー論を梃子としつつ、日本・欧米・アジア諸国の国家リーダー事例を比較検討し、現代的視点からその意義と限界を浮き彫りにしたものである。
読者にとっての気づきとして、次の三点を特に強調したい。
- リーダーは知識を持つだけでは不充分であり、判断と実行に至る胆識が最も問われる。
現代は情報洪水・知識過剰の時代であるからこそ、見識と胆識にこそリーダーの真価が問われる。 - 去る時を見誤るリーダーは、築いた実績も信頼も一夜にして崩れる。
リーダーは、いつ、どのように去るかをあらかじめ設計しうる覚悟と能力を備えるべきである。 - 徳性・人格性を軽視する統治には、長期的持続性が担保されにくい。
強さ・効率・実行力に偏ったリーダーシップは、時とともに反発・崩壊を招くリスクを孕む。
「世界を司るリーダー」は、単に国家機関を指揮するだけでは足りない。歴史的使命・国民統合・国際信義・先見性・退場設計など、複合的資質が問われる。安岡正篤の理論は、まさにその複合資質を見通す枠組みを提供する。
もちろん、理論と現実は乖離を持つ。制度設計・多元主義・国際制約・技術革新など、リーダーが直面する複雑性は増すばかりである。しかし、安岡の枠組みを参照軸としながら、現代リーダー論を構築すれば、より品格ある、責任ある国家指導者像を描くことが可能になると信ずる。
本記事が、これからの時代におけるリーダー論を考える契機となれば幸いである。
📚参考文献一覧(APA第7版形式)
■ 安岡正篤関連文献
- 安岡 正篤 (1940) 東洋宰相学 金鶏学院出版部
- 安岡 正篤 (1957) 政治家と実践哲学 明徳出版社
- 安岡 正篤 (1962) 活眼活学 明徳出版社
- 安岡 正篤 (1975) 人物を修める 致知出版社
- 安岡 正篤 (1983) 安岡正篤講話録―宰相学と人間学 致知出版社
- 致知出版社編集部 (編) (2010) 安岡正篤に学ぶリーダーの条件 致知出版社
■ 日本の宰相・政治史関連
- 吉田 茂 (1957) 回想十年 新潮社.
- 中曽根 康弘 (1998) 自省録 新潮社
- 佐藤 栄作 (1965). 政治と人間 朝日新聞社
- 塩田 潮 (2007) 宰相 吉田茂 講談社
- 保阪 正康 (2014) 戦後日本の首相論 中央公論新社
■ 欧米リーダー論・政治哲学
- Churchill, W. (1948). The Second World War. Cassell & Co.
- De Gaulle, C. (1954). Mémoires de guerre. Plon.
- Roosevelt, F. D. (1933). The Public Papers and Addresses of Franklin D. Roosevelt. Random House.
- Kennedy, J. F. (1961). Profiles in Courage. Harper & Brothers.
- Reagan, R. (1990). An American Life. Simon & Schuster.
- Thatcher, M. (1993). The Downing Street Years. HarperCollins.
- Brandt, W. (1978). People and Politics. Hutchinson.
- Kohl, H. (1996). Ich wollte Deutschlands Einheit. Droemer Knaur.
■ アジア(中国を除く)リーダー史
- 金 大中 (1999) 平和への道 岩波書店.
- 李 登輝 (2004) 自由と民主主義を守るために PHP研究所.
- 朴 正煕 (1971) 国家と革命と私 時事通信社
- 蒋 介石 (1964) 中華民国建国五十年史 台湾国史館
- 馬 英九 (2012) 台湾の未来を語る 天下雑誌
■ 哲学・思想・補助文献
- 孔子 (紀元前5世紀) 論語(加地伸行 訳, 2007, 講談社学術文庫)
- 老子 (紀元前4世紀) 老子道徳経(金谷治 訳, 1984, 岩波文庫)
- マキャヴェリ, N. (1532/2009) 君主論(河島英昭 訳, 岩波文庫)
- Weber, M. (1919/2004) 職業としての政治(松井孝典 訳, 岩波文庫)
- Gardner, H. (1995) Leading Minds: An Anatomy of Leadership. Basic Books
- Burns, J. M. (1978) Leadership. Harper & Row
- Heifetz, R. A. (1994) Leadership Without Easy Answers. Harvard University Press
■ 現代的リーダーシップ理論・応用
- Goleman, D. (1998) Working with Emotional Intelligence. Bantam Books
- Senge, P. (1990) The Fifth Discipline. Doubleday
- Covey, S. R. (1989) The 7 Habits of Highly Effective People. Free Press
- Drucker, P. F. (1967) The Effective Executive. Harper & Row
- Gardner, J. W. (1990) On Leadership. Free Press
ご感想、お問い合せ、ご要望等ありましたら下記フォームでお願いいたします。
投稿者プロフィール

- 市村 修一
-
【略 歴】
茨城県生まれ。
明治大学政治経済学部卒業。日米欧の企業、主に外資系企業でCFO、代表取締役社長を経験し、経営全般、経営戦略策定、人事、組織開発に深く関わる。その経験を活かし、激動の時代に卓越した人財の育成、組織開発の必要性が急務と痛感し独立。「挑戦・創造・変革」をキーワードに、日本企業、外資系企業と、幅広く人財・組織開発コンサルタントとして、特に、上級管理職育成、経営戦略策定、組織開発などの分野で研修、コンサルティング、講演活動等で活躍を経て、世界の人々のこころの支援を多言語多文化で行うグローバルスタートアップとして事業展開を目指す決意をする。
【背景】
2005年11月、 約10年連れ添った最愛の妻をがんで5年間の闘病の後亡くす。
翌年、伴侶との死別自助グループ「Good Grief Network」を共同設立。個別・グループ・グリーフカウンセリングを行う。映像を使用した自助カウンセリングを取り入れる。大きな成果を残し、それぞれの死別体験者は、新たな人生を歩み出す。
長年実践研究を妻とともにしてきた「いきるとは?」「人間学」「メンタルレジリエンス」「メンタルヘルス」「グリーフケア」をさらに学際的に実践研究を推し進め、多数の素晴らしい成果が生まれてきた。私自身がグローバルビジネスの世界で様々な体験をする中で思いを強くした社会課題解決の人生を賭ける決意をする。
株式会社レジクスレイ(Resixley Incorporated)を設立、創業者兼CEO
事業成長アクセラレーター
広島県公立大学法人叡啓大学キャリアメンター
【専門領域】
・レジリエンス(精神的回復力) ・グリーフケア ・異文化理解 ・グローバル人財育成
・東洋哲学・思想(人間学、経営哲学、経営戦略) ・組織文化・風土改革 ・人材・組織開発、キャリア開発
・イノベーション・グローバル・エコシステム形成支援
【主な著書/論文/プレス発表】
「グローバルビジネスパーソンのためのメンタルヘルスガイド」kindle版
「喪失の先にある共感: 異文化と紡ぐ癒しの物語」kindle版
「実践!情報・メディアリテラシー: Essential Skills for the Global Era」kindle版
「こころと共感の力: つながる時代を前向きに生きる知恵」kindle版
「未来を拓く英語習得革命: AIと異文化理解の新たな挑戦」kindle版
「グローバルビジネス成功の第一歩: 基礎から実践まで」Kindle版
「仕事と脳力開発-挫折また挫折そして希望へ-」(城野経済研究所)
「英語教育と脳力開発-受験直前一ヶ月前の戦略・戦術」(城野経済研究所)
「国際派就職ガイド」(三修社)
「セミナーニュース(私立幼稚園を支援する)」(日本経営教育研究所)
【主な研修実績】
・グローバルビジネスコミュニケーションスキルアップ ・リーダーシップ ・コーチング
・ファシリテーション ・ディベート ・プレゼンテーション ・問題解決
・グローバルキャリアモデル構築と実践 ・キャリア・デザインセミナー
・創造性開発 ・情報収集分析 ・プロジェクトマネジメント研修他
※上記、いずれもファシリテーション型ワークショップを基本に実施
【主なコンサルティング実績】
年次経営計画の作成。コスト削減計画作成・実施。適正在庫水準のコントロール・指導を遂行。人事総務部門では、インセンティブプログラムの開発・実施、人事評価システムの考案。リストラクチャリングの実施。サプライチェーン部門では、そのプロセス及びコスト構造の改善。ERPの導入に際しては、プロジェクトリーダーを務め、導入期限内にその導入。組織全般の企業風土・文化の改革を行う。
【主な講演実績】
産業構造変革時代に求められる人材
外資系企業で働くということ
外資系企業へのアプローチ
異文化理解力
経営の志
商いは感動だ!
品質は、タダで手に入る
利益は、タダで手に入る
共生の時代を創る-点から面へ、そして主流へ
幸せのコミュニケーション
古典に学ぶ人生
古典に学ぶ経営
論語と経営
論語と人生
安岡正篤先生から学んだこと
素読のすすめ
経営の突破口は儒学にあり
実践行動学として儒学に学ぶ!~今ここに美しく生きるために~
何のためにいきるのか~一人の女性の死を見つめて~
縁により縁に生きる
縁に生かされて~人は生きているのではなく生かされているのだ!~
看取ることによって手渡されるいのちのバトン
など


