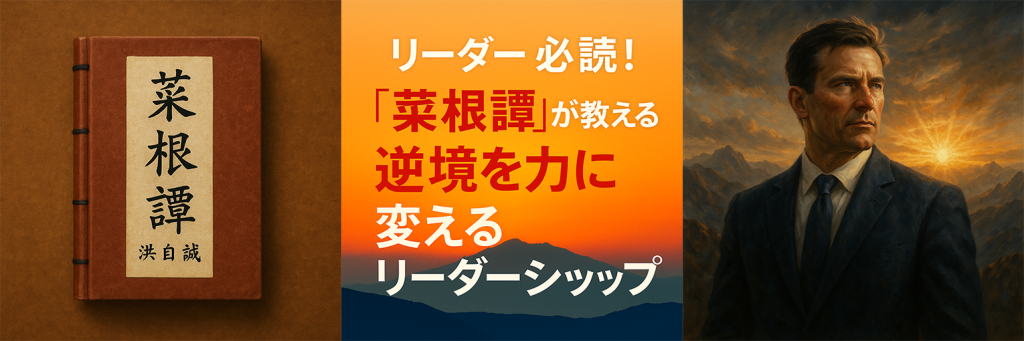
リーダー必読!『菜根譚』が教える逆境を力に変えるリーダーシップ
はじめに
ある日のことを想像してほしい。忙しない日々の中で、心はざわめき、明日の不安に押し潰されそうになる──そんなとき、ふと一冊の古典を手に取る。その本の冒頭に「咬得菜根、百事可做」と書かれている。菜の根を噛むように苦しみに耐えることができれば、あらゆることを成し遂げられる──そう告げる言葉が、不思議と胸の奥に静かな灯をともす。これが『菜根譚』の世界である。
明末清初という乱世に生きた洪自誠は、権力闘争や社会の混乱に翻弄されながらも、心の平安を求め続けた。出世や栄達に見放されながらも、彼は筆をとり、「どのように生きれば、人は心を守り、希望を見出せるのか」という普遍的な問いに答えようとした。その答えが『菜根譚』という形で残され、数百年を超えて今日まで読み継がれているのである。
私たちが生きる現代もまた、不確実で先の見えない時代だ。技術の進化は便利さをもたらす一方で、情報の洪水に心は翻弄され、働き方の加速は人を疲弊させる。グローバル社会は豊かさを広げながらも、分断や衝突を同時に生み出している。いわゆるVUCA時代──予測不能で複雑な世界において、人の心は乱世と同じように試されている。
まるで時代を越えて呼応するかのように、洪自誠の言葉は現代に生きる私たちに語りかけてくる。「静けさの中にこそ真実があり、淡泊さの中にこそ物事の本質が見える」と。成果主義に追われ、日々の競争に心を消耗させている現代人に、この言葉は大きな救いとなる。
では、洪自誠が生きた時代と現代の状況を重ね合わせてみよう。
図表0 洪自誠の時代と現代VUCAの共通点
明末清初(洪自誠の時代) 現代(VUCA時代)
────────────────────────────────
政治の腐敗・宦官の専横 政治的不信・リーダー不在
社会不安・農民反乱 国際紛争・分断の拡大
経済の混乱・飢饉 経済危機・格差拡大
異民族の侵入(明から清へ) グローバル化・価値観の衝突
────────────────────────────────
↓ ↓
不確実性・混乱の中で人間の心が試される
洪自誠はこのような乱世を前に、「外の秩序が崩れても、内の秩序を保てば人生は立つ」との信念を抱いた。彼の思想は儒教の倫理、仏教の無常観、道教の自然観を融合したものであり、ただの処世訓にとどまらず、心の修養を通じて人間らしく生きる智慧を示したのである。
現代のビジネスパーソンもまた、似たような問いに直面している。成果を上げる一方で心を守れるのか、多様性の中で他者とどう関わるのか、欲望に溺れずに持続的に働けるのか──これらはすべて、『菜根譚』が応えてきた普遍的な課題である。
そして日本において、この古典を重視した人物に安岡正篤先生がいる。戦後日本の再建期、多くの政治家や経済人が迷い、進むべき道を見失っていたとき、安岡先生は「人物を養うことこそが国を立て直す鍵である」と説き続けた。ある首相経験者が不安を口にしたとき、安岡先生は静かに『菜根譚』の一節を示し、「苦境の中こそ、人物の真価が現れるのです」と諭したという逸話が残っている。この一言が指導者の心を奮い立たせ、国の舵取りに大きな影響を与えたことは広く知られている。
安岡先生にとって『菜根譚』は、単なる古典の研究対象ではなかった。人を導く実践の書であり、人物形成の根幹をなす座右の書であった。先生が繰り返し強調した「心を養い、志を立て、人物を磨く」という思想は、まさに洪自誠の精神と響き合っている。
名句引用
- 原文:「咬得菜根、百事可做」
- 現代語訳:菜根を噛むように苦しみに耐えることができれば、あらゆることを成し遂げることができる。
本書(本稿)では、序章から第9章にかけて、『菜根譚』の言葉を現代の文脈に引き寄せながら展開していく。そこでは、歴史的背景、具体的事例、ビジネスやメンタルヘルスへの応用、そして安岡正篤先生との接点が織り交ぜられ、読者が自らの人生に引きつけて考えられるように構成されている。
古典を読むことは、過去に戻ることではない。むしろ未来に進む力を養う行為である。『菜根譚』を通して、あなたの心に静かな強さが芽生え、混乱の時代を歩むための確かな手がかりを見いだしていただきたい。
乱世を生き抜いた洪自誠がなぜ『菜根譚』を編み、どのように時代を超える智慧を遺したのか──その背景に迫ることから、私たちの旅を始めよう。
序章 なぜ今『菜根譚』なのか
- 菜根譚の定義と由来
『菜根譚(さいこんたん)』は、明末清初の儒者・洪自誠(1558〜1627)が著した処世訓であり、約600の格言から成る思想書である。その特色は、儒教・仏教・道教を折衷し、人間の心のあり方や人間関係、社会との調和を説いている点にある。「菜根」とは、野菜の根、すなわち固く味気ない部分である。それを噛むという比喩には、忍耐と内面の鍛錬を通じて人生や事業を成就させるという意味が込められている。したがって『菜根譚』は、質素さと強靭さを兼ね備えた「逆境の哲学」であると定義できる。
- 洪自誠の生涯と時代背景
洪自誠は、明朝末期の混乱期に生き、官僚として大成することはなかった。彼が直面したのは、腐敗、戦乱、異民族支配といった不安定な社会状況であった。その失意と退隠の中で記された『菜根譚』は、外的成功に恵まれずとも内面を整えることで生の意味を見出す道を提示している。彼の思想は、時代の混乱を超えて現代人にも通じる普遍的な価値をもつ。
- 現代社会に通じる理由
今日のグローバル社会は、VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)時代と呼ばれ、予測困難な状況が常態化している。多文化環境に適応し、情報過多と激しい競争を生き抜く現代のビジネスパーソンは、洪自誠が生きた混沌の時代と同じように逆境を経験している。したがって『菜根譚』の思想は、メンタルヘルスやリーダーシップの観点から現代においても強い示唆を与えるのである。
- メンタルヘルスとビジネスの接点
『菜根譚』は心の平安と倫理を同時に説く点に特色がある。「処世以誠、待人以寬(世を処するに誠を以ち、人を待つに寛を以つ)」は、現代的には心理的安全性の確保を意味する。また「澹泊以明志、寧静而致遠(淡泊にして志を明らかにし、静かにして遠きを致す)」は、短期的成果ではなく持続的ビジョンを見据える姿勢であり、現代ビジネスに通じる。心の調和と持続可能な働き方の思想を兼ね備える点で、『菜根譚』は今なお有効である。
- 安岡正篤先生と『菜根譚』
私の人生の師父である安岡正篤先生は、日本における東洋思想の大家として『菜根譚』の価値を高く評価し、多くの政治家や経営者にその精神を説いた。安岡先生は『菜根譚』を「時代と人間を貫く精神の糧」と位置づけ、指導において繰り返し引用された。先生の教えを受けた私は、『菜根譚』を単なる古典ではなく、実践哲学として理解している。安岡先生が説かれた「心を養い、志を立て、人物を磨く」三位一体の教えは、『菜根譚』の精神と響き合い、現代のビジネスパーソンにとっても生きた指針である。
- 名句紹介と解釈
- 原文:「菜根を嚼めば、百事成る」
- 現代語訳:「苦労を堪え忍び、質素を旨とすれば、あらゆることが成就する」
- 解釈:この一句は『菜根譚』の象徴であり、忍耐と内面修養を通じてこそ人生の成果が得られると説く。現代においては、短期的な快楽や即効性を求める風潮に警鐘を鳴らし、長期的な努力と堅実さが成功の基盤であることを示している。ビジネスパーソンにとっては、困難な局面を「成長の糧」と捉える発想転換を促す名句である。
第1章 乱世に咲く知恵──洪自誠と『菜根譚』
明末清初という激動の時代、洪自誠は静かに筆をとり、『菜根譚』を書き残した。彼の人生は決して華々しいものではなかった。官僚として大成することもなく、むしろ腐敗した政治と社会不安に翻弄され、失意の中で退隠することを選んだ人物である。しかし、その挫折の中でこそ、人がどう生きるべきかを問い続けた内面の輝きがあった。『菜根譚』はまさにその結晶であり、混乱する時代を生き抜くための「心の羅針盤」となったのである。
この書には儒教の倫理、仏教の無常観、道教の自然観が溶け合っている。言い換えれば、洪自誠は東アジアの精神文化を総合し、「逆境に耐え、欲を抑え、和を尊ぶ」という普遍的な人間の道を示した。例えば、彼は「外的な秩序が崩れても、内面的な秩序を保てば人生は立つ」と説いた。これは、宦官の腐敗や農民反乱に揺れた明末の社会を前にして到達した実感であると同時に、現代のビジネスパーソンにとっても胸に響く言葉である。
思えば欧州のストア派哲学においても、ローマ皇帝マルクス・アウレーリウスが『自省録』に「逆境の中にこそ人の徳は試される」と記した。遠く離れた文明で同じ発想に至っていることは、人間の真理が国や文化を超えて共通することを示している。日本においては、江戸時代の陽明学者・中江藤樹が「知行合一」を唱え、行動を通じて心を正すことを強調したが、これもまた『菜根譚』の精神と響き合う。さらにインドの仏教においては、苦悩を避けるのではなく、受け入れた上で智慧を得ることが強調されるが、それは「菜根を噛む」姿勢と同じ方向を指している。
現代のビジネスに照らせば、この思想は驚くほど実践的である。成果や地位に一喜一憂するのではなく、内面的な強さを涵養すること。単一の価値観に囚われず、多様な文化や思想を融合させること。そして短期的な利益にとどまらず、長期的な社会的価値を生み出そうとする志向。これらはまさに、グローバル社会を生き抜くための必須条件である。
安岡正篤先生は、この洪自誠の思想を日本の指導者育成に繰り返し説かれた。「人物形成は逆境を通じて完成する」との言葉は、先生ご自身が『菜根譚』を座右に置いて語られたものだ。政治家や経営者に、利欲に囚われず心を養うことを勧められた先生の姿勢は、洪自誠の精神を媒介として日本の近代指導者たちに受け継がれた。私自身も先生から『菜根譚』を単なる古典ではなく「実践哲学」として学び、その普遍性を日々実感している。
ここで一つ、よく知られた一句を紹介したい。
「寵辱不驚、閑看庭前花開花落;去留無意、漫随天外雲巻雲舒」──「栄誉や屈辱に心を乱さず、庭に咲き散る花を静かに眺め、出世や左遷に執着せず、空を流れる雲に身を任せる」。
この言葉が示すのは、栄光も挫折も一時の現象にすぎないという真理である。現代の職場においても、昇進や評価に一喜一憂せず、自らの使命に集中する姿勢が求められる。洪自誠の言葉は、時代を超えてなお生き続ける「精神の糧」なのだ。
図表1 洪自誠の思想的背景(概念整理)
明末清初の乱世
│
▼
儒教 ─ 人倫秩序・道徳
仏教 ─ 無常観・心の浄化
道教 ─ 自然との調和・柔軟性
│
▼
洪自誠の融合思想『菜根譚』
│
▼
現代社会への普遍的示唆
引用原文
- 原文:「寵辱不驚、看庭前花開花落;去留無意、望天外雲巻雲舒」
- 現代語訳:栄誉や屈辱に心を乱さず、庭に咲き散る花を静かに眺め、出世や左遷に執着せず、空に流れる雲のように身を任せる。
第2章 心を整える──菜根譚が示す静かな力
人が混乱や不安にさらされるとき、最初に乱れるのは外界ではなく心の内側である。『菜根譚』が繰り返し強調するのは、どんな状況にあっても「心を整える」ことの大切さだ。ここで言う「心を整える」とは、ただ静かに座っていることではない。激しい嵐の中にあっても、しっかりと地に足をつけ、冷静に物事を見つめ、他者に対して柔らかい態度を保つことを指す。現代心理学の言葉でいえば、これは「セルフレギュレーション(自己調整力)」であり、また「マインドフルネス」の姿勢にほかならない。
洪自誠はこう書いている。「靜中見真境、淡中識本然」──「静かな心境の中にこそ真の境地が現れ、淡泊な心でこそ物事の本質が分かる」。浮き沈みの激しい時代に生きた彼にとって、これは単なる精神論ではなく、生き延びるための必須条件であったに違いない。心を静めることができなければ、目の前の混乱に呑み込まれてしまう。だからこそ彼は「心を澄ませること」を人生の核心に据えたのである。
この思想は、現代の実践例と驚くほど重なり合う。欧米ではGoogleをはじめとする企業が、マインドフルネス瞑想を社員研修に取り入れている。目まぐるしく変化するIT業界で、心を「今ここ」にとどめる力が、創造性や冷静な判断力を引き出すからだ。日本に目を転じれば、茶道の精神「和敬清寂」がある。茶室という限られた空間で互いに敬意を払い、心を清らかに保つ営みは、まさに『菜根譚』が説く「心常放寬、事常放簡(心を広く持ち、物事を簡素にする)」の実践そのものである。またインドのヨーガも、呼吸と瞑想を通じて心を静め、外界に左右されない内なる平和を育むという点で、『菜根譚』の思想と軌を一にしている。
では、この「心を整える」という姿勢は、現代のビジネスにおいてどのような意味を持つのだろうか。第一に、ストレスマネジメントである。日々の業務やプレッシャーに呑まれそうになったとき、静かに心を鎮める習慣を持つことは、冷静な判断を取り戻す大きな助けとなる。第二に、人間関係の改善だ。「處世讓一步為高、待人寬一分是福(世を渡るには一歩を譲ることが高尚であり、人に接するには少し寛容であることが幸福をもたらす)」という名句が示す通り、心に余裕を持つことで摩擦は減り、職場の心理的安全性が高まる。第三に、意思決定の質の向上である。心を整えた状態でこそ、短絡的な判断に流されず、長期的なビジョンに基づいた決断が可能になる。そして第四に、多文化環境での適応力だ。異なる価値観と出会ったとき、心を狭くしてしまえば衝突が生まれる。しかし心を広く持てば、違いを受け入れ、協働を実現できる。
このように「心を整える」という行為は、単なる個人の幸福のためだけではない。組織の健全性、社会の安定性に直結している。ストレス社会と呼ばれる現代において、リーダーや組織開発に携わる人間にとって、この実践は欠かせないものとなっているのだ。
安岡正篤先生もまた、「人物を養うには、まず心を鎮め、志を立てることが不可欠である」と語られた。先生が重視されたのは、過剰な欲望や執着を手放し、心を澄ませること。それが人間形成の第一歩であるという教えは、『菜根譚』の精神と見事に響き合っている。現代のビジネスパーソンがこの姿勢を身につければ、ただ成果を追い求めるのではなく、心に余裕を持ちながら持続可能な成長を実現できるだろう。
結局のところ、『菜根譚』が示す「心を整える」という教えは、古代の知恵でありながら、今日のメンタルヘルスの核心を突いている。心を鎮めることは弱さではなく、むしろ最大の強さなのである。静けさの中でこそ、真実が見え、未来への確かな道が拓ける。
図表2 心を整える実践のプロセス
外界の混乱・ストレス
│
▼
心を静める(呼吸・瞑想・茶道・ヨーガ)
│
▼
内面的秩序の回復
│
▼
判断力の明晰化
│
▼
人間関係の調和/多文化環境への適応
引用原文
- 原文:「靜中見真境、淡中識本然」
- 現代語訳:心を静かにすれば真の境地が現れ、淡泊に生きれば物事の本質が見えてくる。
第3章 欲望を制御する智慧──持続可能な働き方の原点
人の心には、際限のない欲望が潜んでいる。富を求め、名誉を求め、快楽を求める心は、尽きることがない。『菜根譚』は、この欲望を敵視するのではなく、いかに調和させるかを説いている。なぜなら、欲望そのものが悪なのではなく、それに振り回されることこそが人を破滅に導くからである。洪自誠は「澹泊明志、寧静致遠(欲に淡泊であれば志は明らかになり、心静かであれば遠大な目標を実現できる)」と記し、簡素さと静けさの中にこそ長期的成功の基盤があることを示した。
この思想を現代的に言えば、それは「セルフコントロール」や「サステナビリティ的働き方」に通じる。過剰な欲望に突き動かされる生き方は、燃え尽きや不祥事を引き寄せる。しかし節度ある欲望の扱い方を学べば、個人の幸福も組織の健全さも持続可能になる。
実際に、歴史や社会に目を向ければ、この教えを体現した人物や実践は数多い。たとえばアメリカの著名な投資家ウォーレン・バフェットは、その巨万の富にもかかわらず質素な暮らしを貫いた。消費に溺れず、自らの哲学を守り続けた姿勢は、『菜根譚』の「澹泊明志」を思わせる。日本においては二宮尊徳が、勤労と倹約を説き、心を安んずることを人々に伝えた。彼の思想は、経済の発展と精神の安定を両立させる道であり、『菜根譚』の精神そのものである。さらに、アジアの小国ブータンが示した「国民総幸福量(GNH)」の政策は、経済成長だけでなく心の豊かさを優先する姿勢を世界に示した。これはまさに「欲望を制御し、心の平和を社会の基盤とする」という菜根譚的な実践例である。
現代のビジネスシーンにおいても、欲望の制御は多くの意味を持つ。第一に、ワークライフバランスを保つこと。過度な成果主義や長時間労働に囚われれば、心身は消耗し、組織全体が疲弊する。第二に、倫理的な経営と消費の実践である。企業が目先の利益に走らず、サステナブルな選択を文化に取り入れることは、長期的な信頼につながる。第三に、冷静な意思決定のためにも欲望の制御は欠かせない。感情や衝動に流されず、倫理と合理性に基づいた判断を下せるのは、心を澄ませている者だけだ。
欲望の制御を欠いたとき、社会には何が起きるだろうか。過剰な利益追求が不祥事を生み、消費主義が人を空虚にし、働きすぎが燃え尽き症候群を招く。洪自誠は「人心有欲而不除、則智慧日消;有妄而不革、則真心日昏(人の心に欲望があって抑えなければ、知恵は日に日に失われ、妄念を改めなければ真心は日に日に曇る)」と警告した。これはまさに現代社会の姿を言い当てている。
一方で、心を澄ませ、欲望を整える者は、静かに遠くを見渡せる。安岡正篤先生は「欲に溺れる者は必ず身を誤る」と戒め、政治家や経営者に対して「欲望を制御してこそ大志が貫かれる」と繰り返し説かれた。先生の教えを受けた多くの指導者は、利欲よりも使命感を軸にして時代を切り拓いた。その姿は、洪自誠の精神を現代に生きた証である。
結局のところ、欲望を制御するとは、抑圧や禁欲ではなく「心を正しく澄ませる」ことだ。「心地既良、欲念自消(心がすでに正しく澄んでいれば、欲望は自然と消える)」と『菜根譚』は語る。強引に欲を押さえ込むのではなく、心を養うことによって自然に静まっていく──その柔らかい洞察が、現代人にとって大きな示唆を与えている。
欲望に流されるのではなく、欲望を調和させて生きること。そこにこそ、持続可能で誇りある働き方の原点があるのだ。
図表3 欲望の制御と持続可能性
欲望(富・名誉・快楽)
│
─────制御できなければ─────▶ 燃え尽き・不祥事・空虚感
│
─────調和できれば────────▶ 心の平穏・持続可能な成長
引用原文
- 原文:「澹泊明志、寧静致遠」
- 現代語訳:欲に淡泊であれば志は明確になり、心が静かであれば遠大な目標に至ることができる。
第4章 人物に宿る力──『菜根譚』が示すリーダーシップの本質
リーダーシップとは何か。地位や権力を振りかざして人を従わせることだろうか。『菜根譚』が描くリーダー像は、まったく異なる。洪自誠が説くのは「利欲に囚われず、誠実と寛容を基盤に人を導く姿」である。そこには現代的なサーバントリーダーシップやトランスフォーマショナル・リーダーシップと響き合う思想が見て取れる。つまり『菜根譚』は、内面の修養を土台とした普遍的リーダーシップ論を早くも数百年前に提示していたのだ。
歴史の中には、その精神を体現した人物が数多くいる。ネルソン・マンデラはその代表だ。27年もの獄中生活を経ても報復ではなく和解を選んだ彼の姿は、『菜根譚』の「以和為貴」の思想に通じる。日本に目を向ければ、渋沢栄一が「論語と算盤」を掲げ、経済活動に倫理を組み込もうとした姿勢がある。誠実を基盤に社会と向き合った彼の姿は、洪自誠の「処世以誠」に重なる。そしてシンガポールのリー・クアンユーは、寛容さと厳格さをあわせ持ち、多民族国家をまとめあげた。彼のリーダーシップには、『菜根譚』が説く「柔軟と堅固の調和」が生きている。
現代のビジネスにおいても、この思想はそのまま実践に応用できる。リーダーに必要なのはまず謙虚さと学び続ける姿勢だ。高い地位にあっても「居高位而不驕(高位にあっても驕らず)」の心を忘れず、自らを律すること。次に、誠実な人間関係を築くこと。信頼は利欲や権威からは生まれず、誠実さからしか芽生えない。そして利他の精神を持つこと。自己の利益ではなく、組織や社会全体の利益を優先する姿勢が、人を心から動かす。さらに、短期的成果に飛びつくのではなく、持続的な安定と調和を重んじることが、リーダーとしての持続力を支える。
『菜根譚』はこう説く。「居高位者宜以濟物為心、處下位者當以安分為守(高い地位にある者は人を救い導くことを心とすべきであり、低い地位にある者は自分の分を守るべきである)」。この言葉に、リーダーの本質が凝縮されている。権力は自己のために用いるのではなく、他者のためにこそ使われるべきなのだ。
この思想は、安岡正篤先生が政治家や経営者に繰り返し伝えられたものと深く重なる。先生は「人物の器量こそがリーダーの真価である」と語り、肩書きや権力に依存しない「人物本位のリーダーシップ」を説かれた。戦後の混乱期に、日本を導いた指導者たちの多くが安岡先生から学んだことは、洪自誠の精神を現代に生き直す営みであったとも言える。
『菜根譚』のもう一つの名句を見てみよう。「居軒冕之中、不可以少驕;處患難之地、不可以少屈(高位にあっても少しも驕ってはならず、困難な境遇にあっても少しも屈してはならない)」。この一句にこそ、リーダーの真価が問われている。立場に甘んじて慢心することなく、逆境に押し潰されることもなく、謙虚さと強靭さを同時に備えること。それが、グローバル社会に生きるリーダーにとって最も重要な資質である。
現代の社会は、権威に依存するリーダーシップを次第に拒むようになり、共感と信頼を基盤とするリーダー像を求めている。『菜根譚』が説いたリーダーシップの本質は、時代を超えてなお光を放つ。リーダーがまず自らの心を整え、欲望を制御し、誠実さを保ち続けるならば、その背中は自然と人々を導く灯となるだろう。
図表4 リーダーシップの資質(『菜根譚』的視点)
高位にあっても ─── 謙虚
困難に直面しても ─ 強靭
人に接するとき ─── 誠実
組織を導く際 ─── 利他心
引用原文
- 原文:「居軒冕之中、不可以少驕;處患難之地、不可以少屈」
- 現代語訳:高い地位にあっても少しも驕らず、困難な境遇にあっても少しも屈してはならない。
第5章 異文化に橋をかける──『菜根譚』が語る人間関係の智慧
人が生きるうえで避けられないのは「人との関わり」である。どれほど才能に恵まれた人物でも、孤立しては力を発揮できない。ましてや今日のグローバル社会においては、多様な文化や価値観をもつ人々との協働が日常となっている。こうした時代において、『菜根譚』が示す「寛容・謙虚・誠実」を基盤とした人間関係の智慧は、ますます重要性を増している。
洪自誠は「處世讓一步為高、待人寬一分是福(世を渡るには一歩譲ることが高尚であり、人に接するには少し寛容であることが幸福をもたらす)」と記した。人間関係において大切なのは、勝つことでも説得することでもない。むしろ一歩引いて相手を受け入れる心の余裕が、長期的な信頼を築く鍵なのである。この姿勢は、異文化理解にもそのまま通じる。
歴史や社会を振り返ると、異文化協働の現場で『菜根譚』の精神が生きている例を数多く見出せる。国連の平和維持活動(PKO)は、多様な文化背景をもつ人々が協力し、対立を調整する現場である。そこには「寬以待人(寛容に人を待つ)」の精神が実践されている。また、日本のトヨタ自動車は海外展開において、現地文化を尊重し従業員との信頼関係を築いてきた。これは「與人方便、自己方便(人に便宜を与えれば、自らも便宜を得る)」を体現する企業文化といえる。さらに、シンガポールでは中国系・マレー系・インド系が共生し国家を発展させてきたが、そこにも寛容と和合の精神が根づいている。これはまさに『菜根譚』の哲学を社会全体に敷き詰めた姿である。
こうした考え方は、ビジネスの実践においてどのように役立つのだろうか。まず必要なのは相互尊重の姿勢である。自文化を絶対視するのではなく、相手の価値観に耳を傾けることから真の信頼が生まれる。次に、利害よりも信頼を優先すること。利害は移ろいやすいが、信頼は長期的な協力の基盤となる。そして柔軟なコミュニケーションである。相手の文化に応じた表現方法を取ることで摩擦を減らすことができる。さらに、多様性を活かすことで、新しい価値を創造できる。異なる視点を融合させることこそ、イノベーションの源泉なのである。
『菜根譚』は「寬厚之人、處世最安(心が寛大で厚い人は、世を渡るのに最も安らかである)」と語る。小さな摩擦や違いにとらわれるのではなく、相手を受け入れる心の広さが、組織や社会における信頼を生むのだ。現代的に言えば、これはダイバーシティ&インクルージョンの理念に重なる。文化や背景が異なるからこそ、互いに学び合い、新しい価値を築くことができる。
安岡正篤先生は「人間関係を円満にするのは才知ではなく、寛容と誠実である」と語られた。政治家や経営者に対して「人を受け入れる器量」を養うことの重要性を説かれたのは、まさに洪自誠の精神を継承されたものである。異文化理解の核心は、知識やテクニックではなく「心の広さ」にある──この真理は、安岡先生が強調された人物形成の教えと見事に響き合っている。
結局のところ、人間関係と異文化理解の要は「譲る心」と「受け入れる心」にある。『菜根譚』の言葉は、国や時代を超えて私たちに語りかけている。「人に便宜を与えれば、自らも便宜を得る」。それは単なる処世訓ではなく、グローバル社会を生き抜くための黄金律なのである。
図表5 異文化理解の鍵(『菜根譚』的アプローチ)
自己主張のみ ─▶ 衝突・分断
│
▼
一歩譲る ─▶ 相互尊重 ─▶ 信頼関係
│
▼
多様性の活用 ─▶ 新しい価値の創出
引用原文
- 原文:「處世讓一步為高、待人寬一分是福」
- 現代語訳:世を渡るには一歩譲ることが高尚であり、人に接するときは少し寛容であることが幸福をもたらす。
第6章 逆境を糧にする──『菜根譚』が教える強さの源泉
人生には思い通りにならない時期が必ず訪れる。病、失敗、経済的困難、社会の混乱──それらは誰もが避けたいと思うものだ。しかし『菜根譚』は、逆境を単なる不幸としてではなく、人格を磨く「砥石」として捉えよと教えている。洪自誠は「逆境之中、能安然自得者、乃真達者也(逆境の中でも安らかに自分を保つ者こそ、真の達人である)」と語り、困難の中にこそ真価が問われることを強調した。
彼の生きた明末清初の時代は、まさに社会秩序が崩れ、未来が見えない混乱の時代であった。宦官の腐敗、飢饉や反乱、異民族の侵入といった状況のなかで、洪自誠自身も栄達の道を閉ざされた。だが、その挫折の只中で彼は「外の秩序が崩れても、心の秩序を失わなければ人生は立つ」と悟ったのである。この姿勢は現代に生きる私たちにも通じる。経済危機、パンデミック、戦争や地政学的リスク──不確実性に満ちた世界で、心をどう保つかが問われている。
歴史の中には、逆境を力に変えた人物や社会の姿が数多くある。ネルソン・マンデラは27年に及ぶ獄中生活を経ても、心を失わずに和解の道を選んだ。その姿は「困難を糧に変える」現代的実践である。日本においては、敗戦後の焼け野原から立ち上がり、経済復興を遂げた人々の姿がある。共同体としての力を結集し、「困苦は人を成す」を体現した社会であった。そして韓国のIMF危機の際、国民が自らの金を寄付して国家再建に貢献した事例は、まさに集団的なレジリエンスの輝かしい例である。
現代のグローバルビジネスに目を向けても、この逆境観は応用可能だ。第一に、リーダーや組織に求められるのはレジリエンス──心理的回復力である。危機の中でも「心を失わず」に冷静さを保つことが、最も大切な資質となる。第二に、長期的視野を持つことだ。「順境でも志を失わず」という態度は、不況や失敗に直面しても、未来を見据えて進み続けるための指針となる。第三に、共同体の力を重視すること。逆境は個人だけでなく、組織や社会全体の強さを鍛える。共感と協力を基盤とする文化は、危機を乗り越える大きな原動力になる。
『菜根譚』はさらに警告する。「困苦能玉汝、亦能毀汝(困難は君を磨くこともあれば、君を滅ぼすこともある)」。逆境は人を成長させもすれば、押し潰しもする。その分岐点は、心の持ちようにある。これは現代心理学のPTG(心的外傷後成長)の考え方にも通じている。苦難をどう意味づけるかによって、その後の人生が変わるのだ。
安岡正篤先生もまた「人物は逆境において真価を問われる」と繰り返し語られた。先生は指導の場で『菜根譚』を引用し、「困難を避けるのではなく、逆境を力に変える心構え」を説かれた。戦後の国難や企業経営の危機にあっても、先生の薫陶を受けた多くのリーダーが『菜根譚』を支えとした。洪自誠の逆境観は、安岡先生の思想を通じて日本の近代史の中にも息づいている。
「居憂患之地、常以樂觀自處(憂いや困難の中にあっても、常に楽観的に対処する)」という言葉が示すように、逆境に対して悲観するのではなく、むしろ楽観の心で向き合うことが大切だ。冷静さと楽観は、困難を突破する両輪である。
結局のところ、逆境は人を試し、磨く場である。恐れるべきものではなく、鍛錬の場として受け入れるべきものなのだ。『菜根譚』の精神を身につけたビジネスパーソンは、困難を避けるのではなく、堂々と向き合い、そこから力を引き出すことができるだろう。逆境を糧にできる者こそ、未来を拓く真のリーダーなのである。
図表6 逆境と成長の関係
逆境に直面
│
▼
心を失う ───▶ 崩壊・停滞
心を保つ ───▶ 成長・人格の完成
引用原文
- 原文:「逆境之中、能安然自得者、乃真達者也」
- 現代語訳:逆境の中にあっても安らかに自分を保てる者こそ、真の達人である。
第7章 グローバル舞台で生きる智慧──『菜根譚』の実践ケーススタディ
『菜根譚』は古典でありながら、その精神は現代のグローバルビジネスに驚くほど応用できる。国境を越えて働く人々は、日々異文化と接し、価値観の衝突に直面する。その時に求められるのは、知識や技術だけではなく「心の姿勢」である。洪自誠が示した心の持ちようは、実務の現場において生きた羅針盤となる。
まず注目すべきは、「処世以誠(世を渡るには誠をもってする)」という姿勢である。グローバルビジネスでは契約や数字が重視される一方で、根底に流れるのは「信頼関係」だ。信頼なくして長期的なパートナーシップは成り立たない。例えば、日本企業が欧州企業と提携する際、短期的利益よりも誠実な対応を続けることで関係を築き上げ、長期的に成功を収めた事例がある。誠実さは、文化を超える普遍的な価値なのである。
第二に、「和を尊ぶ」姿勢である。『菜根譚』は「和気致祥、乖気致戾(和やかさは吉をもたらし、不和は災いを招く)」と説く。これは単なる人間関係論ではなく、組織運営や異文化マネジメントに直結する。アジアの多国籍企業において、経営層が文化間の違いを調整し、和を保つことに力を注いだ結果、現場での摩擦が減り、生産性が高まったという事例がある。逆に、和を軽んじて対立が放置されると、組織はすぐに瓦解する。
第三に、「欲望の制御」である。グローバル市場は常に競争が激しく、企業も個人も成果を追い求めがちだ。しかし、過度な拡大や利益至上主義はリスクを伴う。『菜根譚』は「澹泊明志、寧静致遠」と語り、節度のある欲望の扱い方を示した。シリコンバレーの一部企業が「社員の幸福度」を重視し、成果主義一辺倒から脱却しつつある流れは、この精神と重なる。心を整えた経営こそ、持続可能な成功をもたらす。
実際のケーススタディをさらに見てみよう。
- 欧州の製薬企業は、アジア市場への進出に際して現地文化を尊重し、地域の人々と共に社会貢献活動を展開した。その結果、単なる「外資企業」ではなく「地域社会の仲間」として信頼を得た。これは「與人方便、自己方便(人に便宜を与えれば、自らも便宜を得る)」の実践例である。
- 日本の自動車メーカーは、現地工場で従業員の生活習慣を尊重しつつ、品質管理の理念を根気強く共有した。その結果、文化の違いを超えて一体感のある生産体制を築き上げた。これは「寛厚之人、處世最安」の実践であり、異文化協働の成功例といえる。
- アジアのスタートアップでは、創業者が短期的利益に走らず、社員の成長と幸福を優先したことで、長期的に優秀な人材を引き寄せることができた。これは「欲念を制御すれば、志は遠くに届く」という洪自誠の教えを体現している。
ここから浮かび上がるのは、グローバルビジネスにおいて『菜根譚』の教えは抽象論ではなく、実際の行動規範として役立つという事実である。信頼、和、節度──これらはどの文化でも通じる「人間の根本」であり、時代や国境を超える力を持つ。
安岡正篤先生もまた、国際社会における日本のリーダーには「徳と器量をもって世界と向き合うべし」と説かれた。単なる技術や経済力ではなく、誠実さ・寛容さ・志の高さがあってこそ、真に尊敬される国際的リーダーが育つ。これはそのまま、個々のビジネスパーソンにも当てはまる言葉である。
『菜根譚』が示す普遍的な智慧は、グローバル社会で働く我々に「どう振る舞えば人は信頼し、協力してくれるのか」を具体的に教えてくれる。異文化の摩擦を恐れるのではなく、それを越えて信頼を築き、新たな価値を共に創造すること。そこにこそ、現代における『菜根譚』の真の応用がある。
図表7 グローバルビジネスと『菜根譚』の三原則
誠実 ─▶ 信頼の構築
和合 ─▶ 異文化協働
節度 ─▶ 持続可能性
引用原文
- 原文:「和氣致祥、乖氣致戾」
- 現代語訳:和やかさは吉をもたらし、不和は災いを招く。
第8章 現代に甦る智慧──安岡正篤と『菜根譚』の意義
『菜根譚』は中国で生まれた書物であるが、その精神を近代日本に橋渡しした人物こそ、思想家・安岡正篤である。安岡先生は戦前から戦後にかけて、多くの政治家・経営者を導き、日本の思想的基盤を支えた。彼の思想形成の中心にあったのが、『論語』や『大学』と並んで『菜根譚』であった。
安岡先生が『菜根譚』を重視された理由は明快である。人間の本質はどれほど社会や技術が変化しても変わらない。その人間の心を耕し、欲望を調え、誠実を基盤にする道を説いた古典は、時代を超えて人を育てる「心の教科書」になると信じられていたからである。先生は政治家に「政策以前に人物を磨け」と語り、経営者に「利益以前に人間力を養え」と説いた。これはまさに『菜根譚』の精神を、近代日本の指導者教育に実践された例である。
実際、戦後の日本を背負った多くの政治家や経営者は、安岡先生から『菜根譚』を通じた薫陶を受けた。たとえば経済復興の時代を支えた実業家たちは、物質的繁栄だけを追うのではなく、精神的基盤の重要性を学び取った。政治家たちもまた、利欲や権勢欲に呑まれるのではなく「人物本位」で国家を導くべきだと教えられた。先生の言葉は単なる訓話ではなく、具体的な政治・経営の場で生きた指針となったのである。
安岡先生は『菜根譚』を「人物を養う書」と呼んだ。その背景には「人材教育の本質は知識の詰め込みではなく、心の涵養にある」という信念があった。たとえば『菜根譚』の一句、「處世讓一步為高、待人寬一分是福(世を渡るには一歩譲ることが高尚であり、人に接するには少し寛容であることが幸福をもたらす)」を引き合いに出し、リーダーには寛容と謙虚さが不可欠であると説かれた。これは単なる理想論ではなく、権力や経済的利害の渦中にあっても揺るがない「人物形成の中核」として位置づけられたのである。
この思想は現代のグローバル社会においても鮮やかに通用する。多文化社会では、強権的リーダーシップでは長続きしない。寛容と誠実を基盤としたリーダーこそ、人々の信頼を集める。さらに、AIやテクノロジーが進化する時代だからこそ、知識や情報だけではなく「人物の力」が問われる。誠実さ、節度、信頼構築力──これらは時代や文化を超えて通用する普遍的な力である。
『菜根譚』の精神を現代に活かすにはどうすればよいのだろうか。第一に、日常の中で「心を調える習慣」を持つこと。瞑想や読書、茶道のような静かな実践を通じて、心を落ち着ける時間を確保する。第二に、異文化に出会ったときにこそ「一歩譲る」姿勢を取ること。相手を理解しようとする柔らかさが、協働の扉を開く。第三に、組織経営において「短期的利益よりも長期的信頼」を優先すること。これは洪自誠が説き、安岡先生が繰り返し強調された教えでもある。
結局のところ、安岡正篤先生が『菜根譚』を重視されたのは、それが単なる古典解釈にとどまらず、現実の行動を変える「生きた哲学」だったからである。政治、経済、教育、国際関係──どの領域においても、この智慧は普遍的に応用できる。
「人物を養わずして、真のリーダーシップは成立しない」。安岡先生のこの言葉を噛みしめるとき、『菜根譚』の現代的意義はますます明らかになる。古典に学ぶことは過去に戻ることではない。むしろ未来を切り拓くための力を得ることなのだ。
図表8 安岡正篤が重視した『菜根譚』の要点
人物形成 ─ 心の涵養を第一とする
リーダー教育 ─ 利欲よりも人物本位
国際的視野 ─ 誠実・寛容を基盤にする
引用原文
- 原文:「處世讓一步為高、待人寬一分是福」
- 現代語訳:世を渡るには一歩譲ることが高尚であり、人に接するときは少し寛容であることが幸福をもたらす。
第9章 終章──現代人へのメッセージ
私たちは今、かつてないほど豊かで便利な社会に生きている。テクノロジーは生活を加速させ、情報は瞬時に世界を駆け巡る。しかし同時に、人の心は疲弊し、社会は分断され、未来への不安が増大している。目まぐるしい競争の中で、自分を見失い、心を摩耗させる人も少なくない。まさにこの時代にこそ、『菜根譚』の声に耳を傾ける意味がある。
洪自誠は「寵辱不驚、看庭前花開花落;去留無意、望天外雲巻雲舒」と記した。「栄誉や屈辱に心を乱されず、花の咲き散るのを静かに眺め、去就に執着せず、空に流れる雲を見守る」。この言葉は、移ろいゆくものに心を揺らさず、本質を見据える生き方を教えている。現代の人々にとって、それは「成果や地位にとらわれず、心の静けさを取り戻す」ことにほかならない。
この古典の智慧は、メンタルヘルスの観点からも極めて実践的である。過剰なストレスに押しつぶされるのではなく、一歩引いて物事を眺める姿勢。欲望に翻弄されるのではなく、節度を持って調和を保つ習慣。そして人間関係においては、勝ち負けにこだわらず、相手を受け入れる柔らかさ。これらはすべて、現代心理学が推奨する「レジリエンス」「マインドフルネス」「セルフコンパッション」と深く響き合っている。
また、『菜根譚』はリーダーやビジネスパーソンにとっても指南書である。グローバル社会で成功するには、単なる技術や戦略ではなく、「心の力」が不可欠だ。誠実さによって信頼を築き、寛容さによって異文化を橋渡しし、節度によって持続可能な道を選ぶ。洪自誠の言葉は、まさに現代のリーダーシップに必要な資質を凝縮している。
そして安岡正篤先生が繰り返し強調されたように、『菜根譚』は「人物を養う書」である。社会を導くのは制度や仕組みだけではなく、そこに立つ人物の器量である。人物を養うには、古典を学び、日々心を整え、逆境に耐え、誠実を貫くほかない。先生の言葉を借りれば、「古典は人を過去に縛るのではなく、未来に解き放つ」のである。
読者であるあなたに最後に問いかけたい。今、あなたは心を整え、欲望を調和させ、誠実に人と向き合えているだろうか。もし日々の忙しさに追われているなら、『菜根譚』の一節を手にとってみてほしい。そこには、明末の乱世を生き抜いた洪自誠の声が、時代と国境を越えて届いている。
「咬得菜根、百事可做」──「菜根を噛むように苦しみに耐えれば、すべてのことを成し遂げられる」。
この一句こそ、現代人への最大のメッセージである。苦難に耐える強さと、心を養う静けさ。その両輪があれば、私たちはどんな不確実な時代も生き抜くことができる。
古典の智慧は決して過去の遺物ではない。それは未来を切り拓く「心の羅針盤」である。『菜根譚』を胸に抱きながら、あなた自身の人生を力強く、そして静かに歩んでいってほしい。
図表9 現代人へのメッセージ(『菜根譚』的視点)
成果や地位に囚われる ─▶ 心の摩耗・不安
心を整え誠実に生きる ─▶ 安定・幸福・信頼
引用原文
- 原文:「咬得菜根、百事可做」
- 現代語訳:菜根を噛むように苦しみに耐えられれば、あらゆることを成し遂げることができる。
参考文献一覧(APA形式)
古典・原典
- 洪, 自誠. (1999). 菜根譚. 岩波文庫. (原著は明末清初)
- 論語. (2007). 論語. 岩波文庫. (孔子による言行録)
日本における研究・思想
- 安岡正篤 (1971) 活学としての東洋思想 明徳出版社
- 安岡正篤 (1982) 人物を修める 致知出版社
- 王建華 (2005) 『菜根譚』研究 東方書店
- 中村元 (2002) 東洋の思想 講談社学術文庫
メンタルヘルス・リーダーシップ・異文化関連
- Ivanhoe, P. J. (2019). Confucian Reflections: Ancient Wisdom for Modern Times. Routledge.
- Nisbett, R. E. (2004). The Geography of Thought: How Asians and Westerners Think Differently… and Why. Free Press.
- Seligman, M. E. P. (2011). Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being. Free Press.
- Luthans, F., & Youssef-Morgan, C. M. (2017). Psychological Capital and Beyond. Oxford University Press.
- Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations: Software of the Mind (3rd ed.). McGraw-Hill.
比較思想・応用的文献
- 和辻, 哲郎. (2007). 風土: 人間学的考察. 岩波文庫.
- Marcus Aurelius. (2006). Meditations (M. Hammond, Trans.). Penguin Classics. (原著2世紀)
- Frankl, V. E. (2006). Man’s Search for Meaning. Beacon Press.
ご感想、お問い合せ、ご要望等ありましたら下記フォームでお願いいたします。
投稿者プロフィール

- 市村 修一
-
【略 歴】
茨城県生まれ。
明治大学政治経済学部卒業。日米欧の企業、主に外資系企業でCFO、代表取締役社長を経験し、経営全般、経営戦略策定、人事、組織開発に深く関わる。その経験を活かし、激動の時代に卓越した人財の育成、組織開発の必要性が急務と痛感し独立。「挑戦・創造・変革」をキーワードに、日本企業、外資系企業と、幅広く人財・組織開発コンサルタントとして、特に、上級管理職育成、経営戦略策定、組織開発などの分野で研修、コンサルティング、講演活動等で活躍を経て、世界の人々のこころの支援を多言語多文化で行うグローバルスタートアップとして事業展開を目指す決意をする。
【背景】
2005年11月、 約10年連れ添った最愛の妻をがんで5年間の闘病の後亡くす。
翌年、伴侶との死別自助グループ「Good Grief Network」を共同設立。個別・グループ・グリーフカウンセリングを行う。映像を使用した自助カウンセリングを取り入れる。大きな成果を残し、それぞれの死別体験者は、新たな人生を歩み出す。
長年実践研究を妻とともにしてきた「いきるとは?」「人間学」「メンタルレジリエンス」「メンタルヘルス」「グリーフケア」をさらに学際的に実践研究を推し進め、多数の素晴らしい成果が生まれてきた。私自身がグローバルビジネスの世界で様々な体験をする中で思いを強くした社会課題解決の人生を賭ける決意をする。
株式会社レジクスレイ(Resixley Incorporated)を設立、創業者兼CEO
事業成長アクセラレーター
広島県公立大学法人叡啓大学キャリアメンター
【専門領域】
・レジリエンス(精神的回復力) ・グリーフケア ・異文化理解 ・グローバル人財育成
・東洋哲学・思想(人間学、経営哲学、経営戦略) ・組織文化・風土改革 ・人材・組織開発、キャリア開発
・イノベーション・グローバル・エコシステム形成支援
【主な著書/論文/プレス発表】
「グローバルビジネスパーソンのためのメンタルヘルスガイド」kindle版
「喪失の先にある共感: 異文化と紡ぐ癒しの物語」kindle版
「実践!情報・メディアリテラシー: Essential Skills for the Global Era」kindle版
「こころと共感の力: つながる時代を前向きに生きる知恵」kindle版
「未来を拓く英語習得革命: AIと異文化理解の新たな挑戦」kindle版
「グローバルビジネス成功の第一歩: 基礎から実践まで」Kindle版
「仕事と脳力開発-挫折また挫折そして希望へ-」(城野経済研究所)
「英語教育と脳力開発-受験直前一ヶ月前の戦略・戦術」(城野経済研究所)
「国際派就職ガイド」(三修社)
「セミナーニュース(私立幼稚園を支援する)」(日本経営教育研究所)
【主な研修実績】
・グローバルビジネスコミュニケーションスキルアップ ・リーダーシップ ・コーチング
・ファシリテーション ・ディベート ・プレゼンテーション ・問題解決
・グローバルキャリアモデル構築と実践 ・キャリア・デザインセミナー
・創造性開発 ・情報収集分析 ・プロジェクトマネジメント研修他
※上記、いずれもファシリテーション型ワークショップを基本に実施
【主なコンサルティング実績】
年次経営計画の作成。コスト削減計画作成・実施。適正在庫水準のコントロール・指導を遂行。人事総務部門では、インセンティブプログラムの開発・実施、人事評価システムの考案。リストラクチャリングの実施。サプライチェーン部門では、そのプロセス及びコスト構造の改善。ERPの導入に際しては、プロジェクトリーダーを務め、導入期限内にその導入。組織全般の企業風土・文化の改革を行う。
【主な講演実績】
産業構造変革時代に求められる人材
外資系企業で働くということ
外資系企業へのアプローチ
異文化理解力
経営の志
商いは感動だ!
品質は、タダで手に入る
利益は、タダで手に入る
共生の時代を創る-点から面へ、そして主流へ
幸せのコミュニケーション
古典に学ぶ人生
古典に学ぶ経営
論語と経営
論語と人生
安岡正篤先生から学んだこと
素読のすすめ
経営の突破口は儒学にあり
実践行動学として儒学に学ぶ!~今ここに美しく生きるために~
何のためにいきるのか~一人の女性の死を見つめて~
縁により縁に生きる
縁に生かされて~人は生きているのではなく生かされているのだ!~
看取ることによって手渡されるいのちのバトン
など


