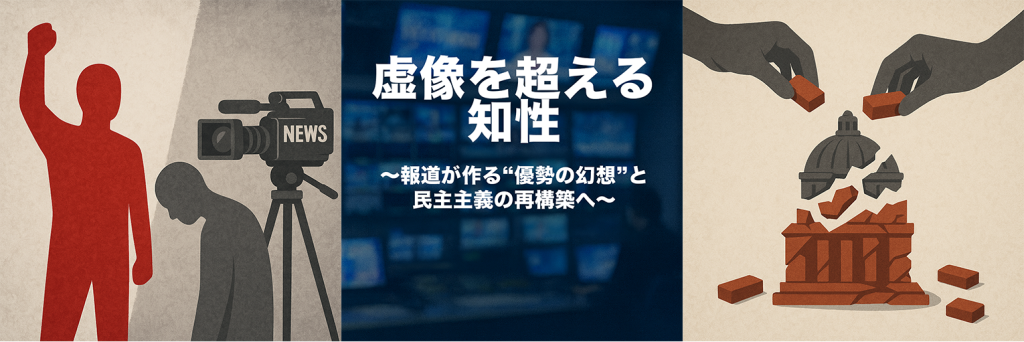
虚像を超える知性 〜報道が作る“優勢の幻想”と民主主義の再構築へ〜
序章 虚像を超える知性を求めて
私たちは、いまどんな「現実」を見ているのだろうか。ニュースが伝える出来事、SNSが拡散する意見、専門家のコメント──
それらは確かに“情報”である。だが、その情報はすでに誰かの手によって選ばれ、整えられ、意味づけられた「構成された現実」である。報道とは、単に出来事を伝える透明な窓ではなく、現実そのものを“編集し、再設計する力”を持つ社会的装置である。
その装置が正しく機能するなら、民主主義は健全に維持される。しかし、その装置が歪み始めると、真実はいつしか虚像に置き換えられる。人々が「誰が勝ちそうか」「どちらが正しいか」と語るとき、その判断の多くは、実はメディアによってつくられた“印象の地図”の上に立脚している。
この“印象の地図”が現実を上書きする現象こそが、本稿の主題である「虚像の優勢(Pseudo-Advantage)」である。
虚像の優勢とは何か
「虚像の優勢」とは、報道によって作られた“有利な印象”が、現実の力関係を凌駕し、社会の判断を支配してしまう現象である。報道が一人の政治家、企業、あるいは思想を“時代の象徴”として持ち上げると、その演出が事実の裏づけを超えて社会に信じ込まれていく。その結果、「見せられた勝者」が“実際の勝者”を上書きしてしまう。この現象は、一見報道の副作用のように見えるが、実は現代のメディア構造そのものに内在する認知的・制度的メカニズムである。
虚像を生む構造──2025年総裁選の警鐘
2025年10月、自民党総裁選で展開された「進次郎優勢」報道は、まさに虚像の優勢が可視化された瞬間だった。主要メディアが一斉に「若さ」「改革派」「共感力」といったイメージを増幅し、国民の間には「勝ち馬は決まった」という空気が広がった。しかし結果は、高市早苗氏の勝利──つまり、“報道の物語”と“現実”の乖離である。この出来事は、虚像の優勢が単なるメディア現象ではなく、民主主義そのものを脆弱化させる構造的問題であることを明らかにした。
本稿の目的と構成
本稿の目的は、報道批判にとどまらない。報道と民主主義の関係を「対立」ではなく「共進化」として再定義し、虚像の時代を生き抜く知的防衛力=〈虚像を超える知性〉を提示することである。そのために、本稿では理論・事例・構造・倫理・再生という五つの軸から、報道の生成・影響・克服を体系的に検証する。
第1章 虚像が優勢になるメカニズム
メディアがどのように「虚像」を生成するのかを分析する章である。編集・選択バイアス、フレーミング、専門家権威の演出、反復報道、数字による“優勢の錯覚”といった具体的メカニズムを抽出し、それらが組み合わさることで社会的認識を歪めていく過程を明らかにする。
第2章 虚像の優勢が生まれる事例
実際の社会・政治・文化の中で「虚像の優勢」がどのように現れるかを描く。落合陽一氏の“天才像”、宝塚歌劇団の“清純神話”、トランプ元大統領の“成功者演出”などを取り上げ、メディアがどのように人物・組織・国家像を演出し、それがどのように社会的信念へと変化していくのかを検証する。
第3章 虚像優勢の社会的リスク
虚像が社会に浸透したとき、どのような副作用が生まれるのかを考察する。判断の歪み、説明責任の欠如、批判の抑制、メディア不信の拡大、そして民主主義の形骸化。この章では、社会心理学と政治社会学の観点から、虚像がもたらす“統治の危うさ”を分析する。
第4章 虚像を克服するための道筋
単なる批判ではなく、解決への道を探る章である。教育における批判的メディアリテラシーの導入、報道倫理の再構築、制度的透明性の確保、AI・テクノロジーによる検証手段の強化などを提案する。虚像を打ち破るのは、報道を拒絶することではなく、報道を「読み解く力」を持つ市民であると位置づける。
第5章 2025年自民党総裁選の分析
実際に「虚像の優勢」がどのように政治報道で作用したのかを、2025年総裁選をケーススタディとして具体的に検証する。報道構成・世論調査・映像演出・専門家解説などを比較分析し、報道の“構造的偏向”と“現実との乖離”を明らかにする。
第6章 報道が作る“虚像優勢”の構造
主要メディアの報道記事を比較し、どのように「下馬評→専門家解説→露出偏重→ネガティブ演出」という一連の報道サイクルが形成されるのかを、構造表・因果関係マップとして可視化する。
この章は第7章で展開する理論モデルへの架け橋となる。
第7章 虚像優勢モデル(5段階循環モデル)
本論の理論的中心。
報道がどのように虚像を構築し、維持し、崩壊後に再生産するのかを「Agenda Setting」「Framing」「Spectacle」「Pseudo-Consensus」「Narrative Resilience」の5段階で体系的にモデル化する。これにより、報道現象を単なるミスではなく、再帰的メディア構造として理解する枠組みを提示する。
第8章 虚像優勢の影響と限界
報道が作り出す虚像が社会に及ぼす影響を整理すると同時に、なぜその虚像が永続できないのか──
現実が虚構を凌駕する瞬間とは何かを考察する。批判的思考、組織的抵抗、情報公開など、虚像を打ち消す社会的要因についても分析する。
終章 メディアと民主主義の再構築へ
結論部では、虚像の優勢を超えるために必要な倫理・教育・構造改革・思想的成熟を総合的に論じる。AI時代の報道と民主主義の“共進化”を提言し、市民が自らの思考で虚像を超える知性を育む道を示す。
読者への呼びかけ
本稿は、単なるメディア批判でも政治論文でもない。それは、「報道とは何か」「真実とは何か」を、社会全体がもう一度問い直すための知的挑戦である。報道の光がときに虚像を照らし出すなら、その影を見抜く力こそが、成熟した民主主義の証である。
虚像の時代を生きる私たちに必要なのは、「信じる力」ではなく、「見抜く力」である。そしてその力こそ、虚像を超える知性なのだ。
第1章 虚像が優勢になるメカニズム
虚像の優勢が生まれる背景・プロセスには、以下のような要素が関わる。
要因 | 内容 |
編集・選択バイアス | 取材対象、視点、発言を選ぶ段階で、「目立つもの」「ドラマ性のあるもの」「強さを感じさせるもの」が優先されやすい。 |
フレーミング効果 | どういう枠組み・切り口で報道するか(見出し・キャッチコピー・写真・配置など)により、印象を操作できる。 |
想像・演出 | 背景情報を補完したり、象徴的な映像や言葉を付け加えたりすることで、実際よりも格好よく、影響力あるように見せる。 |
専門性・難解性の装飾 | 内容を難しく語ることで、「深い知見を持っている」のように錯覚させる。 |
反復・拡散 | 同じイメージが繰り返されることで、読者・視聴者の記憶に刷り込まれる。 |
権威との結びつき | 権威ある人物(学者、政治家、著名人など)を持ち出す、肩書きを強調することで信頼性を担保するように見せる。 |
無批判受容・共犯性 | 受け手自身が検証を放棄し、印象をそのまま受け入れてしまう(「すごそう」「正しそう」と思ってしまう)ことも要因となる。 |
このような作用を通じて、虚像が徐々に現実の「強さ」や「優勢」として扱われるようになる。
第2章 虚像の優勢が生まれる事例
いくつか実際に指摘されている事例を挙げる。
- 落合陽一の「天才イメージ」
日本でメディアによって持ち上げられ、「テクノロジー × 芸術 × 思想の融合者」などという語られ方をされてきた著名人に関して、「実際の研究や成果とイメージとの乖離」が批判されるケースがある。メディアが“わかりにくい語り”や象徴性を前面に押し出すことで、内容よりも印象が先行するという批判がなされている。 (note(ノート)) - 芸能・アイドル・劇団の「美談・清純イメージ」
例えば、宝塚歌劇団などの芸能界において、長年にわたり美しい物語・清楚なイメージが強調され、内部の問題(いじめ、パワハラ等)が表に出にくくされてきた、という批判がある。報道機関がその清らかな虚像を強化してきたという指摘もある。 (PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)) - 政治家・権力者のイメージ操作
政治家がメディアと戦略的に結びつき、ポジティブなイメージを拡散させる手法も、虚像の優勢を作り出す典型である。演出された姿(演説・演出映像・ビジュアル戦略など)が、実際の政策や行動よりも先行して認識されることがある。 - テレビ番組・リアリティ番組による創作
たとえば、アメリカのトランプがテレビ番組 The Apprentice を通じて「成功者・ビジネス界のスター」としてのイメージを広めたという指摘がある。番組プロデューサー自身が、番組上の描写はかなり演出されたものだったと後に認めた例もある。 (Business Insider Japan)
このように、エンタメ性と現実の区別が曖昧になることで、虚像が実像とされるケースが生まれる。
第3章 虚像優勢の社会的リスク
このような現象には、次のような問題点がある。
- 判断の歪み・誤認
人々が虚像を実像と信じ、それに基づいて評価・選択(支持・投票・消費など)をしてしまうと、本来の実態を無視したまま意思決定がなされる。 - 権力の補強
虚像を持たされた人物や集団が、イメージを盾に批判を防ぐ、説明責任を回避する、実績が乏しくても支持を得続けるといった状態になりうる。 - 批判/異論の抑制
虚像を崩す行為は、既得権益者にとって敵対行為になりやすく、メディアや権力が批判的視点を封じようとする動機になる。 - メディア信頼性の低下
虚像が露見したとき、報道そのものへの不信が広がる。特に「裏側を見せなかった/隠していた」という批判を招きやすい。 - 民主主義への悪影響
有権者が虚像を基に判断し、健全な公開的議論や検証を通じないまま思想・政策が選ばれると、民主的なガバナンスがゆがむ可能性がある。
第4章 虚像を克服するための道筋
虚像の優勢が社会に及ぼす害を軽減・防ぐためには、以下のようなアプローチが考えられる。
- メディアリテラシーの向上
受け手が「情報を鵜呑みにしない」「編集・演出の可能性を疑う」視点を持つこと。見出しだけで判断せず、本質・根拠を問い直す習慣を育てる。 - 多様な情報源利用・クロスチェック
複数のメディア、異なる立場の報道、専門的な分析を参照し、比較・検証する。 - 透明性・説明責任の強化
報道機関自身が、取材方法・編集意図・資料・反対意見も含めて開示する姿勢を持つこと。 - 批判的メディア・ジャーナリズムの強化
既存メディアの枠を超える、異分野・市民・独立系メディアなどが検証報道・調査報道を担う。 - 制度的なチェック機構
メディアのガバナンス、第三者監視機関、編集倫理規定、記者クラブ制度の見直しなど、構造的な制度改革も必要。
第5章 2025年自民党総裁選の分析:虚像と実像の乖離
日本のメディア論・報道倫理の文献をもとに、「虚像の優勢」が特に日本社会でどのように作用してきたか、2025年10月4日に行われた自由民主党の総裁選挙を取り上げ分析・展開を試みる。
2025年10月4日に実施された自由民主党(自民党)の総裁選挙は、政界・党内の力学、政策論争、将来シナリオの提示など多くの読みどころを含むものとなった。以下、構造・経緯・結果・意義・課題・展望という視点から分析・展開を試みる。
(ただし、本情報は公開報道・報道分析に基づくものであり、党内非公表情報・裏事情までは保証できない)
背景・前提条件
まず、この総裁選挙が行われるに至った背景を押さえておく。
- 石破茂総裁/首相が、9月7日に辞意表明をしました。これを受けて、自民党は後任の総裁選を実施することとなった。 (NRI)
- 2025年参議院選挙での自民・公明連立与党の苦戦・不振が、党内での反省・刷新機運を高めていた。 (東洋経済オンライン)
- 野党勢力の台頭、浮動票の動向、世論の冷めた目など、従来の自民党支配構造への疑問が強まっているという声も報じられていた。 (東洋経済オンライン)
- 総裁選の方式は「フルスペック方式」(国会議員票+党員・党友票)を採用すると決定されていた。 (テレ朝NEWS)
この方式は、党員票(=党員・党友の意向)を反映させつつ、決選では国会議員票が相対的に重くなるという性格を持ち、候補者は党内組織動員と議員支持双方に配慮しなければならない構造である。
また、有権者・メディアは、「自民党刷新」「自民党を立て直す総裁を望む」という声を無意識に期待しており、候補たちは「新しさ」「改革色」「バランス感覚」「安定感」などをいかにアピールするかが問われていた。 (東洋経済オンライン)
候補者構成と支持基盤・強み・弱み
総裁選に出馬した候補者は5名でした(最終的には上位2名が決選に進出):
高市早苗、小泉進次郎、林芳正、小林鷹之、茂木敏充。 (ウィキペディア)
それぞれの候補について、報道上の見方・評価を整理する。
候補者 | 想定支持基盤・アピール点 | 弱点・リスク要因 |
高市早苗 | 保守派支持、前回総裁選での経験、右派・強硬派色・安定的主張をアピール。女性初総裁という話題性。 | 過激あるいは右傾色を懸念する層との乖離、党員票での支持を維持できるか(全国党員基盤) |
小泉進次郎 | 若手/中道色、柔軟なイメージ、ある世代からの支持を取りやすい可能性 | 党内基盤・派閥支持の弱さ、政策立案力・実行力への疑念 |
林芳正 | 官房長官経験、行政運営能力、調整力をアピールできるポジション | 強烈な支持基盤薄さ、知名度・メッセージの訴求力の弱さ |
小林鷹之 | 経済安全保障分野での主張、特定テーマでの評価を狙える | 全国的認知の低さ、党員票動員力の限界 |
茂木敏充 | 党内実績、経験、人脈 | 新鮮味のなさ、目立つ主張が弱い、支持伸長力の限界 |
報道上も「5人の候補者たちが見落としている点」を指摘する記事があり、政策論点、改革志向、連立・少数政権対応能力などが争点になっているとの分析が出されている。 (東洋経済オンライン)
また、支持層の違いを注視する報道もありました。たとえば、若年層・中道層は進次郎寄りという見方、保守・地方基盤層は高市支持傾向、など。 (選挙ドットコム)
選挙直前時点で報じられていた支持構図は、有力な重鎮・派閥の動きにも注目されており、特に麻生派(麻生太郎元副総理を中心とする派閥)が、もし高市が決選に進めば支持するという指示を出しているという報道もあった。 (ウィキペディア)
投票結果・数字・顛末
総裁選の結果は、次のように報じられている(表は報道・ウィキペディア参照):
- 第1回投票(国会議員票 vs 党員・党友票加重)
高市早苗: 国会議員票 64、党員票から換算 119 → 合計 183票
小泉進次郎: 国会議員票 80、党員票 84 → 合計 164票
林芳正: 72 + 62 = 134票
小林鷹之: 44 + 15 = 59票
茂木敏充: 34 + 15 = 49票
(計 第1回:589票、有効投票) (ウィキペディア) - 過半数(296票超)に達する候補はなく、上位2名(高市、小泉)が決選投票へ進出。 (ウィキペディア)
- 決選投票(国会議員票 + 都道府県連票 47票)
高市早苗: 国会議員票 149、都道府県票 36 → 合計 185票
小泉進次郎: 国会議員票 145、都道府県票 11 → 合計 156票
(決選票合計 341票) (ウィキペディア)
この結果により、高市早苗氏が新たな総裁に選出され、自民党史上初の女性総裁となった。 (ウィキペディア)
さらに補足として、報道では決選投票に至る際、小林鷹之氏が決選で高市に投票した旨の表明があったという報道もあった。 (ウィキペディア)
このように、高市は第1回では国会議員票での得票が他候補に劣っていたものの、党員票換算分で上積みし、さらに決選票での支持拡大を確保して逆転勝利をおさめた構図となった。
意義・読み取りポイント
この総裁選挙をどう読み解くか、いくつか視点を挙げる。
- 党内バランスの変化・右傾移行の可能性
高市早苗は保守強硬派・右派支持の印象を持たれやすく、彼女の当選は党内主流派・保守派勢力の影響力が依然根強いことを示す。今回の選挙では、保守的な路線を望む層・既存党員組織動員能力を持つ派閥が勝負所で動いた可能性も高い。 - 党員票 vs 議員票の力学
第1ラウンドでの党員票の重み、第2ラウンドでの議員票重視性という制度設計により、「議員支持だけでの圧勝」は難しい構図になっており、候補者は両方を意識しなければならなかった。今回のように、議員票でリードしていても党員票で追い上げを受けるパターンが鮮明になった点は、今後の自民党総裁選挙における戦略的教訓ともなるであろう。 - 刷新志向と保守維持の綱引き
総裁選前後には「解党的出直し」などの文脈が語られており、党のイメージ刷新・再構築の期待もあった中で、必ずしも革新的な顔ぶれではない高市の選出は、「大きな変化」志向を期待していた層にとっては必ずしも期待に沿うものとはならなかったかもしれない。 (東洋経済オンライン) - 政策的な舵取り・実行力への期待と疑念
総裁・党首が変わったとしても、国会での多数派支配がない状態(自公で過半数を保っていない)や野党との協議・妥協が不可欠な状況であるため、政策実行力・国会運営能力が厳しく問われるであろう。報道でも、「候補5人が見落としている点」として、実効的な成長戦略・財政政策・連立・少数政権対応力などが争点になると指摘されている。 (東洋経済オンライン) - 世論とのギャップ・信任の課題
総裁が党大会や党員票で選ばれても、国民一般・有権者の支持を広く獲得できるかどうかは別問題である。総裁選は党内の構図や組織動員が強く作用するから、報道における虚像・イメージ戦略も作用しうる領域である。(この点は、前述した「報道が作る虚像の優勢」ともリンクする)。 - 象徴性・女性初総裁の意味
高市早苗が自民党初の女性総裁という点には象徴的な意味があり、党・社会双方にとって「変化」のシンボルとなる可能性がある。ただし、象徴性だけでは支持を続ける原動力にはなり得ず、政策実績・国政運営能力が問われていくであろう。
課題・リスク・批判的視点
この総裁選にはいくつかのリスク・批判が伴う。
- 派閥・重鎮の影響力強さ
報道によれば、麻生派が決選投票で高市を支持するよう派員に指示していたという報道もある。これが事実なら、党員票や議員票を超えた重鎮の“動き”が結果を左右した可能性がある。 (ウィキペディア) - 新しいリーダーシップ像の不明瞭さ
高市は保守派の顔として一定の強さを持つ一方で、「変革」色を前面に出すのには限界があるという指摘もある。既存体制との連続性・既得権勢力との調整との兼ね合いが批判を招く可能性がある。 (東洋経済オンライン) - 国会運営力・政策実行力への懐疑
多数派を持たない状況下では、総裁・首相になっても政権運営は簡単ではない。与野党協調・妥協・根回しが不可欠な中で、有権者期待と実際能力とのギャップが露呈するリスクがある。 - 世論との乖離・支持基盤の弱さ
党内選挙で勝ったとしても、国民・有権者視点から見た信任を得続けられるかどうかは未知数である。党員票での支持はあっても、一般層への浸透や議論の訴求力・説得力が問われるであろう。 - 野党・第三極の動き
野党側、あるいは第三極(新興政党・無所属勢力など)の戦略・動きが、今後の議会構図を揺さぶる可能性がある。自民党が多数を取れない状況下では、連携・折衝・駆け引きが常態化する。
今後の展望・注目点
この総裁選挙後、次の点が特に注目されるであろう。
- 総裁=首相になるか否か/首相就任プロセス
自民党が国会で多数を持っていない状況では、総裁になったからといって自動的に首相になるわけではない。首相指名選挙・議会多数工作・政党間協調などが関わる。 - 政策プランの具体性と実行力
成長戦略、財政・税制、社会保障、外交・安全保障など、候補が掲げた政策をどこまで具体化し、実行可能性を示せるかが鍵。特に有権者・メディア・野党からの突っ込みを受けやすい分野である。 - 党勢回復・党イメージ刷新
参議院選での惨敗も背景にあるため、自民党は党勢を立て直す課題を抱えている。総裁・党執行部が、若年層・無党派層の支持を取り戻すためにどのような戦略を採るか。 - 与野党関係・国会運営の難度
少数与党状態では、法案可決・予算成立・外交政策・安全保障政策などすべてにおいて野党との協調が欠かせない。衆参両院での駆け引きが激しいものになるであろう。 - 次期衆議院選挙・総選挙のタイミング
新総裁・新首相がいつ解散を打つか、またどのようなタイミングで総選挙を行うかは、党内・国会・世論との兼ね合いで戦略が左右される。 - メディア描写・虚像の生成との駆け引き
あなたが先に問われた「報道が作る虚像の優勢」の視点からいえば、新総裁・首相としてメディア戦略・イメージ操作力もまた重要。候補時代に抱いたイメージが、実際の政権運営とズレを起こせば、ギャップ批判が強まるであろう。
総裁選における報道空間での虚像優勢
2025年10月4日の自民党総裁選でどのように作用したかを、以下の視点で分析を試みる。
観点と仮説
まず、報道が総裁選挙をどのように“演出”しうるかを整理すると、以下のような要素が考えられる。
- 勝ち馬予測・下馬評の先出し
メディアが、選挙前に「この候補が有利」「この候補は劣勢」などの見通しを積極的に発表することで、読者・視聴者の期待や支持の流れを事前に誘導する。 - 注目度の偏り・露出の差
ある候補がメディアに多く取り上げられる、発言の切り取り方で印象操作される、写真・ビジュアル演出が有利になるなど、露出量と質の差が印象を変える。 - 「象徴性・ドラマ性」の強調
性別・世代・改革派・保守派というテーマ性を際立たせ、象徴的な構図(例えば「女性初」「世代交代」「保守回帰」など)を演出することで、有力候補を虚像的に強調する。 - 専門家評論・解説の“権威付け”
メディアが出す専門家コメント・予測分析が、そのまま信頼性を帯びて流通し、視聴者・読者がそれを前提として認識枠組を形成してしまう。 - 反転不可能性の演出
(勝ち馬候補を)「もう流れは変えられない」「このまま決まりだろう」といった語り口で、反対勢力に巻き返す余地を与えにくくする演出。 - 数字の錯覚・比較操作
支持率・世論調査結果を切り取るタイミングや比較対象、誤差範囲の扱いなどの操作で、「有利さ」を印象づける数字の虚像を見せる。 - 無視・過小扱い・ネガティブ報道
ある候補に対して、政策の説明を十分報じない、マイナス材料を強調する、といったネガティブな扱いを意図的に行うことで、実力差以上のイメージ差をつくる。
これらの操作が複合的に作用すれば、実態とは異なる「虚像の優勢」が生まれ、それが選挙に影響を与えうるという仮説を立てることができる。
第6章 報道が作った“虚像優勢”の構造
以下、2025年自民党総裁選に関して、報道上見られた事例・指摘をもとに、虚像優勢がどのように現れたかを具体的に考えてみる。
報道的現象・指摘 | どう虚像優勢を助けたか / 演出されたか | 補足・批判的視点 |
「小泉進次郎優勢」の下馬評・メディア推しの論調 | 選挙前に「進次郎が勝つだろう」という報道が先行したことで、有権者・党員・議員に“勝ち馬期待”を誘導しやすくなる | 実際には決選で高市氏が勝利しており、下馬評の逆転要因や過小評価された面を無視する報道もあったと指摘されている (FNNプライムオンライン) |
「専門家」の予測・解説重視、敗北予測の強調 | 報道機関が「この候補は票が伸びない」「逆風だ」と専門家を引いて解説することで、読者・視聴者の後押しに使われ得る | 報道機関批判サイトでは「主要メディアの誤報は意図的か」という論考も出ており、虚像演出の意図性を問う意見がある (Japan In-depth) |
着こなし・映像演出・メディア演出としてのイメージ形成 | 産経系・FNNなどで、メディアファッション・演説映像・見た目戦略も分析材料にされ、「強いリーダーイメージ」の視覚化に使われたという指摘がある (FNNプライムオンライン) | |
注目される争点の移動・焦点操作 | メディアが「連立」「減税」「ステマ(ネットプロモーション操作)」という話題を注目軸に据え、候補者の本質的政策議論を目立たせにくくしたとの分析がある (選挙ドットコム) | |
誤報・報道誤り・ネガティブ拡大 | 「主要メディアが高市氏敗北を断言していた」という批判もあり、事前の報道・解説が虚像的「敗北予測」を先行させたという指摘がある (Japan In-depth) | |
世論調査・報道機関別結果のズレの黙殺・扱い | 世論調査の公表時期・母数・設問の違いが大きいにもかかわらず、報道ではそれを十分に注意書きせず「優劣比較」を印象づける形で示す例があったとの指摘が見られる (毎日新聞) |
これらの例を見ていくと、報道は「進次郎優勢 → 高市劣勢」というストーリーを先行させようという動きを示しつつ、そこからの反転を“驚き”として演出する構図が見られたように思われる。
特に、「下馬評での優勢予測」+「専門家解説の引用」+「露出偏重」が三位一体となるケースでは、読者・視聴者が「これが自然/当然だ」と感じてしまうような受容傾向が生じかねない。
また、報道とは逆方向に票を伸ばした候補(高市氏など)に対して「なぜ伸びたか」「実態要因は何か」を深掘りせず、逆転のプロセスを消化不良に扱う構図も、虚像優勢を後付けで正当化する役割を果たし得る。
最後に、「ネガティブ材料の過大強調」も典型的な操作手段です。たとえば、過去の発言・政策の疑義・批判点を掘り起こし、想起させることで支持を萎ませようとする報道があれば、それも虚像優勢構成に寄与する。
第7章 虚像優勢モデル(5段階循環モデル)
段階 | 英語表記 | 概要(メディアの作用) | 主要キーワード | 結果(社会的影響) |
① | Agenda Setting | メディアが「何を重要とするか」を決定し、関心の方向を誘導する。 | 話題設定・注目誘導・優先順位 | 特定の候補やテーマが“時代の焦点”として認知される。 |
② | Framing | 出来事や人物を特定の枠組み(善悪・新旧・改革保守など)で意味づける。 | 枠付け・対立構造・物語化 | 現実が単純な対比構図で理解される(例:改革派vs保守派)。 |
③ | Spectacle | 視覚的演出・感情訴求・ドラマ化を通じてニュースが「ショー化」される。 | 映像演出・感情刺激・話題性 | 政治が“娯楽化”し、政策より人物印象が重視される。 |
④ | Pseudo-Consensus | 世論調査・専門家コメント・SNS統計で「優勢」「多数派」の錯覚を作る。 | 数字の権威・勝ち馬効果・同調圧力 | 虚像の“多数派”が形成され、実態との乖離が拡大。 |
⑤ | Narrative Resilience | 虚像が崩壊しても、報道がその崩壊自体を新しい物語に再構成する。 | 自己正当化・再演出・循環構造 | メディアは批判を免れ、「物語の継続性」を維持する。 |
このモデルは、報道構造がどのように「虚像の優勢」を生成し、崩壊後も再生産していくかを体系的に示すものである。
第8章 虚像優勢の影響と限界
報道が虚像優勢を作ることができたとしても、それが選挙結果を完全に支配するわけではない。しかし、次のような影響を及ぼした可能性は高いと考えられる。
- 序盤の支持流動性拘束
報道が進次郎有利というストーリーを作り出すことで、党員・議員の一部が「勝ちやすい側」に早期に傾く誘因となった可能性がある。支持の流動性が早い段階で固定化されると、反転が難しくなる。 - 逆風耐性の差を拡大
虚像的に弱いとされていた候補が実際には支持回復・組織動員できたとしても、報道空間でのハードルが上がってしまい、巻き返し努力を目立たせにくくなる。 - 逆転時の“驚き・物珍しさ”としての演出
実態での逆転を「波乱」として物語化することで、逆転した候補への理解・共感が浅いまま終わる可能性がある。逆転後に「なぜ勝てたか」の議論が十分になされず、虚像(先行の見栄え・演出)要素が残る。 - メディア信頼感の揺らぎ
虚像と実態のズレが露呈した場合、報道機関そのものや専門家予測への信頼を揺るがす可能性がある。つまり、虚像を演出しすぎると、報道の信用性を損ねる反動も起こりうる。 - 政策・実行力議論へ結びつけにくくする
虚像優勢のストーリーが先行すると、候補の具体政策や実務能力への精査が後回しにされ、実務運営スタート段階で初動ミスが許されにくい環境を作ってしまう。
ただし、虚像優勢には限界もある:
- 実地での組織動員力・派閥力・党員票動員力が報道操作を上回るケースだってある。
- 候補本人の言動・矛盾・失言が露呈すれば、虚像を簡単に壊され得る。
- 党員・議員・支持層には批判的思考を持つ層もいて、露骨な演出には反発も出る。
この総裁選では、下馬評的には進次郎優勢という虚像が報じられていたものの、実地では党員票の支持や決選票段階の支持取り込みが高市に有利に働いたという構図になったと見られる。つまり、虚像優勢を作ろうとする力と、組織動員・実践力とのせめぎ合いが選挙の中で現実化したわけである。
終章 メディアと民主主義の再構築へ
現代社会において、報道は単なる情報伝達装置ではなく、現実を定義し、社会的真実を「設計」する力を持つ存在となっている。その力が倫理的に運用されるか否かによって、民主主義の健全性は大きく左右される。「虚像の優勢」とは、まさにその力が歪んだ形で行使された結果であり、国民の判断を方向づけ、政治・経済・文化のすべてに影響を及ぼす。本章では、報道と民主主義の関係を再定義し、再構築への道筋を五つの視点から考察する。
Ⅰ 倫理の再構築──「報じる自由」と「責任」の均衡を
報道の自由は民主主義の基盤であるが、それは同時に「説明責任」を伴う自由である。しかし現実には、「視聴率」「クリック数」「速報性」といった商業的指標が、倫理的判断を凌駕する構造が長年にわたって固定化してきた。報道機関は「社会の公器」を標榜しながらも、しばしば自らの権力性を自覚していない。「虚像の優勢」が象徴するのは、報道が自らを批判対象から除外し、無意識のうちに“第4の権力”として振る舞う姿である。
倫理再構築の第一歩は、「報道倫理を自己点検する文化」の再生である。社内におけるチェック体制だけでなく、外部監査・学識経験者・一般市民を交えた第三者委員会による検証を制度化することが求められる。特に政治報道においては、演出ではなく根拠に基づく報道、印象ではなく構造を問う報道への転換が不可欠である。
Ⅱ 教育の再構築──批判的メディアリテラシーの社会実装
情報社会において、国民一人ひとりが「報道を読む主体」になることが、民主主義の存続条件となっている。しかし日本では、メディアリテラシー教育がまだ断片的・形式的に留まっている。授業で「フェイクニュースを見抜こう」と唱えるだけでは、構造的偏向や言説支配を読み解く力は育たない。
必要なのは、批判的メディアリテラシー(Critical Media Literacy)である。これは「報道が社会的に何を再生産しているか」「どの価値観が排除されているか」を読み解く力であり、単なる情報技術教育を超えた知的訓練である。大学・高校だけでなく、小中学校の段階から「ニュースを疑うこと」「映像の構成意図を読むこと」「数字や統計の前提を問うこと」を教える必要がある。
さらに、AI生成情報の拡散が進む現代では、「誰が作り、誰が得をするか」という視点をもつことが、市民の知的防衛力となる。民主主義を守るための教育とは、単に正しい情報を受け取ることではなく、「自らの判断の根拠を問い直す力」を養うことに他ならない。
Ⅲ 構造の再構築──透明性と独立性を確保する仕組みへ
報道の信頼を回復するには、制度設計の刷新が不可欠である。日本における記者クラブ制度、官庁との非公式取引、広告主との共依存は、透明性を損ない、「報道の独立性」を根本から揺るがしている。民主主義国家において、報道機関は国家権力からも企業資本からも距離を保つべきである。
一方、テクノロジーの発展は、新しい可能性を開いている。ブロックチェーンを活用したニュースソースの改ざん防止、AIによるバイアス検知システム、クラウド型監査の導入などがそれである。また、公共メディア基金(Public Media Fund)のような独立財源を創設し、民間広告収入に依存しない報道の仕組みを確立することも有効である。
透明性は、報道の信頼を取り戻す最も強力な通貨である。その通貨を失った社会では、どれほど正しい報道も届かなくなる。信頼を回復するためには、制度とテクノロジーの両輪で報道の「透明化革命」を起こす必要がある。
Ⅳ 思想の再構築──「公共性」と「真実性」の哲学を取り戻す
報道が目指すべきは「センセーショナルな真実」ではなく、「公共的に意味のある真実」である。しかし、現代の報道空間では「感情の消費」と「物語の快楽」が支配し、公共性が置き去りにされている。情報の洪水の中で、誰もが“物語の観客”となり、“現実の参与者”ではなくなっているのだ。
この状況を乗り越えるには、報道哲学の再構築が必要である。ハーバーマスの言う「公共圏(public sphere)」の理念に立ち返り、報道が「討議の場」「熟議の触媒」として機能する社会を再設計すべきである。虚像の優勢に対抗できるのは、討議に基づく理性的な公共性であり、そのためには報道者自身が「真実とは何か」「社会的責任とは何か」を不断に問う姿勢を取り戻すことが求められる。
Ⅴ 未来への展望──AI時代の報道と民主主義の共進化
AIがニュースを生成し、SNSが世論を形成する時代において、報道は新たな岐路に立たされている。AIがもたらす自動化は便利である一方で、「誰が責任を負うのか」という倫理的課題を浮き彫りにした。AIが生み出す“最適化された虚像”が拡散する世界では、人間の判断がAIに吸収され、民主主義の「自由な熟議」が空洞化する危険がある。
したがって、次世代の報道には「AI倫理」と「人間中心設計(Human-Centered Design)」の融合が不可欠である。AIを排除するのではなく、人間の批判的思考を拡張するツールとして活用する。AIが“虚像”を生み出すなら、人間は“虚像を見抜く”AIを開発すべきである。その共進化こそが、テクノロジー時代の民主主義を支える新しい知の形である。
結語──「虚像を超える知性」へ
2025年自民党総裁選は、日本の報道構造がいかにして“物語を先行させ、現実を後追いする”かを示す象徴的事件であった。虚像は一瞬の輝きを放つが、やがて現実の重みに耐えられず崩壊する。しかし崩壊後の沈黙をどう再構築するかこそが、真の報道の力である。
虚像の優勢を乗り越えるためには、報道者の倫理、市民の思考、教育の改革、制度の透明性、そして思想の深化が必要である。民主主義は与えられるものではなく、日々「問い続けること」によってのみ維持される。その知的営為の継続こそが、虚像を超えた現実的な希望を生み出すのである。
📚参考文献一覧(APA第7版準拠)
Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. Garden City, NY: Doubleday.
Goffman, E. (1974). Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. New York, NY: Harper & Row.
McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. Public Opinion Quarterly, 36(2), 176–187. https://doi.org/10.1086/267990
Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication, 43(4), 51–58. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x
Kellner, D. (2003). Media Spectacle. London: Routledge.
Herman, E. S., & Chomsky, N. (1988). Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. New York, NY: Pantheon Books.
NHK放送文化研究所 (2022). 『現代日本のメディアと政治報道』 NHK出版.
堀潤 (2020). 『メディアの責任とは何か』 NHK出版.
Japan In-depth (2025). 「主要メディアの“誤報”は意図的か──総裁選の報道構造を問う」. https://japan-indepth.jp/?p=89050
FNNプライムオンライン (2025). 「“進次郎優勢”報道と高市逆転:メディアの錯覚」. https://www.fnn.jp/articles/-/941531
毎日新聞 (2025). 「世論調査結果の報じ方にみる“優勢”の錯覚」. https://mainichi.jp/articles/20251003/k00/00m/010/060000c
ご感想、お問い合せ、ご要望等ありましたら下記フォームでお願いいたします。
投稿者プロフィール

- 市村 修一
-
【略 歴】
茨城県生まれ。
明治大学政治経済学部卒業。日米欧の企業、主に外資系企業でCFO、代表取締役社長を経験し、経営全般、経営戦略策定、人事、組織開発に深く関わる。その経験を活かし、激動の時代に卓越した人財の育成、組織開発の必要性が急務と痛感し独立。「挑戦・創造・変革」をキーワードに、日本企業、外資系企業と、幅広く人財・組織開発コンサルタントとして、特に、上級管理職育成、経営戦略策定、組織開発などの分野で研修、コンサルティング、講演活動等で活躍を経て、世界の人々のこころの支援を多言語多文化で行うグローバルスタートアップとして事業展開を目指す決意をする。
【背景】
2005年11月、 約10年連れ添った最愛の妻をがんで5年間の闘病の後亡くす。
翌年、伴侶との死別自助グループ「Good Grief Network」を共同設立。個別・グループ・グリーフカウンセリングを行う。映像を使用した自助カウンセリングを取り入れる。大きな成果を残し、それぞれの死別体験者は、新たな人生を歩み出す。
長年実践研究を妻とともにしてきた「いきるとは?」「人間学」「メンタルレジリエンス」「メンタルヘルス」「グリーフケア」をさらに学際的に実践研究を推し進め、多数の素晴らしい成果が生まれてきた。私自身がグローバルビジネスの世界で様々な体験をする中で思いを強くした社会課題解決の人生を賭ける決意をする。
株式会社レジクスレイ(Resixley Incorporated)を設立、創業者兼CEO
事業成長アクセラレーター
広島県公立大学法人叡啓大学キャリアメンター
【専門領域】
・レジリエンス(精神的回復力) ・グリーフケア ・異文化理解 ・グローバル人財育成
・東洋哲学・思想(人間学、経営哲学、経営戦略) ・組織文化・風土改革 ・人材・組織開発、キャリア開発
・イノベーション・グローバル・エコシステム形成支援
【主な著書/論文/プレス発表】
「グローバルビジネスパーソンのためのメンタルヘルスガイド」kindle版
「喪失の先にある共感: 異文化と紡ぐ癒しの物語」kindle版
「実践!情報・メディアリテラシー: Essential Skills for the Global Era」kindle版
「こころと共感の力: つながる時代を前向きに生きる知恵」kindle版
「未来を拓く英語習得革命: AIと異文化理解の新たな挑戦」kindle版
「グローバルビジネス成功の第一歩: 基礎から実践まで」Kindle版
「仕事と脳力開発-挫折また挫折そして希望へ-」(城野経済研究所)
「英語教育と脳力開発-受験直前一ヶ月前の戦略・戦術」(城野経済研究所)
「国際派就職ガイド」(三修社)
「セミナーニュース(私立幼稚園を支援する)」(日本経営教育研究所)
【主な研修実績】
・グローバルビジネスコミュニケーションスキルアップ ・リーダーシップ ・コーチング
・ファシリテーション ・ディベート ・プレゼンテーション ・問題解決
・グローバルキャリアモデル構築と実践 ・キャリア・デザインセミナー
・創造性開発 ・情報収集分析 ・プロジェクトマネジメント研修他
※上記、いずれもファシリテーション型ワークショップを基本に実施
【主なコンサルティング実績】
年次経営計画の作成。コスト削減計画作成・実施。適正在庫水準のコントロール・指導を遂行。人事総務部門では、インセンティブプログラムの開発・実施、人事評価システムの考案。リストラクチャリングの実施。サプライチェーン部門では、そのプロセス及びコスト構造の改善。ERPの導入に際しては、プロジェクトリーダーを務め、導入期限内にその導入。組織全般の企業風土・文化の改革を行う。
【主な講演実績】
産業構造変革時代に求められる人材
外資系企業で働くということ
外資系企業へのアプローチ
異文化理解力
経営の志
商いは感動だ!
品質は、タダで手に入る
利益は、タダで手に入る
共生の時代を創る-点から面へ、そして主流へ
幸せのコミュニケーション
古典に学ぶ人生
古典に学ぶ経営
論語と経営
論語と人生
安岡正篤先生から学んだこと
素読のすすめ
経営の突破口は儒学にあり
実践行動学として儒学に学ぶ!~今ここに美しく生きるために~
何のためにいきるのか~一人の女性の死を見つめて~
縁により縁に生きる
縁に生かされて~人は生きているのではなく生かされているのだ!~
看取ることによって手渡されるいのちのバトン
など


