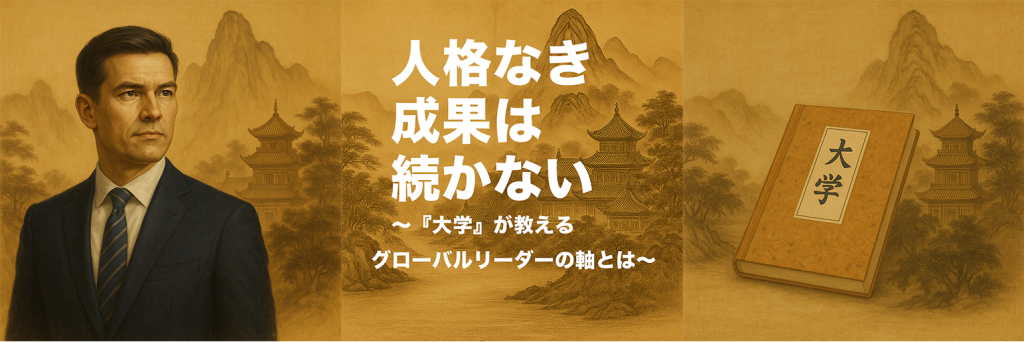
人格なき成果は続かない 〜『大学』が教えるグローバルリーダーの軸とは〜
はじめに──リーダーの“在り方”が問われる時代に、なぜ『大学』か
いま、世界はリーダーの“能力”よりも、“在り方”を問う時代に突入している。
パンデミック、地政学的緊張、環境危機、AI革命──現代社会を取り巻く環境は複雑性と不確実性を極めており、かつてのように知識や技術、分析力だけでは乗り越えられない壁が立ちはだかっている。そのなかで組織や社会を導く者に必要とされるのは、変化を読み解く力でも、スピードある意思決定力でもない。むしろ、その土台となるべきもの──すなわち「人格」「思想」「公共性」そして「倫理」なのである。
現代のグローバルリーダーに必要なのは、“どう行動するか”以前に、“どう在るか”である。変化に流されない軸を持ち、多様な文化や価値観と共存しながら、未来に対して責任を負う意志と構想力。それは決してスキルだけでは身につかない。むしろ、人間としての内的統治──すなわち「自己の統御」が出発点である。
この視座に立ったとき、数千年の時を超えて、再び現代人の心に深く響いてくるのが、中国古典『大学(だいがく)』である。
『大学』は、単なる東洋の古典ではない。それは、一人の人間が「自らを整え、社会を導き、世界を平和に導く」までの道筋を、精緻かつ体系的に記述した“人格とリーダーシップの教科書”である。とりわけ、三綱領(明明徳・親民・止於至善)と八条目(格物・致知・誠意・正心・修身・斉家・治国・平天下)は、内面から外界へと広がるリーダーの成長と責任の軌跡を、哲理と行動の両面から描き出している。
注目すべきは、『大学』が単なる精神論にとどまらず、現代心理学・脳科学の知見と驚くほど整合性を持っている点である。メタ認知・情動制御・動機づけ・共感・倫理的意思決定──これらはすべて、八条目に内包されており、現代科学がようやく言語化した内容を、すでに『大学』は体系化していたとさえ言える。
さらに、本稿では、昭和の大哲人・安岡正篤の思想を重ね合わせることで、“人物学としての『大学』”の真髄にも迫っていく。安岡が読み解いた『大学』は、単なる知識や知見ではなく、「いかに天命に生き、いかに徳を積み、いかに大義に殉ずるか」を説くものであった。現代において、政治・経済・経営・教育など、あらゆる領域で指導的立場にある者こそが学ぶべき「魂の書」として、安岡は『大学』を位置づけていたのである。
本稿は、グローバルビジネスに携わるすべてのリーダーに向けたものである。
地政学的に複雑な世界を生きるリーダーが、どのように自分自身の軸を定め、いかにして多様な文化圏や価値体系の中で信頼を勝ち得ていくか。短期的成果と倫理的選択の狭間で葛藤するなか、いかに理念と公共性を見失わずに進むか。個の強さと、大我の視点の統合こそが問われている今だからこそ、『大学』の教えは新たな光を放つ。
本稿では、全七章にわたり、『大学』の三綱領と八条目を構造的に紐解き、心理学・脳科学・倫理学の視点から再解釈し、松下幸之助、サティア・ナデラ、ハワード・シュルツなど現代のグローバル企業リーダーたちの実践と響き合わせながら、東洋思想が提供するリーダーシップの原理を明らかにしていく。
『大学』が教えるのは、「人格なき成果は続かない」という厳粛な真理であり、「自分を治める者こそ、世界を治めるに足る」という普遍の原理である。
次章より、読者の皆様を『大学』の世界へとご案内する。
それは、単なる古典の学びではない。リーダーとしての“根”を耕し、“幹”を伸ばし、“森”を築くための思想的旅路である。
第1章 東洋思想の中枢としての『大学』──その誕生、構造、そして世界的意義
1-1 『大学』とは何か──その全体像と目的
『大学(だいがく)』とは、中国儒教思想の中核を成す「四書五経」の一書であり、「四書」(『大学』『中庸』『論語』『孟子』)の筆頭に位置づけられている。特にリーダー教育においては、自己の内面修養を起点に、家庭・組織・国家・世界へと影響を及ぼすという思想を体系的に提示した点において、古代から現代に至るまで、東洋思想の「リーダー論の源典」として尊重されてきた。
『大学』はその冒頭で次のように述べる。
「大学の道は、明徳を明らかにするにあり、民を親しむにあり、至善に止まるにあり」
この「三綱領」(明明徳・親民・止於至善)を基軸として、自己修養から天下を治めるという、八つの実践ステップ(格物・致知・誠意・正心・修身・斉家・治国・平天下)を提示する。これは単なる倫理論ではなく、行動科学的な変容のプロセスとして捉えることができ、心理学・脳科学と照応する点も多い。
1-2 『大学』の成立──礼記から朱子へ
■ 成立の原点:『礼記』の一篇として
『大学』はもともと『礼記(らいき)』という古典の中の一篇であった。『礼記』は、儒教の儀礼や倫理を体系化したテキスト集であり、前漢〜後漢の時代に編まれたとされている。
『大学』そのものは、儒家の巨人・孔子の高弟である曾子(曽子、曾参)によって書かれたと伝えられている。曾子は、「孝」の思想で有名であり、『論語』の中でも数多く登場する人物である。曾子が『大学』において重要視したのは、徳を修めて天下を平らかにするための“実践手順”であり、それは「知・情・意」の統合をめざすプロセスであると同時に、東洋的な意味での「人間完成」の設計図であった。
■ 体系化:朱熹(朱子)の再構成
南宋時代の大儒学者朱熹(しゅき、1130–1200)が、『大学』を独立した学問体系として再編成したことにより、今日私たちが読む形式の『大学』が確立した。朱熹は「理気二元論」を唱え、宇宙・人間・倫理を一体として捉える哲学体系を築いたが、『大学』はその実践編として最重要視された。
彼は『大学』を「四書」の筆頭に位置づけ、科挙(中国の官僚登用試験)の教材にしたため、以後数百年間、中国・朝鮮・日本など東アジアの知識人たちは、すべて『大学』を通じて「徳を以て治める」ことを学んだのである。
1-3 『大学』が与えた思想的・政治的影響
■ 東アジア全体に及ぼした影響
『大学』の影響は中国にとどまらない。朝鮮李朝では国家理念として『大学』が尊重され、日本でも江戸時代の朱子学教育の根幹となった。水戸学・陽明学・会津藩校「日新館」などでも、『大学』がリーダーの学問の基本とされた。
■ 近代日本と『大学』
明治維新の立役者である吉田松陰、西郷隆盛、福沢諭吉などの思想形成にも『大学』の影響が見られる。特に「修身斉家治国平天下」の思想は、国家建設と人格養成を一体と捉える思想の基盤となった。
現代の経営者にも多大な影響を与えており、松下幸之助や稲盛和夫といった日本の代表的な実業家は、いずれも『大学』の思想を経営と生き方の基盤に据えていた。
1-4 現代的解釈:心理学・脳科学との交差点
■ 心理学的対応
『大学』のプロセス(格物→平天下)は、現代心理学の行動変容モデル(例:トランスセオレティカルモデル、メタ認知、セルフリーダーシップ論)と一致する。たとえば「正心(心を正す)」は、CBT(認知行動療法)の「自動思考の修正」と近い。
■ 脳科学的視点
- 「修身」は前頭前野の自己制御機能の活性化と対応
- 「誠意」は扁桃体の過活動抑制による感情の統御
- 「斉家・治国・平天下」は共感ネットワーク(デフォルトモードネットワーク)とオキシトシン分泌による対人共鳴性の強化に対応する
このように、『大学』の実践プロセスは、脳の構造的変容(ニューロプラスティシティ)と一致すると考えられる。
1-5 安岡正篤が読み解いた『大学』──人物学の原点
昭和を代表する陽明学者であり、歴代首相の思想的指南役を務めた安岡正篤は、『大学』を「人物の学」の原点と位置づけた。
彼は次のように語っている:
「『大学』が説く三綱八目は、単なる知識の体系ではない。人が人として立ち、天命に従い、大義に生きるための“人間完成の道”である」
安岡は、修身をリーダーの絶対条件とし、人格が未熟なまま地位や権力に就くことは、組織を腐らせ、国家を傾けると警鐘を鳴らした。これは現代のコーポレートガバナンスやコンプライアンスの根幹とも通じる理念であり、『大学』はその“倫理的リーダーシップ”の設計図なのである。
第1章まとめ:『大学』は「自己変容から世界への道」である
項 目 | 内 容 |
成立時期 | 戦国〜前漢期に成立(礼記の一篇) |
著者と再編 | 原案:曾子/体系化:朱熹(南宋) |
中心思想 | 明明徳・親民・止於至善(+八条目) |
思想的影響 | 日本・中国・朝鮮の国家運営・教育・経営哲学 |
現代的意義 | 行動心理学・脳科学と整合性がある人格開発論 |
キーパーソン | 安岡正篤:『大学』は人物教育と宰相学の出発点 |
第2章 修身と自己統御──リーダーにおける“人格の鍛錬”とは
2-1 すべては「己を修める」ことから始まる
『大学』の八条目において、「修身(しゅうしん)」はちょうど中間地点に位置づけられている。格物・致知・誠意・正心という内面の探究と整備を経て、はじめて「修身」に至るのである。ここで言う「身」とは、単なる身体ではなく、その人の人格、すなわち“在り方”そのものを意味する。つまり『大学』が示す道筋においては、自己の内なる真実を見極め、誠実に心を整えたのちに、はじめて「人としての器を磨く段階」に入るという構造なのである。
この点は、現代のリーダーシップ理論においても極めて重要である。企業経営において最も求められるのは、知識やスキルだけでなく、「この人に従いたい」と思わせるような人格的信頼(personal credibility)である。その核となるものこそ、まさに「修身」なのである。
2-2 心理学が解明する「自己統御」とリーダーシップの関係
現代心理学においても、リーダーの資質として「自己認識(self-awareness)」「自己統御(self-regulation)」の重要性が強調されている。心理学者ダニエル・ゴールマンが提唱した「エモーショナル・インテリジェンス(EQ)」の五要素のうち、最初の二つがまさにこの二点である。
「修身」の実践とは、自分の感情や衝動に気づき、それを適切に調整し、意志によって行動を選びとる能力である。これは、ストレス下での冷静な判断、怒りのコントロール、誠実な態度の維持といった、リーダーシップに不可欠な行動と直結している。
また近年の研究では、「内省(reflection)」と「自己効力感(self-efficacy)」が、困難な状況でも倫理的意思決定を貫くリーダーの行動を支えていることが明らかになってきている。『大学』が説く「誠意」「正心」そして「修身」という連続的な内的修養の道筋は、まさにこの心理学的理解と一致しているのである。
2-3 脳科学が示す“修身”の神経的基盤
脳科学の観点から見ると、「修身」は前頭前野(Prefrontal Cortex)の活動と深く関係している。前頭前野は、計画性・抑制力・道徳判断・社会的適応に関わる脳領域であり、これが十分に活性化している人ほど、感情のコントロールができ、他者との関係性を良好に保ちやすいことがわかっている。
また、自己制御力が高い人は、扁桃体(Amygdala)による過剰な情動反応を抑制できるという知見もある。これは「正心(こころを正す)」→「修身(からだを整える)」という『大学』のプロセスが、感情(情)と理性(知)を融合させた行動(意)につながる構造と見事に重なる。
さらに近年の研究では、マインドフルネスや瞑想といった内省的な実践が、前頭前野の灰白質を増加させ、自己制御能力や共感力を高めることが示されている。つまり、『大学』が重視した“内なる鍛錬”は、神経可塑性(neuroplasticity)によって、リーダーの人格を文字通り“構造的に変える”可能性があることを、脳科学が証明しつつあるのだ。
2-4 安岡正篤に学ぶ「人物をつくる」という思想
昭和期の陽明学者・安岡正篤は、『大学』における「修身」を、リーダー教育の核心に位置づけた人物である。彼は政治家・経営者・官僚に対してこう説いていた。
「人を治むるには、まず己を治めよ。己を治めるには、まず心を正し、心を正すには、意を誠にしなければならぬ」
これは、まさに『大学』の八条目を要約したような言葉である。安岡は、“人物学”こそが真の教育であり、「学問とは人格を養い、天命を知ることにある」と主張した。そして、政治や経営においてもっとも恐るべきは、「自己を律することなく権力や影響力を持った人物が、組織の方向を誤らせること」であると警鐘を鳴らしていた。
彼の思想は、「修身なき者にリーダーの資格はない」という『大学』の倫理観を、現代社会に翻訳したものといえる。
2-5 実例:マイクロソフトCEO サティア・ナデラの“内省型”リーダーシップ
グローバル企業の中でも、現代的な「修身」を体現しているリーダーとして注目されるのが、マイクロソフトのCEO、サティア・ナデラである。彼は就任以降、「文化の変革」を旗印に、組織の対話と共感、学習文化の醸成を推し進めた。
注目すべきは、彼のリーダーシップの根底にある「内省と共感」である。ナデラは自身の読書習慣、家族との関わり、部下へのフィードバックを通じて、「リーダーの器は自己理解から始まる」ということを繰り返し語っている。彼の言葉はこうである。
“To be an empathetic leader, you have to be a disciplined learner.”
(共感力あるリーダーであるには、自らを律する学び手でなければならない)
これはまさに、『大学』の修身の思想と共鳴する。共感とは、表面的な優しさではなく、自己を律し、相手を深く理解しようとする内なる努力の延長線上にあるのである。
2-6 “修身”はリーダーの未来を変える
『大学』の教えにおいて、「修身」はあらゆる実践の基盤である。斉家も、治国も、平天下も、すべてこの「修身」が成立してこそ、正しく展開される。つまり、“自己を正しく保つことが、世界を正しく動かす唯一の道”なのである。
現代の混迷する社会においては、テクノロジーや資本だけでは人は導けない。必要なのは、「この人にこそ任せたい」と思わせる人格の力であり、それを裏打ちする日々の自己統御である。『大学』の示す「修身」の思想は、グローバルビジネスの最前線においても、普遍的で実践的なリーダーの羅針盤となるのである。
第3章 斉家とチーム統率──信頼と倫理の共同体をいかにつくるか
3-1 「斉家」とは何か──家から始まる秩序の哲学
『大学』における「斉家(せいか)」とは、「家をととのえる」という意味であるが、ここで言う「家」とは、単なる家庭を指すのではない。それは、人間が最初に所属する最小の共同体であり、あらゆる社会組織の原型である。儒教の世界観においては、「家」が秩序の基盤であり、ここに倫理がなければ、いかなる治国も平天下も成立しないとされてきた。
現代において「家」を「チーム」や「組織」と読み替えれば、リーダーの使命が明らかとなる。すなわち、「小さな共同体をいかに整え、信頼と倫理の文化を根づかせるか」という課題である。『大学』は、この「斉家」を一過性のテクニックとしてではなく、人格と行動の積み重ねによって実現する道として描いている。
3-2 心理的安全性と“家風”の関係──信頼は空気のように存在する
近年、グーグルが発表したプロジェクト・アリストテレスの研究によって、「心理的安全性」がハイパフォーマンスチームの鍵であることが明らかとなった。これは、メンバーが「自分の考えや感情を安心して表現できる雰囲気」があることを意味している。
この「雰囲気」をつくるものこそ、組織内の“倫理的家風”である。『大学』が言う「斉家」は、組織の誰もが互いに敬意を持ち、誠実さを守る空気を育てるという行為であり、それはリーダーのふるまい、言葉づかい、判断基準すべてに影響される。
心理学者エイミー・エドモンドソンが指摘するように、心理的安全性が高いチームほど、失敗を認めやすく、学習が加速し、結果として業績が向上する。これは、リーダーが「安心できる空間」を提供することで、組織の“家”がととのっていく過程に他ならない。
3-3 “感情のリーダーシップ”と安岡正篤の「小事を正す」教え
安岡正篤は、「斉家」をリーダーの生活態度の現れとみなした。つまり、家族や部下に対する態度、日常の約束を守るかどうか、部下の話をどう聴くかといった「小事」の中に、その人の“徳”がにじみ出るというのである。
彼は言う。
「大事を為す者は、まず小事を正す。家に礼あらば、国に礼あり。」
これは、倫理や信頼の文化は、制度や言葉ではなく、日々のふるまいと態度の累積によってしか生まれないという真理を表している。
現代の神経科学でも、感情は“ミラーニューロン”によって無意識に模倣されることがわかっている。つまり、リーダーが苛立っていれば組織に不安が伝播し、リーダーが感情を整えていれば、安心感が広がる。「斉家」とは、まさにリーダーの感情・行動が組織全体を規定する構造そのものなのである。
3-4 実例:松下幸之助の“家族主義経営”と斉家の実践
日本の経営史において「斉家」を最も忠実に体現した実業家といえば、パナソニック創業者・松下幸之助である。彼は従業員のことを常に「社員さん」と呼び、一人ひとりを“家族のように大切にする”ことを経営の根本に据えた。
松下の有名な言葉にこうある。
「会社は人なり。企業とは一つの人間共同体である。」
この思想のもと、彼は「事業は人をつくるための道場である」と捉え、人間性を育む場としての会社づくりに取り組んだ。年始には全社員と握手し、従業員の家族の誕生日に手紙を出すなど、組織の“家”としての機能を意識的に強化していたのである。
その結果、パナソニックは単なる電機メーカーではなく、「共に生きる文化を持った企業」として日本と世界の尊敬を集めた。このように、組織内に「信頼」「倫理」「敬意」の“家風”を醸成することが、「斉家」の実践であり、強い組織をつくる基礎となる。
3-5 チームを一つの“家”として見立てる統率法
では、現代のグローバルビジネスにおいて、どのようにして「斉家」を実践すればよいのか。その鍵は、チームや部署を一つの“家”と見立てて、“親のようにメンバーを導く”姿勢をリーダーが持つことである。
具体的には以下のような実践が挙げられる。
- ✅ メンバーの小さな声を聴く「耳」を持つ
- ✅ 誰かの成功をチーム全体の喜びとする文化をつくる
- ✅ 明文化された行動規範(family values)を共有する
- ✅ ミスを非難せず、学びに転換する仕組みを持つ
これらは、形式としてではなく、リーダー自身が人格的な軸を持っていることによって、初めて実効性を持つ。したがって、「斉家」は、単なるマネジメントスキルではなく、リーダー自身の“人間としての器”を問う実践課題なのである。
3-6 「斉家」が組織文化を決定づける
組織には、制度や戦略以前に、「文化」が存在する。文化とは、人々が無意識に共有している価値観やふるまいの習慣であり、その根幹にあるのが「斉家」である。
『大学』が説くように、家が整えば国家が整う。現代においては、チームや職場が整えば、企業全体の方向性が整う。この思想は、リーダーの態度から始まり、日々のふるまいを通じて、やがて組織全体の「倫理的土壌」となって広がっていく。
「斉家」は、“リーダーの徳が組織文化を形づくる”という事実を突きつけている。グローバル時代においてこそ、国や文化を超えて人をつなげるのは、最終的には「信頼」であり、その信頼は「斉家」すなわち、人間関係の最も小さな単位における丁寧なふるまいの積み重ねによってのみ築かれるのである。
第4章 治国と経営理念──公共性と長期視点を持つリーダーの条件
4-1 「治国」とは単に国家を治めることではない
『大学』における「治国」とは、字義的には「国を治める」ことを意味するが、これは現代のビジネスパーソンにとっては「組織全体を健全に運営すること」と読み替えるべきである。リーダーとしてチームを超えたスコープに立ち、社会に開かれた経営や、企業理念の策定、組織文化の醸成など、“公共性と価値創出”の観点から組織を導く力が求められる。
この「治国」において重要なのは、「斉家」で築いた小さな倫理の共同体を、いかに拡大して社会に通じる原理とするかという視座である。すなわち、“私”から“公”へと視野を転じ、全体最適を志向する姿勢が、ここで問われることになる。
4-2 経営理念は“現代の治国の礎”である
現代において「治国」の実践に相当するものは、企業や組織における「理念経営」「パーパス経営」である。事業そのものが社会や人類にとってどのような価値を生み出しうるか、また、組織の力をどのようにして“善の方向”に向けるか──これらはすべて『大学』が問う「治国」の精神に通じる問いである。
組織のリーダーにとって、理念は単なる言葉ではない。それはすべての判断を貫く背骨であり、困難な状況において何を選ぶかを決定する“規範的羅針盤”である。理念があるからこそ、短期的利益と長期的信頼の間で葛藤する場面でも、誠実で一貫性ある選択が可能となる。
4-3 心理学と“理念遵守”──なぜ理念は人を動かすのか
社会心理学の領域において、人間が行動の指針として共有する理念や信条は、「認知的一貫性(cognitive consistency)」を保つ装置として機能する。つまり、人間は自分が所属する組織の価値観と、自分自身の価値観に整合性があるとき、より強いモチベーションと没入感を持って行動できるのである。
また、組織の理念に共感し、その理念が社会とつながっていると認識する時、個人の内発的動機が高まることが多数の研究で示されている。これは、自己決定理論(Self-Determination Theory)における「自律性」「関係性」「有能感」の三要素と強く関係する。
『大学』における「親民(しんみん)」──民を親しむ、つまり人々の心を得るという発想は、この現代心理学の成果と呼応している。理念を明確に掲げ、それを本気で実践するリーダーこそが、人を惹きつけ、組織の力を最大限に引き出すのである。
4-4 脳科学と“公共性”──利他性は脳を変える
脳科学の観点から見ると、「治国」に通じる“公共性”の行為には、生理的な報酬が伴うことがわかっている。たとえば、社会的な善行や、他者貢献的な行為をすると、脳内でオキシトシンが分泌され、ドーパミン系が活性化する。これにより、利他的な行動は“心地よさ”や“幸福感”を伴うため、持続可能な行動として定着しやすくなる。
また、リーダーが「自分のため」ではなく「組織や社会のため」に行動しているとき、脳の前頭前野とデフォルトモードネットワークが協調的に働く。この状態は、長期視点で物事を捉える能力と倫理的判断を高める状態でもある。『大学』が説く「止於至善(しぜんにとどまる)」、すなわち最高善を志す精神は、脳科学的にも再現可能なリーダーの状態を指しているのである。
4-5 安岡正篤に学ぶ「義を利に先んず」の哲学
安岡正篤は、治国とは“制度で支配する”ことではなく、“道義で導く”ことだと考えた。彼の言葉に、次のような一節がある。
「治国とは、利を以てではなく、義を以てなすことに本義がある。義が通らぬ国に未来はない」
ここで言う「義」とは、短期的な損得を超えて、正しいことを貫く姿勢である。企業経営においても、経済合理性を超えて“何が社会的に正しいか”を問う精神が必要とされる。たとえば環境問題、労働条件、ガバナンスにおける選択肢は、「義」なき経営がいかに致命的であるかを物語っている。
安岡は『大学』の「治国」に含まれる公共性と倫理性を、まさに現代における経営理念の核と見抜いていた。そして「一灯照隅、万灯照国」のごとく、小さな組織内での倫理的行動が、やがて国や世界に波及することを確信していたのである。
4-6 実例:ユニリーバのパーパス経営と“治国”の思想
グローバル企業ユニリーバは、「サステナビリティを生活のあたりまえにする(Make sustainable living commonplace)」というパーパスのもと、社会・環境・経済の調和をめざした経営を実践してきた。その理念は、単なるCSRではなく、すべての製品開発・マーケティング・投資判断にまで浸透している。
たとえば、環境負荷を抑えた製品の開発を推進する一方で、人権デュー・ディリジェンスや、女性の経済的自立支援にも積極的である。このような行動原理は、「企業は社会の公器である」という視座に立っている。
これはまさに『大学』の「治国」、すなわち“私益にとどまらず、公を志向する”姿勢の現代的実践である。ユニリーバは、“倫理を伴った経営こそが持続的な価値を生む”という信念のもとで、従業員・顧客・投資家との信頼関係を築いてきた。
4-7 リーダーに求められる「公共心」と未来視点
最終的に、「治国」において問われるのは、リーダーがどれだけ“公共心”と“長期視点”を持てるかに尽きる。公共心とは、自分や自社の利益を超えて、社会にとって何が正しいかを考え続ける姿勢であり、長期視点とは、明日の数字より10年後の世代の幸福を思い描く視野である。
短期利益を追求するマネジメントは、もはやリーダーシップとは呼べない時代である。むしろ、理念と正義を胸に抱き、個人の良心と社会の期待の交差点に立つ者こそが、真の「治国の主役」なのである。
第5章 平天下とグローバル思考──“大我”に生きるリーダーの視座
5-1 「平天下」とは、共存共栄の思想である
『大学』における最終段階「平天下(てんかをたいらかにす)」とは、単なる国家の統治を超え、人々が調和と秩序の中で共に生きる世界を目指すという思想である。「天下」とは特定の国を意味するのではなく、世界全体、すなわち人類社会そのものを指している。
この「平天下」において、リーダーに求められるのは、自己や自社の枠を超えた「大我的視野」、すなわち人類の福祉と調和を志向する統合的思考である。この精神は、グローバルビジネスが直面する気候変動、人権問題、多文化共存といった複雑な課題に対して、リーダーがどのような立場と倫理観を持つべきかを問いかけている。
5-2 “自他共栄”という東洋的世界観
東洋思想において、「平天下」の核心は自他共栄の原理にある。孔子は「仁」を、「己の欲せざるところは、人に施すことなかれ」と定義した。これは単なる慈悲心ではなく、共存することが最も自然で合理的な在り方であるという世界観を意味する。
この視点は、利害の衝突を前提とした西洋的パワーゲームとは異なり、共に生きることによって持続可能な繁栄が得られるという合力主義の発想である。この思想こそが、「平天下」の背景にある宇宙観であり、現代のグローバルリーダーが身につけるべき核心的価値観なのである。
5-3 心理学と“意味の共有”──人間は「意義のある世界」でしか力を発揮しない
現代心理学、とりわけヴィクトール・フランクルのロゴセラピーにおいて、人間が真に力を発揮するのは、「自分が世界に意味ある存在として貢献している」と実感したときであるとされる。すなわち、“自分の存在が誰かのためになっている”という実感が、モチベーションの最も深い源泉となる。
これは『大学』の「平天下」にも通じる。自己の人格を磨き、家族や組織を整え、社会を善に導いたその先には、世界をより良くするという壮大なビジョンがある。ビジネスリーダーにとっても、自社の活動が地球規模の問題に対してどう貢献しているのかを語れなければ、社員も顧客も共鳴しない時代に突入している。
5-4 脳科学が明らかにする“共感力”とリーダーの世界観
脳科学の研究においても、利他的行動や社会的貢献に関わる脳の仕組みが明らかになってきている。ミラーニューロン系の活性化によって、他者の感情を感じ取り、自分ごととして受け止める能力が養われる。さらに、オキシトシンという神経伝達物質は、共感・信頼・絆の形成を促進する。
「平天下」とは、単に支配し、秩序を作ることではない。むしろ、共感と倫理に基づく“世界の調和的統治”である。これは脳科学的にも、他者の痛みを知覚し、自他を一体化させる脳構造を発達させることによって可能となるのである。
すなわち、「平天下」を目指すとは、リーダー自身の神経系の進化でもある。その意味で、自己修養から始まる八条目の旅路は、人格だけでなく脳そのものの変容の道であるともいえる。
5-5 安岡正篤の「大我を抱く者は、天下を抱くに足る」思想
安岡正篤は、『大学』の思想の中でも特に「平天下」の段階を重視していた。彼は国家・企業・教育界などのリーダー層に対し、「小我(自己利益)を脱し、大我(人類的視野)に生きよ」と説いた。そして、次のように語っている。
「真に天下を治める者は、自己を超えた志、すなわち“大義”に生きる者である。私欲ある者に、世界を導く資格なし。」
この考え方は、現代のグローバルリーダーにとっても極めて示唆に富む。経営判断一つとっても、短期利益ではなく、持続可能性や社会的正義に軸足を置いた意思決定がなされなければ、ステークホルダーからの信頼は得られない。
安岡は、リーダーの資格とは「知識や能力ではなく、大義に生きる覚悟である」と断言していた。その覚悟が、「平天下」に到達する唯一の通路なのである。
5-6 実例:スターバックスの価値中心経営と“天下の和”
スターバックスの元CEO、ハワード・シュルツは、経営において“人間性”を中核に据えたことで知られる。彼は企業を「利益を出すための装置」ではなく、「人と人とが交わる文化の交差点」と捉えていた。
シュルツは、企業の成長とともに、貧困層への奨学金、サステナビリティへの投資、人種間対話の推進など、社会課題への貢献を事業戦略の中に組み込んでいった。その思想の根底には、「経済的成功と社会的意義は両立できる」という信念があった。
この信念は、まさに『大学』の「平天下」と軌を一にしている。企業という一つのエンティティが、文化、宗教、人種、政治的立場を超えて、“共に生きる社会”をデザインしようとする志こそ、「天下の和」の現代的表現である。
5-7 グローバルリーダーに求められる“精神の器”とは
最終的に、『大学』が「平天下」において我々に問うのは、“精神の器”の大きさである。自己修養を重ね、家庭や組織、社会の倫理を整えてきたリーダーが、世界全体を調和させる責務を負うに値するかどうか──それがこの段階の主題である。
グローバル時代において、文化的多様性、歴史的背景、宗教的信条、経済格差が入り混じる中で、「対立ではなく、共生のビジョンを描けるリーダー」こそが、次の時代を切り開く存在である。
すなわち、“自国の利害”から“人類の共益”へと視座を転じられる人物。それが「平天下」に到達したリーダーの姿なのである。
第6章 八条目に学ぶ自己変容モデル──人格と実践をつなぐ行動プロセス
6-1 八条目とは“内面から世界へ至るリーダー成長の地図”である
『大学』における八条目(格物・致知・誠意・正心・修身・斉家・治国・平天下)は、表面的には一連のステップに見えるが、実際には人間の内面構造と行動原理をつなぎ、自己変容から社会的影響力の発揮までを段階的に導く“人格形成のマップ”である。
この構造は、自己の思考や感情の深層に問いを投げかけ、その洞察から意思を明確にし、行動を統御し、周囲との関係性を整え、やがて公共と世界への働きかけに昇華していくという、一貫した論理性を持っている。
現代のビジネスリーダーがこの八条目を活用するならば、それは単なる古典の暗誦ではなく、「人格開発と組織統率を統合するフレームワーク」としての意味を持つ。以下、それぞれの項目を現代的視座から再解釈し、応用の道を探っていく。
6-2 格物(かくぶつ)──“現実を見る力”を磨く
「格物」とは、物に格(いた)る、すなわち対象を深く観察し、その本質に至ることである。これは単なる情報収集ではない。主観や思い込みを排し、ありのままを見つめる力=認識力の修養である。
現代でいえば、これはメタ認知(metacognition)に相当する。自分の考え方の癖を認識し、他者との視点の違いを理解し、常に「本質は何か」と問う姿勢がここで求められる。
グローバルリーダーにとって、この格物の訓練は、国際交渉、多文化理解、複雑な意思決定の場で大きな差を生む要素である。
6-3 致知(ちち)──“深く理解する知”を追求する
「致知」とは、「知を致す」、すなわち真理に到達しようとする探究的な知性を意味する。格物によって得た情報・経験を、自己の内側で熟成させ、「何が真に価値ある知か」を見極める段階である。
これは、現代における批判的思考(critical thinking)と熟考力(reflection)を含む。リーダーにとっての「知」とは、知識量ではなく、「物事の意味と価値を判断する力」である。
“なぜこの事業をやるのか”“この判断は誰に何をもたらすか”といった問いを持ち続けることが、致知の実践となる。
6-4 誠意(せいい)──“偽らざる心”をつくる
「誠意」とは、自分の内面を偽らない、虚飾を排した「真心」を意味する。これは単なる誠実さの強調ではない。意志決定の動機が、自我や虚栄ではなく、“まごころ”から来ているかを常に問い直す態度である。
心理学的にはこれは動機づけの自己一致性(authenticity)に該当する。他者に対してではなく、自分自身に対して誠実であることが、最も信頼される人格の基盤である。
リーダーは時に、利益、名誉、周囲の期待という誘惑の中で意思をねじ曲げられそうになるが、この「誠意」があってこそ、その意思は正しい方向に踏みとどまるのである。
6-5 正心(せいしん)──“心のコンディション”を整える
「正心」とは、思考や感情が歪んでいないか、自我に飲まれていないかを問い、心を整える技法である。ここに至って初めて、人格的行動が安定し、次の段階「修身」に移ることができる。
これは、現代的にはマインドフルネスや情動調整(emotional regulation)の領域に対応する。自分が怒っているとき、焦っているとき、あるいは過度に自信過剰になっているとき、心を調整できなければ判断も誤る。
「正心」できていないリーダーは、どれほど優秀でも組織に混乱をもたらす。反対に、落ち着いた「整った心」で臨むリーダーは、それだけで組織に安定と安心感をもたらすのである。
6-6 修身(しゅうしん)──“人格の土台”を築く
第2章で詳述したように、「修身」とは人格をつくる実践段階である。正しい行いを選び、徳を積むこと。これはリーダーとしての信用を築く唯一の道である。
ここで問われるのは、「私生活と公的態度に乖離はないか」「小さな約束を誠実に守っているか」「感謝と謙虚さを持っているか」といった基本的な人間性である。
修身は、短期的に評価されるものではない。だが、長期的に見れば、最も大きな「組織文化への影響」をもたらす核となる。
6-7 斉家・治国・平天下──“影響力の拡張”の実践ステージ
斉家・治国・平天下については、すでに第3〜第5章で詳述した通りである。ここでは、八条目の後半を、“影響の輪の拡大”の連続過程と再定義しておきたい。
- 斉家:信頼と倫理の共同体をつくる力(ミクロな社会)
- 治国:組織や社会に公共性を浸透させる力(メゾレベルの社会)
- 平天下:人類的共栄を志向する精神と実践(マクロな地球社会)
この段階に進むほど、人格の強さと理念の深さが問われる。そして、真に影響力を持つリーダーとは、この全領域にわたって「内と外の一致」が取れている人物である。
6-8:実践への転換──“八条目”を現代ビジネスに生かす
『大学』が説くリーダーの自己修養のステップは、次の八つの条目(順序)から成り立つ。
八条目:
- 格物(かくぶつ)
- 致知(ちち)
- 誠意(せいい)
- 正心(せいしん)
- 修身(しゅうしん)
- 斉家(せいか)
- 治国(ちこく)
- 平天下(へいてんか)
これは単なる抽象的な道徳訓ではなく、「リーダーとしていかに自己を統治し、組織・社会を導くか」という極めて実践的な“成長の道筋”である。本節では、各条目を現代のグローバルビジネスパーソン向けに再構成し、具体的な記入例・思考の例を示すことで、実践への橋渡しとしたい。
【1】格物──現実を観る力を養う(対象を深く理解する)
定義(現代語訳):事物(対象)に心を向け、真理を追求する態度
現代意義:自己を取り巻く「外的環境」と「人間関係」を正確に捉え、主観的思い込みを排除する
記入例(リーダーの視点):
- 組織内で生じている離職率の増加について、感情的な憶測ではなくデータ・ヒアリング・外部調査を通じて本質的要因を掴もうとする。
- 自社のカルチャーにおける“暗黙の了解”が異文化出身の部下にどう受け取られているかを、フラットに観察・確認する。
【2】致知──知を深め、自分の判断軸を鍛える
定義:真理を知ること、すなわち道理を理解すること
現代意義:得た情報・経験から「洞察」を導き、判断軸を確立するプロセス
記入例:
- 外資系企業での失敗プロジェクトを単なる「人間関係の不和」で片付けず、文化差・意思決定フロー・心理的安全性の欠如など、構造的問題として理解し直す。
- データ分析結果を鵜呑みにせず、なぜそのような傾向が生じているのか、背景要因を知見と照らし合わせて再構築する。
【3】誠意──自己との誠実な向き合い
定義:自分に嘘をつかず、言動を一致させる
現代意義:価値観と行動がずれていないか、内省を深める
記入例:
- 「人を大切にする」と言いながら、数字偏重のマネジメントになっていないかを定期的に内省する。
- 「心理的安全性」をチームに求めながら、自分自身が萎縮を生む態度を取っていないか振り返る。
【4】正心──心を整える
定義:欲や怒りに左右されず、静かな心で物事を判断する
現代意義:リーダーとして冷静さを保ち、判断のブレを最小化する
記入例:
- 会議で批判を受けた際、即座に感情的に反応せず、一度深呼吸して「相手が何を意図して言っているのか」にフォーカスを切り替える。
- 業績不振のストレス下でも、感情に振り回されない意思決定のために、毎朝のマインドフルネスを取り入れる。
【5】修身──人格を磨く
定義:自己修養を重ねることで、徳のある人間になる
現代意義:リーダー自身のあり方が周囲に影響を与えるという“人間力”の自覚
記入例:
- 月に一度、自身の価値観・志を見直す時間を持ち、リーダーとして「どう在りたいか」を再確認する。
- 自己中心的な利得を追い求めない、利他的な決断を貫けているかを内省する(例:昇進ではなく後進育成を優先する選択)。
【6】斉家──最小単位の共同体(家庭や組織)を整える
定義:家庭を治めること=最小の共同体を整えること
現代意義:リーダーとしてまずは自らの直属チーム、最小単位の組織文化を整える
記入例:
- 自身の部門において「心理的安全性」「対話の文化」を実践し、組織全体に波及させていく。
- 家庭とのバランスを整え、「公私一貫」の信頼できるリーダー像を体現する(例:家庭の安定が仕事にも好循環を生むという信念の実践)。
【7】治国──広い組織・国家に貢献する
定義:国や社会全体を治める
現代意義:自分の部署・会社を超えて社会的価値を提供する
記入例:
- 経営幹部として、社内のサステナビリティ推進に取り組み、自社が社会に与える影響について議論と行動を導く。
- ジェンダー平等や人材育成に関する長期方針に積極的に関与し、自組織を社会の善循環に加担させる。
【8】平天下──世界に調和をもたらす
定義:天下を平らかにする、つまり世界を調和に導く
現代意義:リーダーとして自らの行動を通じて、国境や文化を越えた影響力を与える
記入例:
- 多国籍チームにおいて、文化的多様性を尊重したマネジメントにより、調和的な成果創出に貢献する。
- ビジネスを通じて、地政学・国際関係・ESGの視点を踏まえたグローバルな価値創造に関与する(例:グローバル市場における倫理的調達の実現)。
🧭 総まとめ:八条目をリーダーの日常にどう実装するか
チェックポイント例:
- 「格物~致知」で情報リテラシーと判断力の精度を上げる
- 「誠意~修身」で心の筋力を整える
- 「斉家~治国~平天下」で他者・社会への影響力を磨く
この八条目は、「知って終わり」ではなく「行動の指針」として機能させてこそ真価を発揮する。現代のグローバルビジネスパーソンにとっても、自律的なリーダーシップのスパイラルを形成するための優れた“内なるナビゲーション”となるはずである。
以下に「八条目(格物・致知・誠意・正心・修身・斉家・治国・平天下)」の実践的チェックリストを表形式でまとめた。グローバルビジネスリーダーが日常的に自己点検・自己統治するためのガイドとしてご活用いただける。
【八条目の実践チェックリスト(『大学』に基づく現代的応用)】
条目 | 現代的意味 | 実践チェックリスト例 |
格物 | 事象を客観的に観察・理解する力を養う | ・主観を排して現場観察やヒアリングを行っているか?・偏見に基づいた意思決定をしていないか? |
致知 | 情報から本質を見抜く判断力を磨く | ・背景要因まで掘り下げた思考ができているか?・分析と直観を統合しているか? |
誠意 | 価値観と行動の一致を確認する内省を行う | ・自分の言動にズレはないか?・理念と行動が一致しているか? |
正心 | 感情に振り回されず冷静さを保つ | ・判断時に怒りや欲望が影響していないか?・落ち着いて物事を見つめているか? |
修身 | 人格と志を高め、行動の軸を強化する | ・日々、自分の在り方を内省しているか?・利他的な姿勢を持てているか? |
斉家 | 直属のチームや家庭を整える | ・チーム内の信頼関係を築いているか?・私生活とのバランスは取れているか? |
治国 | 広範な組織や社会に貢献する | ・自部署を超えて貢献しているか?・社会的視点を持った判断をしているか? |
平天下 | 文化・国境を超えた調和を目指す | ・国際的視野での倫理を考慮しているか?・多文化共生に貢献しているか? |
終章 “格”あるリーダーとは何か──思想を実践に変えるために
7-1 今、なぜ『大学』なのか──時代の乱流とリーダーの責任
AI、気候変動、分断と格差、国家と市場のねじれ──現代社会は未曾有の変化と不確実性に直面している。テクノロジーが人間の判断を超え、個人の情報がアルゴリズムによって分断される世界において、我々はかつてないほど、「人間とは何か」「人を導くとは何か」という根源的な問いに直面している。
このようなVUCAの時代において、リーダーに求められるのは、変化に適応する能力以上に、変化の中で「不変の軸」を持つことである。すなわち、環境や市場がどう変わろうとも、「自らの在り方」を揺るがせにしない心の土台こそが、最も深く、最も強い競争力となる。
『大学』は、この「不変の軸」をつくる古典である。
7-2 “格”とは何か──地位でも知識でもなく、人格の質である
『大学』は、何よりもまずリーダーに「明明徳」を求める。すなわち、己の内にある善なる本質を明らかにし、それを輝かせることが出発点である。そこには、肩書や権限、知識量では測れない「人間の器」の広さと深さが問われている。
現代風に言えば、それは「インテグリティ(integrity)」に通じる。言行一致、動機の純粋性、感情の整合性、価値観の明確さ──これらすべてが統合され、「この人に従いたい」と思わせるリーダーには、“格”がある。
「格」とは、その人の持つ無言の信頼性と深い敬意を生む磁場のようなものである。それは瞬間的な能力ではなく、長年の思索と実践の積み重ねから生まれるものであり、外から飾ることはできない。
7-3 思想と実践の架け橋──八条目は行動哲学である
『大学』の優れた点は、思想が抽象的なままで終わらず、日々の実践と接続していることである。格物・致知・誠意・正心・修身・斉家・治国・平天下というプロセスは、精神の向上がいかにして現実の行動と世界への影響に転化するかを示している。
これは東洋における「行」と「道」の統合的理解であり、思想と実践を分断しない生き方を説いている。この意味で『大学』は、単なる教養書ではない。リーダーシップの“作法”と“哲学”を一体化させるマニュアルである。
7-4 安岡正篤の“人物学”が示す、真の宰相の条件
安岡正篤は、『大学』を「人物をつくる教え」と位置づけた。彼にとって、真のリーダーとは政策や数値に通じた人間ではなく、歴史と世界を見通す「大義」と「天命」を心に持ち、それに殉じる覚悟を持つ人物であった。
彼は次のように述べている。
「人物の基礎は修身にあり。リーダーに格がなければ、組織は腐る。国家は倒れる。」
これは決して誇張ではない。企業不祥事、政治の混乱、グローバル社会の対立──すべての背後には、「個の未熟さと無責任」がある。だからこそ、『大学』は今なお、リーダー教育の出発点としての輝きを失わないのである。
7-5 グローバル時代における『大学』の現代的意義
世界はますます相互依存を深める一方で、価値観の衝突が頻発している。宗教、民族、政治体制、経済格差、環境倫理──グローバルリーダーは、こうした“正解のない問題”に直面しながら意思決定を迫られる。
そのようなときに求められるのは、普遍的倫理観と自己の内なる指針に基づいた判断である。『大学』が説く「止於至善(しぜんにとどまる)」──最高善を目指して生きるという理念は、文化や国境を超えて、真に普遍的な羅針盤となりうる。
7-6 “自分を治める者こそ、世界を治めるに足る”
最後に、八条目の起点である「格物」から、終点の「平天下」に至る全体像を振り返ってみよう。
これは一人の人間の内面から始まり、社会・国家・世界へと影響を拡大していく道であると同時に、リーダーとしての成長と深化のプロセスそのものである。
- 自分の心を整え(正心)
- 自らを律し(修身)
- 組織に信頼を根づかせ(斉家)
- 理念で人を導き(治国)
- 世界の調和に貢献する(平天下)
このプロセスは、現代のどんなリーダーシップ理論とも異なる、思想・精神・実践を統合する東洋の叡智である。
総括:『大学』はグローバルリーダーの“魂の教科書”である
『大学』は古くとも、古びていない。それは、変わり続ける社会の中で、変えてはならないもの──人格、誠意、理念、公共心、そして世界への志──を静かに、しかし力強く教えてくれる書である。
グローバルリーダーとは、英語が話せる者でも、権力を持つ者でもない。心を整え、人格を磨き、人と世界を結ぶ者である。
そのようなリーダーを目指すすべての人に、『大学』は今なお、生きた指南書として寄り添い続けている。
ご感想、お問い合せ、ご要望等ありましたら下記フォームでお願いいたします。
投稿者プロフィール

- 市村 修一
-
【略 歴】
茨城県生まれ。
明治大学政治経済学部卒業。日米欧の企業、主に外資系企業でCFO、代表取締役社長を経験し、経営全般、経営戦略策定、人事、組織開発に深く関わる。その経験を活かし、激動の時代に卓越した人財の育成、組織開発の必要性が急務と痛感し独立。「挑戦・創造・変革」をキーワードに、日本企業、外資系企業と、幅広く人財・組織開発コンサルタントとして、特に、上級管理職育成、経営戦略策定、組織開発などの分野で研修、コンサルティング、講演活動等で活躍を経て、世界の人々のこころの支援を多言語多文化で行うグローバルスタートアップとして事業展開を目指す決意をする。
【背景】
2005年11月、 約10年連れ添った最愛の妻をがんで5年間の闘病の後亡くす。
翌年、伴侶との死別自助グループ「Good Grief Network」を共同設立。個別・グループ・グリーフカウンセリングを行う。映像を使用した自助カウンセリングを取り入れる。大きな成果を残し、それぞれの死別体験者は、新たな人生を歩み出す。
長年実践研究を妻とともにしてきた「いきるとは?」「人間学」「メンタルレジリエンス」「メンタルヘルス」「グリーフケア」をさらに学際的に実践研究を推し進め、多数の素晴らしい成果が生まれてきた。私自身がグローバルビジネスの世界で様々な体験をする中で思いを強くした社会課題解決の人生を賭ける決意をする。
株式会社レジクスレイ(Resixley Incorporated)を設立、創業者兼CEO
事業成長アクセラレーター
広島県公立大学法人叡啓大学キャリアメンター
【専門領域】
・レジリエンス(精神的回復力) ・グリーフケア ・異文化理解 ・グローバル人財育成
・東洋哲学・思想(人間学、経営哲学、経営戦略) ・組織文化・風土改革 ・人材・組織開発、キャリア開発
・イノベーション・グローバル・エコシステム形成支援
【主な著書/論文/プレス発表】
「グローバルビジネスパーソンのためのメンタルヘルスガイド」kindle版
「喪失の先にある共感: 異文化と紡ぐ癒しの物語」kindle版
「実践!情報・メディアリテラシー: Essential Skills for the Global Era」kindle版
「こころと共感の力: つながる時代を前向きに生きる知恵」kindle版
「未来を拓く英語習得革命: AIと異文化理解の新たな挑戦」kindle版
「グローバルビジネス成功の第一歩: 基礎から実践まで」Kindle版
「仕事と脳力開発-挫折また挫折そして希望へ-」(城野経済研究所)
「英語教育と脳力開発-受験直前一ヶ月前の戦略・戦術」(城野経済研究所)
「国際派就職ガイド」(三修社)
「セミナーニュース(私立幼稚園を支援する)」(日本経営教育研究所)
【主な研修実績】
・グローバルビジネスコミュニケーションスキルアップ ・リーダーシップ ・コーチング
・ファシリテーション ・ディベート ・プレゼンテーション ・問題解決
・グローバルキャリアモデル構築と実践 ・キャリア・デザインセミナー
・創造性開発 ・情報収集分析 ・プロジェクトマネジメント研修他
※上記、いずれもファシリテーション型ワークショップを基本に実施
【主なコンサルティング実績】
年次経営計画の作成。コスト削減計画作成・実施。適正在庫水準のコントロール・指導を遂行。人事総務部門では、インセンティブプログラムの開発・実施、人事評価システムの考案。リストラクチャリングの実施。サプライチェーン部門では、そのプロセス及びコスト構造の改善。ERPの導入に際しては、プロジェクトリーダーを務め、導入期限内にその導入。組織全般の企業風土・文化の改革を行う。
【主な講演実績】
産業構造変革時代に求められる人材
外資系企業で働くということ
外資系企業へのアプローチ
異文化理解力
経営の志
商いは感動だ!
品質は、タダで手に入る
利益は、タダで手に入る
共生の時代を創る-点から面へ、そして主流へ
幸せのコミュニケーション
古典に学ぶ人生
古典に学ぶ経営
論語と経営
論語と人生
安岡正篤先生から学んだこと
素読のすすめ
経営の突破口は儒学にあり
実践行動学として儒学に学ぶ!~今ここに美しく生きるために~
何のためにいきるのか~一人の女性の死を見つめて~
縁により縁に生きる
縁に生かされて~人は生きているのではなく生かされているのだ!~
看取ることによって手渡されるいのちのバトン
など


