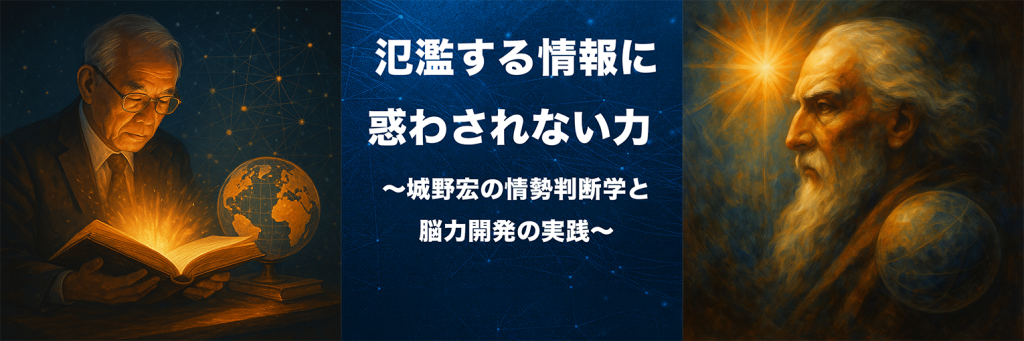
氾濫する情報に惑わされない力 〜城野宏の情勢判断学と脳力開発の実践〜
はじめに
私が城野宏先生に初めてお目にかかったのは、1979年の春のことである。大学卒業を控え、将来に対する期待と同時に、社会の荒波に投げ出される不安を抱いていた頃であった。ある知人に「ぜひ会っておくべき人物がいる」と紹介され、半信半疑で訪ねた先に先生はおられた。
鋭い眼光、明晰な頭脳――それだけなら近寄りがたい存在に思えたかもしれない。だが、先生と対話を始めると、そこに人間的な温かさが溢れていることをすぐに感じ取った。言葉の端々から「この若者を鍛え上げたい」という熱意と、同時に「失敗しても導いてやる」という深い慈愛が伝わってきた。私は瞬時に心を奪われ、門下生となる決意をした。
当時の日本社会は、大きな転換点にあった。前年1978年には日中平和友好条約が締結され、日本はアジア外交に新たな一歩を踏み出した。世界に目を転じれば、米ソ冷戦はなお緊張を増し、同年末にはソ連がアフガニスタンへ侵攻し、国際秩序は一気に不安定化していた。国内では高度経済成長が幕を下ろし、オイルショックの余波が残る中で新しい経済構造への模索が続いていた。新聞もテレビも大量の情報を発信していたが、その多くは断片的で、背後にある意図を読み解く視点を持たなければ本質に辿り着くことはできなかった。
まさにその渦中で、城野先生のもとには多くの門下生が集っていた。企業人、外交官志望の学生、教育関係者、さらには社会運動に関心を持つ若者まで、背景は実に多様であった。私もその一人として、夜ごと、週末ごとに先生を囲む学習会に通った。
学習会では、まず各自が新聞や雑誌の記事を持ち寄り、重要と考える一文に赤線を引き、その解釈を発表するのが常であった。ある時、私は米ソ関係に関する記事を読み上げ、表面的な解説を述べた。すると先生は静かにこう言われた。「君は記事に書かれていることをそのまま説明している。しかし、本当に知りたいのは『なぜこの記事が今、このタイミングで出たのか』だ。」この問いかけに私は答えに窮したが、そこで初めて「情勢判断学」という視点の鋭さを実感した。
門下生同士の議論もまた刺激的であった。ある仲間は大手商社に勤めており、国際経済の現場感覚を交えて議論を展開した。別の仲間は教育学を専攻しており、「脳力開発を子どもにどう応用できるか」を常に模索していた。外交官を志す者は、世界の地図を前に、各国の思惑を推測し合った。異なる背景を持つ私たちが一堂に会し、それぞれの知識や体験を交わすことで、議論は単なる机上の空論にとどまらず、現実に根ざした厚みを帯びていった。
先生は時に厳しく叱責された。発表の準備が甘いと「表面だけをなぞるな」と一喝されることもあった。しかしその叱責は決して人格を否定するものではなく、むしろ「もっと考え抜けるはずだ」という期待の裏返しであった。叱られた後には、必ず丁寧な解説と温かい助言が続いた。その繰り返しが私たちを鍛え上げ、自分の頭で考え抜く習慣を養ってくれた。
一方で「脳力開発」の実践は、学習会の前後で必ず行われた。深く腹式呼吸をし、姿勢を正して静かに目を閉じる。数分後には心が落ち着き、頭が澄み渡る感覚を覚えた。言葉の使い方についても指導があった。「人を動かす言葉は、相手を肯定する言葉でなければならない」と。肯定的な言葉を繰り返すことで場の雰囲気が変わり、議論の流れすら和らぐのを目の当たりにした。
これらの日々は、単なる知識習得ではなく「生き方そのものを学ぶ場」であった。門下生仲間との交流を通じて、私は多様な視点を吸収し、同時に自らの未熟さを痛感した。しかしその経験こそが、後にグローバル企業の現場で、また国際交渉の場で、他者の意見を尊重しつつ本質を見抜く力の基盤となったのである。
1979年から今日に至るまで、世界は大きく変化した。冷戦は終結し、グローバル化と情報化が進み、今ではAIやSNSが社会を揺るがす力を持つようになった。しかし、城野先生が語られた「脳力開発」と「情勢判断学」の意義は少しも色褪せていない。むしろ情報の洪水が深刻さを増す現代だからこそ、先生の教えは一層の輝きを放っている。
本書は、その教えを現代の読者に伝える試みである。序章では先生の壮絶な生涯を辿り、第1章以降では脳力開発と情勢判断学の理念と方法を詳細に解説する。そして冷戦期から現代に至る具体的な国際事例、国内政治の事件、欧米やアジアとの比較を交えながら、その学びが今日どのように応用できるかを明らかにしていく。
どうか読者の皆さんには、単なる歴史や理論の紹介として読むのではなく、自らの人生や仕事に直結する実践の知恵として受け止めていただきたい。そして日常の中で、呼吸を整え、姿勢を正し、言葉を選び、感性を磨きながら、氾濫する情報の中で主体的に判断する力を少しずつ育んでいただきたい。その営みこそが、城野宏先生が託された「人間が自由に生きる道」であると、私は確信している。
序章 城野宏という人物像
- 生涯と経歴
城野宏(1927–2002)は、戦後日本において「脳力開発」「情勢判断学」という独自の思想を打ち立てた人物である。その歩みは、日本の近代史と中国大陸の激動の歴史に深く結びついている。
彼は 長崎県西山町に生まれ、旧制東京府立四中、第八高等学校を経て、1938年に東京帝国大学法学部政治学科を卒業した。卒業後、野村合名会社調査部に入社したが、同年に徴兵され中国へ渡る。ここから、彼の人生は大きな転機を迎えることとなった。
1941年、陸軍中尉として第1軍参謀部に勤務した際、軍閥人脈で知られる河本大作との知遇を得る。そして中国山西省の独裁者閻錫山の政権に関わり、山西省政府顧問補佐官に就任した。これは単なる軍務ではなく、政治・経済・軍事の複雑な権力構造の只中に身を置く体験であり、後年の「情勢判断学」の土台となる「表の情報と裏の構造を読む」視点を磨く場であった。
1945年、日本が敗戦を迎えた後も城野は帰国せず、祖国復興と「山西独立」を掲げ、閻錫山と手を結んで抗中戦線に加わる。彼は**李誠(りせい)**の名を用い、毛沢東率いる中国人民解放軍と戦った。ここで彼が直面したのは、単なる軍事的衝突ではなく、国家イデオロギー、民衆の支持、国際社会の動向が絡み合う「大情勢」の現実であった。
1949年、ついに捕虜となり、中国で禁錮18年の刑を受ける。収容されたのは撫順戦犯管理所であり、ここで彼は長期にわたり思想改造を迫られ、情報統制下での人間の心理や集団行動を深く観察することになった。この体験は「人間はどのようにして情報に支配され、思考を停止するのか」という後年の問題意識につながった。
1964年、ようやく解放されて帰国する。20年近い拘禁生活から解き放たれた彼は、ただの「元軍人」や「元戦犯」ではなく、歴史の激流を生き抜き「情報と情勢の真実」を体感した人物となっていた。
帰国後、1967年には体験をまとめた『山西独立戦記』を刊行。1969年には城野経済研究所を設立し、1970年に日本教育文化協会理事長、産業新潮社会長を歴任。1975年にはスポーツ会館理事長に就任し、教育・文化・スポーツなど幅広い分野に活動の場を広げた。
- 経歴と思想形成の関係
城野の経歴を振り返ると、彼の思想がなぜ「脳力開発」と「情勢判断学」という二つの柱に結実したのかが明らかになる。
- 中国での軍務と顧問経験
権力者との関係、情報の操作、民衆の動員――これらの体験が「表に出る情報の背後にある意図を読む」姿勢を培った。 - 戦後の抗中戦線と捕虜生活
敗戦後も抗戦を続けた背景には「国家と個人の生き方」に対する強烈な信念があった。しかし捕虜生活の中で、彼は「人間は情報次第で善にも悪にも変わる」現実を知り、後の教育体系に「判断力」を不可欠な要素として組み込むことになる。 - 帰国後の研究・教育活動
単なる体験談にとどまらず、彼は自らの経験を学問として体系化し、多くの門下生に伝えた。脳力開発は「個人の潜在力を掘り起こす学問」として、情勢判断学は「社会や国際関係を誤らずに生き抜く学問」として双璧を成した。
- 歴史的背景との接点
城野の思想は、冷戦と日中関係という大きな歴史的文脈の中で理解すべきである。
- 冷戦下の日本
戦後日本は米国の庇護下で高度経済成長を遂げたが、情報や思想はアメリカ的価値観に大きく傾斜していた。ソ連との対立構造の中で、国民の思考も二分化されがちであり、主体的な判断力が求められた。 - 日中関係
1972年の日中国交正常化は、彼にとって感慨深いものであった。中国で戦い、捕虜生活を経験した人物だからこそ、表面的な友好ムードに惑わされず、背後にある歴史や権力構造を読み解く必要性を強く説いた。
このように、城野宏の経歴そのものが「脳力開発」「情勢判断学」を生み出す必然的プロセスであった。
第1章 脳力開発の理念
1-1 「脳力」と「能力」の違い ― 冷戦下の教育と社会
城野は「能力」と「脳力」を明確に区別した。
- 能力:外部的に測定される力。学歴、資格、スキル、点数など。
- 脳力:潜在意識、直観、感性、判断力、表現力など。人間が本来備えているが眠ったままの力。
この区別は、欧米思想とも響き合う。心理学者マズロー(Abraham Maslow)が唱えた「自己実現」は、人間の潜在力を開花させる重要性を強調したが、それは主として心理学的枠組みの中で語られた。城野はそれを日常生活・経営・国際関係に直結させた点で異彩を放った。
戦後日本の教育制度は、米国の占領政策の影響を受けて「民主化」「能力主義」が強調された。アメリカ式の「テストで測れる能力」が重視され、偏差値や資格が人間の価値を規定するようになった。この傾向は、冷戦期の米ソ対立の中で日本が「米国型資本主義の模範国」として振る舞うことと深く結びついていた。
しかし、この「能力偏重」は人間の総合力を狭め、主体的判断を奪った。国際政治の文脈で見れば、朝鮮戦争(1950–53)、ヴェトナム戦争(1960年代〜)といった東アジアを揺るがした戦争の中で、日本は米国の同盟国として振る舞う一方、国民の多くはその意味を深く考えず、報道の論調に流されていた。
城野はこれを痛烈に批判し、「能力ではなく脳力こそ、人間を自由にする」と説いた。彼自身、中国大陸での軍務と顧問経験を通じ、肩書きや学歴がまったく通用しない現実に直面した。生き延びるために必要だったのは、状況を直観で読み、相手の本音を感性で察し、瞬時に判断する力――すなわち脳力であった。
欧米との比較
米国では冷戦期、ソ連の科学技術に対抗するため「能力主義教育」が強化され、SATやIQテストのように測定可能な能力が重視された。だが同時に、ケネディ大統領が「直観に基づく決断」を示したキューバ危機(1962)のように、能力だけでは対処できない局面も多く存在した。
一方ソ連では、イデオロギー的能力(忠誠心・マルクス主義理解)が評価基準となったが、それが逆に人間の自由な発想を抑圧し、体制の硬直化を招いた。城野の「脳力」概念は、これら東西の「能力偏重」への根源的批判とも位置づけられる。
1-2 潜在意識と顕在意識 ― 情勢を生き抜く心理的基盤
フロイトやユング以来、西洋心理学は潜在意識の役割に注目してきた。フロイトは無意識の衝動を抑圧の源とみなし、ユングは集合的無意識を論じた。しかし城野は、潜在意識を「恐れるべきもの」ではなく「開発すべき資源」と捉えたのである。
例えば、彼は呼吸法を通じて潜在意識を活性化する方法を教えた。ある門下生は、営業の現場で緊張して言葉が出なくなる癖があったが、呼吸法の実践で心身の安定を得て、商談成約率が大きく向上した。これは潜在意識をポジティブに活用した事例である。
フロイトやユングに代表される西洋心理学は「無意識」を重視したが、冷戦期の情報戦争においても「人間の無意識」は重要な役割を果たした。米国の心理戦研究やソ連のプロパガンダ戦術は、人々の潜在意識に訴える方法を駆使していた。
城野が注目したのは、この「潜在意識」を防御と成長の両方に活用できる点である。彼は「情報に振り回されるのは、潜在意識を訓練していないからだ」と述べた。門下生には、呼吸法や言葉遣いを通じて潜在意識を整え、直観的に「情報の真偽を嗅ぎ分ける力」を磨かせた。
歴史的事例との接点
- 米ソ冷戦プロパガンダ:1950〜60年代、米国は「自由の防衛」を掲げ、ソ連は「社会主義の勝利」を宣伝した。両者とも潜在意識に働きかけるイメージ操作を行った。城野は門下生に「情報の裏を読むには、自分の潜在意識を澄ませよ」と教えた。
- 日中関係:1970年代、中国は「友好」の言葉を強調したが、国内では文化大革命の混乱が続いていた。この乖離を見抜くには、表面的情報に流されない直観力が不可欠であった。
門下生の証言
「新聞を読んでいても、以前は活字のまま受け入れていました。しかし先生に学んでからは“なぜこの見出しをつけたのか”と考える癖がつきました。その瞬間、私の潜在意識が働いていると実感しました。」(元商社マン)
1-3 脳力開発の体系化 ― 教育・経営・外交における実践
城野の脳力開発は、次の四領域に整理される。
- 感性の開発:自然や芸術に触れ、受容力を養う。
- 直観の開発:即断即決の判断力を養う。
- 思考の開発:論理的分析と創造的発想を融合させる。
- 表現力の開発:言葉・態度・行動を一貫させる。
この体系は、欧米のMBA教育やロジカルシンキングの枠組みを超えて、全人格的な人間形成を目指すものであった。
城野は脳力開発を、単なる精神論ではなく体系的実践として位置づけた。
- 感性の開発
戦後日本では経済成長が優先され、自然や芸術との関わりが軽視されがちであった。城野は「自然を感じる力が直観を育てる」と説き、門下生に茶道や俳句を奨励した。これは西洋の「芸術教育=リベラルアーツ」とも響き合う。 - 直観の開発
国際関係では「一瞬の判断」が国家の命運を分けることがある。1962年のキューバ危機で、ケネディが強硬派の進言を退け海上封鎖を選択したのは、直観力に支えられた判断だったとされる。城野は「脳力を磨けば、誰もがこの直観に近づける」と教えた。 - 思考の開発
日本の製造業が世界をリードした「カイゼン」思想は、論理的改善と現場の直観的工夫の融合であった。城野の思考開発は、まさにこの両面を統合するものである。 - 表現力の開発
外交の場では、言葉と態度に一貫性がなければ信頼を得られない。門下生の外交官は「先生に言葉の重みを叩き込まれたことが、国際交渉で相手の信頼を得る最大の武器となった」と語っている。
1-4 欧米・アジア比較事例
- 欧米の事例:シリコンバレーの起業家たちは、ビッグデータ解析と同時に「直観に従う決断」を重視する。これは城野の脳力開発と共鳴している。
- アジアの事例:韓国の大企業研修で瞑想や呼吸法を導入した結果、社員の創造性が高まり、組織文化が改善された。
- 日本の事例:ある地方企業は社員研修に脳力開発を導入。社員が自ら考え動くようになり、短期間で業績が向上した。
さらに門下生の証言も印象的である。
「先生に学んだのは、成功する方法ではなく“人間らしく生きる方法”でした。その結果、仕事でも人間関係でも道が開けたのです。」(元官僚)
「脳力開発で学んだ直観の力は、国際交渉の場で何度も私を助けてくれました。」(元企業駐在員)
日本
高度経済成長期の日本は「能力主義」の成果で経済大国となったが、同時に精神的な疲弊を生み出した。過労死や家庭崩壊が社会問題化した背景には、脳力開発の軽視があったと城野は指摘した。
アメリカ
シリコンバレーの起業家たちは「データと直観の両立」を強調する。スティーブ・ジョブズが禅に傾倒し、直観を重視したのは、城野の脳力論と深く響き合う事例である。
中国
文化大革命期(1966–76)、知識人は「能力」ではなく「階級的忠誠」で評価された。その結果、国家は混乱し、文化や科学技術は停滞した。城野は「能力主義もイデオロギー主義も、脳力を育てない限り人間を不自由にする」と喝破した。
韓国
儒教的秩序の中で急速に工業化を進めた韓国では、脳力を育む教育的余裕が欠けていたが、1990年代以降、瞑想や心理教育を取り入れ、創造性教育へと舵を切った。この転換は城野の思想と同質の方向性を持つ。
第2章 情勢判断学の誕生と意義
2-1 情勢判断学とは何か
情勢判断学とは、城野宏が提唱した「氾濫する情報の背後に潜む意図や構造を読み取り、誤らぬ判断を下すための学問」である。
単なる「情報収集」や「知識の整理」ではなく、
- 情報源の信頼性を吟味する力
- 表面的事実と隠された構造を見抜く力
- 歴史的文脈と国際的関係性を踏まえた解釈力
を総合する学問であった。城野は「情報は必ず操作されている」と繰り返し述べ、新聞記事や政府発表を鵜呑みにせず、その背後にある意図を読むことを門下生に徹底した。
2-2 歴史的背景:冷戦と日本社会
冷戦は軍事的対立であると同時に「情報戦」であった。米国は「自由と民主主義」を、ソ連は「社会主義と人民の解放」を掲げ、プロパガンダを駆使した。
CIAやKGBが世論操作を展開するなか、日本もまた米国寄りの情報環境に巻き込まれ、ベトナム戦争や沖縄返還をめぐる判断を誤りやすい状況にあった。
国内では高度経済成長で物質的豊かさが広がる一方、安保闘争や学生運動が激化し、国民は「どの情報を信じるか」で迷った。城野は「表面の賛否に惑わされず、国際政治と国内権力構造を読み解け」と指導した。
2-3 中国体験と情勢判断学の誕生
山西省での体験
山西省政府顧問補佐官として現地に関わった城野は、新聞の「大義」と現場の「真実」の乖離を目撃した。政府機関紙が「民衆は独立を熱望」と報じても、村落では飢餓と不安が広がっていた。ここで彼は「報道は権力の言葉である」と痛感した。
撫順での思想改造
1949年に捕虜となり、撫順戦犯管理所で18年間を過ごす。思想改造教育の場で、人々が「与えられた情報を真実と信じ込む」過程を観察し、人間が情報環境に支配されることを確信した。この体験が情勢判断学の出発点となった。
2-4 キューバ危機 ― 情勢判断学の象徴的事例
1962年10月、世界は核戦争の瀬戸際に立たされた。米国の偵察機がキューバに設置されたソ連の核ミサイル基地を発見し、ワシントンは一気に緊張状態に突入した。米軍首脳や強硬派は空爆による先制攻撃を主張し、米国内世論も「迅速な軍事行動」を支持する声が強かった。
だが、ケネディ大統領はその場で即断を下さず、情報の裏に潜むソ連の意図を冷静に探った。彼は「ソ連は米国との全面戦争を望んでいるのではなく、交渉のためのカードとしてキューバを利用している」と直観したのである。その結果、空爆ではなく「海上封鎖」という中間的な選択肢を採用し、最終的にソ連はミサイルを撤去、世界は核戦争を回避した。
城野宏はこの事例を「情勢判断の本質」を理解させるために繰り返し取り上げた。つまり、表面的な事実(ミサイル設置)や世論の激情(強硬策要求)に流されず、背後に潜む意図(ソ連の外交カード)を読み解くことこそが、誤らぬ判断の条件であるということである。
この意味でキューバ危機は、情勢判断学の理念を最も端的に示す象徴的事例であった。
2-5 日中関係のケーススタディ
国交正常化(1972年)
田中角栄と周恩来による日中国交正常化。当時の日本では「友好ムード」と理解されたが、城野は「中国の真意は米ソ対立の中で孤立を避ける戦略」と見抜いた。
天安門事件(1989年)
西側メディアは「民主化の否定」と報じたが、城野は「体制維持と国内安定のための選択」と解釈した。門下生の外交官は「情緒に流されず複眼的に読む習慣を持てた」と証言する。
2-6 国内政治のケーススタディ
安保闘争(1960年)
国会を揺るがした安保闘争。メディアは「民主主義か独裁か」で煽ったが、城野は「米ソ冷戦下の日本の立ち位置こそ本質」と警告した。
ロッキード事件(1976年)
田中角栄の逮捕は「汚職事件」と理解されたが、城野は「米国軍需産業と日本防衛政策の影響」という国際要因に注目せよと説いた。
2-7 欧米・中国比較
米国はCIA・シンクタンクによる「情報分析文化」を育てたが、国民教育には広がらなかった。城野はそれを一般教育に拡張しようとした。
ソ連は情報統制で現実を直視できず崩壊、中国は「人民日報」が唯一の言論機関として虚偽を流布した。城野は「主体的に構えなければ人は支配される」と強調した。
2-8 門下生の証言
- 外交官:「記事と現地実情が食い違うことは日常。情勢判断学のおかげで現場に即した判断ができた」。
- 経営者:「円高不況時、世論と逆に輸入ビジネスを決断できた」。
- ジャーナリスト:「発表の背景を読む視点が記事の差別化になった」。
2-9 教育的意義と現代への示唆
情勢判断学が育むのは、
- 表面的情報にとどまらない複眼的思考
- 国際関係と国内事情を結びつける歴史的洞察
- 冷静な直観と判断の統合
現代はSNS・フェイクニュース・情報操作が冷戦以上に深刻化している。米中対立、ウクライナ戦争、パンデミックを見れば、情勢判断学は「情報リテラシー+歴史洞察+直観力」の総合学問として、今まさに必要とされている。
第3章 脳力開発の具体的方法
3-1 実践重視の思想
城野宏の指導における最大の特徴は、「理念を机上の空論に終わらせない」という徹底した実践主義にあった。彼は門下生にこう語っている。
「脳力は、書物を読んで理解するだけでは決して身につかない。呼吸ひとつ、言葉ひとつ、日常の繰り返しを通じて初めて開花する。」
つまり脳力開発は、特別な才能や非日常的な修行を必要とせず、誰もが日常生活に取り入れられる方法であった。
3-2 呼吸法 ― 潜在意識を拓く扉
- 基本原理
城野が最も重視したのは「呼吸法」である。呼吸は自律神経に直結し、心身の安定と集中力に直結する。浅い呼吸は焦りや不安を増幅させ、深く整った呼吸は潜在意識を安定させる。
- 実践方法
- 背筋を伸ばして座り、肩の力を抜く。
- 鼻からゆっくり息を吸い、丹田(下腹部)に空気を送る意識を持つ。
- 吐く息は長く、心の雑念を押し流すように行う。
- 効果と事例
ある門下生(大手商社マン)は、交渉の直前に深い呼吸法を実践したことで、緊張せずに冷静な判断ができたという。これは脳科学的に見ても、呼吸が前頭前野を活性化し、判断力を高めることと一致する。
欧米では「マインドフルネス呼吸法」が近年注目されているが、城野はそれより数十年早く同様の効果を説いていた。
3-3 姿勢 ― 脳力の器を整える
- 身体と精神の連動
「姿勢が崩れると、思考も崩れる」と城野は繰り返した。姿勢は単なる身体的要素ではなく、潜在意識を支える基盤である。
- 実践方法
- 椅子に座る際は、背骨を一本の柱のように立てる。
- 歩行の際は、重心を下腹部に置き、肩の力を抜く。
- 会話の際は、相手の目を自然に見る姿勢を心がける。
- 効果と事例
門下生の一人は「姿勢を正すことで、自信が湧き、相手に説得力を与えられるようになった」と証言している。これは心理学的にも、姿勢が「自己効力感(self-efficacy)」を高める効果と一致する。
米国のリーダーシップ研究でも「パワーポーズ(堂々とした姿勢)」が注目されたが、城野はすでに1960年代に「姿勢は心を支える」と実践的に教えていた。
3-4 言葉 ― 内面と外界をつなぐ力
- 言葉の重み
城野は「言葉は心を映す鏡であり、同時に心をつくる力でもある」と説いた。言葉遣いを変えることで、思考と感情が変わり、潜在意識の状態も変化する。
- 実践方法
- 否定的な言葉を避け、肯定的・建設的な言葉を用いる。
- 「〜しなければならない」ではなく「〜してみよう」と表現する。
- 相手を尊重する言葉を選び、場の空気を調和させる。
- 効果と事例
ある教育現場で、教師が「失敗するな」ではなく「挑戦してみよう」と声をかけるようにしたところ、生徒の学習意欲が大きく向上した。これは欧米で広まった「ポジティブ心理学」の実証研究とも通じる。
外交の場でも、城野の門下生であった外交官は「相手を否定せず、肯定的な言葉で意見を伝える」習慣を実践し、難しい交渉を円滑に進めることができた。
3-5 感性の開発 ― 自然と芸術に学ぶ
- 感性の重要性
「直観は感性の土壌から生まれる」と城野は強調した。自然や芸術に触れることが、潜在意識を豊かにし、柔軟な判断を可能にする。
- 実践方法
- 日常的に自然に触れる(散歩、庭づくり)。
- 芸術を生活に取り入れる(音楽鑑賞、書道、茶道)。
- 感じたことを言葉にして記録する。
- 効果と事例
日本の門下生の中には、茶道を通じて感性を磨いた経営者がいた。茶の湯の作法から「間合い」と「空気を読む力」を学び、これを経営判断に応用したという。
欧米では、アート思考がイノベーション教育に導入されているが、城野はすでに「感性が直観を育てる」と教えていた。
3-6 思考と直観の統合 ― ケーススタディ
事例1:経営判断
1985年、プラザ合意で円が急騰した際、多くの日本企業は動揺した。しかし、城野の門下生であったある経営者は「為替の動きの背後には米国の国益がある」と直観的に見抜き、輸出依存から内需型ビジネスへの転換を決断。結果として企業は生き残った。
事例2:国際交渉
ある外交官は、相手国の言葉を表面通りに理解せず、その「沈黙」や「視線」に注意を払うことで、交渉の真意を掴んだという。これは城野の「直観は言葉の背後を読む力」という教えの実践例である。
3-7 脳力開発の教育的・経営的応用
教育への応用
- 生徒に呼吸法を教える → 試験前の緊張緩和
- 姿勢を整えさせる → 集中力と自己表現力の向上
- 言葉の使い方を指導する → 自己肯定感の育成
経営への応用
- 社員研修に脳力開発を導入 → 自主性とチーム力の向上
- 経営判断に感性と直観を取り入れる → 迅速な決断力の養成
- 異文化ビジネスでの表現力強化 → 信頼関係の構築
3-8 欧米・アジアとの比較
- アメリカ:シリコンバレーでの「マインドフルネス」導入は、創造性を高める効果を持つが、しばしば短期的ストレス軽減にとどまる。城野の脳力開発は「判断力の持続的強化」を目的とし、より深い。
- 中国:文化大革命期には「思考の自由」が奪われたが、改革開放後には瞑想や気功が再評価されている。これは脳力開発と近似する部分を持つ。
- 韓国:財閥企業での瞑想研修は協調性を育むが、依然として上下関係に縛られる。城野は上下関係を超えて「個人の主体性」を重視した点で異なる。
3-9 脳力開発の今日的意義
現代社会は、AIやデジタル情報が氾濫し、人間の判断力が逆に弱まる危険を抱えている。呼吸法・姿勢・言葉・感性――これらを磨くことで、AI時代に埋もれない「人間の判断力」を保持できる。
城野の言葉を借りれば、
「時代がいかに変わろうとも、呼吸し、姿勢を正し、言葉を選び、感性を磨くことは人間の根本である。」
第4章 情勢判断学の実践
4-1 情勢判断の基本姿勢
城野宏は、門下生に次のように語っていた。
「情報は必ず誰かの意図によって発せられる。事実そのものではなく、意図の反映なのだ。だから、まずは“なぜこの情報を今出したのか”を問え。」
この基本姿勢は、冷戦下の国際政治から日常の新聞記事に至るまで、あらゆる場面で適用できる。
- 第一段階:情報の発信源を確認する(政府・企業・メディア・個人)。
- 第二段階:その情報を出す意図を推測する(国内向け・国際向け・内部統制など)。
- 第三段階:表面的事実と歴史的背景、国際関係を結びつけて解釈する。
- 第四段階:潜在意識を澄ませ、直観で「何か不自然ではないか」を感じ取る。
これらは、単なる情報処理ではなく「主体的に情報に向き合う態度」である。
4-2 メディア情報の読み解き方
日本の事例:経済報道
高度経済成長期、新聞は「日本経済の奇跡」と繰り返し書き立てた。しかし城野は「これは国際政治の文脈で米国が日本に経済的役割を求めた結果であり、単なる“奇跡”ではない」と喝破した。門下生の一人はこれをヒントに為替動向を独自に研究し、バブル崩壊前に事業転換を成功させた。
欧米の事例:ベトナム戦争報道
アメリカでは当初「勝利目前」と報じられたが、実態は泥沼であった。ペンタゴン・ペーパーズの暴露でようやく世論が現実を知ることになる。この「公式発表と現実の乖離」は、城野が説く「情報の裏を読む」典型的な事例である。
アジアの事例:韓国民主化運動
1980年代、韓国政府は「安定」を強調したが、実際には学生や市民の抵抗運動が激化していた。門下生の外交官は、現地の空気を感じ取って報告を上げ、日本の政策判断に貢献した。
4-3 バイアスを見抜く技法
城野は「情報には必ずバイアスがある」と教えた。特に注意すべきは以下の三点である。
- 選択バイアス:都合のよい情報だけを報じる。
- 言語バイアス:表現のニュアンスで印象を操作する。
- フレーミングバイアス:前提条件を決めて議論を誘導する。
ケース:沖縄返還報道(1972年)
政府は「主権の回復」と強調したが、実際には米軍基地の存続が前提条件であった。城野は「これはフレーミングの典型だ」と指摘し、門下生に「言葉の裏を読む」訓練を課した。
4-4 経営における情勢判断学の応用
事例:オイルショック(1973年)
多くの日本企業が石油価格高騰に翻弄されたが、城野の門下生であった経営者は「これは単なる資源不足ではなく、中東の政治戦略の表れ」と分析。いち早く省エネ型製品へ転換し、業界で生き残った。
事例:グローバル企業の進出
欧米の多国籍企業は新興国進出の際、必ず現地メディアや政府発表だけでなく「市民の声」を情報源とした。これは「裏の情勢を読む」実践であり、城野の教えと一致する。
4-5 外交・安全保障における実践
ケース:日ソ漁業交渉
1970年代、日ソ間で漁業交渉が行われた際、日本側は「資源確保」を最優先にしたが、ソ連の真意は「安全保障上の発言権確保」であった。城野は「相手の経済的要求の裏に軍事的意図がある」と門下生に解説した。
ケース:米中接近(1972年)
ニクソン訪中は「友好」と報じられたが、城野は「ソ連包囲網の一環である」と分析した。実際その後、米ソ関係は一層緊張し、国際秩序は大きく変化した。
4-6 門下生の証言
- 商社マン:「交渉の場では、相手が言う“価格条件”よりも、その背後にある“資源確保の焦り”を読むようになった。これは先生に情勢判断を叩き込まれたおかげです。」
- 記者:「上司から“政府発表をそのまま書け”と言われた時、先生の言葉を思い出しました。“報じないことに真実がある”。結果として独自のスクープにつながりました。」
- 教育者:「生徒にニュースを読み解かせる授業をした時、単なる知識の暗記ではなく“裏を読む習慣”を植え付けることが教育の本質だと気づきました。」
4-7 現代における応用
今日、SNSとインターネットによって情報は民主化されたかに見える。しかし同時にフェイクニュースやアルゴリズムによる情報操作が横行している。
- 米中対立:双方がSNSを通じて相手を貶める情報戦を展開。
- ロシア・ウクライナ戦争:戦場映像が即時拡散されるが、その真偽は不明瞭。
- 国内政治:世論調査やネット世論が操作され、実態を見誤る危険がある。
城野が提唱した情勢判断学は、こうした現代社会においてこそ必要不可欠である。
4-8 情勢判断学の実践原則(まとめ)
- 情報は常に意図を帯びると心得る。
- 歴史的文脈を踏まえて解釈する。
- 国際関係と国内事情を結びつけて考える。
- 潜在意識を磨き、直観で違和感を掴む。
- 最終的な判断は、自らの責任で下す。
第5章 脳力開発と組織活性化
5-1 組織は「人の集合」ではなく「脳力の総和」である
城野宏は、「組織は単なる人員の寄せ集めではなく、そこで働く人々の脳力がどのように活かされているかで決まる」と強調した。
- 能力主義に偏った組織 → 学歴・資格の序列が優先され、上下関係に縛られる。
- 脳力開発を取り入れた組織 → 一人ひとりが直観や感性を発揮し、相互に補完し合う。
つまり、組織の生産性や創造性は「制度設計」よりも「人々が潜在力を引き出しているか」によって左右される。
5-2 リーダーシップにおける脳力開発の役割
- リーダーの判断力
冷戦下、国際政治や経済は一瞬で変化した。リーダーが情報に翻弄されるのではなく、直観と論理を融合させて判断することが必要だった。城野は「リーダーはまず自らの脳力を磨き、判断を誤らない存在でなければならない」と説いた。
- リーダーの表現力
言葉と態度が一致しないリーダーは信頼を得られない。門下生の一人であった企業経営者は、社員に対する言葉遣いを改善したことで、組織の士気が大きく向上したという。
- リーダーの感性
リーダーは数値データだけでなく、人々の感情や社会の空気を感じ取る必要がある。城野は「感性を育てよ、感性が人を導く」と教えた。
5-3 組織活性化の実践方法
呼吸法と会議
ある日本企業では、会議前に全員で1分間の深呼吸を行う習慣を導入した。その結果、議論が落ち着きを持ち、建設的な意見交換が増えた。これは脳力開発を組織レベルに応用した一例である。
姿勢と職場文化
欧米の企業では「オープンオフィス」が採用されることが多いが、そこでも姿勢は重要である。背筋を伸ばした姿勢で会話するだけで、相手に与える印象は大きく変わる。日本のあるメーカーは「姿勢研修」を導入し、顧客との信頼関係を強化した。
言葉の選び方
韓国の企業では上下関係が厳しく、上司の言葉がそのまま部下の行動を規定する。しかし、ある企業で「肯定的な言葉遣い」を徹底したところ、若手社員が自主的に提案を行うようになり、組織文化が変化した。
5-4 国際比較:欧米とアジア
- アメリカ:シリコンバレーの企業は「自由な発想」を尊重するが、その根底には「直観を信じるリーダーシップ」がある。ジョブズの例は脳力開発の象徴といえる。
- 中国:計画経済から市場経済に移行する過程で「人材の柔軟な判断力」が求められた。しかし文化大革命で失われた自由な思考は容易に取り戻せず、城野の「情勢判断学」が逆説的に必要とされている。
- 日本:終身雇用と年功序列が組織の硬直を生んだが、脳力開発を導入した企業では「若手の提案を取り入れる風土」が芽生え、活性化につながった。
5-5 ケーススタディ
ケース1:製造業のイノベーション
地方の中小製造業で、社員研修に脳力開発を導入。呼吸法や言葉遣いを学ぶことで、社員が自主的に改善提案を出すようになり、新製品が生まれた。結果、海外市場に進出するまでに成長した。
ケース2:外交組織の活性化
ある外交官チームは、国際会議前に「情勢判断演習」を実施。各国の発言の裏にある意図をシミュレーションすることで、交渉の場で的確に対応できた。これは組織全体で脳力と判断力を高めた例である。
ケース3:教育現場の変革
日本のある高校で、授業前に呼吸法と短い瞑想を導入。生徒の集中力が高まり、学力だけでなく自主性や協調性が向上した。教育現場でも脳力開発が組織文化を変える力を持つことが示された。
5-6 脳力開発と心理的安全性
今日の組織開発で重要視される概念に「心理的安全性」がある。これは、社員が自由に意見を述べても罰せられない環境を指す。城野の脳力開発は、この心理的安全性を実現する土台となる。
- 呼吸法で心の安定を得る
- 姿勢を整え相手を尊重する
- 言葉遣いで相互信頼を築く
これらの習慣が積み重なることで、組織に安心と挑戦の文化が育まれる。
5-7 現代的意義
AIやデジタル化が進む現代社会では、効率性や合理性ばかりが重視されがちである。しかし、組織を真に動かすのは「人間の脳力」である。
- データ分析が正確でも、最後の意思決定は人間の直観に依存する。
- AIが提示する選択肢も、背景を読む判断力がなければ誤用される。
- 国際交渉でも、数字や条文より「人の感情と信頼」が勝敗を決める。
城野が説いた「脳力開発による組織活性化」は、現代においても色褪せるどころか、むしろ必要性を増している。
第6章 情勢判断学と国家戦略
本書第2章では、キューバ危機を情勢判断学の象徴的事例として取り上げた。しかしここ第6章では、同じ事例を国家戦略の冷徹な文脈から再検討する。なぜなら、この危機は単に一人のリーダーの直観的判断にとどまらず、核抑止戦略や外交交渉の全体像を理解するための格好の素材だからである。
6-1 国家戦略における「判断力」の重要性
国家戦略とは、軍事力や経済力といった「ハードパワー」だけでなく、情報分析や外交判断といった「ソフトパワー」によって支えられている。城野宏が強調したのは、誤った判断が国家の存亡を左右するという厳粛な事実であった。
「国家は武力や経済で敗れるのではない。判断を誤った時に滅びるのだ。」
冷戦構造の中で、米国・ソ連・中国は徹底した情報戦を展開し、そこに日本も巻き込まれた。国家指導者が正しい情勢判断を欠けば、国民は大きな犠牲を強いられる。情勢判断学は、国家戦略における「羅針盤」としての役割を持つ。
6-2 冷戦下のケーススタディ
冷戦期、国家戦略における判断はしばしば「国家の存亡」を左右した。ここではその代表例を三つ取り上げる。
- キューバ危機(1962年)
第2章で述べたように、ケネディ大統領の冷静な判断が核戦争を回避したことはよく知られている。だが国家戦略の観点から見ると、この危機は単なる「直観的な判断」の勝利ではなかった。
米国は海上封鎖と同時に、ソ連に対して秘密裏に「トルコ・イタリアに配備された米国の核ミサイル撤去」を条件として提示していた。表向きには「ソ連の撤退のみを勝ち取った」と喧伝されたが、実際には「相互譲歩による危機回避」であった。この事実は長らく伏せられてきたが、後に公開された外交文書で明らかになった。
ここから見えてくるのは、国家戦略における情勢判断は、単なる勇気ある決断ではなく、軍事力・外交カード・国際秩序を総合的に勘案した冷徹な計算であったという点である。もしもケネディが空爆を選んでいれば、ソ連は報復措置を取り、核戦争は現実化していただろう。
この事例は、国家リーダーが「情報をどう読むか」で、国家の運命が決定づけられる典型的な証左である。
- ベトナム戦争(1955〜1975年)
アメリカは「ドミノ理論」に基づき軍事介入を拡大したが、実際にはベトナム民族の独立意志を過小評価した。情報を誤読した結果、国家戦略は泥沼化し、国内世論の分断を招いた。
→ 判断力の欠如が国家を弱体化させた例である。
- ソ連のアフガニスタン侵攻(1979年)
ソ連は「短期で安定化できる」と誤算したが、結果は10年にわたる消耗戦となり、最終的にソ連体制そのものが崩壊に追い込まれた。
→ 情勢を過小評価した代償の大きさを示す事例である。
6-3 日本における情勢判断の課題と可能性
- 日中国交正常化(1972年)
日本国内では「歴史的和解」と歓迎されたが、背景には米中接近の流れがあった。城野は「単なる友好ではなく、米ソ対立を背景にした地政学的再編」と分析し、日本が主体的判断を欠けば大国の思惑に翻弄されると警告した。
- バブル経済とその崩壊(1980〜90年代)
当時の日本政府と企業は「永遠の成長」と錯覚し、国際金融の構造変化を見抜けなかった。米国の金融戦略(プラザ合意)が日本経済を大きく揺さぶったが、その背景を的確に読めた指導者は少なかった。
→ 経済政策における情勢判断力の欠如が国家全体を揺るがした。
- 安保政策の転換
冷戦終結後、日本は「専守防衛」を基本としたが、東アジアの安全保障環境は大きく変化した。中国の台頭、北朝鮮の核開発、ロシアの再軍備などに直面する中で、情報収集と判断の重要性は増す一方である。城野なら「米国の戦略に盲従するな、独自の判断軸を持て」と説いただろう。
6-4 欧米との比較
アメリカ
米国はインテリジェンス機関(CIA、NSA)やシンクタンクを通じて、国家戦略に情報分析を組み込んだ。しかし、時に「イラク戦争(2003年)」のように誤った情報に基づき行動し、国際的信用を損なった。
→ 豊富な情報を持っても、判断の質が伴わなければ国家戦略は失敗する。
ソ連・ロシア
ソ連時代の情報統制は「不都合な真実を隠す」構造を生み出し、最終的に国民と指導者の間に深刻な乖離を招いた。現代ロシアでも「プロパガンダ国家」の傾向が続いており、国際的孤立を深めている。
→ 情勢判断を権力維持に矮小化すると、国家は長期的に弱体化する。
中国
中国は「百年の大計」として国家戦略を描き続けている。だが国内外の報道は厳しく統制され、正しい判断を下す材料が国民に与えられていない。城野の言葉を借りれば「国家指導者が情報を独占する社会は、一見強靱に見えても内部から脆弱になる」のである。
6-5 アジアにおける実践例
韓国
冷戦期の韓国は「反共イデオロギー」に基づく国家戦略をとったが、1980年代以降は民主化の流れに転じた。市民の声を無視した戦略は長続きせず、国家が発展するためには「多様な視点からの情勢判断」が不可欠であることが示された。
ASEAN諸国
ASEANは冷戦期に「非同盟」を掲げ、米ソ両陣営の板挟みを回避した。小国が生き残るために「大国の意図を読み解き、距離を取る」戦略は、情勢判断学の実践に近い。
6-6 現代日本への教訓
- 情報の多元化
SNSやメディアの分断が進む現代では、単一の情報源に頼らず、多元的視点を持つ必要がある。 - 歴史認識の深化
日中・日韓・日米の関係はいずれも歴史問題を背景に持つ。歴史的文脈を理解せずに外交判断を誤れば、国家戦略は短命に終わる。 - 直観と論理の統合
AIやデータ分析が進んでも、最後の判断は人間の直観に依存する。直観を鍛えることが国家戦略においても不可欠である。
6-7 国家リーダーに必要な資質
- 情報を鵜呑みにしない批判精神
- 国際関係を俯瞰する歴史的視点
- 国民に信頼される表現力と説得力
- 潜在意識を整えた直観的判断力
これらはそのまま「脳力開発」と「情勢判断学」の成果に他ならない。
6-8 結論 ― 国家戦略と情勢判断学
情勢判断学は、単なる個人修養の学ではなく、国家戦略の根幹に位置する。
冷戦期の危機、日中関係の変動、国内政治の混乱――いずれも「誤った判断」が国の方向を誤らせた。逆に、冷静かつ深い情勢判断を行ったリーダーは、国家を安定へと導いた。
城野宏が唱えた学びは、現代の日本が国際社会で主体性を確立する上で、依然として強力な指針となり得る。
第7章 脳力開発と人材育成
7-1 人材育成の本質とは何か
城野宏は、しばしば門下生にこう語った。
「人材とは、知識を持つ人のことではない。自分で考え、判断し、責任を引き受ける人のことだ。」
戦後日本の教育や企業研修は、知識やスキルの習得を重視したが、それは「能力開発」にとどまり、人間の全体性を育むものではなかった。城野が提唱した「脳力開発」は、潜在意識・直観・感性を磨き、判断力と表現力を備えた全人格的成長を促すものであり、人材育成における本質的アプローチであった。
7-2 教育における脳力開発
日本の教育現場
高度経済成長期の日本教育は「受験戦争」と呼ばれ、暗記と試験が重視された。だが、その結果「自分で考えない人材」が大量に生まれた。
ある高校では、授業に脳力開発を導入し、授業開始前に呼吸法を行い、授業後に「今日の気づき」を言葉にさせた。その結果、生徒の集中力が高まり、学力向上だけでなく、主体的学習態度が育まれた。
欧米の教育との比較
- アメリカ:リベラルアーツ教育が重視されるが、近年はSTEM偏重で「創造性」や「直観」を養う部分が薄れつつある。
- フィンランド:教育改革で「思考力」「対話力」を重視しており、城野の脳力教育に通じる要素を持つ。
- 日本:依然として偏差値主義が残るが、脳力開発の導入は、創造性教育への突破口となり得る。
アジアの事例
韓国やシンガポールでは、受験競争が激しい一方で、近年は瞑想やマインドフルネスを取り入れた教育プログラムが導入されている。これは「感性と直観」を育てる実践であり、城野の思想と共鳴する。
7-3 企業研修における脳力開発
事例1:日本の製造業
ある中堅製造企業では、脳力開発を社員研修に導入した。呼吸法、姿勢指導、肯定的な言葉遣いを学ばせた結果、社員の自主性が高まり、会議での発言数が飛躍的に増加。結果として新規プロジェクトが立ち上がり、業績も改善した。
事例2:欧米のリーダーシップ教育
アメリカの企業研修では「エグゼクティブ・コーチング」が盛んだが、その多くは「行動改善」に焦点を当てる。城野の脳力開発は「内面の潜在力を整える」点で異なり、より深い変革をもたらす。
事例3:アジアの国際企業
シンガポールのある国際企業は、社員に毎朝3分の呼吸瞑想を導入。集中力が向上し、異文化チームの摩擦が軽減した。これは、脳力開発の普遍性を示す事例である。
7-4 グローバル人材育成と脳力開発
グローバル企業においては、単に語学力やビジネススキルでは不十分である。異文化環境では「相手の意図を直観で察知する力」や「状況に応じて柔軟に判断する力」が必須である。
ケース:日米ビジネス交渉
ある日本人ビジネスマンは、米国企業との交渉で相手の強い言葉に圧倒されそうになったが、脳力開発で学んだ呼吸法で冷静さを取り戻し、論理と直観を統合して反論。結果的に交渉を有利に進められた。
ケース:ASEANでのチーム運営
多国籍チームでは、言語や文化の違いで誤解が生じやすい。脳力開発を実践していたリーダーは、相手の表情や沈黙から本音を察し、チームの信頼関係を築いた。
7-5 脳力開発と人材育成の方法論
城野は、以下の三段階で人材育成を指導した。
- 自己統御(呼吸・姿勢・言葉の修練)
- 判断力強化(情報の裏を読み、直観で補う訓練)
- 表現力と行動(自らの判断を組織内外で発信し、責任を負う)
この三段階を経ることで、単なる「有能な人材」ではなく、「判断力あるリーダー」が育成される。
7-6 現代的意義:AI時代の人材育成
現代はAIやデータ分析が進み、人間の知識的優位性は相対的に低下している。だが、AIには「直観」「感性」「倫理的判断」がない。
脳力開発は、まさにAI時代に必要な「人間ならではの力」を育てる教育である。
- 教育:思考停止ではなく、主体的に考える人材を育てる。
- 企業:変化の激しい国際市場で柔軟に対応できる人材を育成する。
- 国家:情報戦・経済戦を生き抜くために、国民全体の判断力を高める。
7-7 結論 ― 人材育成における普遍的価値
脳力開発による人材育成は、日本社会のみならず、欧米やアジア諸国においても普遍的な意義を持つ。
- 日本 → 偏差値主義を超え、主体的判断力を育てる。
- 欧米 → 論理偏重を補完し、直観と感性を統合する。
- アジア → 受験競争や上下関係を超えて、個人の潜在力を活かす。
城野宏の教えは、国境を越えて「人間が人間らしく判断し、生きる力」を育てるものであった。
第8章 情勢判断学とメディアリテラシー
8-1 情報洪水の時代と「判断力」の危機
21世紀の社会は「情報化社会」と呼ばれる。しかしその実態は「情報洪水」ともいえる状態である。
- テレビ・新聞などの既存メディア
- インターネット、SNS、YouTube
- AIによる自動生成コンテンツ
これらが秒単位で拡散され、人々は常に情報に晒されている。その一方で、情報の真偽を確かめず、感情的に共有・反応する傾向が強まっている。結果として、社会の分断、フェイクニュースによる混乱、選挙や国際関係への干渉が深刻化している。
城野宏が半世紀前に提唱した「情勢判断学」は、この状況に極めて適合する。情報の裏を読む力、意図を見抜く力を持たなければ、個人も国家も誤った方向へ流されるのである。
8-2 冷戦期から学ぶ「情報操作」の構造
米ソのプロパガンダ
冷戦期、米国は「自由と民主主義」を、ソ連は「社会主義と人民解放」を掲げ、互いにプロパガンダを展開した。テレビ、ラジオ、新聞はすべて「国家の意図を浸透させる道具」と化していた。
日本の事例
1960年代、ベトナム戦争をめぐる報道では、米国の意図を反映した記事が多く、日本国民は「正義の戦い」と誤認した面がある。城野は「報道は必ず誰かの利益を背負っている」と指摘し、情報の発信源を吟味する姿勢を門下生に徹底した。
この経験は、現代のSNS時代にもそのまま当てはまる。情報の送り手を問わず受け入れる危うさは、当時も今も変わらない。
8-3 現代における情報の歪みと操作
- フェイクニュース
SNS上で瞬時に拡散される虚偽情報は、しばしば事実よりも影響力を持つ。2016年の米大統領選挙では、ロシアによる情報操作が疑われた。
- アルゴリズム・バブル
SNSのアルゴリズムは、人々に「見たい情報」だけを与え、異なる意見に触れる機会を奪う。結果として、社会の分断が加速する。
- AI生成コンテンツ
AIが大量の文章や画像を自動生成する時代、真偽の見分けは一層難しくなっている。発信源の不明確さが判断を曇らせる。
8-4 情勢判断学を用いたメディアリテラシー実践法
城野の教えを現代のメディア環境に応用すると、次の方法論が浮かび上がる。
- 情報源を確認する
発信者は誰か、どの立場か、利益は何かを問う。 - 表現の選択に注意する
見出しや強調表現の裏に意図が潜む。 - 報じられない情報に注目する
沈黙や省略に真実が隠されている。 - 複数の情報を突き合わせる
国内外のメディア、一次資料を比較する。 - 直観で違和感を掴む
「何か不自然だ」と感じる感性を大切にする。
8-5 ケーススタディ
ケース1:パンデミック報道(2020年〜)
世界中でCOVID-19に関する情報が錯綜した。ある国では感染者数を過小報告し、別の国では過剰に恐怖を煽った。日本国内でも「楽観論」と「悲観論」が交錯し、国民は混乱した。城野の教えを応用すれば、各国の発表を鵜呑みにせず、その背景にある「政治的意図」や「経済的打算」を読み解くことができる。
ケース2:ウクライナ戦争(2022年〜)
ロシアとウクライナ双方がSNSを用いた情報戦を展開。映像や証言が拡散されるが、偽造も混ざり、真偽の判定は困難であった。門下生の一人は「先生の教えを思い出し、複数の情報源を常に突き合わせることで、冷静に判断できた」と証言している。
ケース3:国内政治の世論調査
日本の選挙時、メディアは「◯◯党が優勢」と報じるが、実際の投票結果と乖離することも多い。城野は「世論調査は世論を作るための道具になる」と指摘し、調査方法や設問の仕方に潜むバイアスを見抜くよう指導した。
8-6 欧米・アジア比較
- アメリカ:メディアは多様だが、分断が激しく、CNNとFOXのように真逆の論調が併存する。情勢判断学は、両者を突き合わせて「第三の視点」を得る訓練になる。
- ヨーロッパ:公共放送の信頼性が比較的高いが、移民問題やEU政策では報道にバイアスが生じる。
- 中国:国家統制が強く、情報の自由は限定される。そのため「報じられないこと」を読む力が特に重要になる。
- 韓国:世論の波が強く、感情的報道が社会を揺さぶることがある。日本同様に「冷静な裏読み」が不可欠である。
8-7 情勢判断学と現代教育
現代の教育では、メディアリテラシー教育が求められている。しかし、多くは「情報の信憑性をチェックする」技術的訓練にとどまる。
城野の情勢判断学は、その一歩先を行く。
- 発信者の意図を読み解く
- 報じられない部分に注目する
- 歴史的文脈を踏まえる
これらを教育に組み込むことで、真に主体的な市民を育成することができる。
8-8 結論 ― 情勢判断学が切り拓くメディアリテラシー
現代社会では、情報の真偽を見抜く力が「生きる力」と直結する。フェイクニュースや情報操作は、国家戦略の一部であり、個人が無防備に受け入れれば、社会全体が翻弄される。
城野宏が唱えた情勢判断学は、単なる情報リテラシーではなく、「人間の直観と批判精神を鍛え、情報の背後にある意図を読む学問」である。これは現代のメディア環境にこそ必要な「新しい教養」として再評価されるべきである。
第9章 未来を拓く脳力開発と情勢判断学
9-1 21世紀の環境変化と人間の危機
現代社会は、かつて城野宏が生きた冷戦期以上に複雑かつ不安定な情勢にある。
- AIと自動化:人間の知識・計算能力がAIに代替されつつある。
- グローバル化:国家や企業が相互依存し、ローカルな問題が瞬時に世界に波及する。
- 価値観の多様化:民族、宗教、文化の違いが共存する一方で、対立の火種にもなっている。
- 情報環境:SNSによる情報拡散が社会分断やフェイクニュースを助長している。
この中で問われるのは、「人間はどのような力で未来を生き抜くのか」である。
9-2 AI時代における脳力開発の意義
AIは膨大な情報を処理し、迅速な分析を行う。しかし、AIが持ち得ないのは「直観」「感性」「倫理的判断」である。
人間にしかできないこと
- 直観的判断:状況の本質を瞬時に掴む力。
- 倫理的選択:善悪の基準に基づく行動。
- 感性の共鳴:音楽や芸術を通じて他者と心を通わせる力。
城野が説いた脳力開発(呼吸・姿勢・言葉・感性の磨き)は、まさにAI時代において人間が人間らしく存在するための基盤である。
9-3 グローバル化と情勢判断学
21世紀の国際社会は、米中対立、ロシアの軍事行動、中東紛争、気候変動など、多層的な危機に直面している。
- 米中対立:経済摩擦だけでなく、情報戦・AI戦争に発展している。
- ヨーロッパ:EU統合と移民問題の狭間で分断が進む。
- アジア:ASEAN諸国は大国の間でバランスをとりつつ生存戦略を模索している。
情勢判断学は、こうした複雑な世界で「表面的スローガン」に惑わされず、各国の意図と歴史的背景を読む力を提供する。
9-4 多文化共生と人間力
未来社会の課題は「多文化共生」である。異なる文化や宗教を持つ人々と共に働き、共に暮らす世界において必要なのは、相手を理解する感性と、相手の意図を読む直観力である。
脳力開発で培われる「心を澄ませる習慣」は、異文化コミュニケーションにおける最良の土台となる。欧米企業でも「マインドフルネス研修」が導入されているが、城野の体系はそれを超えて「判断学」と結びつけ、人間関係と組織運営の双方を強化する。
9-5 ケーススタディ:未来社会への応用
ケース1:AIとの協働
日本のある企業は、AIが提示する分析を「最終判断者」が直観で検証する仕組みを導入した。データに従うだけではなく、人間の感性で補完することで誤判断を防いでいる。
ケース2:国際紛争の調停
国際機関に属する日本人外交官が、城野の教えを応用し「発言される言葉ではなく、沈黙にこそ相手の意図がある」と気づき、停戦合意の糸口を見つけた。
ケース3:教育の未来
アジアのある国際学校では、授業に「情勢判断学演習」を導入。生徒は新聞記事を比較し、背景を読み解く訓練を積むことで、将来のリーダーとして主体的な判断力を養っている。
9-6 城野宏の思想が現代に投げかける問い
- 情報は意図を帯びる
AIやSNS時代でも、情報を操作するのは「人間」である。その意図を見抜く目を持て。 - 人間の全体性を育てる
知識や技能だけでなく、直観・感性・判断力を統合する教育が必要である。 - 主体的に生きる
国家や企業の論理に流されるのではなく、自ら判断し、自ら責任を持って行動する人間を育てよ。
9-7 結論 ― 未来を生き抜くために
未来を拓く力は、技術や経済力だけではない。
- 個人においては、呼吸・姿勢・言葉・感性を整える「脳力開発」。
- 国家や社会においては、意図を読み解き誤らぬ判断を下す「情勢判断学」。
この二つの学びは、相互に補完し合いながら、人類が不確実な時代を生き抜く羅針盤となる。
城野宏が半世紀前に提唱した教えは、冷戦を超えて、AIとグローバル化の時代にこそ新たな生命を吹き込まれているのである。
終章 城野宏から現代へのメッセージ
- 城野宏の生涯と思想の結晶
長崎の小さな町に生まれた一人の青年が、中国大陸で苛烈な歴史の渦に巻き込まれ、敗戦と捕虜収容所を経験し、18年の禁錮を経て帰国した。
彼が日本に戻ってから語り続けたのは、単なる回顧録ではなかった。それは、人間は情報に翻弄される存在でありながら、訓練と自覚によって自由な判断を取り戻せる という希望であった。
脳力開発と情勢判断学は、その壮絶な人生を背景にした「生きる知恵」であり、同時に未来への遺産であった。
- 「主体的に生きる」ということ
城野は門下生に繰り返した。
「人間は、自分で考え、判断し、責任を引き受けるときに初めて自由になる。」
これは単なる自己啓発ではない。国家や企業、メディアの意図に流されることなく、自らの内なる直観と感性を信じ、世界の動きを批判的に読み解く姿勢を持てという厳しい呼びかけであった。
この「主体性」は、AIやグローバル化の時代にこそ求められる。データに依存し、他者の判断に従うだけでは、未来を生き抜くことはできない。
- 読者への呼びかけ ― 脳力開発と情勢判断学の実践へ
本書をここまで読んだあなたに伝えたい。脳力開発や情勢判断学は、難解な学問ではない。日々の呼吸法、姿勢の正しさ、言葉遣い、感性の磨き――その一つひとつが「脳力」を育てる。
新聞を読むとき、SNSの投稿を見るとき、必ず「なぜ今この情報が流されたのか」と自問する。それが「情勢判断学」の第一歩である。
- 職場での意思決定に迷ったとき、呼吸を整え、感性を澄ませて直観を信じよ。
- 国際ニュースを見たとき、その背後にある歴史と意図を読み解け。
- 人と対話するとき、言葉と沈黙の両方に耳を澄ませよ。
この実践の積み重ねが、あなた自身の判断力を鍛え、組織を動かし、社会を変える力となる。
- 現代社会における意義
- AIの時代:人間が人間であるために、直観・感性・倫理を鍛え続けること。
- グローバル社会:多様な文化と価値観を理解するために、感性と判断力を統合すること。
- 不確実な国際秩序:国家の宣伝やメディアの偏向を見抜き、主体的に判断すること。
これらはすべて、城野が半世紀前に指摘したテーマである。そして今、その重要性はかつてなく高まっている。
- 終わりに ― 「未来は人間の判断力にかかっている」
城野宏の人生は、激動の20世紀を生き抜いた「人間の証言」であった。同時に、それは21世紀を生きる私たちへの警鐘であり、希望でもある。
未来を決定づけるのは、経済力でも軍事力でもなく、人間が誤らぬ判断を下せるかどうか である。
脳力開発と情勢判断学は、そのための普遍的な学びであり、今を生きる我々に託された責務である。
読者の一人ひとりが、日常の中で呼吸を整え、姿勢を正し、言葉を選び、感性を磨き、情報を批判的に読み解くとき、そこに新しい未来が開ける。
「人間の自由は、判断する力から始まる」
この言葉を胸に、あなた自身の実践を始めてほしい。
参考文献一覧(APA形式)
序章 城野宏の生涯と思想的背景
- 城野宏. (1967). 山西独立戦記. 東京: 産業新潮社.
- 城野宏. (1970). 脳力開発入門. 東京: 産業新潮社.
- 長尾龍一. (2001). 昭和史を生きた知識人. 東京: 中央公論新社.
第1章 脳力開発の理念
- 城野宏. (1973). 人間力の開発. 東京: 講談社.
- Maslow, A. H. (1968). Toward a Psychology of Being (2nd ed.). New York: Van Nostrand Reinhold.
- Frankl, V. E. (1959). Man’s Search for Meaning. Boston: Beacon Press.
第2章 情勢判断学の誕生と意義
- Allison, G. (1971). Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis. Boston: Little, Brown.
- 城野宏. (1975). 情勢判断学入門. 東京: 日本教育文化協会.
- Johnson, C. (1982). MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925–1975. Stanford: Stanford University Press.
第3章 脳力開発の具体的方法
- 城野宏. (1972). 脳力開発と自己実現. 東京: 産業新潮社.
- Kabat-Zinn, J. (1990). Full Catastrophe Living: Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness. New York: Delta.
- Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience. New York: Harper & Row.
第4章 情勢判断学の実践
- 城野宏. (1976). 日本の進路と情勢判断. 東京: 産業新潮社.
- Hallin, D. C. (1986). The “Uncensored War”: The Media and Vietnam. Berkeley: University of California Press.
- Herman, E. S., & Chomsky, N. (1988). Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. New York: Pantheon.
第5章 脳力開発と組織活性化
- 城野宏. (1977). 経営と脳力開発. 東京: 産業新潮社.
- Senge, P. M. (1990). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. New York: Doubleday.
- Edmondson, A. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative Science Quarterly, 44(2), 350–383.
第6章 情勢判断学と国家戦略
- Kennedy, R. F. (1969). Thirteen Days: A Memoir of the Cuban Missile Crisis. New York: W. W. Norton.
- Kissinger, H. (1994). Diplomacy. New York: Simon & Schuster.
- Iriye, A. (1997). Cultural Internationalism and World Order. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
第7章 脳力開発と人材育成
- 城野宏. (1978). 人材育成と脳力開発. 東京: 産業新潮社.
- Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books.
- OECD. (2018). The Future of Education and Skills: Education 2030. Paris: OECD Publishing.
第8章 情勢判断学とメディアリテラシー
- 城野宏. (1979). 情報化社会と情勢判断. 東京: 産業新潮社.
- McLuhan, H. M. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man. New York: McGraw-Hill.
- Sunstein, C. R. (2017). #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Princeton: Princeton University Press.
第9章 未来を拓く脳力開発と情勢判断学
- 城野宏. (1980). 未来を読む情勢判断. 東京: 産業新潮社.
- Nye, J. S. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: PublicAffairs.
- Harari, Y. N. (2018). 21 Lessons for the 21st Century. London: Jonathan Cape.
終章 城野宏から現代へのメッセージ
- 城野宏. (1981). 人間の自由と判断力. 東京: 産業新潮社.
- Fromm, E. (1941). Escape from Freedom. New York: Farrar & Rinehart.
- Sen, A. (1999). Development as Freedom. New York: Knopf.
ご感想、お問い合せ、ご要望等ありましたら下記フォームでお願いいたします。
投稿者プロフィール

- 市村 修一
-
【略 歴】
茨城県生まれ。
明治大学政治経済学部卒業。日米欧の企業、主に外資系企業でCFO、代表取締役社長を経験し、経営全般、経営戦略策定、人事、組織開発に深く関わる。その経験を活かし、激動の時代に卓越した人財の育成、組織開発の必要性が急務と痛感し独立。「挑戦・創造・変革」をキーワードに、日本企業、外資系企業と、幅広く人財・組織開発コンサルタントとして、特に、上級管理職育成、経営戦略策定、組織開発などの分野で研修、コンサルティング、講演活動等で活躍を経て、世界の人々のこころの支援を多言語多文化で行うグローバルスタートアップとして事業展開を目指す決意をする。
【背景】
2005年11月、 約10年連れ添った最愛の妻をがんで5年間の闘病の後亡くす。
翌年、伴侶との死別自助グループ「Good Grief Network」を共同設立。個別・グループ・グリーフカウンセリングを行う。映像を使用した自助カウンセリングを取り入れる。大きな成果を残し、それぞれの死別体験者は、新たな人生を歩み出す。
長年実践研究を妻とともにしてきた「いきるとは?」「人間学」「メンタルレジリエンス」「メンタルヘルス」「グリーフケア」をさらに学際的に実践研究を推し進め、多数の素晴らしい成果が生まれてきた。私自身がグローバルビジネスの世界で様々な体験をする中で思いを強くした社会課題解決の人生を賭ける決意をする。
株式会社レジクスレイ(Resixley Incorporated)を設立、創業者兼CEO
事業成長アクセラレーター
広島県公立大学法人叡啓大学キャリアメンター
【専門領域】
・レジリエンス(精神的回復力) ・グリーフケア ・異文化理解 ・グローバル人財育成
・東洋哲学・思想(人間学、経営哲学、経営戦略) ・組織文化・風土改革 ・人材・組織開発、キャリア開発
・イノベーション・グローバル・エコシステム形成支援
【主な著書/論文/プレス発表】
「グローバルビジネスパーソンのためのメンタルヘルスガイド」kindle版
「喪失の先にある共感: 異文化と紡ぐ癒しの物語」kindle版
「実践!情報・メディアリテラシー: Essential Skills for the Global Era」kindle版
「こころと共感の力: つながる時代を前向きに生きる知恵」kindle版
「未来を拓く英語習得革命: AIと異文化理解の新たな挑戦」kindle版
「グローバルビジネス成功の第一歩: 基礎から実践まで」Kindle版
「仕事と脳力開発-挫折また挫折そして希望へ-」(城野経済研究所)
「英語教育と脳力開発-受験直前一ヶ月前の戦略・戦術」(城野経済研究所)
「国際派就職ガイド」(三修社)
「セミナーニュース(私立幼稚園を支援する)」(日本経営教育研究所)
【主な研修実績】
・グローバルビジネスコミュニケーションスキルアップ ・リーダーシップ ・コーチング
・ファシリテーション ・ディベート ・プレゼンテーション ・問題解決
・グローバルキャリアモデル構築と実践 ・キャリア・デザインセミナー
・創造性開発 ・情報収集分析 ・プロジェクトマネジメント研修他
※上記、いずれもファシリテーション型ワークショップを基本に実施
【主なコンサルティング実績】
年次経営計画の作成。コスト削減計画作成・実施。適正在庫水準のコントロール・指導を遂行。人事総務部門では、インセンティブプログラムの開発・実施、人事評価システムの考案。リストラクチャリングの実施。サプライチェーン部門では、そのプロセス及びコスト構造の改善。ERPの導入に際しては、プロジェクトリーダーを務め、導入期限内にその導入。組織全般の企業風土・文化の改革を行う。
【主な講演実績】
産業構造変革時代に求められる人材
外資系企業で働くということ
外資系企業へのアプローチ
異文化理解力
経営の志
商いは感動だ!
品質は、タダで手に入る
利益は、タダで手に入る
共生の時代を創る-点から面へ、そして主流へ
幸せのコミュニケーション
古典に学ぶ人生
古典に学ぶ経営
論語と経営
論語と人生
安岡正篤先生から学んだこと
素読のすすめ
経営の突破口は儒学にあり
実践行動学として儒学に学ぶ!~今ここに美しく生きるために~
何のためにいきるのか~一人の女性の死を見つめて~
縁により縁に生きる
縁に生かされて~人は生きているのではなく生かされているのだ!~
看取ることによって手渡されるいのちのバトン
など


