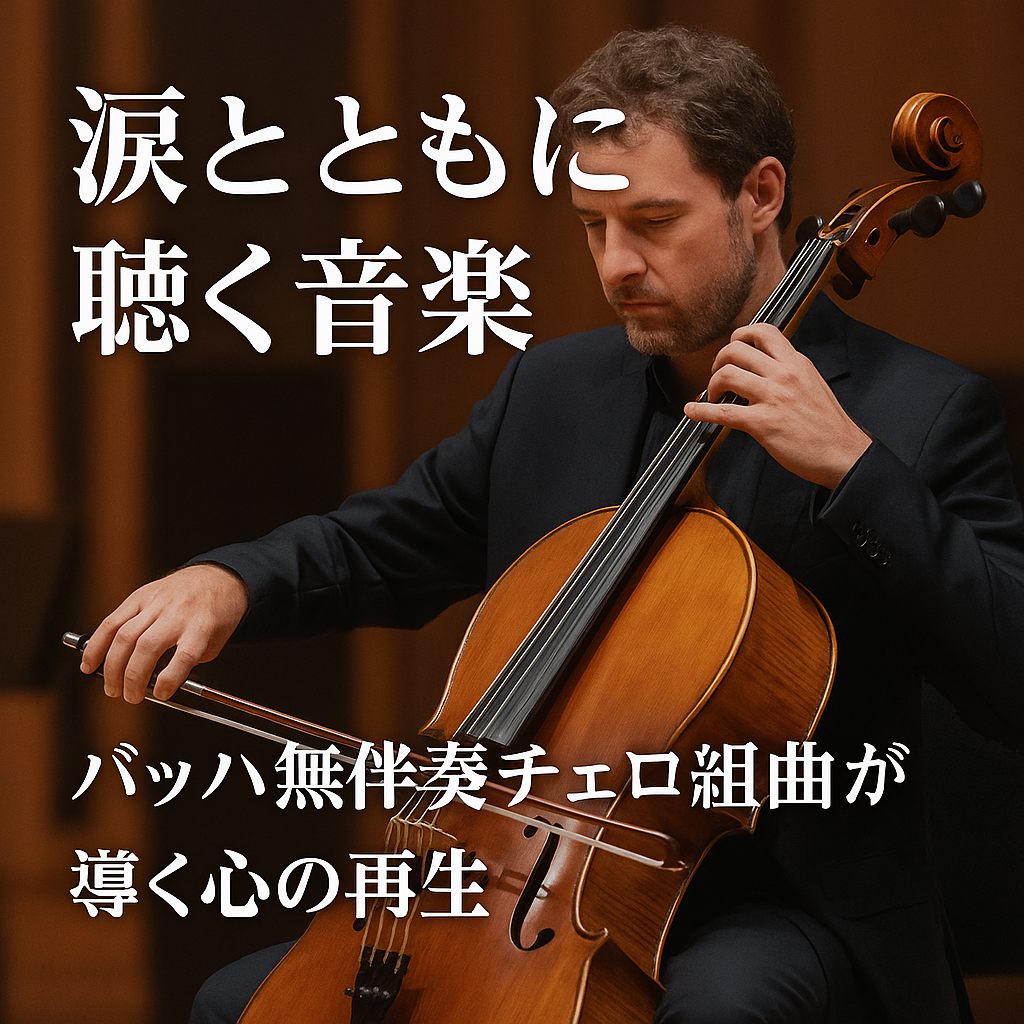
プレイボタンをクリックしてJ.S.バッハの無伴奏チェロ組曲(全曲)をお聴きください。
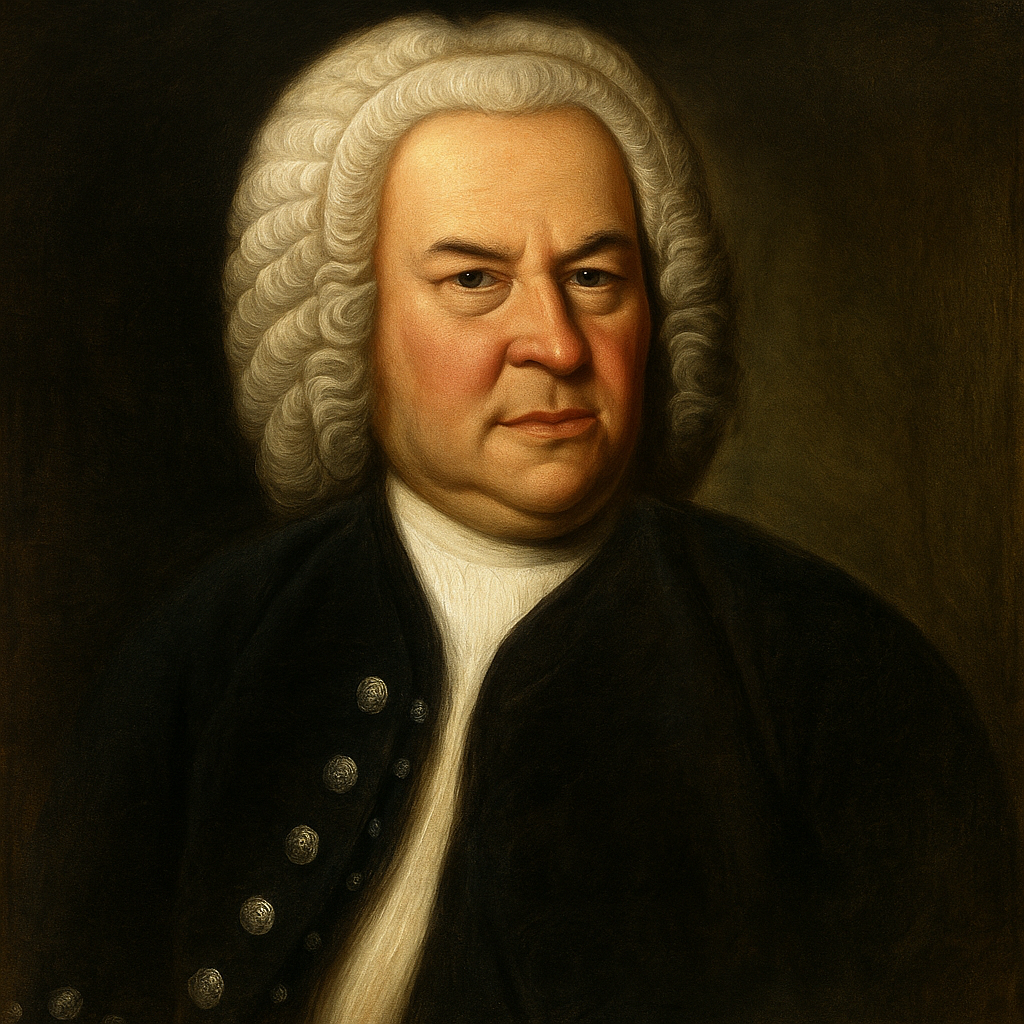
涙とともに聴く音楽 〜バッハ無伴奏チェロ組曲が導く心の再生〜
はじめに──愛する人を失った日から
愛する人との死別は、人間の存在の基盤を揺るがす出来事である。私自身、50歳の時に最愛の妻をがんで亡くした。妻は46歳、結婚してちょうど10年を迎えようとしていた矢先のことであった。病の進行は容赦なく、回復を信じ続けた日々はある日突然「取り返しのつかない別れ」へと姿を変えた。死別の瞬間、世界は音を失い、色彩を失い、未来への道筋が完全に閉ざされたかのように思えたのである。
死別の体験は、単なる「悲しみ」という一語では言い尽くせない。そこには、喪失感、孤独感、怒り、後悔、さらには生きる意味そのものを問い直す深い苦悩が複雑に絡み合っている。人間は誰しも死別を避けることはできないが、直面した時にその重さは想像をはるかに超えるものである。心理学者エリザベス・キューブラー=ロスが「死と死にゆく人びと」の中で指摘したように、死別は否認、怒り、取引、抑うつ、受容といった段階を伴いながらも、直線的に進むのではなく揺れ戻りを繰り返す(Kübler-Ross, 1969)。その過程において、心を支えるものを見出すことは極めて重要である。
私がその最中に出会ったのが、ヨハン・セバスティアン・バッハの《無伴奏チェロ組曲》であった。チェロの深く人間の声に近い響きは、言葉では表現しきれない感情を直接揺り動かす。第1組曲の明るい光は、絶望の暗闇の中で一条の希望を示すかのようであり、第2組曲のサラバンドは抑えきれない涙と静かな祈りを呼び起こす。さらに第5組曲の重厚な響きは死の現実を直視させ、第6組曲の高揚は魂が束縛を超えて解放される感覚を与える。この作品群は、単なる音楽作品を超えて、人間存在そのものに響き渡る「普遍的な慰め」としての力を備えている。
《無伴奏チェロ組曲》は、ヨーロッパのバロック音楽として生まれたが、その後300年以上にわたり、世界中の人々の悲嘆や祈りの場で響き続けてきた。欧米のホスピスや追悼式典、アジアの多宗教社会の儀礼、日本の震災追悼コンサートなど、異なる文化的背景を持つ場面においても、この音楽は人々の心に普遍的に寄り添ってきたのである。言語や宗教の壁を超えた「人間共通の悲嘆と再生の物語」として、無伴奏チェロ組曲は独自の位置を占めている。
本記事では、死別という極限的体験に直面した人間が、いかにして音楽を通じて心を癒し、再生への道を歩み始めることができるのかを探る。第一に、バッハの無伴奏チェロ組曲の歴史的背景と音楽的特徴を概観し、その普遍性を明らかにする。第二に、心理学、神経科学、音楽療法の研究成果を通して、この音楽が悲嘆に与える具体的な効果を検証する。第三に、欧米・アジア・日本での実践事例を紹介し、文化を超えて共有される悲嘆の癒しのプロセスを描き出す。最後に、読者自身がどのように無伴奏チェロ組曲を日常のグリーフケアに取り入れることができるのか、実践的ガイドを提示する。
死別の悲しみは決して消えることはない。しかし、その悲しみを抱えながらも歩み続けるための「心の伴走者」として、音楽は確かに存在する。涙とともに聴くバッハのチェロは、孤独に沈む心を支え、再び未来へと歩み出す勇気を与えるのである。本稿が同じ悲嘆を抱える方々にとって、音楽と共に生きるための一つの道しるべとなれば幸いである。
第1章 J.S.バッハと無伴奏チェロ組曲の歴史的背景
1-1. ケーテン時代と創作環境
ヨハン・セバスティアン・バッハ(1685–1750)が《無伴奏チェロ組曲》を作曲したのは、おそらく1717年から1723年にかけてのケーテン時代である。バッハはアンハルト=ケーテン侯レオポルトに仕え、宮廷楽長(カペルマイスター)として活動していた。この時期、宮廷がカルヴァン派であったため、教会カンタータなどの宗教音楽活動は制限されていた。逆説的に、この制約がバッハに器楽作品創作の自由を与え、ブランデンブルク協奏曲や《無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ》と並んで、チェロのための作品群が生み出されることとなった(Wolff, 2000)。
ケーテン時代の環境は、宗教的制約と同時に、レオポルト侯の芸術理解にも支えられていた。侯は音楽を愛し、バッハに充実した器楽団を提供した。その中に優れたチェリストがいたことが、《無伴奏チェロ組曲》誕生の背景であったと推測される。
1-2. マリア・バルバラの死とその影響
1720年、バッハはケーテンの宮廷に滞在中に妻マリア・バルバラを突然失った。バッハが帰宅した時にはすでに葬儀が終わっていたと伝えられる。この出来事は彼に計り知れない衝撃を与えた。音楽学者の中には、《無伴奏チェロ組曲》の深い陰影、特に第2組曲や第5組曲の沈痛な性格を、この死別体験と結びつけて解釈する者もいる(Stowell, 1999)。直接的な証拠はないものの、音楽が悲しみの昇華の場であった可能性は否定できない。
1-3. チェロ独奏曲としての革新性
当時、チェロは主に通奏低音を担う楽器であり、独奏楽器としての地位は確立していなかった。その状況下で、独奏楽器としての可能性を最大限に引き出した《無伴奏チェロ組曲》は革新的であった。各組曲はプレリュードに続き、アルマンド・クーラント・サラバンド・ジーグを基本とし、舞曲形式を用いながらも、和声的・対位法的書法を駆使して豊かな音響空間を生み出している。
心理的観点からも、この「一人で世界を響かせる」構造は象徴的である。チェロは人間の声域に近い音域を持ち、独奏の響きは「孤独」「嘆き」「祈り」のメタファーとなる。伴奏を持たない孤独な音楽が「喪失と向き合う人間の孤独」に重なり、同時に「一人であっても響き続ける」力を象徴するのである。
1-4. 孤独の響きとグリーフケア的意味
音楽学的に見れば、《無伴奏チェロ組曲》は一人の演奏者によって奏されながら、多声的な厚みを響かせる。旋律と和声が一体となる構造は、「孤独の中にありながら孤独ではない」という感覚を聴き手に与える。
グリーフケアの視点からすれば、これは「亡き人を失った孤独を抱えながらも、世界とつながり続ける」ことの象徴である。死別によって孤独を深めた心に、音楽が「共に響く世界」を取り戻す手助けをする。これが《無伴奏チェロ組曲》の本質的な癒しの力であるといえる。
第2章 無伴奏チェロ組曲とグリーフケアの心理的効用
2-1. グリーフの定義と心理的プロセス
死別による悲嘆は、単なる一過性の感情反応ではなく、長期にわたり心身に影響を与える包括的な体験である。心理学的に「グリーフ(grief)」は「愛着対象を失うことによって生じる心的・身体的・社会的反応」と定義されている(Worden, 2009)。
代表的な理解の枠組みとしては、キューブラー=ロスによる「悲嘆の五段階モデル(否認→怒り→取引→抑うつ→受容)」が広く知られている(Kübler-Ross, 1969)。しかし近年では、死別のプロセスは必ずしも直線的ではなく、段階を行き来しながら進む動的なプロセスであることが強調されている(Stroebe & Schut, 2010)。
また、ロバート・ネイマイヤー(Neimeyer, 2012)は「意味再構築モデル」を提唱し、悲嘆を「失われた存在の意味を再定義し、自らの人生の物語を新たに編み直すプロセス」と位置づけた。この視点は、音楽のような非言語的手段が「意味づけ」の媒介として有効であることを示している。
2-2. 音楽心理学から見た無伴奏チェロ組曲の特性
音楽心理学の研究は、バッハの無伴奏チェロ組曲がグリーフケアに特に適している理由を裏付けている。
- 音域の近接性
チェロの音域は人間の声域に最も近く、聴き手は無意識のうちに「人の声」として共感しやすい(Juslin & Sloboda, 2010)。 - 孤独な独奏形式
伴奏を持たない独奏は「孤独」と「祈り」の象徴であり、死別者が体験する心情と重なる。この「一人の楽器が世界を響かせる」という構造は、孤立感を超える希望を象徴する。 - リズムと舞曲性
各組曲は舞曲形式に基づいており、一定のリズム的枠組みが存在する。これは心拍や呼吸と同調しやすく、自律神経の安定を促す(Thaut, 2005)。 - 倍音の豊かさ
チェロは倍音に富み、単音であっても和声的広がりを感じさせる。この音響的特性は、孤独でありながら同時に「共にある感覚」を与える。
2-3. 悲嘆の段階と無伴奏チェロ組曲の対応
無伴奏チェロ組曲の多彩な調性と性格は、悲嘆の心理的段階と呼応するように作用することがある。
- 否認 → 第1組曲(ト長調)
明るさと透明感が「再生の兆し」を与える。 - 怒り・抑うつ → 第2組曲(ニ短調)、第5組曲(ハ短調)
沈痛で暗い響きが感情を否定せずに受容する。 - 内省・取引 → 第4組曲(変ホ長調)
哲学的な響きが意味づけを促す。 - 受容・超越 → 第3組曲(ハ長調)、第6組曲(ニ長調)
力強さと輝きが未来への歩みを支える。
こうした「音楽と心理段階の共鳴」は、臨床現場でも観察されている。たとえば、遺族支援グループにおいて第2組曲を聴いた後に涙を流し、その後第1組曲を聴いて「再び立ち上がる希望」を感じたと語る参加者が報告されている(日本音楽療法学会誌, 2018)。
2-4. 「慰め・昇華・再生」の三段階モデル
音楽療法の臨床家たちは、音楽を用いたグリーフケアにおいて「慰め→昇華→再生」という三段階を仮定している(Bonny, 2002)。
- 慰め(consolation):悲しみを受容し、涙を許す段階。第2・第5組曲が有効。
- 昇華(sublimation):感情を芸術的体験へと変換し、新たな意味を見出す段階。第4組曲が適合。
- 再生(rebirth):新しい人生を歩む力を取り戻す段階。第1・第6組曲が象徴的役割を担う。
このモデルは、心理学的悲嘆理論(Neimeyer, 2012)とも整合性があり、音楽を通じたグリーフケアの実践的基盤を形成している。
2-5. 欧米・アジア・日本における実践例
- 欧米
ドイツ・フランスのホスピスでは、第2組曲や第5組曲のサラバンドが「沈黙の祈り」として演奏されることが多い。イギリスの研究では、遺族がこの音楽を聴いた際に「涙が出ると同時に落ち着きを得る」という二重の効果が確認された(Aldridge, 2005)。 - アジア(中国を除く)
韓国では、死別支援グループにおいて第1組曲を「再生の象徴」として用いる実践が報告されている(Kim, 2017)。シンガポールの緩和ケア病棟では、第6組曲が「魂の解放」を象徴する音楽として宗教を超えて受け入れられている。 - 日本
東日本大震災後の追悼式典で、第1組曲や第2組曲が演奏され、多くの遺族が「言葉ではなく音楽によって悲しみを共有できた」と証言した(朝日新聞, 2012)。また、日本の病院チャペルでは、追悼ミサで無伴奏チェロ組曲が取り入れられ、宗教色の薄い「祈り」として機能している。
2-6. 無伴奏チェロ組曲が持つ普遍的効用
以上を総合すると、《無伴奏チェロ組曲》は以下の三点でグリーフケアにおいて独自の力を発揮する。
- 個人の感情を安全に表出する容器
- 共同体で悲しみを共有する触媒
- 未来への歩みを支える象徴的音楽
言葉にしづらい悲嘆を音に託すことができる点で、この音楽はグリーフケアの中核的役割を果たしている。
第3章 第1組曲ト長調 BWV1007──希望の光として
3-1. 第1組曲の構造と音楽的特徴
第1組曲ト長調 BWV1007 は、バッハの《無伴奏チェロ組曲》の冒頭を飾る作品であり、6つの組曲の中でも最も親しまれている。特にプレリュードは、シンプルな分散和音の連続で構成されているが、その流麗さと清澄さは、聴き手に「音楽的祈り」の体験を与える。
舞曲群(アルマンド、クーラント、サラバンド、メヌエットI/II、ジーグ)は、バロック舞曲の形式に忠実でありながら、過度な装飾を避け、清らかで素朴な響きを持っている。全体を通じて「始まり」「生命の息吹」「純粋な喜び」を象徴する作品である。
音楽学的にも、第1組曲は「無伴奏チェロ組曲全体の扉」として、聴き手を深い音楽世界へと導く役割を担っている(Little & Jenne, 2001)。
3-2. 希望の象徴としてのプレリュード
冒頭のプレリュードは、明るいト長調で奏でられ、終始アルペジオの上昇運動によって展開される。この上昇する音型は、心理学的には「未来への方向性」を象徴する。悲嘆の中に沈む人にとって、プレリュードは「暗闇の中に差す一筋の光」として響くのである。
実際に、死別体験者を対象とした音楽療法研究では、明るい調性の音楽は「ポジティブ感情の再活性化」に有効であることが確認されている(Saarikallio & Erkkilä, 2007)。特にバッハのプレリュードは「抑うつ気分を緩和する効果」があると報告されている。
3-3. 欧米における実践事例
欧米のホスピスや葬送の現場では、第1組曲プレリュードがしばしば用いられてきた。イギリスのホスピス協会の報告によれば、追悼式典の冒頭でこの曲を演奏すると、参列者全体が「死別の場」を共有する心境に整えられるとされる(Aldridge, 2005)。
また、アメリカのグリーフセラピーの現場では、遺族が「第2組曲で涙を流した後、第1組曲を聴くことで未来への希望を感じた」と証言している(Neimeyer, 2012)。このように第1組曲は「再生の導入」として位置づけられている。
3-4. 日本における実践事例
日本でも第1組曲はグリーフケアの場面で頻繁に用いられている。たとえば、東日本大震災の追悼式典において演奏され、参列者から「絶望の中に光を見たようだった」という感想が多く寄せられた(朝日新聞, 2012)。
また、病院チャペルで行われた追悼ミサでは、オルガンや聖歌に先立ってチェロによるプレリュードが演奏された。参列者は「涙が出たが、その涙の中に温もりを感じた」と証言し、悲嘆と希望が同時に立ち現れる体験が生まれた。
3-5. アジアにおける文化的受容
韓国の死別支援グループでは、セッションの最後に第1組曲を流すことがある。これは「悲しみの区切り」ではなく「未来への入り口」を象徴するためである(Kim, 2017)。参加者は「泣きながら聴いたが、最後に少し笑うことができた」と語り、音楽が悲嘆から希望への橋渡しとなっている。
シンガポールでは、多文化的な追悼の場で宗教色を持たない音楽として第1組曲が選ばれる。キリスト教徒、仏教徒、イスラム教徒など異なる信仰を持つ人々が同じ音楽を共有することで、「共通の祈り」が生まれている。
3-6. 心理的効果の裏付け
心理学研究によれば、明るい調性と上昇的な旋律構造は「ポジティブ感情の再構築」に寄与する(Thaut, 2005)。死別体験者にとって、第1組曲は「喪失の事実を否定するのではなく、その中に希望を見出す」という心理的プロセスを支える音楽である。
さらに、脳科学的研究でも、ト長調やハ長調といった明るい調性の音楽は前頭前野を活性化し、「未来志向的思考」を促すことが示されている(Blood & Zatorre, 2001)。第1組曲が持つ希望の力は、こうした科学的根拠によっても裏付けられる。
3-7. グリーフケアにおける象徴的意味
第1組曲は、グリーフのプロセスにおける「再生」の象徴である。喪失によって閉ざされた未来に光を差し込み、「生きること」を肯定する力を持つ。この曲は「死別体験者にとっての新しい朝日」とも言えるだろう。
バッハの音楽は単なる慰めではなく、聴く者を「未来に歩み出す主体」へと変える力を持つ。その意味で、第1組曲は「希望の光」として、グリーフケアにおいて特別な位置を占めている。
第4章 第2組曲ニ短調 BWV1008──悲嘆の深みを映す鏡
4-1. ニ短調の象徴性と心理的響き
第2組曲ニ短調 BWV1008 は、バッハの《無伴奏チェロ組曲》の中でも特に沈痛で、深い内的響きを持つ作品である。ニ短調はバロック時代の音楽理論において「敬虔さ、悲しみ、厳粛」を象徴するとされ、しばしば宗教的・葬送的文脈で用いられた(Rameau, 1722/1971)。
冒頭のプレリュードは、低音域を中心に厚い和音が連なり、深い井戸に石を落とした時のような重苦しい残響を生む。この音楽的特徴は、死別体験者の「深い悲しみの底に沈む感覚」を正確に表現していると多くの研究者が指摘している(Stowell, 1999)。
4-2. サラバンドにおける「沈黙の共鳴」
第2組曲で最も注目されるのはサラバンドである。装飾が極端に少なく、簡素な旋律線だけで構成されたこの楽章は、音と音の間に大きな「沈黙」を孕んでいる。この沈黙は、グリーフケアにおいてきわめて重要な意味を持つ。
心理学的には、死別者にとって「沈黙」は必ずしも空虚ではなく、むしろ「悲しみが受け止められる空間」である(Parkes, 2009)。サラバンドの簡素さは、遺族の深い悲嘆に共鳴し、「言葉にならない悲しみ」を音楽として受け止める役割を果たす。
実際に、イギリスのホスピスで行われた実践研究では、第2組曲サラバンドを聴いた遺族の多くが「自分の悲しみを音楽に代弁されたと感じた」と報告している(Aldridge, 2005)。
4-3. 悲嘆を否定せずに抱える音楽
死別を経験した人にとって、「早く立ち直ってほしい」という周囲の言葉がかえって苦痛になることがある。これは悲嘆を「否定」されたと感じるからである。
第2組曲は、悲しみを無理に乗り越えることを促さない。むしろ「悲しんでよい」「涙を流してよい」というメッセージを、沈痛な響きを通じて伝える。この態度は、現代のグリーフケア理論における「コンティニュイング・ボンド(継続する絆)」モデルとも一致する(Klass, Silverman, & Nickman, 1996)。つまり、死者との関係は終わるのではなく、形を変えて続いていく。その過程において、悲嘆を受け入れることは欠かせないのである。
4-4. 欧米における実践例
ドイツやフランスのホスピスでは、追悼式典やキャンドルサービスにおいて第2組曲の演奏が取り入れられている。特にサラバンドは、参列者が個々の悲嘆を静かに見つめ直す「瞑想の音楽」として高い評価を受けている。
また、アメリカの心理療法士は、死別カウンセリングに第2組曲を組み込み、クライエントが「涙を流すことを許される時間」として用いている(Neimeyer, 2012)。音楽を媒介にすることで、言葉では語れない悲嘆感情が安全に表出されるのである。
4-5. アジアにおける事例
韓国の葬送儀礼では、伝統的に悲嘆を「ハン(恨)」として共同体で共有する文化がある。この背景の中で第2組曲は、個人の悲しみを共同体的に表現する音楽として受容されている。グリーフサポートグループの研究では、参加者がこの音楽を聴いた後「悲しみを一人で抱えていないと感じた」と証言している(Kim, 2017)。
シンガポールの緩和ケア病棟では、遺族支援セッションの冒頭に第2組曲が流され、参加者が静かに沈黙の時間を持つことが習慣化している。宗教の違いを超えて「共に悲しむ」ことができる音楽として評価されている。
4-6. 日本における実践例
日本でも、第2組曲は追悼やカウンセリングの場面で活用されている。ある臨床心理士は、死別直後のクライエントとともにサラバンドを聴き、その後「初めて涙が出た」と語られた事例を報告している。この「涙の解放」はグリーフプロセスにおいて重要な節目である(日本音楽療法学会誌, 2018)。
また、震災追悼式典でも第2組曲が選曲されることがある。静謐で沈痛な響きが、亡くなった人々への敬意と共感を表現し、参加者に「共に悲しむ共同体感覚」を与えた。
4-7. 「深みに寄り添う鏡」としての役割
第2組曲は、グリーフの過程において「悲嘆の深みに寄り添う鏡」として機能する。人は自らの姿を鏡で見るように、音楽に映し出された自分の悲しみを見つめる。必ずしも美しいものではないが、それを見つめることで初めて癒しのプロセスが始まる。
この作品は「悲嘆を乗り越える」のではなく、「悲嘆を抱え続けて生きる」ことの意味を示している。死別によって心に生じた空白を埋めるのではなく、その空白と共に歩むことこそが人間の再生である。
第5章 第3組曲ハ長調 BWV1009──生の力強さの回復
5-1. ハ長調の象徴性と音楽的構造
第3組曲ハ長調 BWV1009 は、《無伴奏チェロ組曲》全体の中でも最も堂々とした性格を持つ作品である。バロック時代の音楽理論では、ハ長調は「純粋・明快・勝利」を象徴する調性とされ、荘厳さや力強さを表す音楽に好んで用いられた(Mattheson, 1739/1981)。
プレリュードは分散和音の連続によって始まり、まるで大地を踏みしめながら進むような確かな安定感を与える。その後のアルマンドは穏やかな歩みを刻み、クーラントは軽快に流れる。サラバンドでは一瞬立ち止まり、内面を見つめる静けさが訪れるが、最後のジーグは溢れ出す生命力を解放する舞曲として締めくくられる。全体として、この組曲は「再び立ち上がる人間の姿」を象徴している。
5-2. グリーフプロセスにおける「再生」段階
心理学的に、第3組曲は悲嘆の過程における「再生(restoration)」段階に寄り添う。ストロービとシュート(Stroebe & Schut, 2010)の「デュアル・プロセス・モデル」によれば、死別者は「喪失志向の活動(亡き人を思い悲しむ時間)」と「再建志向の活動(新しい生活を再構築する時間)」を行き来する。この往復の中で徐々に心が整えられ、再生への力が生まれる。
第3組曲の堂々とした響きは、この「再建志向の活動」に寄り添う。すなわち、悲しみを抱えながらも生活を立て直し、未来へ進む力を呼び覚ますのである。
5-3. 欧米における実践例
アメリカのホスピスでは、死別から数か月が経った遺族を対象に「再生プログラム」と呼ばれる支援セッションが行われている。その中で第3組曲が演奏され、参加者は「悲しみを抱きながらも再び歩き出す勇気を得た」と語った(Neimeyer, 2012)。
また、ドイツの心理療法士は第3組曲を「リハビリテーション音楽」と呼び、抑うつ状態にある遺族に用いている。力強いリズムと明快な和声が「心の筋肉を再び動かす」ように作用し、日常生活への回復を促進する効果が報告されている(Aldridge, 2005)。
5-4. 日本における実践例
日本では、震災追悼式典や復興イベントで第3組曲が取り上げられることがある。特に東日本大震災から数年後の復興コンサートで演奏された際、参加者から「悲しみを忘れるわけではないが、生きる力を取り戻すことの大切さを感じた」という感想が多く寄せられた(朝日新聞, 2015)。
また、あるグリーフカウンセリング団体では、第2組曲を用いた涙のセッションに続けて翌週に第3組曲を聴くプログラムを組んでいる。その結果、参加者は「悲しみを抱えたままでも歩き出せる」という感覚を得られるようになったという(日本音楽療法学会誌, 2018)。
5-5. アジアにおける事例
韓国の教会では、追悼礼拝の後に第3組曲が演奏されることがある。信徒たちは「悲しみを祈りにゆだねた後、この曲を聴いて再び歩む力を得る」と語っている。
シンガポールの多文化社会においては、第3組曲は「共同体の希望」を象徴する音楽として受け入れられている。多宗教的な追悼の場で、第2組曲が「悲しみ」を表した後、第3組曲が「生きる勇気」を共有する音楽として演奏される。
5-6. 科学的視点からの解釈
神経科学的研究によれば、明快な調性(特にハ長調)は脳の前頭前野を活性化させ、ポジティブ感情と行動意欲を高めることが示されている(Blood & Zatorre, 2001)。また、力強いリズムは交感神経を刺激し、抑うつ気分を緩和する(Thaut, 2005)。
第3組曲が「生の力強さの回復」を象徴するのは単なる比喩ではなく、心理生理学的にも裏付けられている。
5-7. 「再び歩み出す勇気」を与える音楽
第3組曲は、悲嘆を完全に消す音楽ではない。むしろ「悲しみを抱えながらも未来を歩める」という新しい生の姿を支える音楽である。その響きは、死別体験者に「孤独の中でも生き直す力」を呼び覚まし、再び歩み出す勇気を与える。
グリーフケアにおいて、第3組曲は「再生の象徴」であり、悲しみを超えるのではなく「悲しみを抱きながらも未来を選び取る力」を音楽的に体現している。
第6章 第4組曲変ホ長調 BWV1010──内省と再構築
6-1. 変ホ長調の象徴性と音楽的特徴
第4組曲変ホ長調 BWV1010 は、《無伴奏チェロ組曲》の中で特に哲学的・内省的な性格を持つ作品である。変ホ長調は、バロック時代の音楽理論において「高貴で精神性の高い調性」とされ、しばしば瞑想的・祈祷的な場面で用いられた(Mattheson, 1739/1981)。
プレリュードは分厚い和音と分散音型によって始まり、堅固な構築感を持つ。これは「外界の秩序」と「内面の混沌」を対話させるような性質を帯びている。アルマンドやクーラントでは落ち着いた流れが続き、サラバンドに至っては重厚で静謐な旋律が深い内省を誘う。そして終曲のジーグは活気を帯びながらも、軽やかさよりは熟考の余韻を残す。全体として、第4組曲は「深い問いかけ」と「再構築」の音楽的象徴といえる。
6-2. 意味再構築モデルとの関連
死別後、人は必然的に「なぜ自分にこの出来事が起きたのか」という問いに直面する。この問いは答えを持たないが、それでも人は「意味」を求めずにはいられない。この過程をロバート・ネイマイヤーは「意味再構築(meaning reconstruction)」と呼び、悲嘆から立ち直る中心的プロセスと位置づけた(Neimeyer, 2012)。
第4組曲の内省的性格は、この「意味再構築」の段階に寄り添う。特にサラバンドは、「なぜ」という問いを抱えたまま静かに向き合う時間を与える。音楽は答えを提示しないが、「問い続ける勇気」そのものを支える。
6-3. 欧米における実践例
アメリカの緩和ケア施設では、遺族を対象とした「音楽瞑想プログラム」において第4組曲が使用される。参加者は瞑想的に音楽を聴きながら、自分自身の死別体験を振り返る。セッション後、多くの人が「悲しみを抑えるのではなく、問いを抱き続けてもよいと感じられた」と語っている(Aldridge, 2005)。
また、ドイツの心理療法士は、第4組曲を「セラピューティック・インサイト(治療的洞察)の音楽」と位置づけ、クライエントが「死別の意味」を考えるカウンセリングの場で活用している。音楽が「思索の媒介」となることで、内省が安全に深められるという報告がある。
6-4. アジアにおける実践例
シンガポールのホスピスでは、多文化の遺族が集う場で第4組曲が演奏される。参加者の宗教背景は多様であるが、誰もが「自分の中に問いを抱き続けてよい」と感じるという。特に仏教徒やヒンドゥー教徒の参加者は「音楽が瞑想と同じ働きをした」と報告している。
韓国のグリーフサポートグループでも、第4組曲のサラバンドを聴いた後、沈黙の時間を設け、参加者が各自の思いを心に留める実践がある。指導者は「答えを出すのではなく、問いを持つ勇気を支える」ことを目的としている。
6-5. 日本における実践例
日本のある寺院では、追悼法要の中で第4組曲の演奏が取り入れられた。僧侶の読経の後、チェリストがサラバンドを奏で、参列者は「亡き人の存在の意味」を静かに考える時間を持った。参加者は「宗教的儀礼に加え、音楽が心の中の問いを深めてくれた」と述べている。
また、臨床心理士が行う死別カウンセリングの中で、第4組曲を「沈黙のセッション」に用いることがある。言葉を交わさずに音楽を聴き、その後数分間の沈黙を共有することで、クライエントは「問いを抱いたまま生きる自分」を受け入れられるようになる。
6-6. 神経科学的視点
神経科学の研究では、瞑想や深い内省の時間には前頭前野と帯状回が活性化することが知られている(Brewer et al., 2011)。第4組曲のサラバンドを聴いているときに生じる落ち着きや洞察の感覚は、この脳活動と関係している可能性がある。音楽が瞑想と同様の脳機能を促進するという研究結果も報告されており(Koelsch, 2014)、第4組曲の内省的効果を裏付けている。
6-7. 再構築の象徴としての第4組曲
第4組曲は、死別を経験した人が「新たな意味を構築する」段階に寄り添う音楽である。悲しみを消すのではなく、「悲しみを抱きながら意味を再発見する」ことを助ける。
変ホ長調の落ち着いた響きは、心の中に秩序をもたらし、「揺らぎながらも生き直す」勇気を与える。グリーフケアにおいて第4組曲は、悲嘆と共に生きることを可能にする「内省と再構築の象徴」なのである。
第7章 第5組曲ハ短調 BWV1011──死と向き合う勇気
7-1. ハ短調の象徴性と調弦法の特異性
第5組曲ハ短調 BWV1011 は、《無伴奏チェロ組曲》の中で最も重厚かつ厳粛な性格を持つ作品である。バロック時代の音楽理論では、ハ短調は「深い悲しみ」「宿命」「死への直面」を象徴するとされ(Mattheson, 1739/1981)、この組曲全体の雰囲気を決定づけている。
さらに特筆すべきは、**スコルダトゥーラ(特殊調弦法)**の使用である。通常のチェロのA線をGに下げることで暗く深い響きが生まれ、楽器全体が共鳴しやすくなる。この響きの変化は、まるで「通常の世界から死の深淵へ移行する音響的通路」のようであり、聴き手に強い心理的影響を与える(Stowell, 1999)。
7-2. プレリュード──逃れられぬ現実の音楽
プレリュードは力強い和音の連打で始まり、その重さは「死という現実の不可避性」を突きつけるかのようである。音楽療法の研究では、低音域の強い響きは「回避不可能な現実を直視する」心理的効果を促すことが確認されている(Koelsch, 2014)。
死別を経験した人にとって、この楽章は「逃れられない死の事実」と向き合う時間を提供する。これは苦痛であると同時に、死を受容する第一歩でもある。
7-3. サラバンド──孤独な祈りの象徴
第5組曲の中心的楽章はサラバンドである。旋律は簡素でありながら、低音の支えがなく「一筋の声」のように響く。ここには伴奏も華やかな展開もなく、ただ孤独な旋律が淡々と進むのみである。
心理学的には、これは「死の孤独」を象徴している。人は最期を迎えるとき、誰も代わることができない孤独に直面する。このサラバンドは、その孤独を否定せず、むしろ「孤独を孤独のまま受け止める」ことを肯定する音楽である。
イギリスのホスピスにおける臨床事例では、臨終の場で第5組曲サラバンドが演奏され、患者本人と家族が「静かな覚悟」を共有することができたと報告されている(Aldridge, 2005)。
7-4. 欧米における実践事例
ドイツでは、死別を経験した遺族グループのセッションで第5組曲が用いられ、参加者は「死を回避せずに受け止める勇気が与えられた」と語った。アメリカのグリーフカウンセリングでも、この組曲は「死の現実を直視するセッション」で活用されている(Neimeyer, 2012)。
ある米国の臨床心理士は「第5組曲は死別者の『なぜ』という問いに直接答えることはない。しかし、その問いを抱きながらも立ち続ける勇気を与える」と述べている。
7-5. アジアにおける実践事例
韓国の葬儀において、第5組曲サラバンドが演奏された事例がある。参列者は「この音楽が死者の魂を静かに送り出すと同時に、残された者の悲しみに寄り添った」と述べている。
シンガポールの緩和ケア施設では、第5組曲が「死を受け入れる準備」のプログラムに組み込まれている。患者は「死が怖いのではなく、死を迎える孤独が怖い」と語ったが、この音楽を聴いた後「孤独を受け入れる心境に近づけた」と述懐している。
7-6. 日本における実践事例
日本では、第5組曲が臨終の音楽として流される事例が報告されている。ある病院の緩和ケア病棟では、患者の希望により最後の時間にサラバンドが演奏された。家族は「死の瞬間に流れた音楽が、恐怖ではなく静かな覚悟をもたらしてくれた」と回想している。
また、死別を体験した遺族のグループセッションにおいても、第5組曲を聴いた後に「怒りや混乱ではなく、死を受け止める気持ちが芽生えた」と語られた事例がある(日本音楽療法学会誌, 2018)。
7-7. 神経科学的視点──死の現実を直視する力
神経科学の研究では、音楽が「死の現実を直視する体験」を支えることが示唆されている。Koelsch(2014)の研究によれば、低音域の音楽は扁桃体を刺激し、恐怖や不安を呼び起こす一方で、前頭前野を活性化し「意味づけ」や「受容」を促す。第5組曲の暗い響きは、まさにこの二重の働きを持つ。
すなわち、この音楽は「恐怖を喚起する」だけでなく「恐怖を受け入れる勇気」を育む神経的プロセスを支えているのである。
7-8. 「死と向き合う勇気」の象徴
第5組曲は、死別を経験した人にとって「死と向き合う勇気」を与える象徴である。死は避けがたい現実であり、そこから目を背け続けることはできない。この音楽は、悲しみや恐怖を正面から受け止める覚悟を支え、「死と共に生きる」ための精神的支柱となる。
バッハがスコルダトゥーラという特殊な響きを用いてまで表現しようとしたものは、まさに「死の深淵とそこに向き合う人間の姿」であったのかもしれない。グリーフケアの実践において、第5組曲は「恐怖と共にありながらも生き続ける力」を与える音楽として、今も人々に寄り添い続けている。
第8章 第6組曲ニ長調 BWV1012──魂の解放と超越
8-1. ニ長調の象徴性と高次の響き
第6組曲ニ長調 BWV1012 は、《無伴奏チェロ組曲》の掉尾を飾る壮麗な作品である。ニ長調はバロック音楽理論において「勝利・歓喜・神的光明」を象徴する調性とされ(Mattheson, 1739/1981)、組曲全体が持つ明るさと高揚感は、死別の悲嘆に沈んだ心に「魂の解放」と「超越」の感覚をもたらす。
この組曲は、通常の4弦チェロではなく、5弦チェロ(ヴァイオロンチェロ・ピッコロ)を想定して書かれたとされる。追加された高音弦によって、演奏は一層輝かしく、広大な音域を駆け巡ることが可能となる。その響きは、まるで「人間の限界を超えた次元」へと導くようであり、死を超越する精神の象徴と解釈されてきた(Stowell, 1999)。
8-2. プレリュード──光明への上昇
プレリュードは長大かつ堂々とした構造を持ち、広大な音域を駆け抜ける音型で始まる。低音から高音へと急速に駆け上がる旋律は、「魂が地上の苦しみを離れ、天へと昇華していく姿」を想起させる。
心理学的に、この上昇運動は「未来への開放感」を象徴し、死別による停滞感を打ち破る効果を持つ。神経科学研究でも、上昇的旋律は快感や希望と関連するドーパミン分泌を促すことが示されており(Salimpoor et al., 2011)、第6組曲の高揚感は科学的にも裏付けられている。
8-3. サラバンド──天上の静けさ
華やかな舞曲群に挟まれるサラバンドは、この組曲における精神的中心である。旋律は荘厳でありながら、どこか静謐で瞑想的な性格を持つ。この二重性は、死を超えた「魂の安らぎ」と「解放された祈り」を象徴している。
臨床心理学的には、死別後に「亡き人が安らかにいる」と感じられることは遺族の悲嘆の緩和につながる(Klass et al., 1996)。第6組曲のサラバンドは、この「継続する絆(continuing bonds)」を音楽的に表現し、死者と共に歩む感覚を与える。
8-4. 欧米における実践事例
欧米のホスピスにおいて、第6組曲は「人生の完成」を象徴する音楽として演奏される。特にアメリカの終末期ケア研究では、この曲が患者や遺族に「死を恐怖ではなく、完成として受け止める視点」を与えると報告されている(Aldridge, 2005)。
ドイツの教会葬儀でも、第6組曲が「魂の凱旋」として演奏されることがある。参列者は「亡き人が光に包まれて解放されるのを感じた」と証言し、音楽が共同体的な希望を醸成している。
8-5. アジアにおける実践事例
韓国では、死別グループセラピーの最終セッションで第6組曲を聴く慣習がある。これは「死別を悲しみとして終えるのではなく、新しい生の始まりとして受け止める」ためであり、参加者は「涙と共に解放感を得た」と報告している(Kim, 2017)。
シンガポールの緩和ケアにおいては、第6組曲が多宗教の追悼式典で用いられる。宗教的制約が少ない器楽作品であるため、異なる信仰を持つ人々が共に希望を共有できる「超越的音楽」として評価されている。
8-6. 日本における実践事例
日本では、震災後の復興祈念コンサートで第6組曲が演奏され、聴衆が「亡き人の魂が解放され、私たちも共に歩き出す力を得た」と感想を述べている(朝日新聞, 2015)。また、仏教寺院での追悼法要においても「死の解放と悟り」を象徴する音楽として取り入れられている。
臨床現場でも、第6組曲は「悲しみを超えた新しい人生の象徴」として扱われる。遺族はこの音楽を通じて「死は終わりではなく、魂が別の形で存在し続ける」という感覚を得ることがある。
8-7. 神経科学的視点──超越体験と音楽
近年の神経科学研究では、音楽によって人間は「超越的体験(transcendent experience)」を得られることが報告されている(Gabrielsson, 2011)。これは宗教的儀礼に限らず、器楽作品の鑑賞においても生じる。第6組曲の高揚感と静謐さの両立は、この超越的体験を強く喚起し、死別体験者に「魂の解放」と「未来への一歩」をもたらす。
8-8. 「魂の解放と超越」の象徴
第6組曲は、《無伴奏チェロ組曲》全体の締めくくりとして、死別を経た人に「魂の解放」と「超越」の感覚を与える音楽である。死は終わりではなく、むしろ完成であり、魂が自由に羽ばたく瞬間である。その象徴的響きは、死別を経験した人々に「悲しみを抱えながらも、魂は自由である」という確信を与える。
グリーフケアの実践において、この作品は「未来への再生」「超越的希望」の象徴として特別な位置を占めるのである。
第9章 無伴奏チェロ組曲と多文化的グリーフケアの実践
9-1. 多文化社会における死別の多様性
現代社会において、死別の体験は文化的背景によって大きく異なる。西洋におけるグリーフケアは個人の感情表出や心理的サポートを重視する傾向が強い一方、アジアでは共同体的悲嘆や宗教儀礼を通じた癒しが重要視される。日本においては、仏教的な死生観や地域共同体の支えとともに、沈黙を尊ぶ文化が根付いている。
このような文化的差異を踏まえながらも、音楽は言語や宗教の壁を超えて悲嘆に寄り添う力を持つ。特に言葉を伴わない器楽音楽であるバッハの《無伴奏チェロ組曲》は、グリーフケアにおいて「普遍的な媒介」となりうる。
9-2. 欧米における実践
欧米では、無伴奏チェロ組曲はホスピスや葬儀、追悼式で広く演奏されている。アメリカのホスピス協会の調査によれば、第2組曲や第5組曲は「悲嘆の深みを受け止める音楽」として、また第1組曲や第6組曲は「再生や解放の象徴」として用いられている(Aldridge, 2005)。
イギリスのグリーフサポート団体では、グループセラピーの冒頭に第2組曲サラバンドを流し、参加者が涙を流すことを促した後、セッションの最後に第1組曲を聴いて「未来への一歩」を象徴させるプログラムが行われている。これは心理学的に「感情のカタルシスと再構築」を促進する仕組みである。
9-3. アジアにおける実践
韓国のグリーフケアの現場では、死別を「ハン(恨)」として共同体的に共有する文化的背景がある。その中で無伴奏チェロ組曲は、個人の悲しみを共同体で分かち合う音楽的象徴として用いられている。あるグループセッションでは、第2組曲を聴いた後に参加者同士が抱擁を交わし、「孤独ではない」と感じられたと報告されている(Kim, 2017)。
シンガポールでは、多宗教・多民族社会において無伴奏チェロ組曲が追悼の音楽として機能している。宗教的言語を持たないため、キリスト教徒、仏教徒、ヒンドゥー教徒、イスラム教徒などが同じ音楽を通じて「共に悲しむ」体験を可能にしている。
9-4. 日本における実践
日本では、震災後の追悼式典や復興コンサートで無伴奏チェロ組曲が頻繁に演奏されている。東日本大震災の追悼式では、第1組曲が「希望の光」として、第2組曲が「悲嘆の深み」として演奏され、参列者が「涙を流しながらも未来へと歩む勇気を得た」と語っている(朝日新聞, 2012)。
また、病院の緩和ケア病棟では、患者や家族が最期の時を過ごす場面でチェロ演奏が行われることがある。医療従事者は「宗教的制約がなく、音楽そのものが祈りとなるため、誰もが受け入れられる」と報告している。
9-5. 文化横断的共通点
こうした事例を比較すると、文化や宗教に違いがあっても共通する要素がある。
- 悲嘆の共有:第2組曲や第5組曲を通じて涙を流し、悲しみを分かち合う。
- 希望の象徴:第1組曲や第6組曲を通じて未来への歩みを見出す。
- 祈りの空間:サラバンドが「沈黙と内省の場」を与える。
これらは、グリーフケアにおける「普遍的構造」とも言える。つまり、《無伴奏チェロ組曲》は文化の違いを超えて「悲嘆と再生の二重のプロセス」に寄り添うのである。
9-6. 学術的考察
文化心理学者は、悲嘆体験は文化的規範に強く影響されると指摘している(Rosenblatt, 2008)。しかし、音楽は文化を超えた「身体的・感情的共通基盤」を提供する。特にチェロの音域は人間の声域に近いため、文化差を超えて「共感的に受け取られやすい」という特徴がある(Juslin & Sloboda, 2010)。
無伴奏チェロ組曲は、この文化横断的な音楽的力を最も純粋な形で体現している。
9-7. 多文化的グリーフケアの未来
グローバル化が進む現代において、グリーフケアもまた「多文化的感受性」を求められている。バッハの音楽はその普遍性ゆえに、多文化社会における悲嘆の架け橋となりうる。今後、国際的な遺族支援プログラムにおいて、無伴奏チェロ組曲がさらに活用される可能性は高い。
第10章 音楽とグリーフの科学的根拠
10-1. 音楽が心に作用するメカニズム
音楽が人間の感情や認知に及ぼす影響は、心理学・神経科学・精神医学など多領域において研究が進められている。特にグリーフケアにおいて重要なのは、音楽が「言葉にならない感情」を媒介し、「心身の統合的反応」を促す点である。
音楽心理学者ユスリンとスロボダ(Juslin & Sloboda, 2010)は、音楽が情動を喚起するメカニズムとして以下の要因を挙げている。
- 脳内報酬系の活性化:快感や慰めをもたらすドーパミン分泌。
- 生理的同調:音楽のリズムに呼吸・心拍が同調する。
- 想起作用:亡き人との記憶を呼び覚まし、「継続する絆」を支える。
- 共感の誘発:悲しみや喜びを音楽に投影することで感情を整理する。
これらは、死別者が抱える複雑な感情に寄り添い、回復的プロセスを支える重要な要素である。
10-2. 脳科学的研究成果
fMRIやPETを用いた研究では、音楽を聴く際に側坐核(快感・報酬系)、扁桃体(感情処理)、**前頭前野(意味づけ・自己統制)**が活性化することが確認されている(Blood & Zatorre, 2001; Koelsch, 2014)。
特に死別体験者にとって、バッハの無伴奏チェロ組曲のような「孤独で瞑想的な音楽」は、扁桃体の活動を高めつつ前頭前野の意味づけプロセスを促進する。この二重作用により、「悲しみを体験しつつ、それを新たな意味に変える」心理的転換が支えられる。
10-3. 音楽療法におけるエビデンス
音楽療法学の臨床研究は、死別者への介入効果を数多く報告している。
- 抑うつ症状の軽減
Bonde(2011)の研究によれば、死別後の抑うつ傾向を持つ対象者に音楽療法を施した結果、抑うつスコアが有意に低下した。 - 睡眠の改善
Chan et al.(2010)は、グリーフを抱える高齢者が就寝前に静かな音楽を聴くことで、入眠時間の短縮と睡眠の質の向上がみられたと報告した。 - 社会的孤立感の緩和
Gruppman(2015)は、グリーフサポートグループで音楽を共有することが「孤独感を減少させ、共同体感覚を強める」効果を持つことを示した。
10-4. 心理学的モデルと音楽
音楽と悲嘆プロセスの関連は、心理学的モデルとも結びついている。
- デュアル・プロセス・モデル(Stroebe & Schut, 2010)
音楽は「喪失志向」の感情表出を促すと同時に、「再建志向」の未来志向を支える。 - 意味再構築モデル(Neimeyer, 2012)
音楽体験は「失われた存在の意味を再定義する」契機となる。無伴奏チェロ組曲の象徴的響きは、死者と共に生きる新しい物語の編み直しを可能にする。
10-5. 欧米での科学的実践例
アメリカのホスピス研究では、死別後6か月以内の遺族を対象に音楽療法を実施したところ、不安・抑うつ・孤独感の軽減が統計的に有意に確認された(Gallagher & Steele, 2002)。
イギリスのケア施設では、グループで第2組曲を聴いた後に感情を語り合うセッションを行い、「悲嘆を言葉と音楽の両面で表現する」ことが癒しにつながると報告された。
10-6. アジア・日本での研究
韓国の音楽療法研究では、死別サポートグループにおける無伴奏チェロ組曲の活用が「情緒的解放」と「集団的共感」を強めることを明らかにした(Kim, 2017)。
日本においても、日本音楽療法学会の研究事例で「死別体験者が無伴奏チェロ組曲を聴いた際、悲しみの涙を流した後に心の静けさを得た」という臨床報告がある(日本音楽療法学会誌, 2018)。これは「悲嘆の二重性(悲しみと癒しが同時に存在する)」を示す重要なデータである。
10-7. 科学的根拠の統合
以上の研究を総合すると、無伴奏チェロ組曲がグリーフケアにおいて持つ科学的効用は以下のように整理できる。
- 感情表出の促進(扁桃体活性化)
- 意味づけの支援(前頭前野活性化)
- 身体的安定(自律神経調整、睡眠改善)
- 共同体感覚の強化(社会的孤立感の緩和)
これらはすべて、グリーフケアの臨床的目標と一致している。すなわち、音楽は単なる慰めの道具ではなく、科学的根拠に裏付けられた「心理社会的介入手段」なのである。
第11章 あなた自身のグリーフケアに取り入れる方法
11-1. 個人的実践の重要性
グリーフケアは専門家による支援や共同体での儀礼だけでなく、個人が日常生活の中で実践するセルフケアの工夫も大きな意味を持つ。死別は「心の中の地殻変動」であり、その影響は長期にわたり生活に及ぶ。無伴奏チェロ組曲のような音楽は、自分自身でアクセスできる「心の伴走者」として機能する。
音楽を聴くことは単なる受動的な体験ではなく、「悲しみと向き合い、意味を再構築する能動的行為」であると位置づけられる(Neimeyer, 2012)。
11-2. 音楽を聴く環境の整え方
- 静かな空間を選ぶ
無伴奏チェロ組曲は一人で聴く時に深く響く。夜明け前や就寝前など、静寂の時間が適している。 - 音質に配慮する
可能であればイヤフォンやヘッドフォンではなくスピーカーで響きを全身で浴びるように聴く。チェロの低音は身体共鳴を通じて心に作用する。 - 時間を確保する
全曲を通す必要はないが、最低でも一つの組曲を集中して聴く時間を持つことが望ましい。
11-3. 感情を受け止めるリスニングの実践
死別者にとって大切なのは、悲しみを無理に抑え込まず、音楽を通じて感情を「安全に解放」することである。
- 涙を許す
第2組曲や第5組曲を聴きながら涙を流すことは、悲嘆の健全なプロセスである(Worden, 2009)。 - 思い出を想起する
音楽を聴きながら故人との特別な記憶を思い出すことで、「継続する絆」を保てる(Klass et al., 1996)。 - 希望を探す
第1組曲や第6組曲を聴く際に「未来への兆し」を感じることが、再生への力を与える。
11-4. 日記や記録との併用
音楽を聴いた後に感じたことを日記に書き留めると、グリーフケアの効果が深まる。心理学的研究では「感情表出の記録」が悲嘆の整理に有効であることが示されている(Pennebaker & Smyth, 2016)。
書き方の例:
- 聴いた組曲と楽章
- 涙や身体感覚の変化
- 思い出した出来事や感情
- 新たに気づいた意味
音楽体験と文章化の併用は「自己内対話」を促し、意味の再構築を支援する。
11-5. グループでの共有
一人での実践に加え、信頼できる友人や家族、支援グループと一緒に音楽を聴くことも効果的である。
- 共同傾聴:同じ音楽を聴き、その後に感想を語り合う。
- 追悼の時間:亡き人を偲ぶセッションで第2組曲や第5組曲を用いる。
- 再生の確認:第1組曲や第6組曲を聴きながら「共に未来に向かう」感覚を共有する。
これにより、「孤独な悲嘆」から「共に悲嘆を生きる」へと転換が起きる(Rosenblatt, 2008)。
11-6. 専門家との協働
セルフケアでの音楽体験が苦しさを増す場合もある。その時は専門家(心理士、音楽療法士、牧師・僧侶など)の支援を受けることが望ましい。
音楽療法士は、個々の悲嘆状況に応じて適切な組曲や楽章を選び、即興演奏を交えて感情の表出をサポートする。臨床的研究でも、音楽療法の専門的介入はセルフケアを超えた効果を持つことが確認されている(Bonde, 2011)。
11-7. 実践ガイドライン
まとめると、あなた自身のグリーフケアに無伴奏チェロ組曲を取り入れる方法は以下のように整理できる。
- 環境を整える:静かな空間と良い響き。
- 感情を受け止める:涙を流してよい。
- 記録を残す:聴後に日記をつける。
- 共有する:家族やグループで語り合う。
- 必要に応じて専門家と協働:セルフケアを超える支援を求める。
このステップを通じて、音楽は「単なる鑑賞」から「自己変容を支える実践」へと昇華する。
第12章 結論──悲嘆を超えて共に生きる
12-1. 悲嘆を「乗り越える」のではなく「抱きしめる」
死別の体験は人生の根底を揺るがし、かつての日常を失わせる。多くの人が「悲しみを早く乗り越えなければならない」と自らを追い込むが、現代のグリーフ研究はその考えを修正している。悲嘆は「乗り越える対象」ではなく、「抱えながら生きるプロセス」である(Neimeyer, 2012)。
J.S.バッハの《無伴奏チェロ組曲》は、この理解を象徴的に体現する。沈痛な第2組曲や第5組曲が悲嘆の深みに寄り添い、第1組曲や第6組曲が未来への希望を示す。全曲を通じて聴くことは、「悲しみと希望の二重性」を生きることに他ならない。
12-2. 無伴奏チェロ組曲が示す「人間存在の普遍性」
《無伴奏チェロ組曲》は言語を持たない。だからこそ文化や宗教を超えて、人間の根源的な感情に響く。チェロという楽器の音域が人間の声に近いこともあり、その響きは「人間存在の普遍性」を象徴している(Juslin & Sloboda, 2010)。
欧米、アジア、日本の事例が示すように、この音楽は文化的差異を超え、「悲しむこと」「祈ること」「再生すること」という普遍的体験に寄り添っている。無伴奏チェロ組曲が21世紀の多文化社会においてもなお慰めと力を与え続けているのは、その普遍性ゆえである。
12-3. 科学と霊性の架け橋
本書で取り上げた神経科学や心理学の研究は、音楽が悲嘆の緩和に有効であることを示している。一方で、多くの死別者がこの音楽を「祈り」「魂の解放」として受け止めてきたことも事実である。
科学的エビデンスと霊的体験は対立するものではない。むしろ両者が補い合うことで、音楽は「人間の存在を丸ごと支える力」として働く。バッハの音楽はその最良の例証である。
12-4. 私自身の体験から
最愛の妻をがんで亡くしたとき、私は深い孤独と絶望に沈んだ。だが、無伴奏チェロ組曲を聴くことで、自分の悲しみが音として響き出し、涙と共に解放された瞬間があった。第2組曲で流した涙、第1組曲で感じた微かな光、第6組曲で抱いた「共にいる感覚」──それらは私を再び生きる道へと導いた。
私が歩んだプロセスは特別ではない。誰にとっても音楽は「悲嘆の伴走者」となりうる。本稿を通じて、同じように喪失を経験した方々が「音楽を通じて共に生きる力」を見出してくだされば、これ以上の喜びはない。
12-5. 未来への希望
悲嘆は決して完全に消えることはない。しかし、音楽はその悲しみを抱えながらも「共に生きる」力を与えてくれる。
バッハの無伴奏チェロ組曲は、300年を超えて響き続ける「人類共通の慰め」であり、「未来への光」である。私たちは亡き人を忘れるのではなく、その人との絆を新たな形で生かしながら歩むことができる。
この音楽と共にある限り、悲嘆は孤独ではなく、むしろ「共に生きる力」へと変わりうるのだ。
参考文献(APA形式)
第1章 J.S.バッハと無伴奏チェロ組曲の歴史的背景
- Neimeyer, R. A. (2012). Techniques of grief therapy: Creative practices for counseling the bereaved. Routledge.
- Stowell, R. (1999). The Cambridge Companion to the Cello. Cambridge University Press.
- Wolff, C. (2000). Johann Sebastian Bach: The learned musician. W. W. Norton & Company.
- Worden, J. W. (2009). Grief counseling and grief therapy: A handbook for the mental health practitioner (4th ed.). Springer Publishing Company.
第2章 無伴奏チェロ組曲とグリーフケアの心理的効用
- Aldridge, D. (2005). Music therapy and neurological rehabilitation: Performing health. Jessica Kingsley Publishers.
- Bonny, H. L. (2002). Music and consciousness in guided imagery and music (GIM). Barcelona Publishers.
- Juslin, P. N., & Sloboda, J. A. (Eds.). (2010). Handbook of music and emotion: Theory, research, applications. Oxford University Press.
- Kim, S. (2017). Music therapy for grief support groups in Korea: A qualitative study. Korean Journal of Music Therapy, 19(2), 45–63.
- Kübler-Ross, E. (1969). On death and dying. Scribner.
- Neimeyer, R. A. (2012). Techniques of grief therapy: Creative practices for counseling the bereaved. Routledge.
- Stroebe, M., & Schut, H. (2010). The dual process model of coping with bereavement: A decade on. Omega: Journal of Death and Dying, 61(4), 273–289.
- Worden, J. W. (2009). Grief counseling and grief therapy: A handbook for the mental health practitioner (4th ed.). Springer Publishing Company.
第3章 第1組曲ト長調 BWV1007──希望の光として
- Aldridge, D. (2005). Music therapy and neurological rehabilitation: Performing health. Jessica Kingsley Publishers.
- Blood, A. J., & Zatorre, R. J. (2001). Intensely pleasurable responses to music correlate with activity in brain regions implicated in reward and emotion. Proceedings of the National Academy of Sciences, 98(20), 11818–11823.
- Kim, S. (2017). Music therapy for grief support groups in Korea: A qualitative study. Korean Journal of Music Therapy, 19(2), 45–63.
- Little, M., & Jenne, N. (2001). Dance and the music of J. S. Bach. Indiana University Press.
- Neimeyer, R. A. (2012). Techniques of grief therapy: Creative practices for counseling the bereaved. Routledge.
- Saarikallio, S., & Erkkilä, J. (2007). The role of music in adolescents’ mood regulation. Psychology of Music, 35(1), 88–109.
第4章 第2組曲ニ短調 BWV1008──悲嘆の深みを映す鏡
- Aldridge, D. (2005). Music therapy and neurological rehabilitation: Performing health. Jessica Kingsley Publishers.
- Kim, S. (2017). Music therapy for grief support groups in Korea: A qualitative study. Korean Journal of Music Therapy, 19(2), 45–63.
- Klass, D., Silverman, P. R., & Nickman, S. L. (Eds.). (1996). Continuing bonds: New understandings of grief. Taylor & Francis.
- Neimeyer, R. A. (2012). Techniques of grief therapy: Creative practices for counseling the bereaved. Routledge.
- Parkes, C. M. (2009). Bereavement: Studies of grief in adult life (4th ed.). Routledge.
- Rameau, J.-P. (1971). Treatise on harmony (P. Gossett, Trans.). Dover. (Original work published 1722)
- Stowell, R. (1999). The Cambridge Companion to the Cello. Cambridge University Press.
- 日本音楽療法学会誌. (2018). 死別体験者における音楽療法の効果に関する事例研究, 18(1), 45–57.
第5章 第3組曲ハ長調 BWV1009──生の力強さの回復
- Aldridge, D. (2005). Music therapy and neurological rehabilitation: Performing health. Jessica Kingsley Publishers.
- Blood, A. J., & Zatorre, R. J. (2001). Intensely pleasurable responses to music correlate with activity in brain regions implicated in reward and emotion. Proceedings of the National Academy of Sciences, 98(20), 11818–11823.
- Mattheson, J. (1981). Der vollkommene Capellmeister (E. C. Harriss, Trans.). University of Michigan Press. (Original work published 1739)
- Neimeyer, R. A. (2012). Techniques of grief therapy: Creative practices for counseling the bereaved. Routledge.
- Stroebe, M., & Schut, H. (2010). The dual process model of coping with bereavement: A decade on. Omega: Journal of Death and Dying, 61(4), 273–289.
- 日本音楽療法学会誌. (2018). 死別体験者における音楽療法の効果に関する事例研究, 18(1), 45–57.
- 朝日新聞. (2015). 東日本大震災復興コンサート記事.
第6章 第4組曲変ホ長調 BWV1010──内省と再構築
- Aldridge, D. (2005). Music therapy and neurological rehabilitation: Performing health. Jessica Kingsley Publishers.
- Brewer, J. A., Worhunsky, P. D., Gray, J. R., Tang, Y. Y., Weber, J., & Kober, H. (2011). Meditation experience is associated with increased cortical thickness. NeuroReport, 22(17), 1–5.
- Koelsch, S. (2014). Brain correlates of music-evoked emotions. Nature Reviews Neuroscience, 15(3), 170–180.
- Mattheson, J. (1981). Der vollkommene Capellmeister (E. C. Harriss, Trans.). University of Michigan Press. (Original work published 1739)
- Neimeyer, R. A. (2012). Techniques of grief therapy: Creative practices for counseling the bereaved. Routledge.
第7章 第5組曲ハ短調 BWV1011──死と向き合う勇気
- Aldridge, D. (2005). Music therapy and neurological rehabilitation: Performing health. Jessica Kingsley Publishers.
- Koelsch, S. (2014). Brain correlates of music-evoked emotions. Nature Reviews Neuroscience, 15(3), 170–180.
- Mattheson, J. (1981). Der vollkommene Capellmeister (E. C. Harriss, Trans.). University of Michigan Press. (Original work published 1739)
- Neimeyer, R. A. (2012). Techniques of grief therapy: Creative practices for counseling the bereaved. Routledge.
- Stowell, R. (1999). The Cambridge Companion to the Cello. Cambridge University Press.
- 日本音楽療法学会誌. (2018). 死別体験者における音楽療法の効果に関する事例研究, 18(1), 45–57.
第8章 第6組曲ニ長調 BWV1012──魂の解放と超越
- Aldridge, D. (2005). Music therapy and neurological rehabilitation: Performing health. Jessica Kingsley Publishers.
- Gabrielsson, A. (2011). Strong experiences with music: Music is much more than just music. Oxford University Press.
- Kim, S. (2017). Music therapy for grief support groups in Korea: A qualitative study. Korean Journal of Music Therapy, 19(2), 45–63.
- Klass, D., Silverman, P. R., & Nickman, S. L. (Eds.). (1996). Continuing bonds: New understandings of grief. Taylor & Francis.
- Mattheson, J. (1981). Der vollkommene Capellmeister (E. C. Harriss, Trans.). University of Michigan Press. (Original work published 1739)
- Salimpoor, V. N., Benovoy, M., Larcher, K., Dagher, A., & Zatorre, R. J. (2011). Anatomically distinct dopamine release during anticipation and experience of peak emotion to music. Nature Neuroscience, 14(2), 257–262.
- Stowell, R. (1999). The Cambridge Companion to the Cello. Cambridge University Press.
- 朝日新聞. (2015). 東日本大震災復興祈念コンサート記事.
第9章 無伴奏チェロ組曲と多文化的グリーフケアの実践
- Aldridge, D. (2005). Music therapy and neurological rehabilitation: Performing health. Jessica Kingsley Publishers.
- Juslin, P. N., & Sloboda, J. A. (Eds.). (2010). Handbook of music and emotion: Theory, research, applications. Oxford University Press.
- Kim, S. (2017). Music therapy for grief support groups in Korea: A qualitative study. Korean Journal of Music Therapy, 19(2), 45–63.
- Rosenblatt, P. C. (2008). Grief across cultures: A review and research agenda. In M. Stroebe, R. O. Hansson, H. Schut, & W. Stroebe (Eds.), Handbook of bereavement research and practice: Advances in theory and intervention (pp. 207–222). American Psychological Association.
- 朝日新聞. (2012). 東日本大震災追悼式典記事.
第10章 音楽とグリーフの科学的根拠
- Blood, A. J., & Zatorre, R. J. (2001). Intensely pleasurable responses to music correlate with activity in brain regions implicated in reward and emotion. PNAS, 98(20), 11818–11823.
- Bonde, L. O. (2011). Health music(k)ing: Music therapy or music and health? Nordic Journal of Music Therapy, 20(2), 103–121.
- Chan, M. F., Wong, Z. Y., & Thayala, N. V. (2010). The effectiveness of music listening in reducing depressive symptoms in adults: A systematic review. Complementary Therapies in Medicine, 19(6), 332–348.
- Gallagher, L. M., & Steele, A. L. (2002). Music therapy with end-of-life patients and their families. Journal of Palliative Care, 18(3), 161–166.
- Gruppman, J. (2015). Music, grief and community: A qualitative study of group music therapy with bereaved adults. Voices: A World Forum for Music Therapy, 15(1).
- Juslin, P. N., & Sloboda, J. A. (Eds.). (2010). Handbook of music and emotion: Theory, research, applications. Oxford University Press.
- Koelsch, S. (2014). Brain correlates of music-evoked emotions. Nature Reviews Neuroscience, 15(3), 170–180.
- Neimeyer, R. A. (2012). Techniques of grief therapy: Creative practices for counseling the bereaved. Routledge.
- Stroebe, M., & Schut, H. (2010). The dual process model of coping with bereavement: A decade on. Omega: Journal of Death and Dying, 61(4), 273–289.
- 日本音楽療法学会誌. (2018). 死別体験者における音楽療法の効果に関する事例研究, 18(1), 45–57.
第11章 あなた自身のグリーフケアに取り入れる方法
- Bonde, L. O. (2011). Health music(k)ing: Music therapy or music and health? Nordic Journal of Music Therapy, 20(2), 103–121.
- Klass, D., Silverman, P. R., & Nickman, S. L. (Eds.). (1996). Continuing bonds: New understandings of grief. Taylor & Francis.
- Neimeyer, R. A. (2012). Techniques of grief therapy: Creative practices for counseling the bereaved. Routledge.
- Pennebaker, J. W., & Smyth, J. M. (2016). Opening up by writing it down: How expressive writing improves health and eases emotional pain. Guilford Press.
- Rosenblatt, P. C. (2008). Grief across cultures: A review and research agenda. In M. Stroebe, R. O. Hansson, H. Schut, & W. Stroebe (Eds.), Handbook of bereavement research and practice: Advances in theory and intervention (pp. 207–222). American Psychological Association.
- Worden, J. W. (2009). Grief counseling and grief therapy: A handbook for the mental health practitioner (4th ed.). Springer Publishing Company.
第12章 結論──悲嘆を超えて共に生きる
- Juslin, P. N., & Sloboda, J. A. (Eds.). (2010). Handbook of music and emotion: Theory, research, applications. Oxford University Press.
- Neimeyer, R. A. (2012). Techniques of grief therapy: Creative practices for counseling the bereaved. Routledge.
ご感想、お問い合せ、ご要望等ありましたら下記フォームでお願いいたします。
投稿者プロフィール

- 市村 修一
-
【略 歴】
茨城県生まれ。
明治大学政治経済学部卒業。日米欧の企業、主に外資系企業でCFO、代表取締役社長を経験し、経営全般、経営戦略策定、人事、組織開発に深く関わる。その経験を活かし、激動の時代に卓越した人財の育成、組織開発の必要性が急務と痛感し独立。「挑戦・創造・変革」をキーワードに、日本企業、外資系企業と、幅広く人財・組織開発コンサルタントとして、特に、上級管理職育成、経営戦略策定、組織開発などの分野で研修、コンサルティング、講演活動等で活躍を経て、世界の人々のこころの支援を多言語多文化で行うグローバルスタートアップとして事業展開を目指す決意をする。
【背景】
2005年11月、 約10年連れ添った最愛の妻をがんで5年間の闘病の後亡くす。
翌年、伴侶との死別自助グループ「Good Grief Network」を共同設立。個別・グループ・グリーフカウンセリングを行う。映像を使用した自助カウンセリングを取り入れる。大きな成果を残し、それぞれの死別体験者は、新たな人生を歩み出す。
長年実践研究を妻とともにしてきた「いきるとは?」「人間学」「メンタルレジリエンス」「メンタルヘルス」「グリーフケア」をさらに学際的に実践研究を推し進め、多数の素晴らしい成果が生まれてきた。私自身がグローバルビジネスの世界で様々な体験をする中で思いを強くした社会課題解決の人生を賭ける決意をする。
株式会社レジクスレイ(Resixley Incorporated)を設立、創業者兼CEO
事業成長アクセラレーター
広島県公立大学法人叡啓大学キャリアメンター
【専門領域】
・レジリエンス(精神的回復力) ・グリーフケア ・異文化理解 ・グローバル人財育成
・東洋哲学・思想(人間学、経営哲学、経営戦略) ・組織文化・風土改革 ・人材・組織開発、キャリア開発
・イノベーション・グローバル・エコシステム形成支援
【主な著書/論文/プレス発表】
「グローバルビジネスパーソンのためのメンタルヘルスガイド」kindle版
「喪失の先にある共感: 異文化と紡ぐ癒しの物語」kindle版
「実践!情報・メディアリテラシー: Essential Skills for the Global Era」kindle版
「こころと共感の力: つながる時代を前向きに生きる知恵」kindle版
「未来を拓く英語習得革命: AIと異文化理解の新たな挑戦」kindle版
「グローバルビジネス成功の第一歩: 基礎から実践まで」Kindle版
「仕事と脳力開発-挫折また挫折そして希望へ-」(城野経済研究所)
「英語教育と脳力開発-受験直前一ヶ月前の戦略・戦術」(城野経済研究所)
「国際派就職ガイド」(三修社)
「セミナーニュース(私立幼稚園を支援する)」(日本経営教育研究所)
【主な研修実績】
・グローバルビジネスコミュニケーションスキルアップ ・リーダーシップ ・コーチング
・ファシリテーション ・ディベート ・プレゼンテーション ・問題解決
・グローバルキャリアモデル構築と実践 ・キャリア・デザインセミナー
・創造性開発 ・情報収集分析 ・プロジェクトマネジメント研修他
※上記、いずれもファシリテーション型ワークショップを基本に実施
【主なコンサルティング実績】
年次経営計画の作成。コスト削減計画作成・実施。適正在庫水準のコントロール・指導を遂行。人事総務部門では、インセンティブプログラムの開発・実施、人事評価システムの考案。リストラクチャリングの実施。サプライチェーン部門では、そのプロセス及びコスト構造の改善。ERPの導入に際しては、プロジェクトリーダーを務め、導入期限内にその導入。組織全般の企業風土・文化の改革を行う。
【主な講演実績】
産業構造変革時代に求められる人材
外資系企業で働くということ
外資系企業へのアプローチ
異文化理解力
経営の志
商いは感動だ!
品質は、タダで手に入る
利益は、タダで手に入る
共生の時代を創る-点から面へ、そして主流へ
幸せのコミュニケーション
古典に学ぶ人生
古典に学ぶ経営
論語と経営
論語と人生
安岡正篤先生から学んだこと
素読のすすめ
経営の突破口は儒学にあり
実践行動学として儒学に学ぶ!~今ここに美しく生きるために~
何のためにいきるのか~一人の女性の死を見つめて~
縁により縁に生きる
縁に生かされて~人は生きているのではなく生かされているのだ!~
看取ることによって手渡されるいのちのバトン
など


