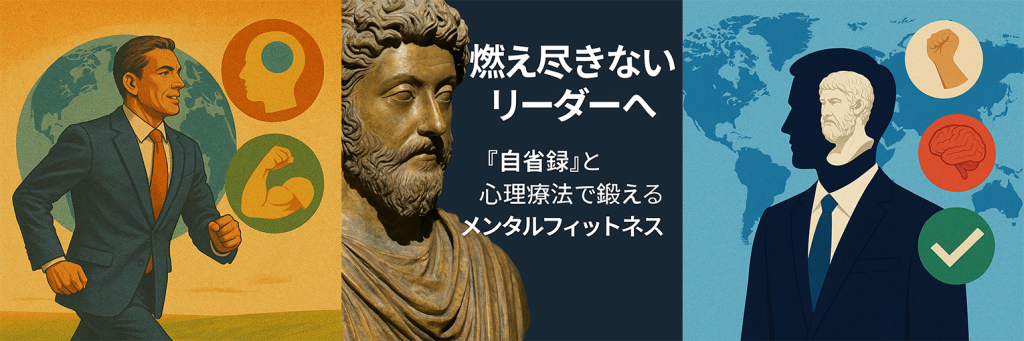
燃え尽きないリーダーへ 〜『自省録』と心理療法で鍛えるメンタルフィットネス〜
はじめに
現代のグローバルビジネス環境は、かつてないほどリーダーに苛酷な試練を突きつけている。市場の急激な変動、国際的な政治・経済の不安定さ、予測不可能なパンデミックやサプライチェーンの分断──いわゆる VUCA時代(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) のただ中で、リーダーは常に迅速かつ正確な意思決定を求められる。同時に、多文化チームを率い、異なる価値観や働き方を持つ人材をまとめあげなければならない。こうしたプレッシャーの積み重ねは、リーダーの心と体を蝕み、やがて 「燃え尽き症候群(バーンアウト)」 という深刻な状態に追い込む。
バーンアウトは単なる一時的な疲労ではない。慢性的なストレスや精神的消耗によって、エネルギーが枯渇し、意欲や創造性が失われ、最終的には組織全体の生産性にも甚大な影響を及ぼす。実際、世界保健機関(WHO)もバーンアウトを「職業性ストレスに起因する症候群」と定義しており、リーダーにとって避けて通れない課題となっている。特にグローバル企業を率いるエグゼクティブ層においては、文化的摩擦・成果至上主義・長時間労働など複数の要因が重なり、メンタルヘルスのリスクは年々高まっている。
では、リーダーはどのようにして「燃え尽きない心」を育むことができるのだろうか。ここで注目したいのが、二千年前にローマ皇帝マルクス・アウレーリウスが書き残した 『自省録(Meditations)』 である。権力の頂点に立ちながら戦争・疫病・裏切り・政治的陰謀に直面し続けたマルクスは、自らの心を守るために日々の思索を記録した。それが『自省録』であり、現代においてもなお読み継がれる「心の取扱説明書」である。
興味深いことに、この『自省録』の実践は、現代心理療法の重要な方法論──例えば 認知行動療法(CBT) や アクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT) と驚くほど共鳴している。CBTは「認知の歪みを修正して感情の反応を整える」技法を体系化し、ACTは「不快な感情を受け入れつつ、価値に基づいた行動を選ぶ」ことを重視する。マルクスが『自省録』で繰り返し説いた「外界の出来事は私を害さない。それを害と見なすのは私である」という洞察は、CBTの認知再構成に通じる。また「死や苦痛も自然の一部であり、恐れるに値しない」という姿勢は、ACTにおける受容の態度そのものである。
さらに近年注目される概念に 「メンタルフィットネス」 がある。これは心を筋肉のように鍛え、柔軟性・持続力・回復力を高めるアプローチであり、単なる治療ではなく予防とパフォーマンス向上を目的とする点が特徴である。『自省録』の哲学、CBTやACTの技法を日常に取り入れることは、このメンタルフィットネスを実現する強力な道となる。
本記事では、マルクス・アウレーリウスの『自省録』と現代心理療法(CBT・ACT)の比較を通じて、グローバルビジネスリーダーがいかにして「燃え尽きない心」をつくり、メンタルフィットネスを鍛えることができるのか を考察する。欧米、日本、そしてアジア(中国を除く)の具体的な事例を紹介しながら、実践に直結するガイドを提示することで、読者が日常に取り入れやすい形で「心の筋力」を強化できるように導く。
あなたがもし、リーダーとして激しいプレッシャーにさらされ、燃え尽きの不安を感じているなら、ここで紹介する『自省録』と心理療法の融合実践は、きっと新しい道を照らすだろう。
序章 なぜ今「メンタルヘルスと自省録」なのか
- グローバルビジネス環境とメンタルヘルスの危機
21世紀のビジネス環境は、かつてないほどの不確実性に満ちている。地政学的リスクの激化、パンデミックによる社会変動、AIやデジタル技術の急速な進展、そして市場競争のグローバル化が同時進行するなか、リーダーは常に「変化の荒波」にさらされているのである。このような状況下において、経営層やマネジメント層に求められるのは単なる戦略的判断力だけではない。むしろ、自らの精神をどのように安定させ、心のバランスを保ちつつ組織を牽引するかという、メンタルヘルスの維持が極めて重要になっている。
近年、欧米諸国では「メンタルフィットネス」という概念が注目されている。これは、従来の「心の病を予防・治療するメンタルヘルス」から一歩進み、心を筋肉のように鍛え、ストレス耐性・感情調整力・持続的な集中力を高めることを意味する。シリコンバレーの企業や欧州のグローバル企業では、CEO自らが瞑想や哲学的読書を習慣化し、心を調律する実践を行っていることが報告されている。日本においても長時間労働や過労の問題が社会課題化するなかで、精神的セルフケアへの関心が高まっている。アジア諸国(中国を除く)でも、韓国やシンガポールの企業ではストレスマネジメント教育が導入されつつあり、グローバルに共通した課題として浮上しているのである。
こうした時代背景のもとで再評価されているのが、古代ローマ皇帝マルクス・アウレーリウスの『自省録』である。この書物は、単なる哲学書でもなく、権力者の備忘録でもない。むしろ、**一人の人間が自らの心を整え、世界の荒波のなかで生き抜くための「実践書」**なのである。
- 『自省録』に込められた普遍的メッセージ
『自省録』は、マルクス・アウレーリウスが皇帝としての職務を果たしながら、日々の葛藤や苦悩を自らに語りかけた記録である。彼は軍事遠征の陣中でも、書物を開き、自らの心を整えるために言葉を綴った。そこには「人は外界を支配できない。しかし、自己の心の在り方は支配できる」というストア哲学の核心が息づいている。
ストア哲学の基本は、以下の三つに要約できる。
- 理性(logos)に従って生きること
- 自然の秩序(physis)を受け入れること
- 自己の感情や欲望を統御すること
これらは2000年前のローマ帝国でも、今日の多文化ビジネス社会でも同じ効力を持つ。なぜなら、外的環境を完全にコントロールすることは不可能であるが、内的態度を整えることは常に可能だからである。ここにこそ、『自省録』が現代人にとっても実践的な意味を持つ理由がある。
- 現代心理療法との接点
現代心理療法の代表的アプローチである認知行動療法(CBT)やアクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)は、驚くほど『自省録』と共通する思想を持つ。CBTは「自動思考の歪み」を認識し、合理的な認知へと修正する技法である。マルクスが自らに「怒りに任せるのは愚かである」「死もまた自然の一部である」と言い聞かせる姿は、まさに認知の修正であり、現代のCBTと同質の営みである。
一方、ACTは「思考や感情を無理に消そうとせず、受け入れつつ価値に基づく行動を選択する」ことを重視する。これはストア哲学の「外界の出来事は我々の支配の及ばぬものとして受容せよ」という態度と響き合う。つまり、『自省録』はCBT的でもあり、ACT的でもあるのである。
このように、哲学と心理療法は異なる道を歩んできたが、最終的には「人間が心をどう整えるか」という共通の目的に収斂している。その意味で、『自省録』は現代心理療法とグローバルビジネスリーダーをつなぐ「架け橋」となる。
- グローバルリーダーにとっての実践的価値
現代のグローバルリーダーが直面する課題は、マルクスの時代と同じく「予測不可能で制御不能な外的環境」と「絶え間ないプレッシャー」である。株主からの要求、異文化チームの摩擦、地政学的リスク、突発的な危機対応――これらに直面したとき、リーダーは往々にして精神的疲弊に陥る。ここで『自省録』を活用することは、単なる知識習得にとどまらず、「心の筋トレ」=メンタルフィットネスの実践として機能する。
例えば、欧米のあるCEOは、重要な交渉や決断の前に『自省録』を開き、自らの判断が短期的利益ではなく長期的価値に基づいているかを確認する習慣を持っている。日本の企業リーダーは、夜に『自省録』を音読し、その日の感情の揺れを振り返ることで翌日の冷静さを確保している。アジア(中国を除く)では、シンガポールの多国籍企業の幹部が『自省録』を「リーダーシップ研修」の教材に取り入れ、異文化マネジメントの中で「受容」と「理性」を養う実践を行っている。
図表1:グローバルビジネス環境における主要ストレス要因
カテゴリー | 欧米の特徴 | 日本の特徴 | アジア(中国除く)の特徴 |
労働環境 | リモートワーク拡大、成果主義 | 長時間労働、和を重視 | 高成長による過重労働、成果志向 |
社会的要因 | 政治的分断、格差問題 | 高齢化、人口減少 | 多文化共存、競争激化 |
技術的要因 | AI・自動化への適応 | デジタル化の遅れ | スマートシティ、急速なIT導入 |
国際要因 | 貿易摩擦、地政学リスク | 輸出依存、近隣国との緊張 | グローバル市場依存の高さ |
- 本記事の目的と読み方
本記事の目的は、『自省録』を現代心理療法の視点から読み解き、グローバルビジネスリーダーのセルフケアに応用する方法を提示することにある。哲学は抽象的に見えるが、実は極めて実践的である。心理療法は科学的に見えるが、その根底には人間の生き方に関する哲学が横たわっている。両者を架橋することによって、読者は「自らの心を鍛える具体的な道筋」を発見できるはずである。
読み進めるにあたり、読者は「哲学を知識として学ぶ」のではなく、「日々の生活にどう組み込むか」という実践的視点を持ってほしい。朝の始業前の5分、夜の就寝前の10分――その短い時間に『自省録』の一節を思い出し、自らの感情や行動を見つめ直すことができれば、それは確実に心の筋力を強化する習慣となるだろう。
- 次章への橋渡し
以上のように、『自省録』は単なる古典ではなく、現代心理療法と響き合い、グローバルビジネスリーダーのセルフケアに直接的な価値を持つ実践書である。本記事では、次章以降で『自省録』の思想的基盤を丁寧に解説し、さらにCBTやACTといった現代心理療法との比較を通して、具体的な応用法を示していく。哲学と心理療法を往復する旅路のなかで、読者自身の心の在り方を再発見してほしい。
第1章 マルクス・アウレーリウス『自省録』とは何か
- 皇帝であり哲人であったマルクス・アウレーリウス
マルクス・アウレーリウス(Marcus Aurelius, 121–180年)は、ローマ帝国の「五賢帝」の最後に位置づけられる人物である。彼の治世は一見すると帝国の安定を保った時代のように見えるが、実際には外敵の侵入、自然災害、そしてペストの大流行に見舞われる激動の時代であった。彼は絶え間ない戦争の指揮を執り、皇帝としての責務を果たす一方、私的な時間においてはストア哲学を深く学び、その成果を自らの心の支えとした。
ここで注目すべきは、マルクスが哲学を権力の道具や理論的趣味としてではなく、自己の心を整える実践として用いた点である。哲学は彼にとって「戦場における盾」であり、また「精神を鍛える訓練」であった。彼は軍の遠征先で、寝床の横に羊皮紙を置き、自己への問いかけを綴り続けた。それが後に『自省録(Meditations)』と呼ばれるようになるのである。
- 『自省録』の成り立ちと性格
『自省録』は、もともと出版を意図した書物ではない。マルクスが自分自身の心を律するために書き記した覚え書きであり、自己訓練の記録である。彼はそこに、皇帝としての栄誉や戦略を誇ることは一切しない。むしろ、自らの弱さや怒りを戒め、外界の不確実性に対して冷静であろうとする内面の格闘を赤裸々に記録している。
この点において、『自省録』は「自己との対話の書」と言える。古代ギリシアの哲学者ソクラテス以来、哲学は「自分を知る」ことを出発点としてきたが、マルクスの記録はその最も実践的な形を示している。まさにこれは自己の心を整える「セルフカウンセリング」の書であり、現代心理療法にも通じる。
- ストア哲学の基本原理と『自省録』
『自省録』の思想的基盤には、ストア哲学がある。紀元前3世紀にキプロス出身のゼノンによって始められたストア派は、理性と自然の秩序に従って生きることを最高善とした。エピクテトスやセネカといった思想家を経て、マルクスに至るまで受け継がれたその教えは、以下の三つに集約できる。
- 制御できるものとできないものを区別すること
外部の出来事や他者の行動は我々の支配下にはない。支配できるのは自らの意志と態度のみである。 - 自然(physis)の秩序を受け入れること
生と死、栄光と衰退は自然の循環に属する。人はそれに逆らうのではなく調和するべきである。 - 理性(logos)による自己統御
人間は理性的存在であり、感情や欲望に流されず、理性によって自己を導くべきである。
マルクスはこれらを日々の実践に落とし込み、「今日、私は誰かに侮辱されるだろう。しかしそれは彼らの問題であり、私が理性を失う理由にはならない」と自らに言い聞かせる。ここに『自省録』の実践性がある。
図表2:ストア哲学の基本原理(三本柱)
原理 | 内容 | 『自省録』での表現例 |
理性(logos) | 感情に流されず理性的に判断する | 「怒りに任せるのは愚かである」 |
自然(physis) | 世界の秩序を受け入れる | 「死もまた自然の一部である」 |
自己統御 | 自分の心を制御する | 「外界は支配できないが、心は支配できる」 |
- 『自省録』の主要なテーマ
『自省録』には多様なテーマが織り込まれているが、特に以下の点が現代人にとっても示唆的である。
- 無常観と死の受容
「人間の命は一瞬のことである。明日の保証は誰にもない」との記述は、現代の死生観やマインドフルネス実践と響き合う。 - 怒りの制御
権力者であるがゆえに多くの批判や敵意に晒されるなか、マルクスは「怒りは自分を滅ぼす毒である」と繰り返し戒めた。 - 普遍的人類観
「人は皆、理性を共有する存在である」という認識は、異文化間の共感やグローバル倫理の基盤となりうる。 - 自己省察の習慣
朝夕に自己の感情や行動を振り返る姿勢は、現代のメンタルヘルスルーティンに直結する。
- 現代における『自省録』の再評価
今日、『自省録』は単なる古典文学ではなく、「実践哲学」として再評価されている。欧米のリーダーシップ教育では、MBA課程やエグゼクティブ研修で『自省録』が教材として取り上げられることが増えている。ハーバード・ビジネス・スクールの一部のプログラムでは、ケーススタディと並行して『自省録』を読み、「自己統御がいかに意思決定に影響するか」を議論する授業が行われている。
日本においても、『自省録』は経営者やリーダー層に読まれ続けている。とりわけ「己を戒める」という日本文化の伝統と響き合い、心を律する書として親しまれてきた。さらにアジア諸国、特にシンガポールや韓国では、多文化環境で働くリーダーにとって「自己統御」と「受容」の実践的価値が強調され、リーダーシップ研修の一環として導入されている。
- 『自省録』とメンタルヘルスの接点
現代社会では、うつ病やバーンアウト(燃え尽き症候群)が経営者やリーダーを含むビジネスパーソンの大きな課題となっている。そこで注目されているのが、日々の「自己対話」による心の安定である。『自省録』の記述は、現代心理療法が重視する「認知の修正」「価値に基づく行動」「セルフモニタリング」と驚くほど一致している。
例えば、CBTにおける「自動思考の記録表」に相当するものは、マルクスが夜に自らの感情を振り返り、「今日私は怒った。しかしその怒りは理性に基づいていたか」と検証する姿勢に表れている。またACTにおける「価値の明確化」は、マルクスが「人としての本分を果たすことが最大の価値である」と繰り返し述べている点と重なる。
- 次章への橋渡し
『自省録』は、皇帝の孤独な内面告白であると同時に、現代のリーダーが「心の筋力」を養うためのトレーニングマニュアルでもある。本章でその成り立ちと思想的背景を整理したが、次章では現代心理療法の主要枠組み――認知行動療法(CBT)とアクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)――を取り上げる。それらを理解することで、『自省録』と現代心理療法の共鳴点をより明確に見出すことができるだろう。
第2章 現代心理療法の枠組み
- 現代社会における心理療法の位置づけ
21世紀において、メンタルヘルスはもはや個人の問題にとどまらず、組織・社会全体の生産性や持続可能性に直結する課題となっている。特にグローバルビジネスの現場では、多文化間の摩擦、長時間労働、成果主義的プレッシャー、さらにはリモートワークに伴う孤立感など、従来以上に多層的なストレス要因が存在する。
このような状況に対応するため、欧米、日本、アジア各国で広く導入されているのが心理療法的アプローチである。心理療法は医学的治療と異なり、薬物に依存せず、「心の在り方」や「思考と行動のパターン」を変化させることによって、精神的健康を回復・強化する実践法である。
その中でも特に現代において注目されているのが、**認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy: CBT)とアクセプタンス&コミットメント・セラピー(Acceptance and Commitment Therapy: ACT)**である。両者は科学的根拠に基づきながらも、日常生活に即した具体的手法を持ち、ビジネスリーダーのセルフケアにも有効である。
- 認知行動療法(CBT)の基本原理
(1)定義と歴史
認知行動療法は、1970年代にアーロン・ベック(Aaron T. Beck)やアルバート・エリスらが体系化した心理療法である。その基本的前提は、**「人間の感情や行動は、出来事そのものではなく、それをどう認知するかによって決まる」**という点にある。すなわち、同じ出来事に遭遇しても、人によってストレス反応が異なるのは、出来事の解釈や意味づけが異なるからである。
(2)主要概念
- 自動思考(Automatic Thoughts)
日常的に瞬間的に浮かぶ思考。多くは無意識的で、ネガティブに偏りやすい。 - 認知の歪み(Cognitive Distortions)
物事を極端に一般化したり、白黒思考に陥るなど、非合理的な思考パターン。 - スキーマ(Schema)
長期的に形成された信念体系。例えば「私は失敗者である」という根深い信念が、日常の認知に影響を及ぼす。
(3)技法
- 思考記録表を用い、出来事・感情・自動思考を整理する。
- 認知の歪みを特定し、合理的で柔軟な考えに置き換える。
- 行動実験を通じて新たな認知を検証する。
この過程は、自己観察と修正のサイクルを通して、より健康的な思考習慣を身につけることを目的とする。
図表3:CBTの基本構造
出来事 | 認知(自動思考) | 感情 | 行動 | 修正例 |
会議で意見を否定された | 「私は無能だ」 | 落ち込み | 消極的発言 | 「意見と人格は別である」 |
- アクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)の基本原理
(1)定義と背景
ACTは1990年代にスティーブン・C・ヘイズらによって開発された、いわゆる「第三世代認知行動療法」の一つである。その特徴は、CBTのように思考を修正するのではなく、**「思考や感情をあるがままに受け入れ、価値に基づいた行動を選択する」**ことを重視する点にある。
ACTの根底にあるのは、人間の苦悩は「思考や感情をコントロールしようとすること」から生じるという理解である。ネガティブな思考や感情を完全に消し去ることは不可能であり、それを消そうとする努力がむしろ苦悩を増幅させる。したがって、ACTは「消そうとするのではなく、受け入れる」ことを出発点とする。
(2)6つのコアプロセス
ACTでは、心理的柔軟性を育むために以下の六つのプロセスを強調する。
- 認知的脱フュージョン(Cognitive Defusion)
思考に巻き込まれず、距離をとって観察する。 - アクセプタンス(Acceptance)
不快な感情や思考を排除せず、存在を認める。 - 現在志向(Contact with the Present Moment)
今この瞬間に注意を向ける。 - 自己観(Self-as-Context)
思考や感情に左右されない「観察する自己」を育む。 - 価値の明確化(Values)
人生で本当に大切にしたい価値を特定する。 - 価値に基づく行動(Committed Action)
価値を実現する行動を具体的に選び、持続する。
(3)実践技法
- マインドフルネス瞑想を通じて思考を観察する。
- 自分の価値観を言語化し、それに沿った行動目標を設定する。
- 行動の実践と評価を繰り返し、心理的柔軟性を高める。
図表4:ACTの6つのコアプロセス
プロセス | 内容 | 『自省録』との対応 |
認知的脱フュージョン | 思考に距離をとる | 「怒りの正体を観察せよ」 |
アクセプタンス | 感情を受け入れる | 「死や苦痛を自然の一部と見よ」 |
現在志向 | 今に集中する | 「現在の瞬間を生きよ」 |
自己観 | 観察する自己を育む | 「理性ある自己を守れ」 |
価値の明確化 | 大切なものを特定 | 「人間の本分を果たせ」 |
価値に基づく行動 | 行動を持続する | 「義務を果たすことが最大の善」 |
- CBTとACTの比較
観点 | CBT | ACT |
思考へのアプローチ | 歪みを修正し、合理的に置き換える | 思考を修正せず、距離をとり受け入れる |
感情へのアプローチ | 不適応感情を軽減・修正 | 感情を排除せず、受容 |
行動へのアプローチ | 行動実験で認知を検証 | 価値に基づいた行動を実践 |
目的 | 不適応的思考・行動の改善 | 心理的柔軟性の向上 |
両者は異なるアプローチを取るが、「人がより健全に生きるために心を整える」という目的は共通している。この点が、『自省録』との接点を見出す上で重要となる。
- グローバルビジネスの現場での導入事例
欧米
アメリカの大手IT企業では、マネージャー研修にCBTの要素を取り入れ、リーダーが部下との対話において「認知の歪み」を減らすトレーニングを行っている。イギリスの金融業界では、ACTに基づいた「価値に基づくリーダーシッププログラム」が導入され、社員が自らの価値観に沿った意思決定を行うことを奨励している。
日本
日本では、CBTを基盤とした「ストレスチェック制度」が普及し、従業員が自分の自動思考を把握する取り組みが広がっている。一方、ACTはまだ新しいが、外資系企業の一部ではマインドフルネス研修と統合され、リーダー層に提供され始めている。
アジア(中国除く)
韓国では、若年層のメンタル不調を背景にCBTを基盤とする学校教育が導入され、企業研修にも応用されている。シンガポールでは多国籍企業がACTを採用し、異文化チームにおいて「多様性を受け入れつつ価値に基づいた行動を取る」訓練を行っている。
- 『自省録』との接点への布石
ここまで見てきたように、CBTとACTはいずれも「思考・感情・行動の在り方を変える」ことで人間の心を健全に導こうとするアプローチである。次章では、これら現代心理療法を『自省録』と対照しながら比較する。そこで明らかになるのは、2000年前の皇帝が自らに語りかけた言葉が、いかに現代心理療法の理論と共鳴しているか、そしてそれが今日のグローバルビジネスリーダーにとってどのように応用可能であるか、という点である。
第3章 『自省録』とCBTの比較
- 『自省録』とCBTをつなぐ視点
認知行動療法(CBT)は、思考と感情と行動の相互作用を重視し、「認知の歪みを修正すること」によって心の健康を取り戻すアプローチである。他方、マルクス・アウレーリウスの『自省録』は、皇帝として日々の困難に直面しながら、自己の心を理性によって整えようとした記録である。表現は異なるものの、両者の基盤には驚くほどの共通性がある。
すなわち、人間は出来事そのものではなく、その解釈によって苦悩するという認識である。CBTが科学的言語でこれを定式化したのに対し、マルクスは哲学的言葉で同じ実践を行っていたのである。
- 認知の歪みとストア派的修正
CBTでは、人間がストレスを感じるのは「認知の歪み(cognitive distortions)」によると考える。代表的な歪みには「全か無か思考」「過度の一般化」「破局的思考」などがある。これらは出来事を極端に解釈し、感情を不必要に強めてしまう。
『自省録』においても同様の発想が見られる。マルクスは繰り返し「外的出来事は善でも悪でもない。善悪は心の解釈に依存する」と述べる。例えば「侮辱された」と感じた出来事を彼はこう言い換える。「彼は自分の理性に従って行動したに過ぎない。それをどう解釈するかは私の自由である」。これはまさにCBTにおける「認知の修正」に等しい。
具体例
- CBTの思考記録表
出来事:会議で部下に意見を否定された
自動思考:「私は無能だ」
感情:落ち込み(70%)
認知再構成:「彼の意見は私の提案に対するものであり、私の人格を否定しているわけではない」 - 『自省録』の記述
「他者の批判は彼の判断である。理性ある者は、自分の義務を果たし続けるのみである」
両者は形式こそ異なるが、出来事を距離をおいて再評価し、感情の過剰反応を和らげる点で共通している。
図表5:CBTと『自省録』の共鳴点
認知の歪み | CBTでの修正 | 『自省録』での実践例 |
全か無か思考 | 「失敗=全て無価値」→「部分的成功もある」 | 「侮辱は私を害しない。それを害と見なすのは私だ」 |
過度の一般化 | 「一度の失敗で私は無能」 | 「失敗も自然の一部である」 |
破局的思考 | 「最悪の事態が必ず起こる」 | 「死も自然の循環である」 |
- 自己対話の技法
CBTは、患者に「自動思考を書き出し、問いかけを行い、合理的な答えに導く」という手順を踏ませる。これは言い換えれば「自己との対話」である。
マルクスも『自省録』において、常に自らに問いかけている。「なぜ怒るのか?」「死は恐れるに値するか?」。彼は自分を外から観察するようにして、感情を理性で吟味する。
この「メタ認知的視点」は、CBTが強調する「思考のモニタリング」と完全に一致している。すなわち、『自省録』は皇帝による壮大な思考記録表とも言えるのである。
- 欧米のビジネスリーダーの実践事例
(1)米国:シリコンバレーのCEO
ある米国のテック企業のCEOは、毎晩「思考ジャーナル」を記録している。これはCBTの思考記録表を基盤としたもので、「今日の出来事」「自動思考」「代替思考」を記す。彼はマルクスの『自省録』を愛読しており、そのスタイルを参考に「自己との対話」を経営判断の前提としている。
(2)英国:金融業界の幹部
英国ロンドンの金融機関では、リーダー層に『自省録』の抜粋を配布し、CBTのワークシートと並行して自己省察を促すプログラムを導入している。参加者は「市場の不確実性に巻き込まれるよりも、自分の認知を制御する方が生産的である」と語る。
- 日本における実践事例
日本では、CBTがうつ病治療やストレス対策として普及しているが、同時に『自省録』も経営者に読まれてきた。
ある製造業の社長は、朝礼で社員に「今日、我々は予期せぬ問題に直面するだろう。しかしそれは我々の制御外である。大切なのは、我々がどう対処するかである」という言葉を伝える。これはマルクスの思想を引用したものであり、同時にCBT的な「認知のフレーミング」を実践している例である。
さらに近年は、産業医やメンタルヘルス研修において、CBTの手法と『自省録』の言葉を組み合わせ、「古典と科学の融合」として紹介する試みも出てきている。
- アジアにおける実践事例(中国除く)
シンガポールの多国籍企業では、異文化チームの摩擦を軽減するために「自己省察ジャーナル」を活用している。参加者は「今日のストレス状況」「その時の思考」「合理的解釈」を記録する。研修の参考文献として『自省録』を併読させることで、「認知を変える力」が単なる技法ではなく人類普遍の知恵であると学ばせている。
韓国の大企業でも、幹部研修にCBTを導入しているが、同時に『自省録』を「リーダーの心構え」として読ませることで、合理的認知と倫理的自省を両立させるプログラムが実践されている。
- 『自省録』とCBTの統合的価値
『自省録』とCBTを比較すると、両者は次のような補完関係にある。
- CBTの強み:科学的・実証的に体系化されており、誰でも習得しやすい。
- 『自省録』の強み:2000年の歴史を通じて人類が共感してきた普遍性があり、言葉の力によって感情に深く訴えかける。
したがって、両者を統合することで、**「科学的根拠に裏づけられた普遍的実践」**が可能になる。グローバルビジネスリーダーにとって、これは単なるセルフケアを超え、リーダーシップそのものを支える基盤となる。
- 次章への橋渡し
本章では『自省録』とCBTの共鳴点を明らかにした。次章ではさらに一歩進め、ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)と『自省録』の比較を行う。受容と価値に基づく行動というACTの理念が、ストア哲学といかに共振し、現代のリーダーに新たな実践的示唆を与えるかを考察する。
第4章 『自省録』とACTの比較
- ACTの核心とストア哲学との親和性
アクセプタンス&コミットメント・セラピー(以下、ACT)は「第三世代認知行動療法」と呼ばれる心理療法の一つであり、**「不快な思考や感情をコントロールしようとするのではなく、受け入れつつ価値に基づいた行動を選択する」**ことを重視する。
この姿勢は、『自省録』の根幹をなすストア哲学ときわめて近い。マルクス・アウレーリウスは「外界の出来事は我々の制御外であり、それに抵抗するのではなく、自然の秩序として受け入れるべきである」と繰り返し説いた。ここに両者の思想的親和性が存在する。
ACTが現代の科学的枠組みで「アクセプタンス(受容)」を提唱するのに対し、『自省録』は哲学的言語で「アモール・ファティ(運命愛)」を語っている。すなわち、不快な現実を否定せず、むしろ積極的に肯定し、その中で価値に従って生きるという態度である。
- 「受容」の態度:苦痛を避けない心
ACTの第一歩は「アクセプタンス」、すなわち不快な思考や感情を排除しようとせず、その存在を認めることである。これは「痛みを避けるほど苦しみは増す」という逆説を踏まえた実践である。
『自省録』の随所に現れる死や苦痛に関する記述は、まさにこの「受容」を示している。
- 「死は自然の営みの一部であり、恐れるに値しない」
- 「苦痛もまた、心が解釈を変えれば耐え得るものとなる」
これらの言葉は、苦痛を消そうとするのではなく、自然の流れとして受け止めることを促している。これはACTにおける「感情を押し殺すのではなく、観察し、抱えながら生きる」という態度と一致する。
- 「認知的脱フュージョン」と『自省録』
ACTにおけるもう一つの核心は「認知的脱フュージョン(defusion)」である。これは「思考をそのまま真実とみなすのではなく、距離をとって観察する」技法である。例えば「私は失敗者だ」という思考が浮かんでも、それを「私は失敗者だと思っている」と捉えることで、思考に巻き込まれずに済む。
『自省録』でも同様の姿勢が見られる。マルクスは「怒りが湧くとき、その怒りがどのように生じたかを分析せよ」と述べる。これは感情と自己を切り離し、観察者としての立場を取ることを意味する。すなわち、自分の思考や感情を対象化する視点は、ACTと『自省録』の共通点である。
- 「価値に基づく行動」と『自省録』
ACTの大きな特徴は、「価値(values)」を人生の指針とし、それに基づいて行動(committed action)を取る点にある。例えば「家族を大切にする」「社会に貢献する」という価値を明確にし、それに沿った行動を選択することで、困難な状況でもブレない生き方ができる。
マルクスもまた『自省録』のなかで「人としての本分(duty)」を繰り返し強調した。彼にとって最大の価値は「理性ある人間として共同体に奉仕すること」であった。外敵との戦争や政治的陰謀に直面しても、彼は「皇帝として、父として、人間として、理性に従い義務を果たす」と自らに誓った。これはまさにACTの「価値に基づく行動」と同質である。
図表6:ACTと『自省録』の比較表
項目 | ACT | 『自省録』 |
感情 | 受け入れる | 自然の一部として受容する |
思考 | 距離をとる(defusion) | 観察対象とする |
行動 | 価値に基づく | 義務・人間本分に基づく |
目的 | 心理的柔軟性 | 理性的な自己統御 |
- 欧米における実践事例
(1)米国:医療現場でのACTと『自省録』
アメリカの病院では、医師や看護師の燃え尽き症候群対策としてACTが導入されている。ある研修プログラムでは、ACTのワークと併せて『自省録』の一節を朗読し、参加者が「死や苦痛を受け入れつつ、医療従事者としての価値に基づく行動を選ぶ」ことを学んでいる。
(2)欧州:リーダーシップ教育
オランダやドイツのMBA課程では、ACT的ワーク(価値の明確化演習)に加え、『自省録』を教材として配布するケースがある。学生は「私はどのような価値に基づいてリーダーとして決断するか」を記録し、それをマルクスの言葉と照らし合わせる。これにより、「哲学的背景を持つ心理的実践」が体得される。
- 日本における実践事例
日本では、近年「マインドフルネス」が注目される中で、ACTも少しずつ導入されている。外資系企業の管理職研修では、「価値カード」を用いて自分の価値を明確化し、そこに基づいて意思決定を行うトレーニングが行われている。その際、講師が『自省録』から「人としての務めを果たすことが最大の善である」という一節を紹介し、価値の明確化を哲学的に補強している。
また、経営者向けの勉強会では、『自省録』を読みながら「自分の経営理念は単なる利益追求ではなく、社会的使命に基づいているか」を確認する作業が取り入れられている。これはACTの「価値に基づく行動」を実務に応用した好例である。
- アジア(中国除く)における実践事例
シンガポールでは、異文化混成チームにおける対立解消のためにACTが導入されている。チームメンバーが「相手の文化を受け入れる」だけでなく、「自分自身がどのような価値に基づいて行動するか」を確認するプロセスを重視している。このとき、研修資料に『自省録』を引用し、「人類は理性を共有する存在である」という普遍的人類観を強調している。
韓国でも、大学や企業でのリーダーシップ教育においてACT的手法が活用されつつあり、『自省録』を「アジアにおける古典的倫理観との橋渡し」として取り入れる試みが始まっている。
- ACTと『自省録』の統合的意義
ACTと『自省録』を比較すると、両者は以下のような共通点を持つ。
- 感情の受容:不快な感情を否定せず、存在を認める。
- 自己と感情の分離:思考や感情を観察対象として扱う。
- 価値の重視:人生を導く価値を明確化し、それに基づいて行動する。
違いとしては、ACTは科学的フレームワークと技法を提供する点に優れ、『自省録』は哲学的洞察と言葉の力で人間の精神を励ます点に優れている。両者を統合することで、**「科学と哲学が支え合うセルフケア実践」**が可能になる。
- 次章への橋渡し
本章では、ACTと『自省録』の響き合いを明らかにした。次章では、これまでの理論比較を踏まえて、**「グローバルビジネスリーダーと『自省録』」**というテーマに進む。異文化環境におけるストレス、リーダーシップのプレッシャー、決断の重圧――それらをいかにして哲学と心理療法の力で乗り越えるかを具体的事例とともに考察する。
第5章 グローバルビジネスリーダーと『自省録』
- 多文化環境におけるリーダーのメンタルヘルス課題
グローバルビジネスのリーダーは、単に企業の業績を牽引するだけでなく、異なる文化的背景を持つ人々をまとめ上げ、共通の目標に向かわせる役割を担っている。その過程で直面する課題は多岐にわたる。
- 文化的誤解や摩擦:欧米では「率直なフィードバック」が評価される一方、日本では「和を乱さない配慮」が重視される。こうした価値観の違いは、リーダーに精神的負担を強いる。
- 長時間労働・成果主義のプレッシャー:特に日本や韓国では「働きすぎ」が美徳とされやすく、リーダー自身がバーンアウトに陥ることが少なくない。
- VUCA環境での意思決定:変動性(Volatility)、不確実性(Uncertainty)、複雑性(Complexity)、曖昧性(Ambiguity)のもとで、正解のない決断を迫られる。
こうした状況では、単に経営スキルを持つだけでは足りず、自らの心を調律し続ける力が不可欠となる。ここで、『自省録』はリーダーにとって強力なセルフケアの道具となりうる。
- 『自省録』から学ぶ「内面の安定」
マルクス・アウレーリウスが皇帝として直面した状況は、現代のグローバルリーダーが直面するプレッシャーと驚くほど似ている。彼は戦争、疫病、政治的陰謀という制御不能な外的環境の中で、なお自己の心を理性によって支えた。
彼の言葉において繰り返されるのは、
- 「外部の出来事は私を害さない。私がそれを害と見なさない限り」
- 「人は皆、理性を共有する存在である」
という二つの原則である。
前者は「認知のフレーミング」によってストレスを軽減する方法を示し、後者は「異文化間の共通基盤」を見出す道を指し示している。これは現代のリーダーにとってもきわめて実践的な教えである。
- 欧米の事例:倫理的リーダーシップの基盤として
図表7:リーダーが直面する主要課題
課題 | 欧米の特徴 | 日本の特徴 | アジアの特徴 |
文化摩擦 | 意見衝突、率直さ | 調和重視、暗黙的理解 | 多文化混成、対立調整 |
成果プレッシャー | 四半期決算重視 | 長時間労働 | 高速成長の競争圧 |
VUCA環境 | 不確実性への対応 | 慎重な意思決定 | 柔軟な適応を迫られる |
(1)米国のテクノロジー企業CEO
シリコンバレーのある大手テクノロジー企業のCEOは、毎朝『自省録』を数ページ読み、日々の決断に備える習慣を持っている。彼は「株主や市場の期待は制御不能だが、私の判断の誠実さは制御可能である」というマルクスの教えを経営理念に組み込み、倫理的リーダーシップを実践している。
(2)欧州の政治リーダー教育
欧州の一部のビジネススクールでは、『自省録』を教材として用い、リーダーが「権力に固執するのではなく、価値に基づいた退き際を判断する」ことを学ばせている。これはストア哲学の「義務を果たし、時が来れば去る」という姿勢を現代のリーダー教育に応用したものである。
- 日本の事例:和と自己統御の融合
(1)大手製造業の経営者
ある日本の製造業の経営者は、『自省録』を座右の書としており、特に「怒りを抑える」章を繰り返し読んでいる。彼は会議で部下の提案に苛立ちを覚えたとき、「怒りは自分を滅ぼす毒である」というマルクスの言葉を思い出し、冷静に対処する習慣を養った。結果的に、組織の心理的安全性が向上し、社員の創造性が高まったという。
(2)リーダー研修での活用
日本の一部の外資系企業では、リーダーシップ研修でCBTやACTと併せて『自省録』を取り上げている。参加者は「今日、自分が最も価値を発揮できた場面」を振り返り、その言葉をマルクスの記述と照らし合わせる。これにより、哲学的省察と科学的手法を融合させた実践的トレーニングが行われている。
- アジア(中国除く)の事例:多文化チームにおける実践
(1)シンガポールの多国籍企業
シンガポールでは、多国籍企業の管理職研修で『自省録』が取り上げられている。特に「人は理性を共有する存在である」という一節は、異文化間の共通基盤として強調される。ACTのワークと組み合わせ、各国籍のリーダーが「自分の価値観」と「普遍的人類観」を照らし合わせることで、文化摩擦を減らす実践が行われている。
(2)韓国の大企業
韓国の財閥系企業では、若手幹部向けに『自省録』を題材とした「哲学的セルフケア」研修が導入されている。CBTを応用した思考記録表と『自省録』の引用を組み合わせることで、「自分の認知を修正しつつ、理性に基づく行動を選ぶ」トレーニングが行われている。
- 『自省録』の実践がもたらす三つの効果
グローバルビジネスリーダーが『自省録』をセルフケアに応用すると、次の三つの効果が期待できる。
- ストレス耐性の向上
出来事を「解釈次第」と捉えることで、外的環境に左右されにくくなる。 - 意思決定の安定性
感情に流されず、理性に基づく判断ができる。 - 異文化共感の促進
「人は理性を共有する存在」という認識が、文化の違いを超えた共感の基盤となる。
これらは、VUCA時代におけるリーダーシップの中核的資質であり、まさに「心の筋力」を鍛える実践である。
- 次章への橋渡し
本章では、欧米・日本・アジアの事例を通じて、グローバルビジネスリーダーが『自省録』をどのようにセルフケアに応用できるかを示した。次章ではさらに具体的に、**「実践ガイド:『自省録』を日常に活かす」**に進み、朝の自省、夜の内省、意思決定や交渉の場面における応用方法を体系的に紹介する。
第6章 実践ガイド:『自省録』を日常に活かす
- なぜ実践が重要なのか
『自省録』は単なる哲学書ではなく、日々の自己訓練の記録である。マルクス・アウレーリウスは権力者でありながらも、毎日の生活の中で自らの心を律する実践を積み重ねた。その本質は、現代で言えば「セルフケア・ジャーナリング」と「メンタルトレーニング」にほかならない。
グローバルビジネスリーダーにとっても同様に、抽象的な理念を知るだけでは不十分である。重要なのは、具体的な実践習慣として『自省録』を活用することである。以下では、朝・昼・夜の時間帯別に、自省録的な習慣をどのように導入できるかを解説する。
- 朝の自省 ― 1日のスタートに心を整える
マルクスは『自省録』で「朝目覚めたとき、今日一日どのような人々に会うかを想起せよ」と述べている。これは現代的に言えば、一日の心理的準備にあたる。
実践例
- 5分間の自問
- 「今日出会う困難は何か?」
- 「それにどう理性的に対応するか?」
- 「自分の価値に基づいて行動するにはどうするか?」
- 呼吸と読書
- 朝の5分間、深呼吸しながら『自省録』の一節を読む。
- 例:「今日、私は不遜な人間に出会うだろう。しかしそれは彼らの本性であり、私を害するものではない」
- グローバル事例
- 米国のあるCEOは、出社前に『自省録』を音読し、意識を「自分に制御できること」へ向け直す。
- 日本の経営者は、朝礼の前に一節を読み上げることで、組織全体に落ち着いた空気を醸成する。
- シンガポールの幹部は、朝の瞑想と合わせて『自省録』を活用し、多文化チームの調和を意識する。
- 昼の活用 ― 意思決定と交渉の現場で
グローバルリーダーにとって、昼の時間帯は最も多忙であり、同時にストレスが高まる場面でもある。会議、交渉、危機対応などで感情的になりやすい。ここで『自省録』は「内的アンカー」として役立つ。
実践例
- 意思決定の前の問い
- 「この判断は私の価値に沿っているか?」
- 「外部の評価に左右されていないか?」
- 交渉における応用
- マルクスは「相手の行為は彼の理性に基づく」と述べた。これは交渉相手を「敵」と見なさず、「彼の立場における合理性」と理解する視点に通じる。
- 欧米の交渉研修では、この思想をCBT的リフレーミングと結びつけ、交渉時の感情コントロールに活用している。
- グローバル事例
- ドイツの製薬企業の幹部は、重大な投資判断の前に「この判断は一時的な利益か、長期的な価値か」を『自省録』の言葉と照らす。
- 日本の商社マンは、海外交渉の現場で緊張を感じた際に「怒りや恐怖は自然の感情であり、それ自体は害ではない」と内心で反復し、冷静さを保った。
- 韓国のIT企業リーダーは、チーム内の対立場面で「人は理性を共有する」という哲学を共有し、異文化間の共感を促した。
- 夜の内省 ― 1日の感情を整理し、心を休める
マルクスは夜の時間に「今日一日、私は理性に従って行動したか?」と自らに問いかけた。これは現代の「リフレクション・ジャーナル」や「CBTの思考記録表」に通じる習慣である。
実践例
- 自己省察の質問
- 「今日、私は怒りに支配された場面はあったか?」
- 「そのとき理性に従っていただろうか?」
- 「明日はどのように対応するか?」
- 感情の可視化
- ネガティブな出来事を一行で記録し、それに対する解釈を書き換える。
- 例:「部下の失敗に苛立った → 彼は学ぶ機会を得た、と捉え直す」
- グローバル事例
- 米国の投資銀行幹部は「夜の15分」を必ずリフレクションに充て、『自省録』の一節を引用しながら日記を書く。
- 日本の企業リーダーは就寝前に音読を行い、「心を沈める儀式」としている。
- シンガポールのマネージャーは、内省ジャーナルをチームでシェアする文化を築き、心理的安全性を高めている。
図表8:『自省録』実践の一日モデル
時間帯 | 実践内容 | 具体例 |
朝 | 自省 | 「今日どのような困難があるか?」を問う |
昼 | 意思決定・交渉 | 「相手の合理性を理解する」 |
夜 | 内省 | 「今日理性に従ったか?」を記録 |
- ケース別応用 ― 危機対応・交渉・意思決定
『自省録』の思想は、特定の場面でセルフケアに役立つ。
(1)危機対応
パンデミックやサプライチェーン危機など、制御不能の事態では「出来事そのものは善悪ではない。解釈が問題である」とのマルクスの言葉が支えとなる。欧州の航空会社CEOは、COVID-19危機の最中にこの言葉を引用し、従業員に「我々は外部要因を変えられないが、態度は変えられる」と伝えた。
(2)交渉
『自省録』は「相手の誤りもまた理性に基づく」と説く。これは交渉相手を敵視せず、「相手の文化的合理性」を理解する姿勢につながる。韓国と日本の合同ベンチャーでは、この発想を共有することで交渉の緊張が和らぎ、合意形成がスムーズに進んだ。
(3)意思決定
大きな投資判断の際、短期的利益に流される誘惑がある。そのとき「人間としての本分に基づく判断か?」と自問することで、長期的かつ倫理的な判断を下すことができる。これは欧米の経営者研修でも重視されている。
- 実践を継続するための工夫
- 習慣化:朝・昼・夜に各5分の時間を割り当てる。
- 言葉の力:お気に入りの一節をメモに書き、机やスマホに貼る。
- 仲間と共有:チームで一日一節を共有する「哲学的朝礼」を導入する。
- デジタル活用:アプリや日記ツールに「自省録ジャーナル」を組み込み、毎日振り返りを記録する。
こうした小さな工夫の積み重ねが、リーダーの心の筋力を確実に鍛える。
- 次章への橋渡し
本章では、朝・昼・夜の習慣や危機対応の具体的応用を示した。次章では総括として、哲学と心理療法の融合がもたらす未来への示唆を考察する。『自省録』が現代リーダーのメンタルフィットネスにどのような可能性を開くのか、そしてグローバル社会にどんな貢献ができるのかを展望していく。
第7章 まとめと未来への示唆
- 『自省録』と心理療法の架橋
ここまでの章で見てきたように、マルクス・アウレーリウスの『自省録』は、単なる古代の哲学書ではなく、現代心理療法と響き合う「普遍的な心の実践書」であることが明らかになった。
- 認知行動療法(CBT)は、思考の歪みを修正し感情の過剰反応を和らげる技法を提示する。
- アクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)は、思考や感情をあるがままに受け入れ、価値に基づいて行動する道を示す。
- 『自省録』は、2000年前にすでにこれらのエッセンスを哲学的言語で記し、皇帝自身が実践していた。
すなわち、『自省録』は科学と哲学の橋渡しを行い、「人間が心をどう整えるか」という問いに普遍的な答えを与えているのである。
- グローバルビジネスリーダーへの示唆
現代のグローバルビジネスリーダーは、株主の期待、国際政治の揺らぎ、多文化チームの摩擦といった複雑な課題に日々直面している。こうした環境において求められるのは、**戦略的知性だけではなく、精神的安定を支える「心の筋力」**である。
『自省録』がリーダーに与える示唆は三つに整理できる。
- 制御できるものとできないものを区別する力
→ 外部要因に翻弄されず、自分がコントロールできる態度と判断に集中する。 - 理性に基づいた冷静な意思決定
→ 怒りや恐怖といった感情の嵐を超えて、長期的かつ倫理的な視座から決断を下す。 - 人類普遍の理性を共有する視点
→ 異文化の違いを超え、人間同士が理性によって結ばれているという共感の基盤を持つ。
これらは、グローバル企業を率いるリーダーにとって不可欠な心構えである。
図表9:リーダーに求められる三つの心の力
力 | 内容 | 自省録での表現 |
制御力 | 外部に左右されない | 「害と見なさぬ限り害ではない」 |
理性力 | 感情に流されぬ決断 | 「怒りは理性を曇らせる」 |
共感力 | 人類普遍の理性を認める | 「人は皆理性を共有する存在である」 |
- 欧米・日本・アジアの未来的実践
欧米ではすでに、MBA教育やエグゼクティブ研修に『自省録』が組み込まれ、哲学と心理療法を融合したリーダー教育が始まっている。日本でも、企業研修や自己啓発の場で『自省録』とCBT/ACTを統合したプログラムが導入されつつある。さらにシンガポールや韓国といったアジア諸国では、多文化マネジメントに『自省録』を応用する試みが進められている。
これらの潮流は、単なる一過性の流行ではなく、**「哲学を再評価し、科学と統合して心を鍛える」**という世界的な動きの一部である。未来のリーダー教育は、経済学や経営学の知識に加え、哲学と心理学を基盤とした「人間力の育成」へと進むだろう。
- 個人へのメッセージ ― 読者に向けて
ここまでの議論を読んだ読者には、「では具体的に何をすればよいのか」という問いが残るかもしれない。答えは驚くほどシンプルである。
- 朝の5分間、『自省録』の一節を読み、今日の心構えを定める。
- 昼の会議や交渉の前に、「これは自分の価値に沿った判断か」と問いかける。
- 夜の10分間、その日の感情を振り返り、理性に従ったかを自己点検する。
この小さな実践を積み重ねることこそが、リーダーの心を鍛える最良の方法である。重要なのは、完璧に実行することではなく、繰り返すこと、継続することである。
- 未来への展望 ― 「哲学する組織」へ
最後に、組織レベルでの応用について触れておきたい。企業や組織が『自省録』を学び、日常の実践に取り入れることで、「哲学する組織」が生まれる。そこでは、短期的利益だけでなく、長期的価値や社会的責任が意思決定の基盤となる。社員一人ひとりが「自己の感情に振り回されず、理性に従って行動する」文化が根付けば、組織全体の心理的安全性と持続可能性は大幅に向上するだろう。
グローバル社会において、リーダーシップの本質は「他者を支配すること」ではなく、「自己を統御し、共通の価値に基づいて人々を導くこと」である。その意味で、『自省録』は古代から未来への道標であり続ける。
- 結び ― 心の筋力を鍛える旅へ
本記事全体を通して見てきたのは、古代哲学と現代心理療法が出会い、グローバルビジネスリーダーのセルフケアを支える道筋である。
マルクス・アウレーリウスが荒波の時代を生き抜いたように、現代のリーダーもまた、『自省録』を心の支えとし、理性に基づいて未来を切り拓くことができる。
最後に、マルクスの言葉を現代のリーダーへの贈り物として記して結びとする。
「人は外界の出来事にではなく、その出来事への解釈に傷つくのである。ゆえに、自らの心を守る者こそ、真に自由である。」
読者一人ひとりが、この言葉を日々の実践に取り入れ、自らの心の筋力を鍛える旅を歩み出すことを願う。
参考文献一覧(完全版)
- Marcus Aurelius. Meditations. (邦訳:『自省録』岩波文庫、中公クラシックス、講談社学術文庫ほか)
- Beck, Aaron T. Cognitive Therapy and the Emotional Disorders. International Universities Press, 1976.
- Ellis, Albert. Reason and Emotion in Psychotherapy. Lyle Stuart, 1962.
- Hayes, Steven C., Strosahl, Kirk D., & Wilson, Kelly G. Acceptance and Commitment Therapy: The Process and Practice of Mindful Change. Guilford Press, 2011.
- 日本産業カウンセラー協会『職場のメンタルヘルスハンドブック』
- 厚生労働省『職場におけるメンタルヘルス対策指針』
- Harvard Business School Executive Education. Leadership and Ethics curriculum (教材資料)
- European School of Management and Technology (ESMT) Berlin. MBA Leadership Program materials.
- シンガポール国立大学(NUS)エグゼクティブ教育プログラム資料
- 韓国・延世大学 経営大学院 リーダーシップ教育研究報告書
ご感想、お問い合せ、ご要望等ありましたら下記フォームでお願いいたします。
投稿者プロフィール

- 市村 修一
-
【略 歴】
茨城県生まれ。
明治大学政治経済学部卒業。日米欧の企業、主に外資系企業でCFO、代表取締役社長を経験し、経営全般、経営戦略策定、人事、組織開発に深く関わる。その経験を活かし、激動の時代に卓越した人財の育成、組織開発の必要性が急務と痛感し独立。「挑戦・創造・変革」をキーワードに、日本企業、外資系企業と、幅広く人財・組織開発コンサルタントとして、特に、上級管理職育成、経営戦略策定、組織開発などの分野で研修、コンサルティング、講演活動等で活躍を経て、世界の人々のこころの支援を多言語多文化で行うグローバルスタートアップとして事業展開を目指す決意をする。
【背景】
2005年11月、 約10年連れ添った最愛の妻をがんで5年間の闘病の後亡くす。
翌年、伴侶との死別自助グループ「Good Grief Network」を共同設立。個別・グループ・グリーフカウンセリングを行う。映像を使用した自助カウンセリングを取り入れる。大きな成果を残し、それぞれの死別体験者は、新たな人生を歩み出す。
長年実践研究を妻とともにしてきた「いきるとは?」「人間学」「メンタルレジリエンス」「メンタルヘルス」「グリーフケア」をさらに学際的に実践研究を推し進め、多数の素晴らしい成果が生まれてきた。私自身がグローバルビジネスの世界で様々な体験をする中で思いを強くした社会課題解決の人生を賭ける決意をする。
株式会社レジクスレイ(Resixley Incorporated)を設立、創業者兼CEO
事業成長アクセラレーター
広島県公立大学法人叡啓大学キャリアメンター
【専門領域】
・レジリエンス(精神的回復力) ・グリーフケア ・異文化理解 ・グローバル人財育成
・東洋哲学・思想(人間学、経営哲学、経営戦略) ・組織文化・風土改革 ・人材・組織開発、キャリア開発
・イノベーション・グローバル・エコシステム形成支援
【主な著書/論文/プレス発表】
「グローバルビジネスパーソンのためのメンタルヘルスガイド」kindle版
「喪失の先にある共感: 異文化と紡ぐ癒しの物語」kindle版
「実践!情報・メディアリテラシー: Essential Skills for the Global Era」kindle版
「こころと共感の力: つながる時代を前向きに生きる知恵」kindle版
「未来を拓く英語習得革命: AIと異文化理解の新たな挑戦」kindle版
「グローバルビジネス成功の第一歩: 基礎から実践まで」Kindle版
「仕事と脳力開発-挫折また挫折そして希望へ-」(城野経済研究所)
「英語教育と脳力開発-受験直前一ヶ月前の戦略・戦術」(城野経済研究所)
「国際派就職ガイド」(三修社)
「セミナーニュース(私立幼稚園を支援する)」(日本経営教育研究所)
【主な研修実績】
・グローバルビジネスコミュニケーションスキルアップ ・リーダーシップ ・コーチング
・ファシリテーション ・ディベート ・プレゼンテーション ・問題解決
・グローバルキャリアモデル構築と実践 ・キャリア・デザインセミナー
・創造性開発 ・情報収集分析 ・プロジェクトマネジメント研修他
※上記、いずれもファシリテーション型ワークショップを基本に実施
【主なコンサルティング実績】
年次経営計画の作成。コスト削減計画作成・実施。適正在庫水準のコントロール・指導を遂行。人事総務部門では、インセンティブプログラムの開発・実施、人事評価システムの考案。リストラクチャリングの実施。サプライチェーン部門では、そのプロセス及びコスト構造の改善。ERPの導入に際しては、プロジェクトリーダーを務め、導入期限内にその導入。組織全般の企業風土・文化の改革を行う。
【主な講演実績】
産業構造変革時代に求められる人材
外資系企業で働くということ
外資系企業へのアプローチ
異文化理解力
経営の志
商いは感動だ!
品質は、タダで手に入る
利益は、タダで手に入る
共生の時代を創る-点から面へ、そして主流へ
幸せのコミュニケーション
古典に学ぶ人生
古典に学ぶ経営
論語と経営
論語と人生
安岡正篤先生から学んだこと
素読のすすめ
経営の突破口は儒学にあり
実践行動学として儒学に学ぶ!~今ここに美しく生きるために~
何のためにいきるのか~一人の女性の死を見つめて~
縁により縁に生きる
縁に生かされて~人は生きているのではなく生かされているのだ!~
看取ることによって手渡されるいのちのバトン
など


