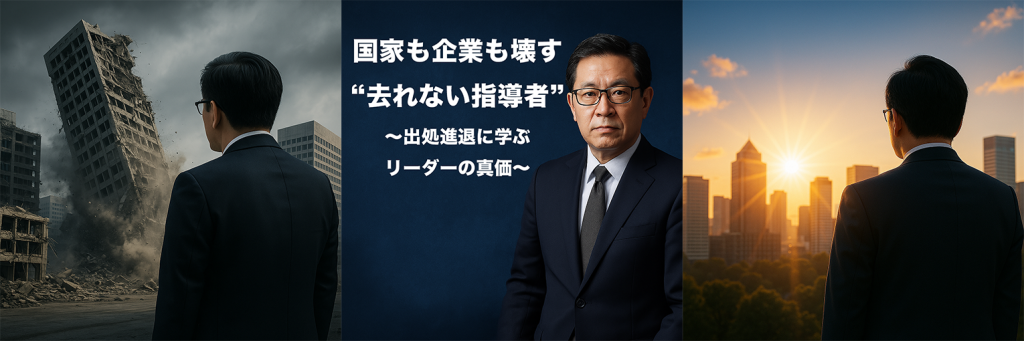国家も企業も壊す“去れない指導者” 〜出処進退に学ぶリーダーの真価〜
はじめに──「なぜ去れないリーダーは、組織を壊すのか」
歴史を見渡せば、数多くの組織や国家が「崩壊」や「混迷」に陥ったとき、そこには共通する特徴がある。それは、トップに立つべき人物が「去るべきときに去らなかった」という事実である。リーダーの“去り際”──この一見単純な行為こそが、国家の命運を分け、企業の未来を決定づける分水嶺である。
「去る勇気」が持てなかったリーダーは、時にその功績までも失墜させる。周囲が見限っても本人が気づかず、組織が次の一手を打てないまま時間だけが過ぎてゆく。そんな“去れない指導者”の影が、私たちの周囲──政治、企業、教育、宗教、国際社会のあらゆる場面に、確かに存在している。
では、なぜリーダーは“去れない”のか。そして、なぜ“潔く去る”ことがこれほどまでに難しいのか。本稿はこの問いを出発点とし、安岡正篤という20世紀日本の思想家の視座から、その根底にある「出処進退(しゅっしょしんたい)」の哲学を紐解いていく。
「出処進退」とは、古代中国の儒教に端を発し、「いつ、いかに世に出るべきか、そして、いかに退くべきか」を示す倫理的・人格的判断基準である。安岡正篤は、この出処進退を単なる行動指針としてではなく、「人物完成の要」として捉え、リーダーにとっての真価は「去り際にこそ現れる」と強調した人物である。
いま我々が直面している社会の分断、企業の凋落、政治の迷走の根底には、「出処進退」を正しく実践できないリーダーの姿がある。去る時を見誤れば、どれほどの業績も、築いた信頼も、積み重ねた歴史も、瞬く間に崩れ去るのである。
本稿では、日本の近現代の政治指導者をはじめ、欧米やアジアの国家元首、さらにはグローバル企業の創業者たちの「出処進退」の実例を取り上げながら、私の人生の師父である安岡正篤先生(以後、敬称略)の人間学に根ざしたリーダー論を展開する。「義に従い、時を知り、私を退ける」──この哲学がなぜ今、あらゆる組織に求められているのか。
読者諸賢が「去り際とは何か」を深く見つめ直すきっかけとなることを願い、ここに筆を執る。
第1章 安岡正篤と「人物」としてのリーダー論
安岡正篤(1898–1983)は、陽明学を中核とする東洋倫理思想を探究し、それを近代日本の指導者教育に応用した思想家である。東洋哲学の中に西洋的近代合理主義を調和させ、「人間学」としての体系化を試みた。戦前から戦後にかけて、歴代の宰相(吉田茂、佐藤栄作、中曽根康弘など)に精神的影響を与え、「参謀の参謀」「影の教育者」と称された。
彼が説いた「人間学」とは、単なる知識の修得ではなく、「人物としての完成」を目指すものであり、リーダーはまず“人として正しくあること”を土台としなければならないとした。リーダーに求められるのは、能力や知識だけではない。「大義に生きる覚悟」「利己を超えた志」「時代の声に応える柔軟性」こそが必要であると説いた。
安岡によれば、出処進退とは「義に生きる者の行動指針」であり、「時に順う勇気」と「私を捨てる覚悟」を意味する。真のリーダーとは、自己に厳しく、時代と民意に敏感で、静かにそして潔く退くことのできる人物である。
第2章 日本における出処進退の変遷と事例分析
明治維新後の近代国家建設期には、出処進退の美学が随所に見られる。大久保利通の死後、山県有朋は一時政界を退き、国家機構の近代化に専念した。また、浜口雄幸首相は昭和初期、国家経済の再建に尽力していたが、凶弾に倒れても尚、職責を全うせんとする意志を示し、国民に強い感銘を与えた。
戦後の出処進退の模範とされるのが吉田茂である。吉田はサンフランシスコ講和条約の成立とともに、自ら退陣を計画し、敗戦国日本における国際復帰の道筋を整えた上で潔く身を引いた。
一方、田中角栄は列島改造論に象徴される経済政策を推進し、地方と都市の格差是正に貢献したが、ロッキード事件によって政治倫理が問われ辞任。その後も「闇将軍」として政界に強い影響力を保持し続け、組織運営の健全性を損ねた。これこそが「出処進退の失敗」が国家・政党にもたらす悪影響の典型例である。
2022年、安倍晋三元首相は奈良市で凶弾に倒れ、日本中に衝撃を与えた。安倍氏は、憲政史上最長の在任期間(通算8年8か月)を記録し、戦後日本の政治において圧倒的な存在感を誇った指導者である。アベノミクスによる経済再生、安全保障関連法の整備、日米同盟の深化、対中国・韓国外交の再構築など、賛否両論を巻き起こしつつも日本の方向性を大きく規定した。
しかし、その政治手法は「決断と実行」を標榜する一方で、強権的な側面を併せ持ち、統治手法に対する懸念も絶えなかった。また、森友・加計・桜を見る会といった一連の疑惑や説明責任の不在が政権運営に影を落としたことも事実である。
安倍氏が銃撃された背景には、犯人の山上徹也による「母親が統一教会に献金し家庭が崩壊した」という動機があり、安倍氏と統一教会(世界平和統一家庭連合)との接点が事件の一因であるとされた。だが、事件後の検証においては、「単独犯による怨恨事件」との見方だけでなく、「警備体制の不備」「安倍氏の政治的影響力を懸念した勢力の存在」など、複数の見解が存在する点に留意すべきである。
安倍氏の死は、単なる個人の悲劇にとどまらず、戦後日本の「権力のあり方」や「国家と宗教の距離」、「リーダーシップの継承」を考える契機となった。皮肉にも、その最期は「出処進退の判断を自ら下す余地」を奪われた形であり、安岡正篤の説く「義に従い、時を見て去る」理想を実現する機会を失ったともいえる。
だが一方で、彼が遺した政策やネットワーク、政治的志向は、死後も自民党内外で影響を与え続けており、出処進退とは「姿を消すこと」ではなく「次世代への理念の継承」であることを体現しているとも評価できる。
安倍晋三元首相の後、菅義偉、岸田文雄を経て2024年に首相に就任した石破茂は、自民党内で党内野党としての言動が問題視されていたが、党内の権力闘争により総裁になり、2024年に首相に就任した。しかし、その言動には、自己保身を第一に考え、国家・国民のことは考えず、常に媚中政治家の言動を繰り返している。その結果として、支持率の急落が止まらず、そのリーダーシップには国内外から強い疑問が呈されている。
特に、国民生活の苦境に対する後手の経済対策、諸外国との外交の稚拙な対応、説明不足な記者会見、政務官の倫理的失言、さらには新人議員に対する商品券提供問題など、相次ぐ政治的失策が続いている。これらの問題は、石破首相がかつて掲げた「誠実で透明な政治」との乖離を浮き彫りにしている。
石破首相は、かつての「異端児」的存在としての独自性や政策主張で支持を集めたが、政権の座に就いてからは「決められない首相」「発信力に欠けるリーダー」との烙印を押されつつある。結果として、党内結束も脆弱化し、政権運営の安定性を著しく欠いている。
このような状況下において、石破茂がいつ、どのようにして自身の「出処進退」を判断するかは、日本のリーダーシップの未来にとって極めて象徴的な課題である。安岡正篤が説く「義に従い、時を知り、己を退く勇気」を今まさに試されている局面である。
第3章 欧米の指導者に見る出処進退の哲学
出処進退の美学は、東洋的価値観に根ざした概念と思われがちだが、西洋政治においてもその重要性は深く認識されている。
たとえば、アメリカ合衆国初代大統領ジョージ・ワシントンは、国民から圧倒的な支持を受けながらも2期8年で自ら政権の座を退いた。彼は「権力の座にとどまりすぎることは共和国の腐敗を招く」として、憲法上の任期制限がなかった時代に自ら範を示した。この行動が、アメリカにおける民主主義の基盤を確立する一因となったことは言うまでもない。
ドイツのアンゲラ・メルケル元首相もまた、16年間に及ぶ政権を経て、自ら後継体制の準備を整えたうえで静かに政権を退いた。彼女は政界からの“引き際”を公表した後も冷静かつ誠実に国政に従事し、退任後も一切の影響力行使を控えている。その「去り際の知性」は、ドイツ国民から高い評価を得ている。
一方で、アメリカのドナルド・トランプ前大統領のように、「去るべき時」に固執した指導者の姿勢が国を分断し、民主主義の機能不全を引き起こした事例もある。2021年の連邦議会襲撃事件は、「出処進退の誤り」が国家全体に与える衝撃の大きさを物語っている。
フランスのド・ゴール将軍もまた、国民投票での敗北を機に潔く退任を選んだ。自身が信任されなければ政治を行う意味はないとする明快な姿勢は、指導者の責任と覚悟を象徴するものである。
第4章 アジアにおけるリーダーと出処進退の現実
アジア諸国でも、出処進退の判断が国家の命運を左右してきた事例は少なくない。
シンガポール建国の父、リー・クアンユーは長期政権を維持しながらも、次世代への移行を政治的かつ制度的に設計し、政権移譲の過程で国家の安定を保った。「個のカリスマ」ではなく「制度と理念」を次世代に遺すという姿勢は、アジア政治における模範とされる。
その対照となるのが、インドネシアのスハルト元大統領である。30年以上にわたり独裁体制を築き上げたが、アジア通貨危機と民衆の怒りによって政権が崩壊。退陣の時機を見誤ったことで、自らの政治的功績も否定される形で去らざるを得なかった。
韓国でも、大統領の出処進退は極めて厳しく問われる。朴槿恵前大統領の罷免や、李明博・全斗煥らの逮捕は、「去るべき時に潔く去らなければ、信頼も功績も帳消しになる」という厳しい教訓を現している。
第5章 経済界における創業者と出処進退の倫理
政治家だけでなく、企業のトップにも出処進退の倫理が問われる時代である。
アップル社創業者のスティーブ・ジョブズは、一度同社を追われた後に復帰し、イノベーションによって企業を再興した。だが晩年には自らの病を公表し、次世代の指導者ティム・クックへとスムーズに経営を委譲した。「創業者が組織の障壁になってはならない」という自覚が、出処進退の成功につながった。
一方で、創業者が執着することで企業が混迷する事例も少なくない。日本企業では、長期的に会長職に留まり意思決定を支配し続けた結果、イノベーションが阻害される例が見られる。経営トップの「去り方」は、企業文化と競争力の形成に直結しているのだ。
稲盛和夫は、京セラ創業後に潔く経営から退き、後進に理念と判断軸を伝えることで、継続的な成長と信頼を確保した。JAL再建でも同様に「必要なことをやった後は潔く去る」姿勢を貫き、多くの経営者に影響を与えた。
第6章 出処進退の教育と文化への定着
安岡正篤は、出処進退の実践には「義に従う判断力」「時を知る感性」「己を退ける勇気」の三要素が不可欠であると説いた。これは単なる倫理観ではなく、「人格の完成」としての哲学である。
現代において、この思想を教育・研修・制度設計に取り込む必要がある。政治においては任期制や信任投票の制度的仕組みだけでなく、「退くことの美学」を内在化する倫理観の涵養が不可欠である。企業でも、経営者研修において「去り際の設計」を戦略的に捉えるべきである。
また、社会全体が「去る者に敬意を払う文化」を持つことが、健全な出処進退を促進する前提条件である。単に成功を称えるのではなく、「どう去ったか」に焦点を当てることが、次世代のリーダーシップ形成に資する。
おわりに──未来を託すための“去り際”
出処進退とは、単なる地位の移動でも、任務の終了でもない。それは「未来を託すための最終行為」であり、「人物」としての完成の証明である。
安倍晋三元首相の不慮の死、石破茂現首相の迷走、欧米諸国の模範的事例、アジアの教訓──すべては、「去ることの難しさ」と「去ることの大切さ」を我々に教えている。
安岡正篤の言葉に従えば、真のリーダーとは「出処進退を通じて、時代と民に誠を尽くす者」である。
今、我々が問うべきは、「誰が残るか」ではなく、「誰がどう去るか」である。