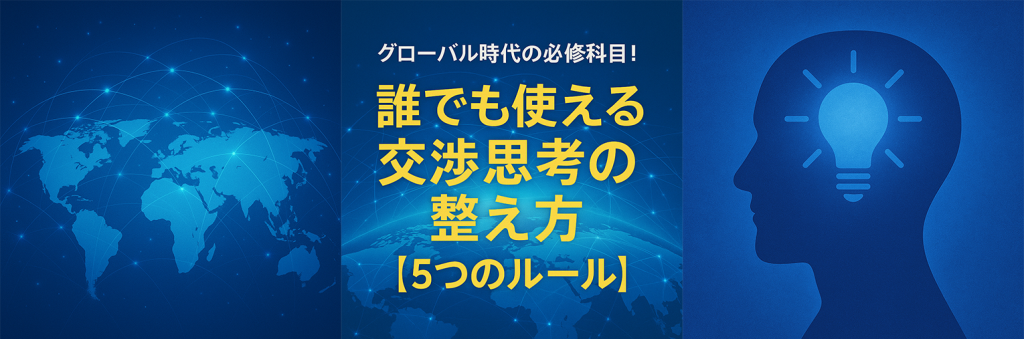はじめに:交渉は“思考の質”で勝敗が決まる
「もっと交渉がうまくできたら──」
そんな思いを抱いたことはありませんか?
ビジネスの現場で、あるいは日常のささいなやり取りの中でも、「相手とうまく話が噛み合わない」「本音を引き出せない」「合意にたどり着けない」と感じる場面は少なくありません。特に相手が海外の企業や異なる文化圏の人であれば、なおさら戸惑うことが多いでしょう。
実は、交渉がうまくいくかどうかは「話し方」よりも「考え方」によるところが大きいのです。頭の中が整理されていなければ、どれだけ上手に話しても相手には伝わりません。逆に、しっかりとした“思考の軸”を持っていれば、自信を持って交渉に臨むことができ、相手の信頼も自然と得られるのです。
本記事では、交渉の現場で多くの成果を上げてきた筆者の経験をもとに、誰でも実践できる「思考の整え方」5つのルールをご紹介します。ビジネスパーソンはもちろん、学生、研究者、NPOスタッフ、行政職の方など、あらゆる場面で「伝える力」「対話する力」が問われる今こそ、身につけておきたい知的スキルです。
「自分の考えを、相手と共有し、動かす」。
そんな力を高めたいあなたに、ぜひ最後まで読んでいただきたい記事です。
第1項:常に中心点を明らかにし、中心・骨組で考える習慣をつくる
▷ 定義と解説
本項目は、「常に目的・目標を明確にする習慣」を持つことの重要性を説いている。交渉や会議において、話題が細部に入り込むにつれて本来の「中心(目的)」が見えなくなる事が多い。これを防ぐには、常に中心点=議論の本質的な目標と、骨組=目的を達成するための主要論点を明示し続ける必要がある。
中心を失えば、議論は枝葉末節にとらわれ、時間もエネルギーも浪費される。
図解(文章形式)
【思考の構造モデル】
目的(中心点)
└── 論点A(骨組)
└─ 小論点a1、a2…
└── 論点B(骨組)
└─ 小論点b1、b2…
▷ 実例:アジア事例(タイ・マレーシア拠点統合)
ある日系製造業が東南アジアの複数拠点を統合し、地域統括法人を設立しようとした際、税制・労務・言語の違いが論点となり、交渉が膠着した。筆者がコーチングした担当者は、会議冒頭で「本件の中心目的は“統一的な意思決定の迅速化”であり、統合自体は手段である」と中心点を再定義。これにより議論が再構築され、不要な枝葉議論が整理された。
▷ 実践スキルの習得法
- 会議前に「この議論の中心目的は何か?」を紙に書き出す
- ロジックツリーやマインドマップで骨組を可視化
- 議論がズレた際に、「本来の目的は?」と問い直す習慣を持つ
第2項:常に両面とも考え、どちらが主流かも考える習慣をつくる
▷ 定義と解説
この項目は、「物事を対比的に捉える思考習慣」を指す。あらゆる条件・主張には**肯定面と否定面(両面性)**がある。交渉においては、片面だけで評価・判断すると失敗する可能性が高い。両面の比較を行い、どちらが主流として優位かを見極める力が求められる。
▷ 実例:欧米事例(米国ベンチャーとの契約)
日本のSaaS企業が米国スタートアップとパートナー契約を結ぶ交渉に臨んだ際、相手から「初年度の価格を大幅に引き下げる代わりに、3年間の継続契約」という提案があった。このとき交渉担当者は、単なる「利益減」の片面でなく、「長期契約による顧客基盤形成」というもう一方の面を提示。結果、ディスカウントとロイヤルティ契約を組み合わせた提案で合意に至った。
▷ 実践スキルの習得法
- Pros & Cons表で両面の比較を視覚化する
- 意図的に「反対側の立場」から再検討する練習
- 各提案に対して「この条件の裏側には何があるか」を自問する習慣を持つ
第3項:立場・観点を整理し、多角度から考える習慣をつくる
▷ 定義と解説
この思考法では、単一の立場・観点に固執せず、多様な立場(社内外・上位下位・地域別)から論点を見ることを重視する。とくにグローバル交渉では、関係者の数が多く、誰がどんな価値観・目的で関与しているかを整理しないと、交渉が行き詰まる。
▷ 実例:日本事例(自治体・企業・大学の三者連携)
日本の地方都市で、製造業・自治体・地元大学が共同で新工場・研究施設を誘致するプロジェクトに関与した際、それぞれ「企業:投資対効果」「自治体:雇用創出」「大学:研究活用」が異なる観点で交渉に臨んでいた。製造業の担当者はステークホルダーマップを作成し、各立場の目的を整理することで、補助金制度と人材派遣制度を連動させた合意形成に成功した。
図解:ステークホルダー整理表(例)
立場 | 主な関心事 | 優先順位 |
企業 | 投資回収 | 高 |
自治体 | 雇用増・税収 | 中〜高 |
大学 | 技術連携 | 中 |
▷ 実践スキルの習得法
- 交渉前に関係者ごとの「立場・価値観・目的」を一覧化
- ブレストで他の立場に“なりきって”仮説を立てる演習
- メディア記事を複数の視点で読み比べ、観点の違いを認識する
第4項:確定的要素から出発して考える習慣をつくる
▷ 定義と解説
交渉や提案において、「主観」と「客観」を区別し、確定した事実(=客観)から思考を始める習慣が極めて重要である。主観的な印象や憶測を交渉に持ち込むと、信頼性が下がり、説得力も弱まる。
▷ 実例:アジア事例(中国地方都市での出店計画)
日本の小売業が中国・浙江省で新規出店を検討した際、「現地の購買力は低い」との感覚的な反対意見が多かった。日本の小売業担当者は中国統計局データとECプラットフォームの販売データを用い、「人口10万都市で平均可処分所得が前年比15%上昇」という確定情報を提示。これにより社内承認が得られ、初年度黒字化に成功した。
▷ 実践スキルの習得法
- 情報を「Fact/Assumption/Opinion」に分類し直す練習をする
- 根拠となるデータに出典を明記する習慣をつける
- “それは事実か?仮説か?”という内省的チェックリストを活用
第5項:行動のつながりで具体的に考える習慣をつくる
▷ 定義と解説
概念的なアイデアを提示するだけでなく、それがどのような行動につながるのか、どう連動して成果が生まれるのかを明確に描く思考である。抽象だけでは動かない。相手が“動きたくなる”具体性と連鎖性を提示する力が問われる。
▷ 実例:欧州事例(ドイツ企業との導入交渉)
ドイツの製薬会社に設備導入を提案した際、相手は「導入後のサポート体制」に不安を示していた。担当者は、「導入→操作研修→月次レポート→改善サイクル」という行動連鎖モデルを提示し、導入後の運用ビジョンを描写。これにより相手の不安が払拭され、受注獲得に成功した。
図解(行動連鎖モデル)
提案 → 初期導入 → 操作支援 → 実行計画 → 評価・改善
▷ 実践スキルの習得法
- 提案のたびに「次に誰が何をするか」を明記する
- 行動のフローチャートやプロセスマップを描く訓練
- 概念に「現場でどう動くか」を常にセットで考える癖を持つ
結びにかえて:整備された思考が、信頼される交渉人をつくる
交渉の成果は、単に条件の優劣にあるのではなく、思考の深さと構造の明晰さにある。
本稿で紹介した「思考方法の整備5大項目」は、いずれも一朝一夕で身につくものではない。しかし、意識的な訓練を重ねれば、確実に“知的武器”として機能し、どの国・どの文化においても信頼される交渉者となる礎となる。
読者がこの5つの整備項目を日常に取り入れ、グローバルディールを“創り出す側”として活躍されることを願ってやまない。
👉スキル演習ワークシートダウンロード
👉自己チェックリストダウンロード
参考文献:
・脳力開発入門-基礎編-(株式会社脳力開発センター)
・脳力開発指針集(株式会社脳力開発センター)
※本稿の基本になっているのは、恩師・城野宏先生が創始された「脳力開発」「情勢判断学」である。
城野宏
1913年 誕生
1938年 東京帝国大学法学部政治学科を卒業、その後戦争で中国へ渡る
1964年 18年間の監獄生活の後、51歳で日本へ帰国
1969年 城野宏経済研究所を発足し、脳力開発・情勢判断学を提唱。
脳力開発の基礎となる考え方は、城野宏氏本人の戦争体験や投獄生活などの様々な体験から生み出されたものである。その後、日本アラブ協会理事長、財団法人日本教育文化協会理事長など様々な方面で活躍、また30冊以上の著書を発刊した。
1985年 72歳で逝去。」